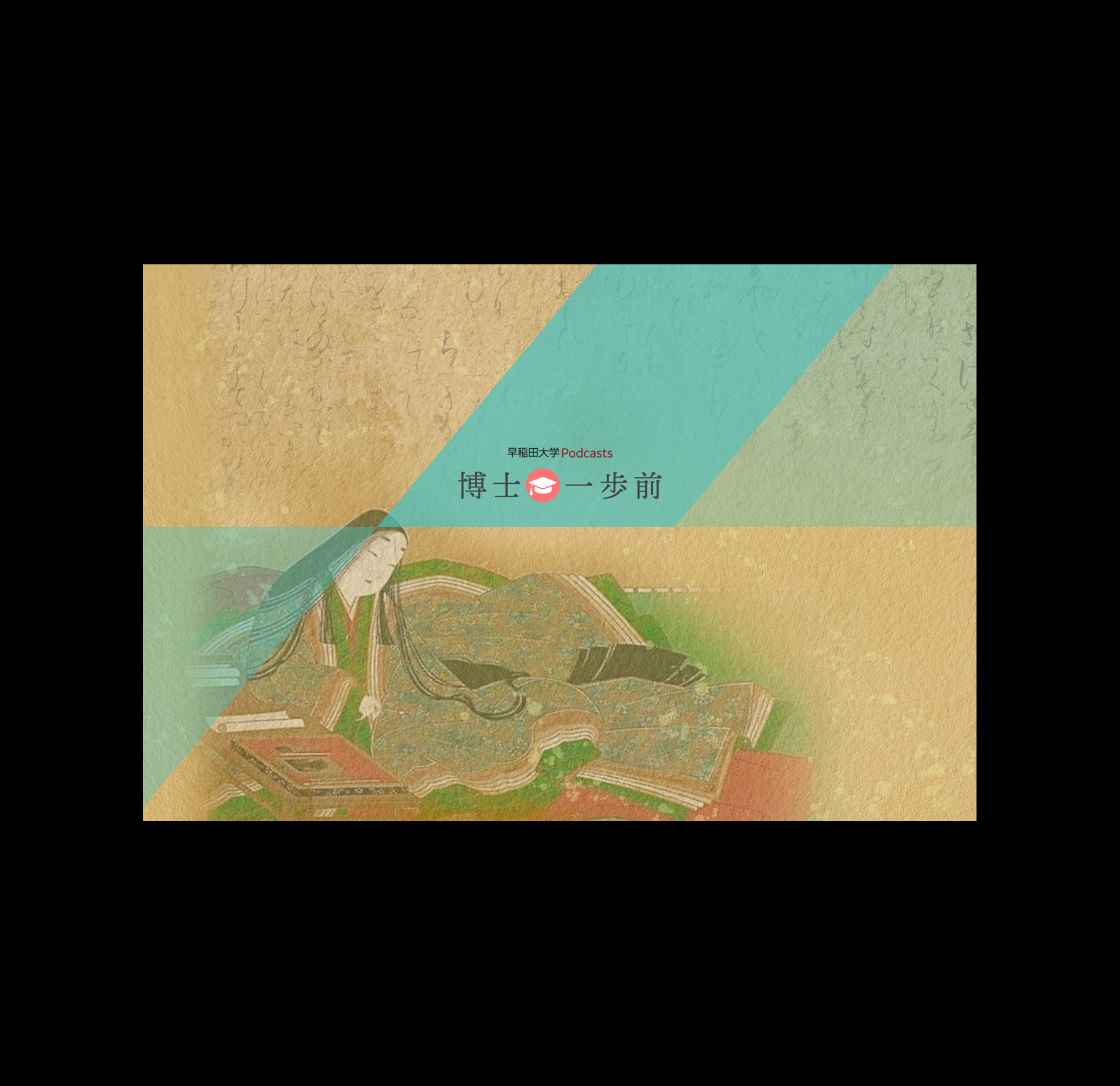- Featured Article
【Podcastコラム】ユーモアのある日記文学
Tue 04 Mar 25
Tue 04 Mar 25
早稲田大学では現在、ポッドキャスト番組「博士一歩前」 を配信中です。
今回は配信中のエピソードのうち、教育・総合科学学術院の福家俊幸教授にご自身の研究分野である国文学について語っていただく中で、研究の醍醐味をお話いただきましたので、その部分を抜粋してご紹介いたします。
Q.研究を通じて見えてきた世界観ですとか、研究の醍醐味を教えていただきたい。
福家 俊幸 教授: 国文学の世界は膨大な先行研究があります。そこにどういったものを加えていくのかが、日夜課題となっているところで、どこに新しいものを加えていくのかというところです。
私も十分できているとは思いませんが、例えば先ほど申し上げたところに結びつけますと、『更級日記』は前半、冒頭から5分の1ぐらい、全体の5分の1ぐらいが、孝標女が13歳に、上総国、千葉県になりますが、当時上総国の国府から、都に向かって旅立つ様子が書かれています。
ここが面白いことに色々な面白い地名、「いかだ」とか、現在どこかはっきりしない、「いけだ」が訛ったというか、聞き違えたんじゃないかとも言われたりしますが、実は「いかだ」という土地に来たら雨が激しく降ってきたと、木が浮きそうだったと書いてあります。
実は「いかだ」って木を組み立てて浮くじゃないですか。つまりこの『更級日記』の13歳の旅の地名は、そうした言葉遊びみたいなものが多くて、しかもやたらと様々な色が出てきたり、絵みたいな表現が出てきたり。あと数字へのこだわり。1とか3とか、いっぱい出てきます。

結構ダジャレみたいな、そういう表現もたくさん出てくる。これは思うに、孝標女という『更級日記』の作者は、宮仕えに出たときに30数歳ぐらい。それぐらいで宮仕えしていますが、彼女が仕えた祐子内親王はまだ幼児、子供です。2、3歳ぐらいなんですよね。その後ちょっと成長していきますが、彼女が宮仕えした初期の時期は子供なんです。
そうしたことを考えると、この旅の記録は、まだ幼い祐子内親王が読むことを考えて、楽しめるように作っているのではないかという仮説が成り立つのではと思います。
実は祐子内親王は、主催した歌合わせ、歌合せとは歌と歌を合わせて、優劣を競う遊びですが、祐子内親王家の歌合わせは結構地名をめぐる歌合わせが多くて、ひょっとすると祐子内親王は、記録にはありませんが、地名マニアだったのではと思ったりもします。

そういうことを考えると、実は孝標女は自分の経験は間違いないですが、それを読む、読者である祐子内親王、自分の主人のことを考えて、いわば絵本のような形で子供向けに作り直して、そうした自分の経験を書いている。
そうなってくると、読者の好みに合わせて自分の体験を改変していくということにもなってきますので、必ずしも個人に解消されない問題がそこにあるんじゃないかと思います。
そのような形で、平安時代の仮名日記、日記文学は自分の体験をそのまま書いて、『蜻蛉日記』の場合だと兼家が通ってこない悲しみみたいなものをぶちまけてるみたいですね。そういうイメージがあると思います。もちろんそういった部分もあるかもしれませんが、もう少し読む人のことを意識して、ある意味『蜻蛉日記』も過剰に書いているところもあるかもしれません。一定の読者受けみたいなところも狙っているかもしれない。そんな感じで考え直してみても面白いのではと思っています。
福家 俊幸 教授
教育・総合科学学術院教授。専門は平安時代の文学・日記文学。1962年香川県生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。博士(文学)。早稲田大学高等学院教諭、国士舘大学助教授、早稲田大学教育学部助教授を経て現職。著書に『紫式部日記の表現世界と方法』(武蔵野書院)、『更級日記全注釈』(KADOKAWA)、共編著に『紫式部日記・集の新世界』『藤原彰子の文化圏と文学世界』『更級日記 上洛の記千年』(以上、武蔵野書院)、『紫式部日記の新研究』(新典社)、監修に『清少納言と紫式部』(小学館版・学習まんが人物館)など。
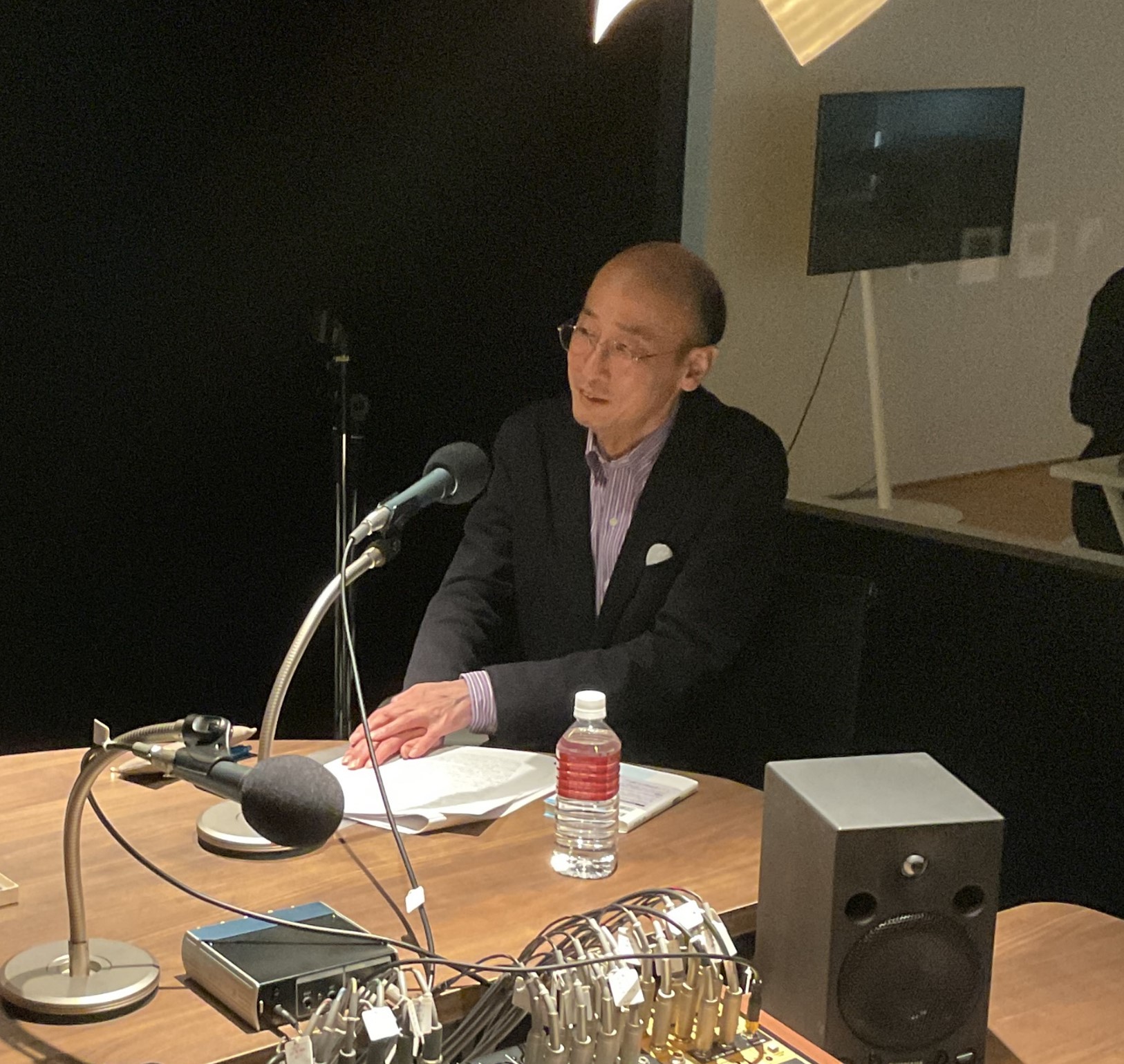
城谷 和代 准教授(番組MC)

研究戦略センター准教授。専門は研究推進、地球科学・環境科学。2006年 早稲田大学教育学部理学科地球科学専修卒業、2011年 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻博士課程修了 博士(理学)、2011年 産業技術総合研究所地質調査総合センター研究員、2015年 神戸大学学術研究推進機構学術研究推進室(URA)特命講師、2023年4 月から現職。