- Featured Article
Vol.1 社会学(前編)【都市とは何か?】日常を問い直す社会学的感覚 / 若林教授
早稲田大学Podcasts:博士一歩前
Tue 23 Apr 24
早稲田大学Podcasts:博士一歩前
Tue 23 Apr 24
今回と次回のエピソードでは、教育・総合科学学術院所属で、社会学者の若林幹夫教授をゲストに、2023年に刊行された著書『社会学入門一歩前』の内容を基に、「世の中の前提を紐解く、社会学的感覚」 を探求します。
前編の今回は、 「社会学的感覚とは」 「都市とは何か?」「<役に立つ>に潜む危険性」「大学教育の価値」などをテーマに、日常生活の中で見過ごされがちな社会を理解する視点を、若林教授とともに、社会学的感覚から紐解きます。
学問が直接的に「役に立つ」ことに焦点を当て過ぎることの危険性、都市と大学の関係、リモート社会が進展する現代において大学で学ぶ意義とは。
配信サービス一覧
ゲスト:若林 幹夫
教育・総合科学学術院教授。専門は社会学、都市論、メディア論。
1962年東京生まれ。東京大学教養学部卒。東京大学大学院博士課程中退。博士(社会学)。筑波大学教授等を経て、2005年より現職。著書に、『社会学入門一歩前』(河出書房新社)、『郊外の社会学――現代を生きる形』(ちくま新書)、『モール化する都市と社会――巨大商業施設論』(NTT出版)、『都市論を学ぶための12冊』(弘文堂)など、多数。

ホスト:島岡未来子

研究戦略センター教授。専門は研究戦略・評価、非営利組織経営、協働ガバナンス、起業家精神教育。
2013年早稲田大学公共経営研究科博士課程修了、公共経営博士。文部科学省EDGEプログラム、EDGE-NEXTプログラムの採択を受け早稲田大学で実施する「WASEDA-EDGE 人材育成プログラム」の運営に携わり、2019年より事務局長。2021年9月から、早稲田大学研究戦略センター教授。2022年2月から、アントレプレナーシップセクション副所長 兼任。
- 書籍情報
-
-
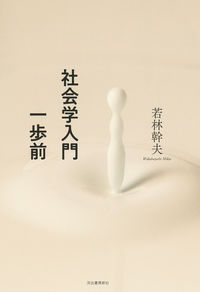
社会学入門一歩前
出版社:河出書房新社
発売日:2023/4/27
言語:日本語
単行本:240ページ
ISBN-10:4309231322
ISBN-13:978-4309231327
-

エピソード要約
-『社会学入門一歩前』の狙い
『社会学入門一歩前』のタイトルは、哲学者・廣松渉の『哲学入門一歩前』に触発されて名付けている。社会学の専門的な言葉や考えを理解する前の準備運動としての役割を果たし、学問としての社会学だけでなく、私たちの日常生活との関連性を強調し、学問に触れる前の「ストレッチ」のようなものとして位置づけている。
若林教授は『社会学入門一歩前』を社会科学の専門的な知識を持つ人だけでなく、社会を生きるあらゆる分野の人々が社会学的なセンスを発見し、社会と再び出会うきっかけになる本になればいいと述べている。
− 社会学について
社会学者のスタンスについて、距離をとって一定の価値観に立脚しないことが原則ではあるが、一方で人間は中立ではなく、そのような中立的でない人間が学問をやる上の動機として、情熱や価値観を持つことは必要であると考えている。
日常に見え隠れするさまざまな社会的構造や仕掛け、または異なる社会での「当たり前」の違いを発見できることに若林先生は社会学の魅力を感じている。
– 専門である都市論について
都市という場を作り出している社会的な関係や、人々の振る舞い等があって都市があるということを思考実験のように考えていく。それを現実に見えている都市の姿や人々の営みと重ね合わせて実証的にも考え直していくことで、都市とはどういうものなのかを理解することができてくる。
コロナウイルスの影響でリモートワークが普及し、都市に出なくても仕事や勉強が可能になったが、対面でのコミュニケーションにおける「余剰」の重要性に気づき始めた人も多くいるはずである。コロナ禍を経た今、物理的な空間でなくてもできる事が見えてきた時に、物理的な空間は人々にとってどういった意味があるのかを考え直す大きなテーマになっているのではないか、と述べている。
-「役に立つか立たないか」について
学問が直接的に「役に立つ」ことに焦点を当て過ぎると、世界を見る視野が狭くなり、人間の複雑さや社会の面白さを見落とすリスクがあり、役に立つこととそうでないことの両方が人間の喜びや楽しみを形成すると指摘している。
役に立つことだけを追求することは、時に弱者の排除や人間性の縮小につながる危険性がある。
– 大学の意味
大学は都市のような場所であり、さまざまな文化や考え方が交差する自由な出会いの場である。大学教育は、学問の自由や失敗する自由を含む多様な経験を提供し、個人の成長や視野の拡大に貢献する。
エピソード書き起こし
島岡教授(以降、島岡):
まず、若林幹夫先生のご紹介をさせていただきます。若林先生は、2005年より教育・総合科学学術院教授につき、学部では社会科公共市民学専修、大学院では社会科教育専攻で教鞭をとっています。専門は、社会学・都市論・社会的時間・空間論です。今回は、2023年に刊行されたご著書『社会学入門一歩前』の内容をベースにお話を伺います。この『博士一歩前』という番組名は、先生のご著書より拝借しております。この本のタイトルに先生が込められている意味について、お聞かせいただきたいと思います。
若林教授(以降、若林):
『社会学入門一歩前』で私が参考にした本のタイトルがあって、哲学者で廣松渉さんという方がかつておられましたけれども、廣松さんが『哲学入門一歩前』っていう本を出したんですね。私それ買って読んだんですけれども、そこで廣松さんが、『哲学入門一歩前』っていうタイトルには2つの意味があると言っていて、一つは哲学の門をくぐる一歩前、その手前でまずそれを読む。もう一つは、門をくぐってそこから一歩前に進むっていう2つの意味があるんだっていうふうに述べてたわけです。私は、社会学の入門的な面白い本で、できれば知的関心の高い高校生ぐらいでも読めるような本を書きたいなっていうふうに思っていて、廣松さんの本を読んだときに「あ、俺がやりたいのはこういうことなんじゃないかな」っていうふうに思って、それでその言葉を借りて、私の本のタイトルに『社会学入門一歩前』っていうタイトルを付けました。
島岡:
そもそも先生がこの本を執筆、特にですね、内容をまとめるにあたって、どのような活動とか取り組みとか経験が元になっているのでしょうか?
若林:
大学で社会学を教えるようになって、学問って社会学に限らずですけれども、例えば専門書があって、授業があって、学生は社会学だけではなくて社会科学全般そうかもしれないですけれども、高校までで必ずしもそういうことを勉強しているわけではない。高校までの社会科はあります。あるいは私が書いた文章も高校生が現代文の授業で習ってたりしますけれども、大学で社会学や、あるいは政治思想史や経済学ということを勉強する学問の言葉や考え方っていうのは、高校生まで勉強してきたこととちょっとギャップがあると思うんですね。でもその一方で、社会学あるいは社会科学っていうのは、私たちが生きている社会について考える学問だから、本当はみんな知ってるはずなんですよ。もちろん高校生が株式市場のことをよく知らなかったりとか、裁判所のことをよく知らないとかって当たり前ですけれども、でも社会の中を生きているのは当たり前。だから本当は私たちが社会を生きている感覚と社会科学ってどこか地続きのはずなんだけど、大学の勉強として出てくると、それがちょっと生活と勉強って距離があるっていうのがやっぱりあると思うんですね。そういう大学生たちに社会学を教えていると、学問の世界と、自分たちが生きている世界を別のものだと思って、勉強としてだけ社会学の本を読んだり授業を聞いたりっていうことが結構あるなっていうふうに思っていたわけです。それから、その社会学の思考の肝みたいなところが、うまく学生に伝わっていかないっていう感覚も社会学を教えながら結構ありました。その時にその学問の言葉で最初から教えるんじゃなくて、学問の言葉に出会って学問の思考を始める以前の準備体操っていうんですかね、ストレッチングっていうのか、体の動きをまず学問に慣れさせた上で、学問の言葉とか、あるいは大学の授業とか専門書っていうことに出会うっていうのが結構重要なんじゃないかなと思って、そういうふうに思ってこういう本を書こうと。たまたまそういう話をある編集者にしたら「いいですね」っていうふうに言ってもらえたので、自分が学生たちと話をしたり、授業をしたりしながら作っていったっていうのがこの本ですね。
島岡:
まさにその地続き、学問と社会を地続きにするとかですね、そこに入る前のストレッチっていう準備運動っていうところも先生のご著書を表すのに非常にいいお言葉だとに思っています。学生さん以外にもこの本を読んでほしい対象はいらっしゃいますでしょうか?
若林:
ある意味では対象を絞ってないっていうか、誰にでも読めるような本にしたいと思ったんですよ。社会って我々は誰でも生きてますよね。社会科学を知らなくても生きてるわけですよ。でも社会科学や社会学を知ることによって、私たちが社会を生きているっていうのは、他者達と共に同じ世界を作って、生きていて、自分自身もその他者達との関係の中で作られてるんだっていうことなんだと思うんですね。そのことを知る。そのことを知るということは、自分の人生とか他者との関わりが、この世界をより良くしていくためにも結びついていくことだと私は思ってるんですね。
だからこの『社会学入門一歩前』は、全ての人のためにある意味で書かれていて、実は内容的にはかなり専門的な、社会学の理論として極めて重要なコアになる部分を私は書いたと思っていて、でも同時にそれは誰でも読めて、この本の中にも書きましたけど、例えばスポーツでプロの、大谷選手とかメッシ選手とか、極めてレベルの高いプレイってあるじゃないですか。あれ素晴らしいですよね。社会科学でもそういうプロの仕事ってあるわけだけど、でも同時に草野球とか、職場の仲間とやるサッカーとかもあるわけじゃないですか。それもまた楽しいわけでしょ。社会科学、社会学にもそういうアマチュアのプレイがあっていいし、あるべきだなって思うんですよね。だからこの本に会った人が自分で社会学をする、社会学的に考えることができるような、そういう本にしたいと思って書いたので、あらゆる分野の人が読んで社会学的なセンスを発見して、社会と出会い直すっていうことができたらいいなと思ってますね。
島岡:
私も先生のご著書を拝読させていただいて、おっしゃるように、すごく本当は難しい内容を、私みたいなこの分野の素人にもわかるように書いてくださっている。あとピックアップされているテーマが非常に幅広くて、私はこの本を読んで、すごく自分が元気になったっていうか、自分と社会の関係っていうのを相対的に捉えるっていう視点が貫いて、やっぱり人を元気づけるような、そんな本に思ったんですね。
今日先生にお会いする前までは、先生のことは直接には存じ上げなかったんですけど、お会いして、この本だともう少しクールな感じ? クールというか、俯瞰的に全てを見ておられるような感じもしたんですけど、実際先生に会ってみると、やっぱりすごく想いというか、社会を良くしたいとか、そういう想いをすごく感じております。
私が実はお聞きしたかったのは、社会学者っていうのは、何かのポジションを取るべきなのか、あるいは完全に俯瞰して社会を分析すべきなのか。この辺について、社会学者のスタンスってどういうふうに先生は思いますか?
若林:
学問をするっていう点では、まず第一には距離をとって、一定の価値観に立脚しないっていうのが社会学の原則だと思うんですよ。社会学だと、古典的な学者でマックス・ウェーバーっているじゃないですか。ウェーバーが「価値・自由」っていうことを言ったわけだけど、学問的には。人間は価値観を持って当たり前なんですよ、どんな人でもね、こう生きたいとか、こういう世の中がいいとか思うじゃないですか。でも、学者としてはそういう自分の価値観も、あるいは世の中で支配的な価値観も、括弧にくくった上で。もう一人社会学の巨匠の名前を挙げれば、エミール・デュルケムって人がいて、デュルケムは「社会を物のように見よ」って言ったわけですけど、「まるで物であるかのように客観的に見ることが重要だ」と。これは私もそう思ってます。
でも、同時に学問って、じゃあなんでそういう見方をするのかっていうと、そういうことをやろうっていう動機があるわけじゃないですか。で、それはもちろん社会が理解できて面白いっていうのがあります。私もそれが一番大きな動機だけれども、同時に私たちは社会を生きていく中で、いろいろこれはちょっとおかしいんじゃないかと思ったりとか、これは嫌だなと思ったりとかってことありますよね。そういうことに対して、これはこういうことだから嫌だったんだとかね。これは今こうなってるけど、別の生き方もあるよねっていうようなことを理解、あるいはもっと政策的にこういうことが問題になってるけど、こういう立場に立って考えたらこういう解き方もありますよね。だからこういう政策を立てると、別の何かいい方向に行けるかもしれませんよっていうような提言をすることもできるわけじゃないですか。そういうことに役立てたら嬉しいですよね。私自分で研究やってて、特になにか役に立つために書いたものじゃなくても、人から先生の本を読んで、なんかこういうことができるんじゃないかとか、元気が出ましたとか言われて、やっぱ嬉しいわけですよ。
学問は中立的だけど、人間って中立的じゃなくて、中立的じゃない人間がやってて、そうすると学問やっていく上でも何か動機として、そういう情熱とか価値観みたいなものって絶対必要だと思うんですよ。だから学問やってく上ではどっちも必要だと思いますね。
島岡:
やっぱりこういうパッションが先生方の研究を押してるんだなと思うんですけど、先生は社会学をやっていて、面白いなって思う瞬間って、例えばどんな瞬間ですか?
若林:
ある存在が、例えば都市やあるいは都市の文化でも、あるわけじゃないですか。当たり前のようにありますよね。外に出れば街があるし、人が歩いてるし、いろんなことが起こってるわけだけど。でもその向こう側にある仕掛けがあったりとか、あるいはこれは今私たちの社会だと当たり前だと思ってるけど、他の社会だと全然当たり前じゃないことで、その「当たり前さ」と「当たり前じゃなさ」みたいなものを生み出してるのは何に拠っているんだろうかとか、そういうことが見える瞬間ってあったりするんですよね。そこが面白いところですかね。私にとっての社会学をやってることの魅力の一つはそこかなと思いますね。
島岡:
先生が面白いなって思う「発見する」っていうのは、どういうふうに発見するんですか?例えばいろいろ観察したりとかいろいろあるじゃないですか。
若林:
すごく難しいことなんですけど、いろんなタイプの発見の仕方ってあると思うんですけど、私の場合には、ある出来事を抽象的なパターンで捉え直すってことが結構あって、例えば私の専門「都市」ですけれども、都市って(そこに)あるじゃないですか。でも都市があるってどういうことなのかっていうことを最初に考えようと思ったんですよ。都市があるっていうのは、実は都市は都市だけであるわけじゃなくて、学生によく授業で話すんですけど、今の東京をそのまま火星に移転させたとしたらそれは都市だと思う? 火星に行った途端にね、東京だけポツンとあっても、それは都市じゃないと思うんですよ。東京が都市であるのは、他の地方とか世界の他の都市とか地域との関係の中で人が流れ込んだり、東京から情報が発信されたりする、関係の中で都市が都市として出来上がってるんですよね。あるいは、今ある東京から人がみんな消えちゃったらどうなると思う? その時東京は都市って言える? って質問を学生に授業でするんですけど、これは都市の遺跡ではあっても都市じゃないでしょ。つまり、人がある活動をして、でもそこで農村でやってるようなことをやっても都市には絶対ならないわけですよね、都市っていう場を作り出している社会的な関係とか、人々の振る舞いとかがあって都市があるんだっていうことを思考実験みたいに考えていく。それを現実に見えている都市の姿とか、人々の営みと重ね合わせて実証的にも考え直してみる。そういうことをすると、「あ、都市ってこういうものなのね」ということが例えば分かってくるっていう、そういう考え方をしますかね、私の場合にはね。
島岡:
今やっぱり都市ってものすごく流動的というか、人流が激しいですし、東京を目指して世界からいろんな人が来たりしてますよね。この辺の現代的な都市っていうのは、今やっぱりコロナを経て、都市っていうのは変わってるんでしょうかね。
若林:
都市に出なくても実は我々は仕事も勉強もできるんだなっていうことを多分コロナの中で経験したってことあると思うんですよ。でも、それだとなんか足りないものもあるかもっていうこともみんな気がついたんじゃないかなと思うんですよね。例えば大学でよく話をするんですけど、大学の会議がオンラインになりました。で、オンラインになってほとんどの教員は喜んでると思うんですよ。会議のために大学に出てこなくて。でもね、なんか足りない。何が足りないのかっていうと、会議の途中で隣の人とコソコソ話したり、会議の前後に話をしたりっていう、そういう会議の本筋から考えたら余計に思えるような、なくても済んでいたかもしれないコミュニケーションが実は意味があったことに気がついた人も結構いると思うんですよ。
つまり社会ってね、社会学でも社会ってある種の機能的なシステムとして考えることがあります。機能的なシステムが高度化して、合理化していくっていうのが近代だという捉え方もあります。でも、私たちが生きている社会って、同時にそれに対するある意味で余剰というか、余分に見えるような部分こそが社会の面白いところとか、あるいはそういうところがあってこそ、ある種の効率性が上がることもあるんだと思うんですよ。そういう、つまり物理的な空間じゃなくてもできることが見えてきた時に、じゃあ物理的な空間って私たちにとってどういう意味があるんだろうっていうことが、再度私たちにとっての大きなテーマになるということはあるんだと思うんですよね。コロナを通して見えてきた都市の問題、あるいは都市の問題っていうよりも、都市を考えるための視覚っていうんですかね。そういうことが一つあるかなと思ってますね。
島岡:
今、余剰っていうお話も出たので、先生のご著書の方にちょっと戻らせていただきますと、先生がこの中でも述べられている「役に立つか立たないか」。これも非常に面白い議論だと思うんですけど、先生からご説明いただけますか。
若林:
まず私は個人的には、あんまり役に立つ学問をしてない感が自分ではあって、直接的にはね、例えばこのことを先生の本を読むと何か役に立つんですかって学生に聞かれても難しいなって思っているわけですよ。でも、役に立つことだけを考えて、役に立つための知識を増やしていくことって、本当に役に立つんだろうかとも思うんですよね。
つまり、役に立つという時は、ある種の目的があって、目的のために合理的であるかどうかで判断されるわけですよね。その時に世界を見る見方がある価値観の尺度によって決定されますよね。でも人間にとって、楽しいこととか面白いこととか有意義なことって、いわゆる役に立つことももちろん重要で必要なんだけど、そうじゃない部分もあるわけじゃないですか。そうじゃないことの喜びとか楽しさっていうこと、そうしたことにこだわっていたり、例えばね、不健康だけど楽しいことってあるじゃないですか。不健康だけど楽しいことっていうのは世の中にあっちゃいけないのかって考えると、不健康だけど楽しいことがない世の中の方が不健康かもしれないっていう気も私はして。そういう、何て言うんだろう、人間の複雑さとか社会の面白さ、あるいは役立つっていうこと自体が役立たないことも含めて支えられていたりするような、そういうことが見えなくなっちゃうと思うんですよね多分、役立つことだけで考えていると。その意味で、役に立つことが無意味だとは全然思わないですけど、役に立つことがたくさんあったほうがいいと思いますけど、役に立つことで頭が固くなってしまうことはすごく良くないことだと思いますね。
島岡:
先生もこのご著書の中で役に立つっていうことだけを考えていくと視野が非常に狭くなると、まさに私もそのとおりだと思っていて、私もアントレプレナーシップ教育とかイノベーションに関わってますけども、やもすると役に立つことだけを求める、そこだけに集中しがちなんですね、効率的とかそういうのを考えていくと。でもやっぱりその周りにはものすごくいろんな無駄とか失敗とかが山のようにある。そのことが別に役に立つことに向かっていかなくてもいいと思うんですけど、その辺の全体感を見失うなっていつも思っていて、やっぱり役に立つっていうのが役に立つのか、社会学が役に立つのかっていうのを括弧書きでいろんな言い方でされてますけども。
若林:
本質的な意味では役に立つと思ってます、私は。でもそれは、世の中で言われている意味での役に立つっていうことを相対化するという点でも役に立つんだと思う。例えば役に立つっていう考え方は場合によってはすごく危険ですよね。役に立たない人はいなくてもいいのかという議論を招き寄せますよね。それは弱者を排除したりとか、そうしたことにつながっていく可能性がある考え方。でも人は、そこにいること、幸せであることと、あるいは楽しいことと、役に立つことっていうのは必ずしも結びつかないような生き方をする生き物ですよね。それを役に立つことのためにという回路で考えていくと、すごく人間も思考も痩せ細っていくんじゃないかなって思いますよね。
島岡:
そうですね。今の価値観での役に立たないかっていうことなので、これが50年、100年、150年っていうふうに考えたときに常に変わっていくものもあって、今の役に立つっていうところだけに縛られていくのはどうか? そういう問題提起を社会学っていうのはしてるんじゃないかなって思いました。
ではここから「社会学の観点から問う」っていうタイトルで、社会学的な観点から世の中を考えてみるということで、私が一番お聞きしたいと思っていたのが、今の時代に大学で学ぶ意味。先生もご著書の中でその大学教育におけるスキルと学問とかですね、大学の意味っていうのを語っておられまして、私もこういう企業家教育、アントレプレナーシップ教育をしてると、大学ってどういう意味があるのって学生からも聞かれることがあるんですね。
若林:
大学って都市みたいな場所だと思うんですよ。私が若い頃から付き合っていて、研究上も影響を受けている吉見俊哉さんという方がいるんです。彼も大学って都市だっていうふうに言ってるんですけど、どういう意味かというと、私の都市論の理論とも関係あるんですが、都市って共同体とか村とか部族とか他の都市とか国とかから人々がやってきて出会う場所ですよね。いろいろなものの間で、その人たちがそれまで属していた文化とかルールとか考え方から一旦解放されて自由になれるような場所。それが都市というものの基底にある社会的な場のあり方だと思うんですよ。
大学もある社会の中で例えば4年間勉強するわけだけど、大学生って勉強だけじゃなくていろんなことしますよね。それは、別にそれが例えば利益が上がるとか、ものすごく役に立つとか、もちろん大学出た後役に立った方がいいと思いますけど、そういうことを考えないでいろんなことを試すことができる。それからさまざまな考え方、もともと自分が知らなかった考え方とか、自分の価値や心情とは違うかもしれないような考え方に出会うことができる、そういう自由な出会いの場所なんだと思うんです。そういう自由な出会いの場所に4年間、もっといてもいいんですけど、いることによって自分の考え方とか経験とかをすることができる。そうした自由、これは失敗することの自由も含めて、失敗したっていいじゃないか大学時代だからと思うこともできますよね。あるいはそこで今まで知らなかった全く新しいものと出会って、大学に入る前とは違う自分になることができる、そういうのが大学っていう場所だと思うんですね。
その中の核になるものとして学問があると思うんです。それは学問というのも実は都市みたいなもので、日常的な考え方とか道徳とか偏見とかそういうものから自由に、理性と事実を手がかりにして、何かを考えて発見して、あるいは作り出していくっていうのは学問だと思うんですよね。そういう都市的な場所で都市的に生きる。それによって自分を豊かにし、そこで得たものを社会に持ち帰って、社会をより良い場所にしていく、ということのために大学があって。そうだとすると、大学で勉強することって、大学は自動車教習所ではないので、すぐにこのライセンスを取ったらこれができますみたいなことじゃなくて、考え方とか何かをやることの手札を増やすっていうのかな、そういうことができる場所だと思うんですよね。それが世の中、さっきの役に立つじゃないけど、すごく役に立つことが求められていたり、効率性が求められていたりしますけど、そういうのがあればあるほど、大学っていう都市的な場、学問っていう都市的な地っていうものが意味あるんじゃないかなと思いますね。
島岡:
このご著書が、もともとは2007年に刊行されておられて、2023年に復刊、名著復活って書いてありますが、やはり今の非常に先行きも不透明な時代っていうのもあるかもしれませんが、なぜ今これが復活、世の中で求められているのでしょうか?
若林:
『社会学入門一歩前』って最初の方にもお話しましたが、私にとっては、全ての人に向けて書いた結構思い入れのある本で、たくさんの人にも読んでもらえたと思っているんですよ。
でも、しばらく品切れになっていて、ぜひもう一回命を与えたいなって思っていた時に、長く付き合っていた編集者の方と、たまたま、私が学生時代に出会ってすごく影響を受けた見田宗介という社会学者がいるんですが、その先生を偲ぶ会で編集者の方と会って、あの本もう一回出たらいいなと思うんだけど、一緒にやりませんかって言ったら、ぜひやりましょうって言ってもらって、それでこういう形で復刊することができたっていう、成り行きといえば成り行きですけれども、でもそういう形でもう一回この新しい形で出すことができたっていうことなんですね。
島岡:
ありがとうございます。またより多くの人にですね、この本を手に取っていただいて、元気に、複眼的な目を持ってある意味ですね、世の中と自分の関係を見つめ直しながら前向きにいけるような、そんな本だと思いますので、ぜひ皆さんに手に取っていただきたいなというふうに思っております。






