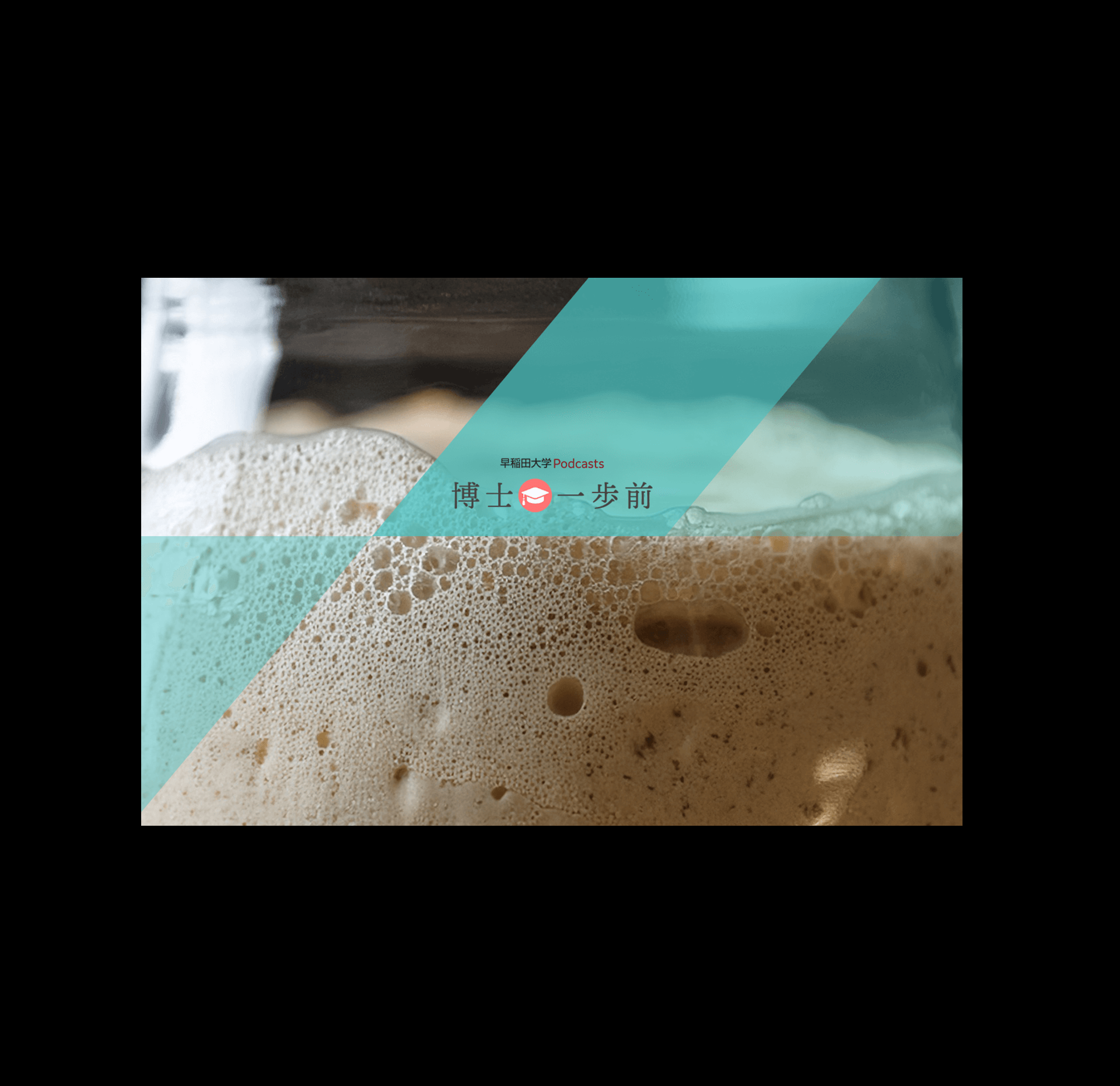- Featured Article
Vol.14 発酵メディア学(2/2)/ 【問いに伴走し共に解く】学生の好奇心に火を灯す『発酵メディア研究ゼミ』 / ドミニク・チェン教授
Thu 12 Feb 26
Thu 12 Feb 26
文学学術院のドミニク・チェン教授を迎えてのシリーズ後編では、学生たちの切実な違和感に伴走する「ゼミ運営」の現場と、大学という場所の意義を深掘りします。
「アバターファッションを通じた自己表現」や「訪問看護における電子カルテが患者・看護師の関係に及ぼす影響」など、チェン先生のゼミで取り扱うテーマは多岐にわたります。学生一人ひとりが抱く多様な問題意識を尊重し、先生自身は「自分のテーマを押し付けない伴走者」として共に研究手法を開拓する──。そんな『発酵メディア研究ゼミ』での熱い対話の裏側を伺います。
さらに、チェン先生は効率至上主義の社会で、あえて立ち止まり「良い問い」を育てることにも言及。大学という知の最前線で起きている、静かでクリエイティブな実験の記録です。
【前編エピソードはこちら】
配信サービス一覧
ゲスト:ドミニク・チェン
早稲田大学文学学術院教授。1981年生まれ、フランス国籍。2013年東京大学 学際情報学 博士号を取得。NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]研究員、NPO法人クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(現コモンスフィア)理事、株式会社ディヴィデュアル共同創業者等を経て、2017年4月から早稲田大学文化構想学部准教授、2022年より現職。 デジタル・ウェルビーイングの視点から、テクノロジーと人間・自然存在の関係性を研究。
ホスト:井上 素子
研究戦略センター准教授。専門は研究戦略・推進、美術史学、文化財保存学。2014年筑波大学人間総合科学研究科芸術専攻博士課程修了、博士(芸術学)。2013年 国立文化財機構 東京国立博物館保存修復課アソシエイトフェロー、2018年 東京工業大学研究・産学連携本部主任URA等を経て、2025年4月から現職。

左から、井上素子准教授、ドミニク・チェン教授。
早稲田大学国際文学館(村上春樹ライブラリ)のスタジオで収録。
エピソード要約
ー研究者への転機と、大学という「立ち止まる場」
ドミニク・チェン教授は、博士課程在籍中に起業し、テクノロジー産業の現場で活動する中で、情報技術が人間の心理や心に及ぼす影響の大きさに違和感を抱くようになりました。スマートフォンやSNSの広がりが社会に与える変化を見つめる中で、テクノロジーを腰を据えて研究したいという思いが強まり、再び研究の道へ。現在は、本を読み「問いをじっくり育てられる」大学の環境に研究者としての喜びを感じ、加速する社会の中で立ち止まってテクノロジーと向き合う重要性を語ります。
ーSNS・生成AIへの問題意識と「摩擦」を取り戻す試み
既存SNSに新たに生成AIの発展・普及によって、想定される問題から距離を置くのではなく、どのように向き合っていくかについても、自身の身をもった新たな実験的姿勢を示しています。さらに生成AIの普及についても、情報の効率化や“ファストフード化”が思考の「摩擦」を奪うことを危惧。あえて「分かりにくさ」や「遅延」を取り入れることで、人間に立ち止まって考えさせる「望ましいAIの姿」を模索しています。
ー教育と研究の現場:ゼミ展示と「伴走者」としての指導
大学教育では、指標化できる学術的成果だけでなく、人文系の学生が社会で発揮できるアウトプットとして、グループ制作による学外向けの展示活動「ゼミ展示」を重視しています。ゼミではメタバース、人間拡張、ケアの現場における電子カルテなど、学生自身の切実な問題意識を尊重し、チェン教授は特定のテーマを押し付けるのではなく、テクノロジーを多角的に批判・批評するための手法を共に開拓する「伴走者」として指導にあたっています。加えて、「リサーチ・スルー・デザイン」を用い、ジャーナリングツール「Pickles」などの開発を通じてAIの影響を探究しています。
エピソード書き起こし
井上准教授(以下、「井上」):
本日も、早稲田大学早稲田キャンパス内にある村上春樹ライブラリー(国際文学館)2階の収録スタジオから、情報学をご専門とされるドミニク・チェン先生をゲストにお迎えし、「意味の多様性を紡ぐ ― 発酵のメカニズムから見る情報技術の新たな可能性」をテーマにお話をお届けします。
後半では、チェン先生が研究の道へ進まれたきっかけや、ゼミ運営の現場、そしてAIとの適切な距離感について、さらに深く伺ってまいります。チェン先生、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
ドミニク・チェン教授(以下、「チェン」):
よろしくお願いします。
井上:
まずは、チェン先生ご自身がなぜ研究の道に進まれたのか、そのきっかけから伺えますでしょうか。
チェン:
私は博士課程在籍中に休学して起業しており、博士論文を提出するまでに実に7年かかりました。あまり褒められないアカデミックなキャリアの始まりかもしれませんが、博士取得後も会社経営を続け、2017年に早稲田に着任しました。研究の道へ本格的に向かうきっかけはいくつかありますが、簡単に言えば、加速していくテクノロジー産業のただ中にいるほど、違和感が増えていったことです。端的に言うと、会社で作っていた情報技術や情報サービスが、本当に人々にとって良いものとして届けられているのか、という問いです。プロダクトとしては、ユーザーがつき、対価をいただくことで一定の評価はされるかもしれません。
しかしそれ以上に、情報技術が私たち一人ひとりの心理、つまり心の領域に深い影響を及ぼしているのではないかということが、現場にいながらずっと気になっていました。ちょうど2010年代後半、スマートフォンが登場してから約10年が経った頃です。スティーブ・ジョブズの有名なプレゼンもあり、私自身も興奮し、アプリケーションを作り始めました。ところが次第に、スマートフォンに依存する人が増え、SNSが過密化する中で社会的分断が見えるようになっていく。そうした変化を目の当たりにして、テクノロジーをめぐる言説が楽観的すぎるのではないか、という違和感が自分の中で大きくなっていきました。会社を事業譲渡するタイミングでもあり、ここで一度、テクノロジーを腰を据えて研究したいという思いが抑えられなくなりました。会社の仲間にも相談し、快く送り出してもらえたことには、今でも感謝しています。
井上:
ありがとうございます。今「SNS」というお話もありましたが、先生は普段SNSはお使いなのでしょうか。
チェン:
2000年代前半からFacebookやTwitter、Instagramも初期から使っていました。ただ、昨年4月にすべてのアカウントを削除しました。自分の中では、ある種の実験でもありました。
一つには、プラットフォームを運営する企業や経営者の思想、そして社会的な言動に、倫理的に大きな問題があると感じるようになったことです。たとえば、イーロン・マスク氏やマーク・ザッカーバーグ氏の言動には、利用者の心理や「利用者にとっての良い人生」を軽視しているように見えるものが目立ちます。言動だけでなく、プラットフォームの設計にも問題があることが次第に露呈していく中で、昨年の春先に我慢の緒が切れ、「これは消さねばならぬ」と思って削除しました。
井上:
ありがとうございます。今「良い人生の軽視」という言葉も出ましたが、「良い人生」を考えると教育とも関わってくるように感じます。
先生は「発酵メディア研究ゼミ」を主催されていますが、教育についても伺えますでしょうか。芸術や情報学など学際的な領域を扱う中で、学生の学びを成果としてアウトプットに結びつける際に、意識されていることはありますか。
チェン:
まず「成果」とは何か、という話になりますよね。大学で言えば論文や学会発表など、いわゆるアカデミックレコードとして指標化される成果があります。大学院では研究者の道に入りますから、その積み重ねはもちろん重要です。ただ、学部、とりわけ人文系の学部では大学院に進学する人が少なく、企業に就職して研究者以外のキャリアを歩む学生も多い。そうした学生にとっては、アカデミックな成果とは別のアウトプットもあり得るのではないかと考えています。
そこで私のゼミでは、卒業論文だけでなく、毎年「ゼミ展示」を行っています。学生たちにグループ制作で作品を作ってもらい、学外の方にも開いた形で展示する取り組みです。
井上:
なるほど。ゼミとして展示も実施されているんですね。ありがとうございます。話題を少し広げて、AIとの付き合い方について伺います。学生だけでなく教員も直面している問題だと思います。先生のご著書では「読み言葉」「書き言葉」「聞くこと」について多く触れられていましたが、急速に展開が進むAIを、これらとの関係からどのように捉えていらっしゃいますか。
チェン:
大きく言うと、SNSの問題の上にAIの問題が重なってきている、というのが現状だと思っています。
ChatGPTが出てきたとき、私は非常に衝撃を受けました。ここまで人間らしい、あるいはそれっぽい文章を高速に出力できるのかと。そのとき真っ先に考えたのは、それが私たちの生き方にどう影響するのか、という点です。十分な検証もないまま、OpenAIがそうした技術を社会に出してしまったことの無責任さに、第一印象としては憤りも感じました。ただ、怒っていても技術は社会に浸透していきます。私も完全に距離を置くのではなく、使いながら問題点と可能性を理解しようと思い、その一環として「Pickles(ピクルス)」というツールを自分で作りました。AIを使うプロジェクトを通して、AIの問題点や私たちへの影響を捉えようとしている、ということです。結論にはまだ至っていませんが、ジャーナリングの文章をAIに読ませ、レスポンスを書いてもらうなどの試行を重ねる中で、私が一番強く意識するのは「摩擦」です。たとえば会話では、言い淀んだり、考えをうまく言葉にできなかったりします。私はそうした過程を「摩擦」と呼んでいます。ところがAIの登場によって、「摩擦がないほうが良い」という風潮が加速しているように感じるのです。たとえばAIに聞くと、箇条書きで返ってくることが多い。箇条書きは分かりやすく、摩擦なく飲み込めるように情報を“ファストフード化”してしまう。助けになる場面ももちろんありますが、文学や芸術のように、摩擦や違和感、立ち止まる時間も含めて経験する領域では、美的体験を阻害する側面もあるのではないかと思います。つまり、あらゆる知識を分かりやすく整理することが常に正義なのか、という問いです。効率化や時短に思考や認識が収斂していくことへの危機感もあります。だから私はAIに対して「箇条書きにするな」という命令を必ず入れています。箇条書きで返ってきたら「それじゃダメだ」と。
井上:
言い淀みや会話の間に触れる機会が減っている、というのは確かに日常でも感じます。箇条書きの話も、とても腑に落ちました。ありがとうございます。先ほどPicklesのお話が出ましたが、生成AIについて先生が感じていることは、Picklesの制作過程にも影響しているのでしょうか。
チェン:
はい。私が採っている研究手法の一つに「リサーチ・スルー・デザイン(Research Through Design)」があります。日本語で言うと「デザインを通した研究」です。イギリスのRCAという美大で生まれた手法です。通常のデザインは「こういう目的がある」「こういう素晴らしいAIを作れば、これだけ良いことがある」と仮説を立て、作り方を議論します。
一方、リサーチ・スルー・デザインでは、「AIは人間にどう影響を及ぼすのか」という問いそのものが出発点になります。その問いに近づくために、ものをデザインしていく研究手法です。
井上:
リサーチ・スルー・デザイン、ですね。
チェン:
そうです。「リサーチするデザイン」ではなく、Through=通り抜ける、ですね。Picklesはまさにこの手法として、可能性にワクワクしつつも、懐疑的な目で自分の作っているものを見続ける、いわばダブルバインドな視点で取り組んでいます。Picklesは作品というより、問いを考えるための道具です。Nukabotも同じです。Picklesを通して、箇条書きの問題にも気づきましたし、応答の時間設計にも発見がありました。Picklesは1週間に一度、AIがジャーナルを読んで返信する仕組みにしていますが、テスターの方が今40〜50人ほどいて、「ChatGPTは即答してくれるけれど、Picklesは1週間の遅延があるから、対等な相手と手紙をやり取りしているような気持ちになる」というフィードバックをいただいたんです。つまり、チャット形式の生成AIとは異なる時間軸を設計できる。その発見はとても面白かったですね。
そうなると、内容だけではなく、応答の時間や、曖昧さを応答に含めることも可能になります。分かりやすくするのではなく、少し謎めいた表現で返してもらう。詩的な手紙風に書いてもらう。そういうプロンプトを試すことで、受け取った人が「はいはい、そういうことね」と摩擦なく飲み込むのではなく、メールを開いてしばし立ち止まる。「これはどういうことだ?」と考える。分かりにくいことが良い、という話ではありません。ただ、自分に関係しつつ、考えさせてくれる情報をどう生成できるか。Picklesを通して、望ましいAIの姿が少しずつイメージできてきている段階です。
井上:
非常に興味深いお話です。1週間に一度という設定も「意外とゆっくりだな」と思っていましたが、その背景がよく分かりました。最近は「問いを立てる力が求められる」「AIで代替されないものは何か」といった議論も多いですが、まさにそこにもつながるお話だと感じました。少し話を戻します。先生のもとで学ばれている学生さんは、どのような方が多いのでしょうか。
チェン:
大学院では修士の学生を迎えてきましたが、テーマは本当にそれぞれ違います。必ずしもそうとは限りませんが、テクノロジーを社会の主流とは少し違う視点から捉える研究が多い印象です。たとえば今いる学生の例で言うと、一人はメタバース空間でアバターのファッションを着替えることが、操作する人の心理やファッション感覚にどう影響するかを扱う「バーチャルファッションスタディーズ」を研究しています。もう一人は「人間拡張(Human Augmentation)」という工学分野の概念に対して、エイブリズム(Ableism)の問題が潜んでいないかを問い、障害学やケアの視点から、テクノロジー設計とどう接合できるかを探っています。
他にも、精神看護の現場で電子カルテが訪問看護師の考え方や患者さんとの関係にどう影響するか、といったテーマもあります。私は学生に自分の研究テーマを押し付けたくありません。むしろ教えてほしいと思っています。私が提供できるのは、テクノロジーという媒介をどう批評的・批判的に捉えるか、その研究手法を一緒に開拓していく伴走者としての役割です。現代のテクノロジーを、ただ礼賛するでも、ただ全否定するでもなく、その中間で、可能性と問題の両方を複雑に捉えたい人には向いていると思います。
井上:
情報学、芸術、社会学的な視点まで、多様な観点が学生さんの中から立ち上がっていることがよく分かりました。ありがとうございます。最後に、起業を経て大学に移られた先生にとって、研究者として大学に戻って良かったこと、そしてリスナーへのメッセージがあればお願いします。
チェン:
会社時代はなかなか本も読めず、美術館にも行けず、文化的に貧しい生活だった、という話をしていました。もちろん集中して取り組んだからこそ、そこで培った技術や経験は今に生きていると思います。大学に来て8年ほど経ちますが、本を読み、自分の問いを育てられる環境で仕事ができることが、研究者として一番の喜びです。それこそが「研究者として良い生き方ができる」ということなのかもしれません。問いをじっくり育てたい人、あるいは、加速し続けるテクノロジーに対して「ちょっと待った!」をかけ、腰を据えて向き合いたい人にとって、大学という環境はとても良い場所なのではないかと思います。
井上:
ありがとうございます。『早稲田大学Podcasts:博士一歩前』。今回は、ドミニク・チェン先生とともに「意味の多様性を紡ぐ ― 発酵のメカニズムから見る情報技術の新たな可能性」をテーマにお話をお届けしてまいりました。本日お招きしたのは、早稲田大学文学学術院のドミニク・チェン先生でした。チェン先生、ありがとうございました。
チェン:
ありがとうございました。