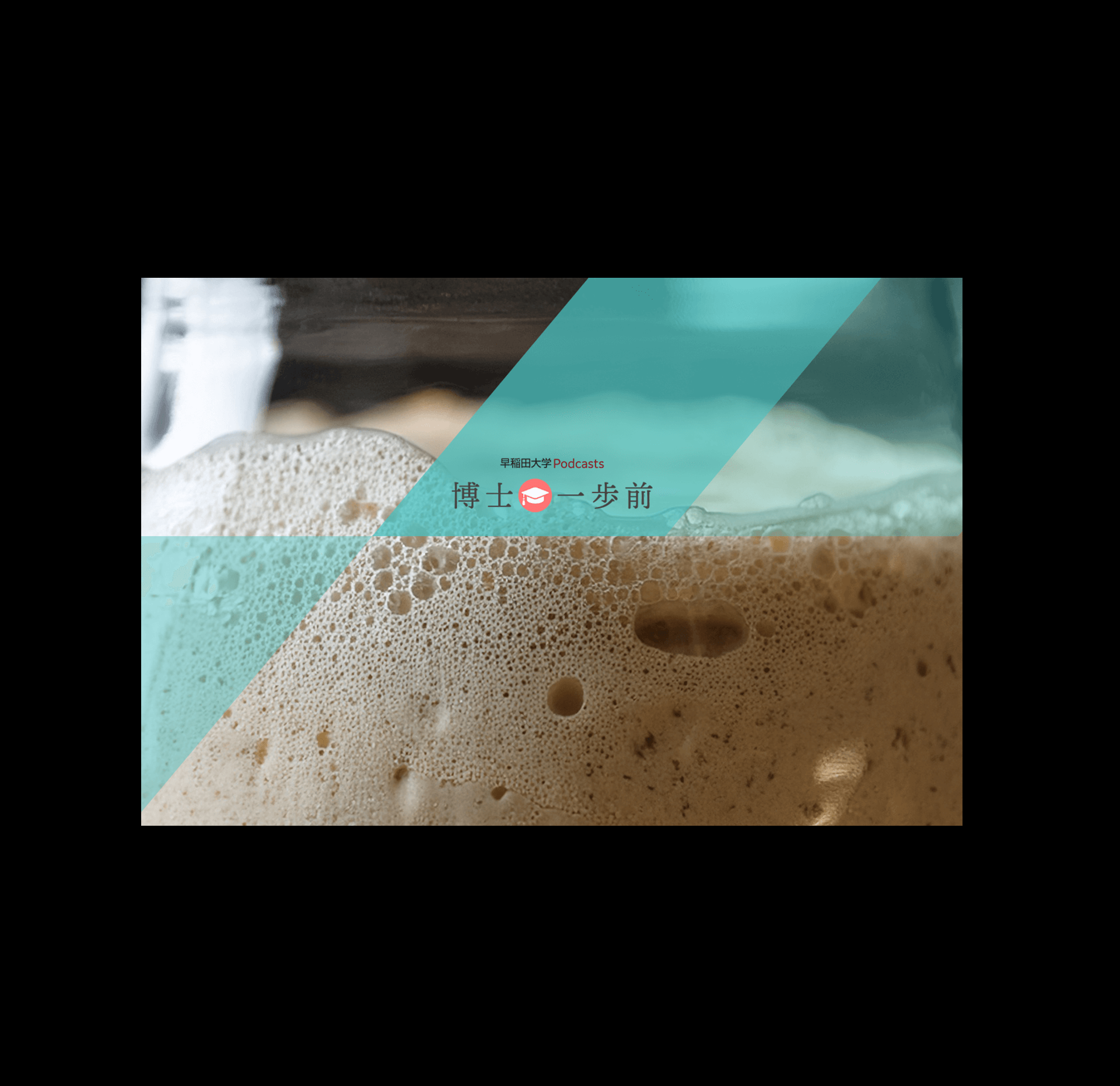- Featured Article
Vol.14 発酵メディア学(1/2)/ 【情報技術に「発酵」は足りているか?】非効率は「悪」なのか?「思考の熟成」という価値 / ドミニク・チェン教授
Thu 05 Feb 26
Thu 05 Feb 26
今回と次回の2回にわたって、早稲田大学文学学術院のドミニク・チェン教授をゲストに、「意味の多様性を紡ぐ― 発酵のメカニズムから見る情報技術の新たな可能性」をテーマにお届けします。
先生自身の多文化な背景から導き出された「翻訳」という視点を軸に、人間と微生物という本来分かり合えない存在とのコミュニケーションの可能性を追求しています。
エピソードでは、ぬか床を腐らせた実体験から着想を得た研究や、あえて「待つ」プロセスをテクノロジーに組み込むことで生まれる思考の熟成。
効率化の先にある「委ねる」デザインが私たちの生活をどう豊かにするのか、知的好奇心を刺激する「発酵メディア学」の世界を紐解きます。
【後編エピソードはこちら】
配信サービス一覧
ゲスト:ドミニク・チェン
早稲田大学文学学術院教授。1981年生まれ、フランス国籍。2013年東京大学 学際情報学 博士号を取得。NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]研究員、NPO法人クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(現コモンスフィア)理事、株式会社ディヴィデュアル共同創業者等を経て、2017年4月から早稲田大学文化構想学部准教授、2022年より現職。 デジタル・ウェルビーイングの視点から、テクノロジーと人間・自然存在の関係性を研究。
ホスト:井上 素子
研究戦略センター准教授。専門は研究戦略・推進、美術史学、文化財保存学。2014年筑波大学人間総合科学研究科芸術専攻博士課程修了、博士(芸術学)。2013年 国立文化財機構 東京国立博物館保存修復課アソシエイトフェロー、2018年 東京工業大学研究・産学連携本部主任URA等を経て、2025年4月から現職。

左から、井上素子准教授、ドミニク・チェン教授。
早稲田大学国際文学館(村上春樹ライブラリ)のスタジオで収録。
エピソード要約
ー研究領域の全体像と「発酵メディア学」
ドミニク・チェン教授は、情報技術を用いて人間同士のコミュニケーションの「場」をいかに設計できるかを探究してきました。近年は関心を人間以外の存在にも広げ、微生物のような生き物を射程に含めた研究として「発酵メディア学」を提唱・実践しています。人と技術、人と自然存在の関係性を捉え直す視点から、テクノロジーデザインの新たな可能性を探っています。
ー研究における問い:翻訳・不完全さ・協働
チェン教授の研究を貫くのは、多文化・多言語のルーツに根ざした「翻訳」への関心と、「人は本当に分かり合えるのか」というライフワークの問いです。コミュニケーションは完全な情報伝達ではなく、こぼれ落ちるものを含みながらも、イメージに向かって少しずつ近づく営みである—その前提に立ち、不完全さの中でいかに合意形成やコラボレーションが可能になるのかを探究しています。
ーNukabotとPickles
チェン教授は、発酵という時間軸を手がかりに、現代の情報技術が生むスピード感を捉え直す実践にも取り組んでいます。「Nukabot」では、ぬか床を一晩で腐らせた喪失体験を起点に、微生物への愛着やケアのあり方を問い直し、センサーと音声合成によってぬか床に「行為主体性」を付与する試みを展開しています。さらにAIを活用したジャーナリング支援「Pickles」では、「謎床」の発想を応用し、AIが学生の私的な記述にフィードバックすることで、自己との対話や研究の継続を支える仕組みを構築しています。
エピソード書き起こし
井上准教授(以下、「井上」):
本日も、早稲田大学早稲田キャンパス内にある村上春樹ライブラリー(国際文学館)2階の収録スタジオから、前回に引き続き文学学術院シリーズをお届けします。今回と次回の2回にわたり、早稲田大学文学学術院で情報学をご専門とされるドミニク・チェン先生をお迎えし、「意味の多様性を紡ぐ―発酵のメカニズムから見る情報技術の新たな可能性」をテーマにお話を伺います。発酵という概念に基づいたテクノロジーデザインの研究について、その核心的な問いと社会への示唆を探ってまいります。チェン先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
ドミニク・チェン教授(以下、「チェン」):
よろしくお願いいたします。
井上:
まずは先生のプロフィールをご紹介します。ドミニク・チェン先生はフランス国籍で、1981年生まれ。2013年3月に東京大学で博士号(学際情報学)を取得後、NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]の研究員を務められました。その後、NPOクリエイティブ・コモンズ・ジャパン(現在のコモンスフィア)を立ち上げ、理事に就任されています。
また2008年には株式会社ディヴィデュアルを創業し、2018年1月にスマートニュース株式会社にM&Aされました。2017年4月から早稲田大学文化構想学部准教授、2022年からは同大学教授として活躍されています。デジタルウェルビーイングの視点から、テクノロジーと人間・自然存在の関係性を研究テーマとされています。
あらためて、先生の研究分野の概要をご説明いただけますでしょうか。
チェン:
私はもともと、インターネットや情報技術を使って、人と人がどのようにつながり、コミュニケーションできるのか、その「場」をどう設計できるのかを研究してきました。研究しながらものを作り、実際に場をつくって実践し、その取り組みを分析・評価する、といった形で博士論文を書きました。
その後、発酵という文化と出会ったことで関心が広がり、人間だけでなく、微生物をはじめとする人間以外の生き物も、研究の射程に入れるようになりました。
井上:
先生が別メディアで連載されている中で、「情報技術には発酵の時間が足りていないのではないか」というお考えを拝見しました。ここでいう「情報技術には発酵の時間が足りない」とは、どういう意味なのでしょうか。また、先生のご研究とどのようにつながっているのでしょうか。
チェン:
「発酵と情報技術」と言われても、何のことだろうと思われるかもしれません。
私は以前、博士課程を休学して起業した時期があり、当時は情報技術にどっぷり浸かった生活を送っていました。会社に行っては案件を開発し、まさにインターネットのスピード感のなかで働いていたんです。
そんなときに、偶然発酵食と出会い、ぬか漬けを作るようになりました。ぬか床に野菜を入れて一晩置くと、おいしく変化していく。そのメカニズムがどうなっているのかに、純粋な好奇心を持ちました。
さらに発酵の世界には、作りたてのぬか床だけでなく、世代を超えて継承され、100年を超えるぬか床が存在するといった話もあります。酒蔵でも、創業100年はまだ若いと言われたりするほどです。長い時間をかけてゆっくり変化し、時間が経つほど複雑に生成変化していく――そういう世界があることに、私は驚きました。
一方で、当時自分が使っていた情報技術の世界は、日進月歩で新しい技術が現れては消えていく、非常に速い時間の中にありました。発酵の時間とは対照的です。そのギャップを体験したことで、コンピューターやAIに急かされるような感覚、仕事や生活のスピードが加速していく感覚を、自分自身が抱いていたことにも気づきました。
そこで、発酵の時間の持ち方やスピード感には、別の可能性があるのではないか、と感じたんです。今からすると17年ほど前のことになります。
当時はまだ博士論文も書き終えておらず、教員でもありませんでしたが、その問題意識だけは自分の中で、まさに“発酵し続けて”いました。早稲田に着任してから、これを研究分野として立ち上げようと思い、「発酵メディア学」と名付けて掲げるようになりました。体系化された学問があるわけではないので、自分で旗を立てて考え始めた、ということです。
井上:
ありがとうございます。のちほど詳しく伺う「Nukabot」や「Pickles」も、先生の実践的な研究の一環だと理解しました。ここで話題を少し広げて、先生が解明したいと考えている研究上の大きな問い「リサーチクエスチョン」についてお聞かせください。
チェン:
まだ一言でうまくまとめられるほど“熟成”が進んでいないのですが、私の場合は「コミュニケーション」が根本的なテーマです。
私は多文化的なルーツの中で育ち、多言語環境に身を置いてきました。エスニシティで言うと日本・台湾・ベトナムという文化的ルーツがあり、日本で生まれ育ちながら国籍はフランスで、教育もフランスやアメリカで受けています。そうした背景から、「翻訳」は自分の中で大きなテーマになってきました。
そして、「人は本当に他者とわかり合えるのか」という問いが、ライフワークとしてのリサーチクエスチョンです。言葉を使えばコミュニケーションはできますが、完璧なコミュニケーションは存在しません。考えていることを言葉にした瞬間に、こぼれ落ちるものもあります。
だから私は、コミュニケーションを単なる情報伝達ではなく、不完全でありながらも、何かのイメージに向かって少しずつ近づいていく行為として捉えています。その制約の中で、人はどう話し合い、合意形成し、あるいは合意だけでなくコラボレーションを通じて一緒にものを作ったり表現したりできるのか。そこが大きな問いです。
さらに、ぬか床を作るうちに、微生物のような存在は人間と同じ意味で「わかり合う」ことができませんし、人間的な概念がそのまま適用できるわけでもありません。そうした微生物とどう付き合っていけるのか、という問いも、コミュニケーションや表現の問題として、今はリサーチクエスチョンの中に取り込もうとしています。
井上:
ありがとうございます。では、先ほど話題に出た「Nukabot」について伺います。Nukabotは「人と微生物が会話できるぬか床発酵ロボット」だと伺っていますが、このプロジェクトが始まった経緯と、探究しているテーマを教えてください。
チェン:
先ほどの話と矛盾するようですが、「ぬか床の微生物と喋りたい」という思いが、半ば妄想のように自分の中で湧き上がり、それを実際にシステムとして作ってみたものがNukabotです。現在は研究プロジェクトの一つになっています。
そもそも、なぜ微生物と話したいと思ったのか。そのきっかけは、17年ほど前にぬか床を始めた頃にさかのぼります。起業当時、共同創業者の方から、彼の家で約30年にわたり、お母さんが大切に育ててきたぬか床の一部を分けていただいたことがありました。それをもとに新しいぬか床を作ったところ、とてもおいしいぬか漬けができるようになったんです。
調子に乗って、いろいろな人にぬか漬けを配ったり、行きつけの定食屋の方に「僕の作ったぬか漬けです」と渡したりしていました。ところが、その大事なぬか床を、凡ミスで一晩のうちに腐らせてしまったことがありました。
この出来事は非常に衝撃的でした。一晩で腐ってしまう事実にも驚きましたし、何より、ペットロスに近いような喪失感に襲われたんです。ぬか床を「おいしいものを作る道具」と捉えることもできますが、実際に腐らせてしまったことで、「生きている存在を失う」という側面があることに気づきました。
しばらくは自信をなくし、ぬか床を再開できないくらい落ち込んでいたのですが、時間が経ってから振り返ると、「なぜ目に見えず、コミュニケーションもできない微生物に、これほど愛着を抱いていたのか」という問いが、一つの起点になりました。
そこで、ぬか床の中の微生物をより良くケアする方法はないか、と考え始めました。机に向かってすぐ計画を立てたわけではなく、数年間その問いを頭の中で“発酵”させていたところ、ある時ふと「ぬか床に喋ってもらうのがいいのではないか」というアイデアが降りてきました。
そこから実験を始め、センサーを購入し、自宅のホーロー容器のぬか床に差し込んで、リアルタイムにデータを取るようにしました。わざと腐らせたぬか床も用意し、腐る時にどんなデータが出るのか、うまく発酵している時はどう違うのかを比較しながら分析しました。その結果、安価なセンサーの組み合わせでも、発酵しているのか、腐りそうなのかが分かるようになりました。
ただ、データは数値で入ってくるので、開発時はデータベースやチャートで確認していましたが、それだけだと味気ない。そこでスピーカーとマイクを仕掛け、「元気?」「調子はどう?」と聞くと「今大丈夫だよ」と言葉で返してくるようにしたんです。もちろん微生物にそうした意識があるわけではありませんが、いわば“ごっこ遊び”として、そう見立てて喋ってもらう。
このシステムを媒介させることで、たとえばキッチンでぬか床をかき混ぜるのを忘れているとNukabotが「そろそろかき混ぜないと腐っちゃうよ!」と話す。行為主体性を付与することで、私のように凡ミスで腐らせてしまうことが減るのではないか――そうした、少し“ふわっとした”期待から作り始めたのがNukabotです。
井上:
ありがとうございます。続いてもう一つのプロジェクト「Pickles」についても伺います。Nukabotは物理的に発酵が進むぬか床でしたが、Picklesは「頭の中での発酵」に関わる取り組みだと理解しています
PicklesはAIを活用してジャーナリングを支援するプロジェクトだそうですが、立ち上げた経緯と探究しているテーマを教えてください。
チェン:
Picklesは比較的新しいプロジェクトで、2025年6月頃から開発を始めました。まだアカデミックな研究としてのアウトプットはありませんが、ぬか床を始めて以来、「放置する」「寝かせる」といった消極的に聞こえる表現を、もっと肯定的に捉え直せるのではないかと、ずっと考えてきました。
すぐに問いを立て、最短距離で答えにたどり着かなくてもいい。そういう思いが自分の中でだんだん大きくなっていったんです。
このことを深く考えるきっかけの一つが、編集者の松岡正剛さんと共著で『謎床』という本を書いたことでした。今から8年ほど前のことです。いろいろな話をする中で、「人間の頭にもぬか床のように、自分の問いを漬け込んでおくと、変化して突き返されてくる――そういうものが必要だ」という話になり、それを「謎床」と名付けよう、という結論になりました。
そこから約8年かけて「謎床とは具体的にどう実践できるのか」を考え続け、たどり着いたアウトプットがPicklesです。
Picklesは、ジャーナリングという研究手法をベースにしています。研究者が研究ノートを取り続けるように、リサーチクエスチョンに関連する知識や経験を書き留めていく。私はこのジャーナリングをゼミでも奨励し、1〜2年ほど続けてきました。
ただ、特に学部の若い学生にとっては、書き続ける習慣を維持するのが難しい場合もあります。そこで、自分のジャーナルに誰かがコメントを返してくれたら、続けやすくなるのではないかと思いました。
しかし、私がゼミで取り入れているジャーナリングは、研究だけでなく生活についても書く、自伝的(オートバイオグラフィカル)な側面が強いものです。自分自身を研究対象として、来歴や社会的背景、生きづらさなども含めて書くことがあり、オートエスノグラフィーの考え方も参照しています。
そうなるとプライベートな記述が増え、第三者と共有しにくくなります。教員である私が学生の私的な記述を直接読むことは難しい。では、誰かにコメントしてもらう仕組みをどうするか――そこで「AIなら差し支えが少ないのではないか」と考えました。
具体的には、AIに週に一度、1週間分のジャーナルを読んでもらい、その感想や問い返しを返してもらう仕組みを作っています。返答は週1回、メールの形で自動的に届くようにしています。
井上:
ありがとうございます。本日のポッドキャストはここまでを前半とし、後半では、チェン先生ご自身が起業家を経て再び大学の研究者に戻られた背景や、その波乱万丈なキャリアパス、そして学生たちとの熱いゼミ活動について、さらに深くお話を伺います。
『早稲田大学Podcasts:博士一歩前』。次回の放送もお楽しみに。チェン先生、ありがとうございました。
チェン:
ありがとうございました。