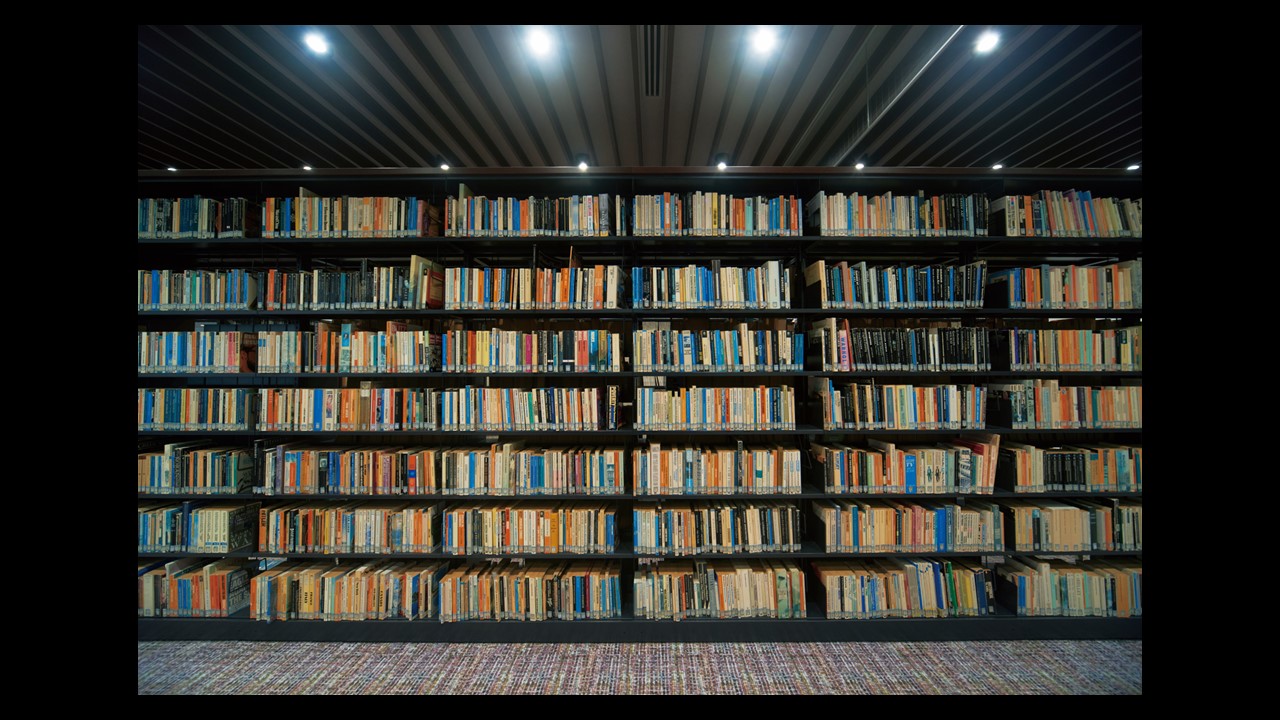- Featured Article
美術作品に残された痕跡から 人間の営みをとらえる
特集:図書館での学び、叡智との出会い
Wed 07 May 25
特集:図書館での学び、叡智との出会い
Wed 07 May 25
書籍だけでなく、絵巻や掛幅(かけふく)などの画像資料も多く所蔵されている早稲田大学の図書館。日本の仏教絵画史をテーマに研究されている文学学術院の山本聡美先生に、美術史研究における図書館の活用方法や、 人文科学のもつ可能性について伺いました。

撮影=戸山キャンパス 戸山図書館 研究図書フロア
仏教絵画に死生観を読み解き 現代を生きる人間の生活を想う
日本の古代・中世絵画を中心とした美術史が専門で、「九相図(くそうず)」という死体が腐敗し白骨となるまでの様子を9つの相で表す主題を起点に、仏教絵画史を研究しています。日本では九相図が鎌倉時代から20世紀初頭ごろまで連綿と描き継がれ、多くの作品が生まれました。なぜそれほどまでに世の中に必要とされたのか、この絵を見ていた当時の人々の精神は現在とどう違うのか、といった視点から、人間の営みとしての思想、宗教、文化、美術について考えています。
近年取り組んでいるのが「廃墟」と「捨身(しゃしん)」というテーマです。廃墟のイメージには、過去の繁栄と未来への復興という二つの側面があります。この概念には、現代社会においても自然災害や、戦争によって生じる都市や社会の荒廃と、どう向き合っていくかを考えるヒントがあると感じています。
また、捨身とは他者のために我が身を捨てることで、お釈迦様の前世の物語に多く見られます。そして長い年月の中で、さまざまな人物のエピソードと組み合わされ、多様な物語や美術に姿を変えてきました。九相図もその一部です。人々にとってそれらの美術作品がどのような存在だったかを考え、人間の生きた痕跡をたどっていけるのが、美術史の面白いところです。
図書館で一次資料に触れることは 研究の第一歩となる
美術史の研究にとって、美術作品は最も大事な一次資料。作品を実際に観察しないことには何も始まりません。学生たちには、とにかく足を運び作品を見に行くように伝えています。展覧会で実物を見ることはもちろん、寺社や個人で所蔵している作品を見せてもらう調査もあります。ただし学生にとって学外で後者を経験するのはハードルが高いものです。
早稲田大学の図書館には、研究に未着手のものもあるほど多くの貴重書や美術作品が収蔵されています。在学生はそれらに簡便な手続きでアクセスすることができるので、一次資料から学ぶ良い経験になるはずです。研究者を志すのであれば、掛幅や巻子(かんす)を正しく扱えるかは、所蔵者からの信頼に直結する必須のスキルですから、取り扱いに慣れるという点でも貴重な機会となります。
また、図書館は調査先で美術品を観察する前の準備にも欠かせない存在です。所蔵されているレプリカや、デジタルアーカイブ化された情報を活用して、入念に事前調査を行うからこそ、実物を見たときに新たな発見ができるもの。素材は紙なのか絹なのか、絹の場合は表と裏の両面から絵の具を重ねることがあるため、どんな順番で塗り重ねられているのか、現状どこが剝落して、どの層が残っているのかなど、その場で注意深く観察しなければいけないことは山ほどあります。調査現場で最大限の結果を得るためにも、基本的な情報を事前に把握しておく必要があるのです。
ただし、学生がインターネット上の情報だけでレポートを作成するのは、あまりおすすめしていません。非効率的だとしても、学生のうちに、物質としての美術品や本にたくさん触れることが、自分の興味に出合うための第一歩だと考えているからです。学生の皆さんには、情報の形や種類に合わせて、適切な活用方法を選択できるようになってほしいと思います。
長期的な視点を社会に提供する 人文科学の可能性を伝えていく
美術史を含め、人文科学とは歴史や文化、宗教、思想からの視座を提供することで、社会に貢献していくことができる学問だと考えています。100年、1000年といった大きなスパンで人間を考えること。これは人文科学が得意とする方法であり、社会に不可欠な視点です。図書館は、そんな学問の先人たちの叡智や、過去の人間の営みについてのヒントが詰まっている場所だと言えるでしょう。
今後は人文科学の面白さを学生たち、ひいては社会に広く伝えていき、これから育っていく次世代の研究者たちとともに、世界と双方向的に対話できる人文科学の環境を整えていけたらと考えています。
PROFILE
文学学術院 教授 山本聡美
早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学、博士(文学)。大分県立芸術文化短期大学講師、金城学院大学准教授、共立女子大学教授などを経て、2019年より現職。著書『九相図をよむ朽ちていく死体の美術史』(KADOKAWA, 2015年 )で、平成27年芸術選奨文部科学大臣新人賞、第14回角川財団学芸賞を受賞