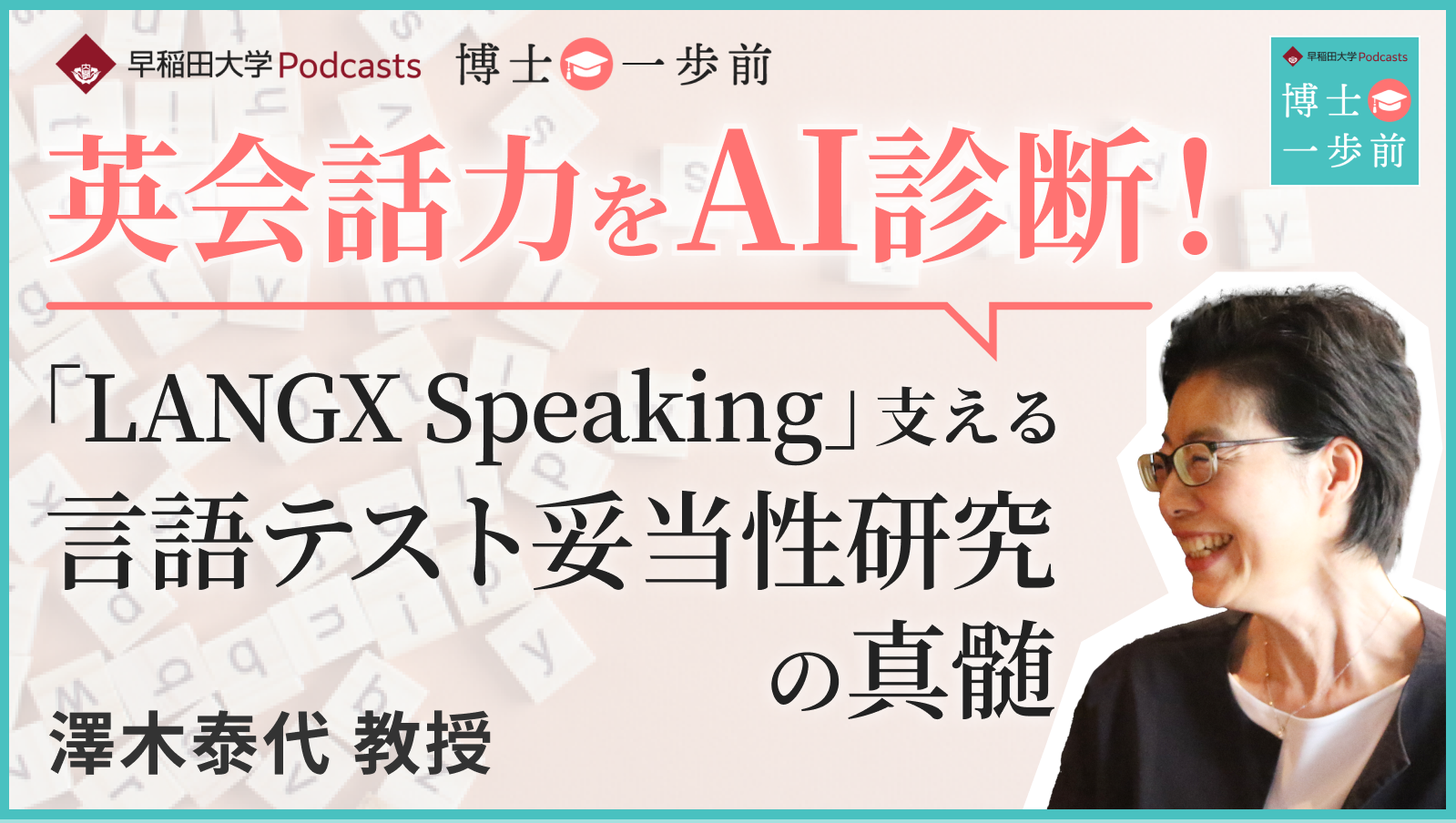- Featured Article
【Podcastコラム】言語テストの今
Wed 26 Feb 25
Wed 26 Feb 25
早稲田大学では現在、ポッドキャスト番組「博士一歩前」 を配信中です。
今回は配信中のエピソードのうち、教育・総合科学学術院の澤木泰代教授にご自身の研究について語っていただく中で、TOEFL iBTなどの言語テストの今についてお話いただきましたので、その部分を抜粋してご紹介いたします。
Q. 澤木先生が研究されている言語テスト妥当性研究という分野の研究対象の全体像や、その中でも特に澤木先生が注力されているテーマについて教えていただきたい。
澤木 泰代 教授:
言語テストといっても色々な分野がありますが、私は主に妥当性という視点から言語テストを見ていますので、その中で番組冒頭にお話しましたように、いわゆる現在ですと論証モデルと言われるものが主流になっており、それを使ってスピーキングだけではなく、さまざまなテストについて見ることができます。
そのため、英語4技能ですとリーディング・リスニング・スピーキング・ライティング、それから語彙・文法等がすぐ頭に浮かぶかと思いますが、どれを取っても妥当性の枠組みを使ってその質を検証することができるわけです。
最近の動向として、4技能を測るテストが多くなったというのが一つ、特徴としてあると思います。

例えば昔ですと、英語のテストだとリーディングとリスニングしかないとか、語彙・文法とリーディングとかだったと思いますが、今それが4技能のテストになってきた。
そうなるとどういうことができるかというと、例えばこれはリーディング、これはリスニングではなく、それを複数組み合わせる統合型のテストタスクが作れるようになります。そのため、読んで書く、読んで聞いて話すなど色々なことができます。
私としてはそこが一番興味のあるところで、例えば私が前にかかわっていたTOEFL iBTというテストの中には、スピーキングとライティングのセクションの中にそのような統合型のタスクがあります。

私の場合、実はライティングを自分の研究プロジェクトの中でかなり長くやっているものがあるのですが、それは読んで書くなんですね。
読んで書くというのは、英文を読んでその要点を短く要約するというものです。学術的なライティングをする際にはとても大事なものになりますので、私はそこにずっと興味を持ってやっていますが、そのような統合型のスキルを測るテストは、最近結構盛んになっているので、私もそこで頑張ろうかなと思っているところです。
澤木 泰代 教授
教育・総合科学学術院教授。専門は、言語テスト妥当性研究。熊本大学教育学部卒業後、熊本県公立中学校教員となる。その後、イリノイ大学修士課程(英語教授法)で学び帰国。昭和女子大学英米文学科助手を経て、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)博士課程(応用言語学)へ。2003年よりETS(Educational Testing Service)妥当性研究センターにて常勤研究員として勤務。2009年より早稲田大学教育・総合科学学術院准教授。2014年より現職。

島岡 未来子 教授(番組MC)

研究戦略センター教授。専門は研究戦略・評価、非営利組織経営、協働ガバナンス、起業家精神教育。2013年早稲田大学公共経営研究科博士課程修了、公共経営博士。文部科学省EDGEプログラム、EDGE-NEXTプログラムの採択を受け早稲田大学で実施する「WASEDA-EDGE 人材育成プログラム」の運営に携わり、2019年より事務局長。2021年9月から、早稲田大学研究戦略センター教授。