- プロジェクト研究
- 知覚的意識の生起における高次認知過程の役割
知覚的意識の生起における高次認知過程の役割

- Posted
- Fri, 11 Apr 2025
- 研究番号:25C12
- 研究分野:technology
- 研究種別:奨励研究
- 研究期間:2025年04月〜2026年03月
代表研究者
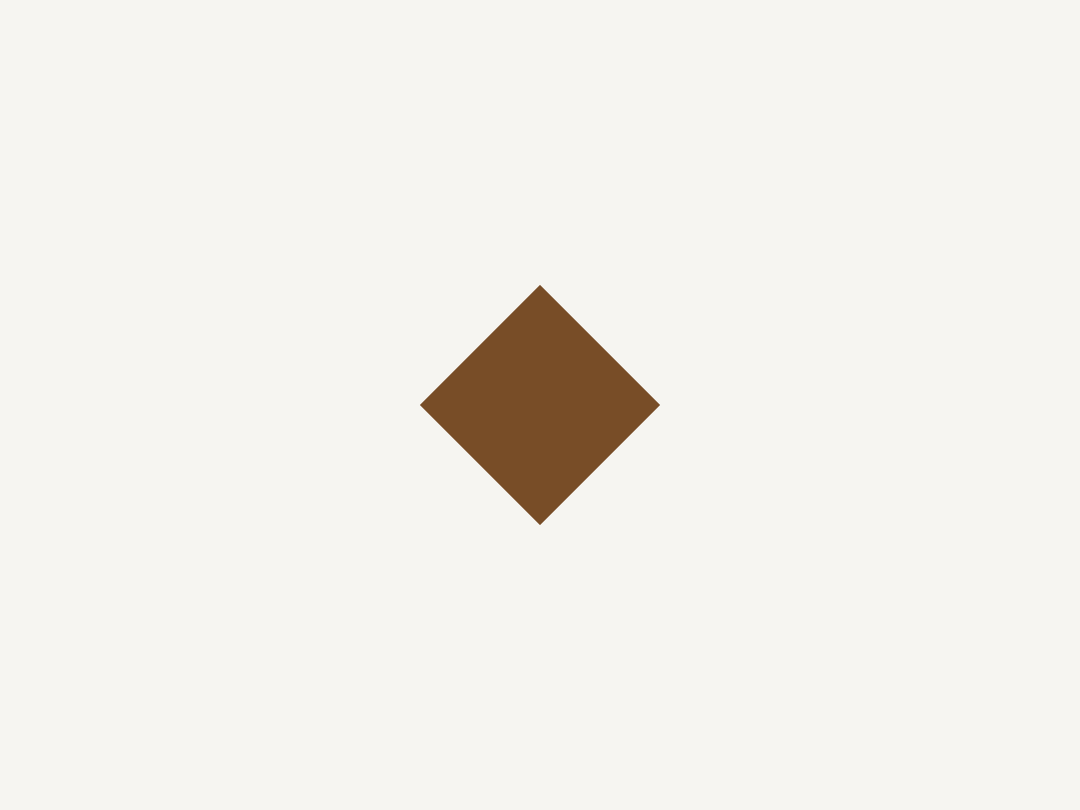
山本 浩輔 理工総研が募集する次席研究員
YAMAMOTO Kosuke Junior Researcher
理工学術院総合研究所 渡邊 克巳 研究室
Waseda Research Institute for Science and Engineering
研究概要
ヒトの意識が生起するための情報処理過程における,注意や判断といった高次認知過程の関与の仕組みについて,実験心理学的手法を主としたアプローチによる解明を目指す。先行研究では,神経科学的および数理的アプローチにより,脳全体の組織化された情報処理による意識の形成理論が提案されているが,感覚統合,注意,判断・報告など,低次感覚野以降の処理過程がどのように寄与しているかについては統一的な見解が得られていない。例えば,グローバル神経ワークスペース理論では脳の感覚野における再起的な情報処理によって生成された前意識的な情報が高次認知処理に関連する前頭葉に伝播することで意識が形成される,すなわち意識の形成には高次認知過程が不可欠との立場をとる。一方意識の統合情報理論では,感覚野における局所的な再起処理の時点で意識が生じ,前頭葉は意識の報告に対応するものと考えられる。本研究では,意識の生起過程に関する実験パラダイムにおいて,注意や判断,報告などの高次認知的過程の関与を操作した検討を行うことで,意識の理論的枠組を整理し知覚的意識の情報処理過程について統一的な解明を目指す。
情報統合による神経ネットワークの情報量変動により意識の成否が決定するという統合情報理論をベースとして,視覚と聴覚や嗅覚などとの感覚統合による実験パラダイムを用いる。本年度は視覚と聴覚の感覚統合に加え,嗅覚刺激と視覚刺激との対応を操作した両眼視野闘争課題を用いることで,感覚特異的な処理過程を超えた視覚的意識の変容過程について検討する。具体的には,視覚における色と嗅覚から連想されるオブジェクトの色情報を操作し,特徴が一致する視覚情報の意識が生起しやすいという仮説を検証する。その上で,刺激の予測や知覚表象に対する判断課題を操作することで,これらの高次認知処理と知覚的意識との関連について明らかにする。実験における反応課題として,主観的な知覚の直接的報告と間接的報告による課題を実施する。例えば視覚刺激の運動方向の知覚的意識についての実験では,直接的報告では運動方向について報告するが,間接的報告では刺激の運動方向と色を対応づけ,見えている刺激の色について報告する。このことで,視覚的運動の意識の生起において,運動に対する注意が不可欠なものであるかを検討できる。
意識の数理的理論による予測を実験的に検討することで,心理学,神経科学や情報科学等の分野を横断した学際的な知見が期待される。さらに意識・無意識的過程の情報処理の解明により,AI等の情報ネットワークへの意識の実装に貢献できる可能性が考えられる。
年次報告
- Tags
- 研究活動
