- プロジェクト研究
- 大規模量子分子動力学計算プログラムDCDFTBMDの機能強化と新規解析手法の開拓
大規模量子分子動力学計算プログラムDCDFTBMDの機能強化と新規解析手法の開拓

- Posted
- Tue, 01 Oct 2024
- 研究番号:24C15
- 研究分野:science
- 研究種別:奨励研究
- 研究期間:2024年10月〜2026年03月
代表研究者
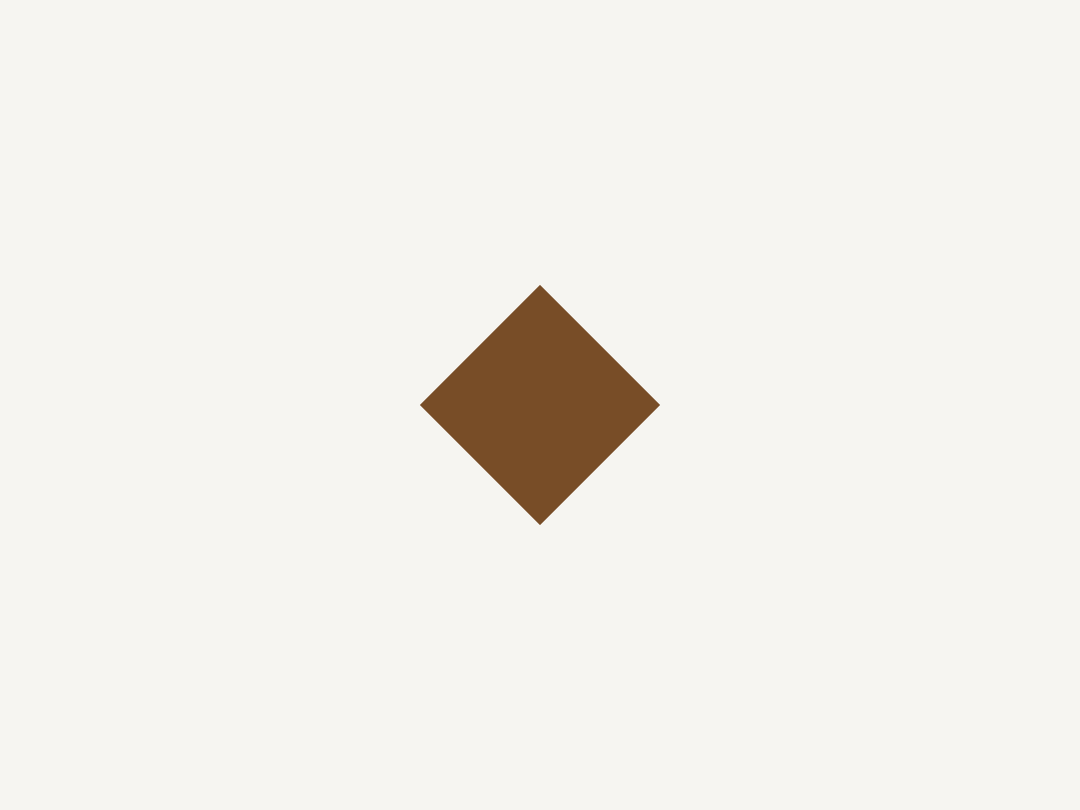
西村 好史 理工総研が募集する次席研究員
NISHIMURA Yoshifumi Junior Researcher
理工学術院総合研究所 中井 浩巳 研究室
Waseda Research Institute for Science and Engineering
研究概要
量子分子動力学(QM-MD)計算は系の電子状態と原子核の運動方程式をコンピュータ上で繰り返し解くことで原子・分子の運動を追跡し、物質・材料の構造・特性・ダイナミクスの原子・分子レベルでの解析に貢献する技術である。QM-MD計算は、従来採用されてきた経験的な古典力場に基づく分子シミュレーションでは取り扱いが困難な電子移動や化学反応が関与する現象を必要十分な精度で記述できる。近年、深層学習などの人工知能技術を活用した高速かつ化学結合の生成・開裂に対応した機械学習ポテンシャルを分子動力学計算に用いる研究が発展途上であるが、その適用範囲は未だ明確ではない。したがって、QM-MD計算手法の発展は依然として重要な研究課題である。
候補者の西村氏は1.に記載の通り、QM-MD計算が抱えていた計算コストの問題を線形スケーリング法・半経験的量子化学計算法・並列実装方法技術の融合によって解決し、大規模複雑系の応用計算によって開発した大規模QM-MD計算手法を実装したDcdftbmdプログラムの化学プロセスの問題に対する有効性を実証してきた。2021年10月より開始した理工総研が募集する次席研究員の奨励研究では、大規模QM-MD計算技術の社会実装に専心し、Dcdftbmdがもつ大規模量子化学計算の特徴を他の計算化学ソフトウェアとの連結によりマルチスケール計算などへ展開するための枠組みの開発や多数の原子・分子および複数の反応素過程が関係する複雑な化学プロセスにおける化学反応イベントの加速サンプリングアルゴリズム拡張、プログラムマニュアルのwiki化などについて取り組んだ。
2.で言及した計算パラメータの充実により、Dcdftbmdに基づく大規模QM-MD計算が取り扱う分野は広がると予測される。これまでに想定されてこなかった計算内容を他の研究者でも容易に使える形で計算できるように整備する必要があり、そのための新たなアルゴリズムの導入が求められている。また、計算結果から所望の知見・物性値を引き出すためには、問題に即した解析手法を考案し、その手順の標準化が重要になる。本研究課題では、上記2点に着目した以下の研究を推進する。
・Dcdftbmdプログラムの機能強化
Dcdftbmdプログラムは、ポテンシャル曲面の底上げによる活性化障壁の減少、高温条件下での熱運動効果の取り込み、反応空間の収縮による反応物の衝突頻度の上昇、のいずれかに立脚した加速サンプリング法を既に内蔵し、有機・生体分子系の大規模QM-MD計算に威力を発揮してきた。金属元素に対する計算パラメータが最近利用可能となったことを考慮し、触媒反応や表面反応に対して効果的と見込まれる計算手法の開発・実装を進める。また、系の一部に強制的な力をかけて非平衡過程を模擬する手法の組み込みを検討する。これは、高分子の挙動やタンパク質―リガンド複合体の分子間相互作用の調査研究への足がかりとなる。さらに、研究室内では励起状態ダイナミクス手法の開発が継続しており、未統合機能の移植を完了させる。
・ナノリアクター分子動力学法における熱力学量計算手法の開発
ナノリアクター分子動力学法は、反応物間の衝突頻度を上昇させて化学反応を誘発し、反応経路探索を容易化できる計算手法である。この方法の未踏領域として、シミュレーション結果からの熱力学量、特に自由エネルギーの算出が挙げられる。統計力学などを駆使してこの問題を解決を試みる。系がナノリアクターからされる仕事量の見積もりを研究の出発点とする予定である。
・熱的に活性な原子がもつ特徴量の探索
触媒反応において、反応の駆動に関係する触媒の各原子の運動および構造ゆらぎの基礎的理解が高活性な触媒の開拓に向けて鍵を握ると考えられている。大規模QM-MD計算によって触媒のダイナミクスを含めた特性を詳しく解析し、説明可能な状態とすることは、この問題にアプローチするための有効な手立ての一つである。一方、計算結果からより動的に運動する原子と活性点との間の関係を解釈するための手続きは十分に確立されていない。そこで、熱的に活性な原子を特徴づける記述子や触媒特有の動的挙動を数値的に抽出する解析手法の確立を目指す。原子間距離の情報から粒子の無秩序の度合いを見積もる指標や系の運動エネルギー・ポテンシャルエネルギーを原子ごとに分割した値の評価、およびそれらの相関関係を調査する。
年次報告
- Tags
- 研究活動
