- プロジェクト研究
- 生理活性物質科学
生理活性物質科学

- Posted
- Tue, 19 May 2020
- 研究番号:14P00
- 研究分野:technology
- 研究種別:プロジェクト研究
- 研究期間:2014年04月〜2017年03月
代表研究者
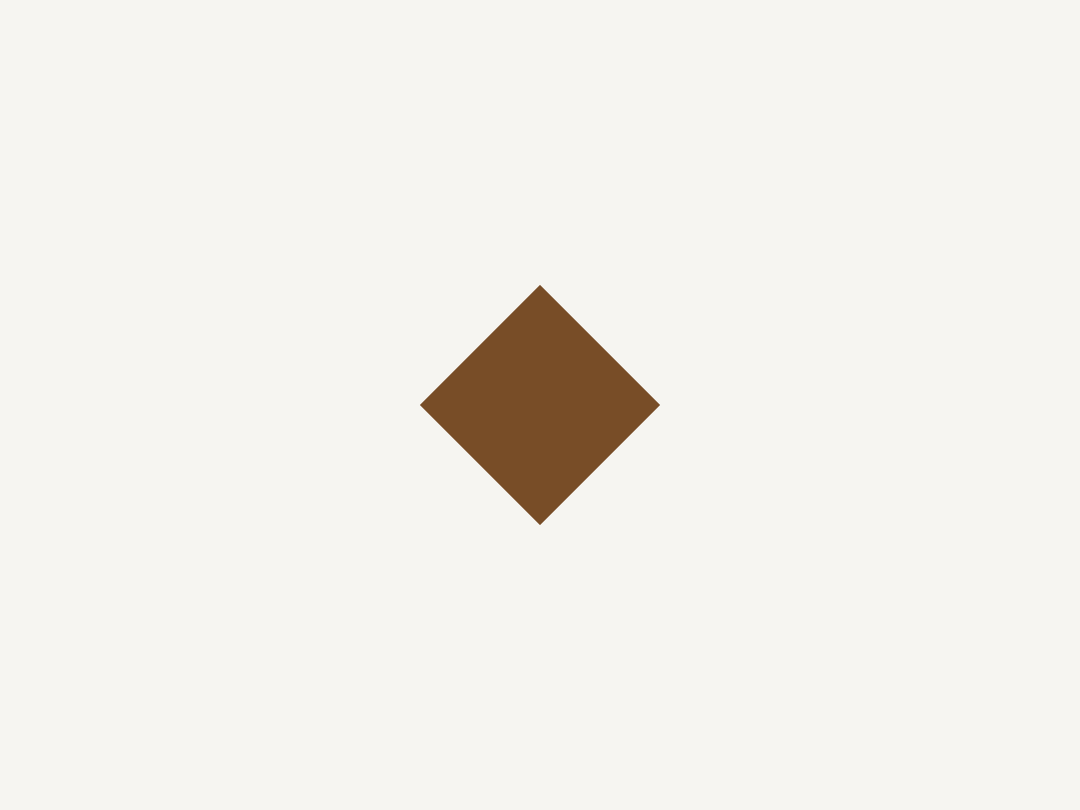
竜田 邦明 教授
TATSUTA Kuniaki Professor
理工学術院
Waseda Research Institute for Science and Engineering
研究概要
多様な生理活性を併せもつ天然生理活性物質(天然物)においては、ある活性が他の活性の副作用として働き、実用化に問題を生じる場合が少なくない。したがって、それらの活性発現機構を明らかにすることによって、活性を構造ユニット別に分離することができれば、副作用の低減のみならず望みの活性を増強できる可能性がある。それはナノレベル以下で精密に分子設計・合成することにより初めて成し遂げられる。
そこで、本研究は多様な活性をもつ天然物の実践的な全合成を完成することを第一の目的とする。つぎに、その合成手法を用いて種々の構造ユニットを合成して、構造-活性相関研究をナノレベルで行い、それぞれの活性発現に必要な最小ユニットを明らかにすること(活性分離)を第二の目的とする。さらに、天然物より優れた生理活性や新しい活性をもつリード化合物を創製して創薬に資することを第三の目的とする。すなわち、全合成は最終目的ではなく、学際領域を広く活性化することから、つぎの科学への出発点であるという概念を例証する。すなわち、“すべては全合成から始まる”。
社会問題にもなっている生活習慣病(がん、糖尿病、高血圧症など)に有効な医薬品を主に指向して研究対象の天然物を選択してきた。
主な研究成果を以下に列挙する。
- これまで102種の天然生理活性物質(天然物)の全合成の達成に成功したが、そのうち96種については世界最初の全合成である。その完成数は世界的にも傑出しており、平成24年10月の朝日新聞に「神の業、世界初連発」と報道されるなど特筆すべきである。また、その合成研究において、新規の反応も見いだし、独創的な合成法も確立している。
- 特に、主要な医薬品として実用されている四大抗生物質群の全合成研究において多大の功績を挙げている。特異な構造と抗菌活性を示すことから、アミノグリコシド系、マクロライド系、テトラサイクリン系およびベーターラクタム(ペニシリン)系抗生物質は四大抗生物質群と称されているが、それぞれの代表物質の世界最初の全合成を含むすべての光学活性な天然型の全合成に世界に先駆けて成功し、国内外に極めて大きいインパクトを与えた。五大陸の最高峰制覇に匹敵すると報道された。中でも、テトラサイクリンの全合成(平成12年に完成)は、発見以来約50年ぶりの世界初の完成であった。
- 糖質を原料に用いる合成法を開拓して、多種多様な天然物の全合成を完成し、絶対構造のみならず生理活性も確証した。特に、上記の光学活性体の全合成は、すべて糖質を不斉炭素源に用いて達成されたものであり、その他の約60種の天然物の全合成にもその方法論と概念の有用性と重要性を例示したことから、糖質を不斉炭素源として用いる天然物の合成法は有機合成化学の重要かつ一般的な方法となり、有機合成化学の発展に貢献した。
抗生物質を始め自然界に存在する天然物の多くは不斉炭素原子を含み、ほとんどの場合その立体異性体はもとの生理活性を示さないので、天然物と同じ立体配置を持つ化合物を合成し、天然物の構造と生理活性の確証を得るには、立体配置の確定している物質を原料として、立体特異的な反応を組み合わせて目的の天然物のみを合成することが重要となる。すなわち、立体配置が確定している糖質を出発原料(不斉炭素源)に選び、目的の天然物のみを合成する立体特異的合成法を開拓して、多種多様な天然物の全合成に成功した。また、天然物の全合成や関連物質の合成に有用な数々の新しい有機合成反応も創出した。これら一連の研究によって、糖質を不斉炭素源に用いる方法は多種多様な構造を有する複雑な天然物の合成にも極めて有用であることを示し、有機合成の重要な一つの方法論としての基礎を築いた。 - 天然物の全合成研究をさらに発展させ、その知見と方法論を駆使、結集して構造-活性相関研究を行って、活性発現の最小ユニットを明らかにし、多くの天然物の活性発現機構を化学的に解明した。特に、糖尿病、肥満症、がん転移ウイルスなどに関与する糖質分解酵素の阻害物質の研究において、阻害活性を示す天然物を全合成した後、構造-活性相関研究を分子レベルで行い、それらが相当する酵素に拮抗的に作用して阻害することを見いだし、理論的にすべての糖質分解酵素(グリコシダーゼ)阻害物質の創製が可能であることを初めて例証した。このことは、抗糖尿病薬の開発に寄与すると共に、糖質分解酵素を多用する糖鎖工学、生化学などの発展にも貢献した。
- さらに、実用化にも力を注ぎ、構造-活性相関研究により天然物より強力な活性を示す多くの新規化合物を創製した。中でも、アドリアマイシンの誘導体の構造-活性相関研究を徹底的に行った結果、従来の心臓毒性、脱毛などの副作用が極めて低く、制がん活性が強力であるTHP-アドリアマイシンを創製し、抗腫瘍剤(制がん剤)ピラルビシンとして実用に供した。これは、特に膀胱がんの特効薬として評価されている。また、歯周病菌検出薬(ペリオチェック)も開発・実用化した。
- 全合成の知見を活用して基礎的な新規合成法のみならず工業化可能な実践的合成法を数多く開発し、いくつかの実用化を実現している。中でも、独自の骨格転位反応を用いて開発したセフェム系抗生物質(ファーストシン)の側鎖部分の合成法の工業化は、有機合成化学のみならず有機工業化学の発展にも貢献した。また、有害な塩素系有機溶剤の代替溶剤としてチアジアゾールを実用化した。
