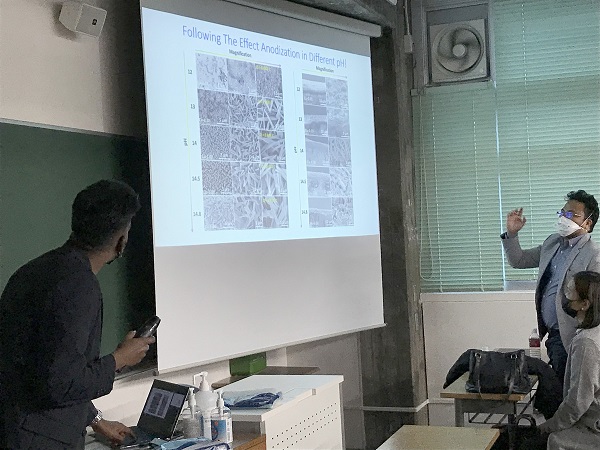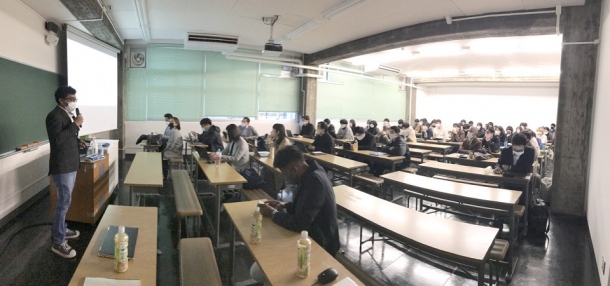- ニュース
- 【開催報告】2023年2月27日「第16回先端化学知の社会実装コロキウム」について
【開催報告】2023年2月27日「第16回先端化学知の社会実装コロキウム」について
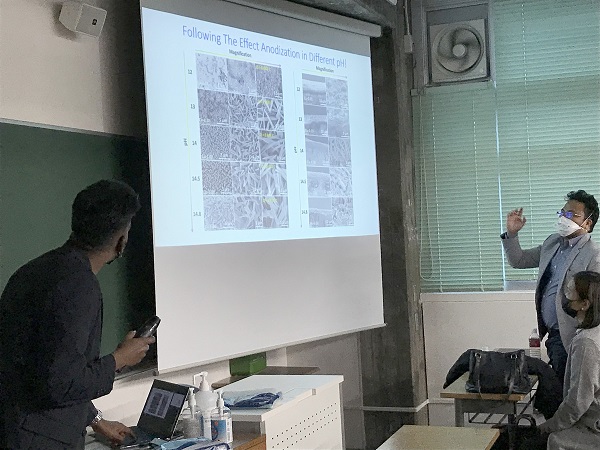
- Posted
- Wed, 01 Mar 2023
Joey D. Ocon教授からは「Energy Transition in Off-Grid Islands: From Least Cost to a Net-Zero System」の講演を頂いた。原子スケールの理論計算から材料合成、デバイス開発、太陽電池・蓄電池・ディーゼル発電など多数のエネルギーデバイスを組み合わせたシステム、さらに系統電力に繋がっていない離島への再エネベース発電所の建設まで、総合的な研究をご紹介頂いた。質疑では、「複数の離島を繋げたマイクログリッドを設けるとコストが下がらないか」という質問に対し、離島間の送電ケーブルの分コストが上がってしまうが災害に対してよりレジリエントになるなど、多面的な議論を行った。Julie Anne D. del Rosario准教授からは「Influence of Electrolyte Cations on Oxygen Evolution Reaction」の講演を頂いた。再エネ電力を用いた水電解はグリーン水素製造に欠かせない技術であり、アルカリ水電解について触媒間の比較ではなく電解質の観点から行った研究が紹介された。Li+, Na+, K+, Cs+とカチオンを変えると電解の過電圧と電流が変化しK+が最も優れることが紹介され、そのメカニズムの考察が紹介された。質疑では、「カチオンを変えると同じ濃度でもpHが変わる、pH変化によるポテンシャル変化は計算で補正できるが触媒活性変化も考慮する必要がある」など技術の詳細について活発な質疑がなされた。花田信子専任講師より「Development of hydrogen storage and supply process using high content hydrogen storage media」の発表がなされた。水素貯蔵技術の概略の解説に続き、水素化マグネシウムを用いた水素貯蔵タンクおよび材料の研究、さらに水素キャリアとしての液体アンモニアの電解による水素生成の研究が紹介された。質疑では「液体アンモニアの電解における副反応の有無」について質問がされ、アンモニア水溶液系では副反応なく電流効率が約100%となるが、液体アンモニアでは電流効率が85%程度まで低下し溶媒和電子生成の副反応が原因と考えられるなど、技術の詳細が議論された。S. Anantharaj博士より「Self-supported 1D CuO/OH Nanostructures: Pushing the Limits in Fabrication and MOR Electrocatalysis」の発表がなされた。Cuはアルカリ水溶液中で電気化学サイクルを回すと1分と短時間でナノワイヤーが高密度に形成すること、アルカリ水溶液を高濃度にすると8秒といった短時間でナノワイヤ形成が可能になること、さらに酸化処理を施すとメタノールの電気化学酸化に高い活性を発現することなどが紹介された。質疑では「銅箔中に混ざる不純物の影響」について質問がなされ、この研究の前に行っていた銅フォームでは混入しているニッケルが構造形成に大きな役割を果たしていたなどの議論がなされた。S. Natarajan博士からは「Recycling spent Li-ion batteries (LIBs) electrodes into high performance LIB electrodes」の発表がなされた。リチウムイオン電池の普及に伴い廃棄量も急増していること、そのうち5%程度しかリサイクルされておらず環境汚染を起こす懸念が高まっていることが紹介された。続けて使用済みLIBを解体して再生した活物質を用いた黒鉛||酸化バナジウム(V)電池が紹介された。さらにHeng Yi Teah博士より「Life cycle assessment supports environmentally-friendly technology development: case of lithium-sulfur battery and thin-film silicon solar cell」の発表がなされた。確立している実用化製品のLCAに対し、研究開発途上の技術のLCAはまだ発展途上だが効率的に研究開発を進めるには重要であることが強調された。続けてカーボンナノチューブを活用した新型リチウム硫黄電池、および使用済みバルク結晶シリコン太陽電池の結晶シリコン膜太陽電池へのアップサイクルのLCAの結果が紹介された。質疑では「太陽電池のシリコンのリサイクルが進まない理由」が質問され、我が国でもNEDO事業で太陽電池のリサイクル研究がなされたが、freshな高純度シリコン原料にリサイクル原料を数%混ぜることができるといった程度で留まっていること、使用済みシリコンをセメントに混ぜて廃棄するのが安価であること、しかし珪砂から高純度シリコンを製造するエネルギー・環境負荷・コストが大きいため高純度シリコンをリサイクルすることが重要であることなどが議論された。終了予定時刻を20分超過して17:40に閉会とした。