- 研究科について
- 研究科長挨拶
From the Dean
研究科長挨拶
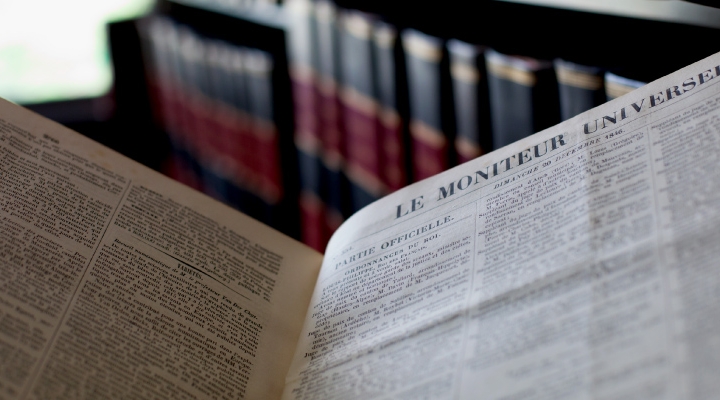
法学研究科の研究教育と人材養成

早稲田大学大学院法学研究科長
勅使川原 和彦
早稲田大学大学院法学研究科の歴史は、1951年の早稲田大学における新制大学院の修士課程設置、さらに1953年の博士課程発足まで遡ります。新制大学院としての法学研究科は、研究者の養成をその存在目的として発足しました。その後、法を学問として研究する場として、修士課程に高度の研究能力を備えた専門の職業人の養成という役割が与えられたことに伴い、研究者を目的とする者以外の入学者が多数を占めるようになりました。法学研究者をめざす者、修士課程で再び学問の深みに辿り着こうとする法律実務家、国家公務員試験を受験したり旧司法試験の時代には司法試験を受験する者、とりわけ早稲田のプレゼンスの高い東アジアや海外から留学してきた者など、さまざまな志望の学生が、本研究科の「自由な学問の場」に加わり、優れた法学研究者・法曹実務家・公務員等を多数輩出してきました。多くの本研究科出身者が、教育・研究関係、法曹関係、国際関係、行政関係等において、精力的に活動し、高い社会的評価を受けていることは、本研究科の教育研究体制の評価に繋がるものと考えます。2004年の大学院法務研究科設置からは司法試験受験者は法務研究科に所属することになりましたが、2025年から、独立研究科としての「法務研究科」は、法学研究科の法曹養成専攻として統合され(法曹養成専攻の運営は法科大学院[法曹養成専攻]長の率いる教員がそのまま行います)、法学研究科は組織的に研究者・法曹の二つの人材養成を担うことになりました。もともと「法務研究科」の授業を主として担当する法学学術院専任教員も法学研究科の授業を担当し、実質的な研究指導も行ってきましたが、法学部・法学研究科という一連の早稲田法学の流れの中で、研究者養成に加え、法曹の養成も、本研究科に帰ってきました。「法曹養成」のルートから「研究者」を育てるということもまた本研究科の目的の一つになりました。
本法学研究科修士課程(博士前期課程)は、民事法学専攻・公法学専攻・基礎法学専攻と先端法学専攻があり、博士後期課程は、民事法学専攻・公法学専攻を有しており、原則として、修士課程2年と博士後期課程3年を一貫させた博士課程5年の教育システムを採用しています(MD一貫教育)。本研究科は研究者養成目的を基本的に維持し、一貫した教育研究体制を堅持してきました。その成果は、研究者のスタート地点に立ったことを客観的に示す「博士(法学)」学位の取得者の大幅な増加がみられた上で、本研究科の修了者が本学法学部および本研究科の専任教員となるだけではなく、全国の大学や研究機関の教員・研究者として活躍していることにも現れています。
さらに本法学研究科の重要な役割は、法学系高度専門教育の必要性の高まりに対する実践として、専門性を育むプログラムです。2018年より、高度な法的分析能力を有する人材を育てる「先端法学専攻」(LL.M.コース)が設置され、社会人が自分の業務範囲で扱う法律知識に加え知的財産の全体的な法体系を習得する「知的財産法LL.M.コース」と、現代アジアの経済一体化と法の関係を英語での授業で学ぶ「現代アジア・リージョン法LL.M.コース」とが設けられました。いずれも1年間のコースですが、知財の専門家、アジア法制の専門家を育てることを目的としており(取得できる学位は「修士(先端法学)」です)、多くの社会人や留学生の参加を得ています。本研究科では、1994年に「企業法務と国際化」という形で「特定課題」方式の社会人向け修士課程を創設しました。現在は5つの社会人研究課題(「環境問題と法」「知的財産紛争と法」「租税紛争と法」「社会保障、社会福祉・成年後見の法と行政」「国際海事問題の実務と法」)を修士課程に開設し、多くの社会人が正規学生として研究に励んでいます(修士論文審査に合格すると、修士(法学)の学位が取得できます)。社会人の方は、修士課程修了で社会に戻られることが多いのですが、なかには博士後期課程に進学され、博士学位を取得し、現在は大学教授という方も少なからずおられます。社会人は、一般の学生と同様に通常の修士課程に入学することもできますが、「社会人研究課題」というプロジェクト研究のもと、このプロジェクト関連として設置されている科目を履修し(もとより、通常の修士課程向けに設置された科目も履修することができます)、その領域を専門とする本学専任教員だけでなく学外の専門家をも交えたティーチングチームをもってなされる教育プログラムは、本研究科の社会人教育の特徴の1つです。加えて、現役の法曹(裁判官、検察官、弁護士)の博士後期課程への編入を認めていることも特筆すべきことかもしれません。現に、裁判官が博士号を取得されたケースもあります。
本法学研究科は、たくさんの留学生を積極的に受け入れています。成果は、留学生が本研究科で博士学位を取得し、本国において研究者として大学の教職に就き、あるいは社会的に重要なポストに就任していることからもうかがい知れます。本研究科が一方でめざす「グローバル・ハブ大学院」の重要な担い手である留学生との活発な交流を通して、国際的な感覚と学問の広さを習得し、国際的に通用する専門的知見を身につけることができるでしょう。
本法学研究科は、受入学生数・教員数・設置科目数のいずれにおいても、法学系大学院として日本で最大規模を誇ります。研究指導は、長きにわたって形成されてきた師弟関係という伝統もあれば、専修科目での集団指導体制やプロジェクト研究といった新しい体系的な教育システムも併せてあり、個別にきめ細やかになされ、充実した大学院生活を履修者に提供しています。
本ページをご覧戴いて有り難うございました。われわれ早稲田大学大学院法学研究科の全教員・職員は、皆さんの入学を待っています。
