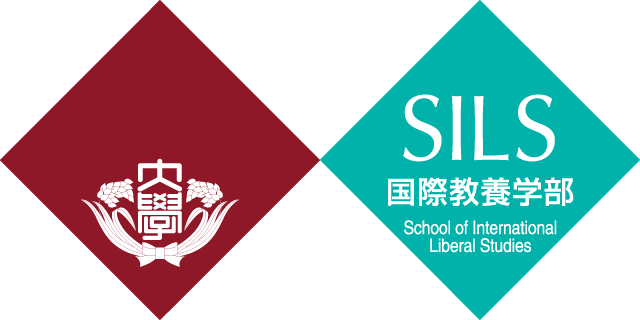- ニュース
- 【卒業生インタビュー】TANG Nanさん:実験物理の研究の道へ
【卒業生インタビュー】TANG Nanさん:実験物理の研究の道へ

- Posted
- Tue, 03 Oct 2023
 東京都立国際高等学校 2012年3月卒業
東京都立国際高等学校 2012年3月卒業- 早稲田大学国際教養学部 2016年9月卒業
- 東京大学新領域創成科学研究科物質系専攻
- Institute for Physics, University of Augsburg
― 現在のドイツでの職場での生活について簡単にお伺いしたいです。研究所の概要について教えてください。
私はアウクスブルク大学のInstitute for Physicsという物理研究所に所属しています。アウクスブルク大学は名前も聞いたこともないかもしれませんが、潤沢な予算がある大学で、物理だけではなく最近は生物分野等多種多様なサイエンスに力を入れているとてもいい大学です。実は私もここでポスドクをやっていた先輩から聞くまでは知らなかったのですが、こちらに来てからすごく驚きました。研究や留学を考えている方にとっては、まさに穴場で、競争が激しくない割にはとても良い環境だと思うのでおすすめです!
― 今の研究内容を教えていただけますか。
ドイツにはまだ三週間弱しかいないので、実際に進んでいるわけではないのですが、東大時代のものと似ているのでそれも合わせてお話します。
まず物理の分類についてです。物理は実験と理論に分かれており、私は実験物理の方を研究しています。その中でも、固体物理、凝縮系物理の方の研究をしています。固体物理の面白さは、「固体であるものの研究」という点です。例えば、皆さんが使っているパソコンのメモリ等の熱電素材(熱を電気に変える素材)の性質などが研究対象です。応用面では例えば「もっと効率の良い素材にしよう」とか、基礎研究では「新しい量子力学の法則はないだろうか」といった観点から研究をしています。百年後、何かの役に立つかもしれないし、立たないかもしれません。
私が研究している物質は磁石の一種で「フラストレート磁性体」といい、普通の磁石にはない面白い性質を示す磁石です。量子力学的な法則を調べる際には室温が重要で、温かい室温では調べたい原子の性質がかき消されてしまいます。そのため、希釈冷凍機という超高性能の冷蔵庫のような装置を使って、-153度の極低温をつくり、その中に自分たちの試料を入れて測定し、何か新しい現象がないかを研究しています。
― 研究環境も日本とドイツで全く異なるのですね。
予算や装置の面でいえば、東大と現在の研究所でそこまで変わらない気がします。ただ、みんな仕事に関する考え方が違います。ドイツではみんな朝8時に研究所に来て夕方5時に帰りますが、日本ではみんな朝10時に来て夜の10時に帰ります。東大時代の研究室はそういう人が多かったです。そのため、ドイツに来てからは長時間労働ができなくなりました。ドイツだと8時間頑張るとそのあと疲れて働けなくなります。ドイツ人の仕事効率に関して、日本人より25%労働時間が短い一方で、25%生産性が高いというデータもあるみたいですよ。
― 今の生活のスケジュールはどのようなものですか。
私は大学の近くに住んでいるので、8時に起きて、9時前には研究室に着き、夜6時には退室します。こちらのスーパーは夜8時に閉まるので、すぐにスーパーに行って買い物をして帰宅して、晩御飯を食べ、メールを打って…という感じです。
土曜日は唯一の休みなので市内、日本でいう渋谷のような街に出て、洋服や他の生活用品等の買い物をします。。そういったお店も夜8時までしか開いていません。アウクスブルクの街の散策をすることもあります。日曜日は仕事や勉強をしています。
― 東大時代から続く現在の研究の楽しさ、難しさを教えてください。
楽しさですか…。つらいことしか思い出せません…(笑)
新しいことを学ぶのはとても楽しいです。例えば初めて希釈冷凍機をみたときに、私はこれを使うのか!と思いました。5~6000万円くらいする高い装置で、その原理を学んで使えるようになると、フェラーリを乗り回しているような気分になりました。乗ったことないのでわかりませんが(笑)。装置自体が熱力学の原理を使って低温を実現しているので、物理って凄いと思いながら装置を使っています。
データをとった後に、何が起きているのかを理論家と話したり、みんなと議論したりすることも楽しいです。最初は議論にプレッシャーを感じましたが、分からないことがあるのはみんな同じなので安心できました。意見を出しあっているうちに論文が出来上がります。一人で研究を進めるのが好きな人もいるかもしれませんが、私はみんなと交流し、いろいろな人の意見をきいて、どんどん自分にインプットされていく感じが好きなので、楽しいです。人と話すのが好きな人は研究者に向いていると思います。
― Tangさんは大学4年生のときに東大の大学院入試を受けて進学されましたが、そのときに考えられていたことを中心にお伺いしたいです。まず、ざっくりとした当時の志望理由、背景やきっかけをお聞かせください。
稲葉先生の授業を受けたことがきっかけです。稲葉先生の微分方程式の授業がとても面白かった。私は数学がすごく好きだったり得意だったりしたわけではなかったのですが、稲葉先生は物理学者なので、微分方程式の説明も全部物理現象と繋げて話してくれました。例えばある方程式が地震の波の減衰で表せるといった説明が目からうろこで、「はっ!確かに!」とその瞬間に数式が現実のものに変わり、それがすごく面白かったです。物理とか数学は難しそうだなという印象を持っていましたが、そのとき面白くて身近なものに感じました。
でもそれだけでは大学院進学までは決断できず、ただ興味本位で勉強していたのですが、勉強していくうちにどんどんはまっていってしまっていました。知れば知るほどもっと勉強したいと思いました。当時3年生くらいでインターンや就活もしていたのですが、勉強の世界も知ってから就活は違うなと感じてきて、大学院進学しようと思ったのがきっかけですね。すごい研究をしたい!というよりは、物理が面白かったのでもっと勉強したいというのが志望理由でした。
― 大学院入試は、どのように準備を進めてこられたのですか。
私は東京大学新領域創成科学研究科物質系専攻を受験しました。ここの過去問が古典力学、電磁気学、量子力学、統計力学、固体物理、化学などから4問選ぶ形だったので、私は物理の基本の4大力学に絞ることにしました。その4大力学を勉強するためには、まずある程度の数学ができないといけないので、数学は東大のカリキュラムをみて勉強しました。新領域創成科学研究科よりも入試の難易度が高く、数学と物理の両方が受験に必要である東大の物理工学科のカリキュラムを参考にしました。
東大の説明会にいったときに、東大の別の学科の学生と知り合って、一緒に勉強しました。彼からおすすめの授業をきいて早稲田の物理の授業を聴講し、量子力学や統計力学を学びました。あとはひたすら過去問を解くという感じですね。オーソドックスな授業を聴いて、あまりわかっていないかもしれない状態の中でも、そのあとに授業後の練習として教科書の練習問題を解いたり、過去問を10年分集めてそれをひたすら解いたりしていました。
研究室選びに関しては、苦労はしていません。説明会に行ったときに物理をやりはじめたばかりで研究内容等もわかっていなかったので、一番説明がわかりやすいところにしました。東大の中辻研究室を選んだ理由は2つあります。まず、海外の研究者とのコラボが多く、海外を視野にいれている点は他のラボにはあまりなかったところです。これはSILS生だとわかってくれると思います。そして、説明がすごくわかりやすかったところです。自分たちで結晶を合成して自分たちで測定する(基本的に合成と測定のどちらかです)ことの両方を行い、物性の知見が深まるとの説明があったので、わかりやすい!と思い、選びました。
― SILSは数学や物理を勉強していない人が多いと思うのですが、どのような人がSILSからでも理系大学院に進めると思われますか。
2つ条件があると思います。1つ目は「めちゃくちゃ頑張りたい!」と思える人です。2つ目は自分で勉強のスケジュールを立てられる人です。学部で理系の学生さんは何もしなくてもカリキュラム通りに学べば、大学院入試はほぼ問題ないと思うのですが、SILSの学生は基本的にそういったサポートがありません。そのため、様々な大学の理系科目のカリキュラムを見比べたり、みんなが使っているものではなく自分にあった教科書を選んだり、次の一歩としてどの練習問題を解くかを決めたりする必要があります。だから、自分で学習プランを立てられる人であることが条件なのです。
― 東京大学の研究室では、東大内部から進学された方も多かったとおもいます。内部生と比較してのTangさんの強みはなんでしたか。
内部進学をした方と比較して、我々SILSの卒業生は色々なことを勉強してやっと好きな学問を見つけたことが挙げられます。内部進学をした方は、例えば研究をやめて企業に就職するというように意外と研究に執着しないのですが、私自身は困難を乗り超えて進学しているので研究への執着は強いと思います。それは、何か困難があったときに立ち向かえる意志の強さでもあると思います。誰かと比較して得たものではなく、自分の人生に基づいて得た意志の強さです。
東大だけではなく一般的に理系の学生は普通修士まで進みますが、何となく流れで進む人もたくさんいますし、研究が好きだったのに、博士課程で急に嫌いになる人も私は目の当たりにしてきました。たとえアカデミアの世界に行かなくとも、少なくともこの数年間研究できる環境にいて辞めたくなることはないと思います。そういったconsistencyを得られたかと思います。
また、SILS生はみんな英語ができるので英語でコミュニケーションができるのも強みだと思います。東京大学でも、英語はできるのですが話すことに関しては不慣れだったり抵抗があったりする人も多い中で、SILS生は抵抗がありません。
英語は研究だけでなくて何をするにしても大事なのでもちろん語学の強みはあります。
― 一般的な高校生は英語が文系の科目だと思っている人が多い印象です。
むしろ理系の方が使いますよね。論文も全部英語ですし、私の研究室は国外の研究者とのコラボが多かったので、私の研究のコラボだとインドの先生、ドイツの先生、その他5、6人の先生と毎日英語でミーティングしていました。高校生がこのインタビューを見ていましたら、絶対に必死で英語をやってくださいというのが私のメッセージです!
― なぜSILSに進学したのですか。
選んだというよりはそのときの受験の都合でした。もともと高校は日本だったのですが、私はアメリカをはじめとした海外留学に興味があったので、大学受験時にSATを受けていました。日本の大学でSATを使える学部があまりない中で、SILSはSATでも受験を認めてくれる受験条件(AO9月入試)がありました。早稲田はいい大学であったこともあり、SILSを選びました。
― 今にして思うSILSの魅力や強みはいかがですか。
SILSの大きな魅力は勉強したいことを入学する前から決めなくてよいことですね。私も勉強したいことが決まっておらず、とりあえず色々なことを勉強してから自分のやりたいことを見つけました。例えば経済学部に進学していたら、絶対物理を勉強していないと思いますし、SILSでは教育熱心な先生が面白い授業をしてくれたので、そういった意味でやりたいことが決まってない人にはすごく合っていると思います。是非そこでやりたいことを見つけてほしいと思います。
学習面以外のSILSの魅力としては多種多様な生徒がいることですね。特定の分野の学科だと似たような人が集まりがちですが、SILSはバックグラウンドが様々で帰国生と純ジャパが混ざり、理系科目に興味がある人もいれば全然違う人もいます。色んな課外活動している人がいたり起業をしている人結構いたりしますよね。多様性がある文化はよいと思います。
― 在学中は稲葉先生のゼミに所属されていましたが、ゼミでの学びはいかがでしたか。
稲葉ゼミは学びしかありませんでした。私のSILSにいたすべての意義です。稲葉ゼミの中心人物は稲葉先生なので、稲葉先生からどれほど学びとれるかが重要でした。私は稲葉先生とお話しする1分1分がすごく貴重でした。稲葉先生の科学に対する考えに感銘を受けました。稲葉先生って、わからないことにはいくらでも時間をとってくれます。それが本当に素晴らしい先生でした。稲葉先生のすごいところは「これをやれ、あれをやれ」とは言わないのですが、学生が疑問を持っていることに対して本当に時間をかけて説明してくれるところです。常に答えてくれる姿勢をもった先生ですね。
わからなかった概念も、稲葉先生に聞くとわかったりするのです。そういった体験を積み重ねたことによって大学院を受験する決断もできましたし、物理は難しいけど不可能な壁ではないと思えたのも、先生がいたからだと思いますね。
研究者になるためには基礎知識や基本的な科学的思考が必要だと思うのですが、その入門編を教えてくれたのが稲葉先生です。科学は難しいものではなくみんなができるものであると啓蒙されました。それが全てです。いまどのように具体的に役に立っているかはわからないですが、それがなかったら今の自分は確実にいません。稲葉先生は科学の道に私をいざなってくれました。それが一番大事です。
もうひとつは、私は文系から物理を勉強したという大きな転換をしました。物理においても様々な手法があり、自分のできることを増やさないといけませんが、「文系から物理学を学べたのだから他の教科もできるでしょう」と先生に励まされ、それが自信になっています。物性物理はわからないことがたくさんありますが、いつかわかるはずだという気持ちになれたのは、稲葉ゼミでの勉強の成果だと思います。
全ては稲葉先生という中心にいる先生に支えられ、本当によい経験をしました。稲葉先生はよい先生です!
― 最後になりますがSILSを目指す高校生にメッセージをお願いします。
もし進路が決まっていなくて悩んでいても、焦る必要は全くないです。SILSをはじめとする勉強したいことを見つけるための手助けをしてくれる大学や学部があるので、そういった場所に行けばいいと思います。幅広く学びたい高校生、色々なことに興味があって自分の軸がまだ決まっておらずこれから見つけたい高校生は、ぜひSILSを考えてください。
海外志向があり英語力を鍛えたい人にもおすすめです。1年生の頃にあまり英語ができなかった人も卒業する頃には結構できるようになっていますよ。
掲載情報は、取材時点のものになります。