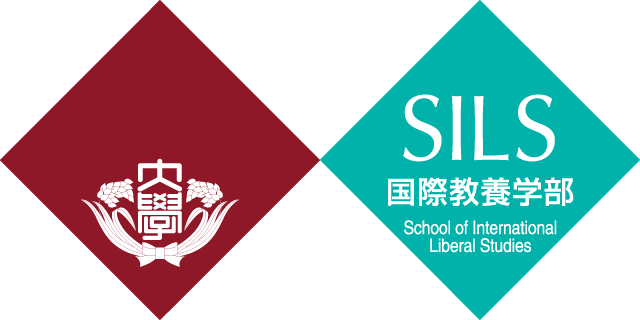- ニュース
- 授業紹介:Seminar on Mind and Body
授業紹介:Seminar on Mind and Body

- Posted
- 2023年4月25日(火)
 |
||||
|---|---|---|---|---|
東 玲奈
|
||||
| 昨日ニュースで見た、あの著名な作者。名前を知っているのに、今思い出せない。なぜ?私の小さな姪を抱っこしたら泣き出した。こないだは大丈夫だったのに。私は普段炭酸飲料を飲まないのに、今日はつい買ってしまった。なぜ?私の母がミールキットで料理するのは簡単だと言っていたけど、説明文より倍くらい時間がかかってしまった。なぜ?
心理学は行動と心の科学であり、見過ごしがちな事に気づき、なぜ起きるのか考えることから始まる。情報が様々な量や形で、探さなくてもどんどん届く今の世の中でも、ふと立ち止まって気づきさえすれば周囲に不思議はいくらでも転がっている。説明だって見つかるだろうが、自身で確認し新発見があったら、面白くてさらなる好奇心がかきたてられる。 本ゼミでは、学生はそんな不思議を見つけ、個人でもグループでも、教員と相互のサポートを常に受けながら追及できる。身の回りの不思議を自由に追求できる場なのだ。 |
||||
– 精神疾患の理解という点で遅れをとっている日本ですが、そんな社会が少しでも良い方向に向かうよう精進したい –
私は留学を機に東ゼミに入ることを決めました。留学先は韓国のYonsei Universityで、様々な観点で精神疾患について考えさせられた留学生活でした。主に精神疾患の研究を目的とした学問である臨床心理学の授業を受講し、精神疾患をもつ生徒のための学校でボランティア活動をしました。心の病を持つ人や自身を制御できない人、意思疎通が難しい人など、他の人のサポートが必要不可欠な方々に出会い、「障害って自分には関係ない」という考え方がいかに甘かったか痛感させられました。彼らについてもっと学びたいと思い帰国後に東ゼミに入りました。
東ゼミは唯一、国際教養学部で心理学を扱うゼミです。東教授は認知心理学専門なのですが、認知以外の心理学も担当されています。授業はゼミ長や副ゼミ長を中心に学生主体で進行されます。内容としては、1. 指定された論文を用いたディスカッション、2. 心理学関連の議題に沿った討論、3. 興味関心によって分けられたグループでの実験活動等があげられます。
1.ディスカッション
論文は認知心理学や社会心理学など各分野1本ずつ持ち込まれます。その週の代表グループが専門分野の論文を選択しdiscussion questionsを設けます。学生たちは授業日までに目を通しディスカッションに臨みます。授業当日は分野関係なしにランダムで分けられたグループ内で議論します。「トランスジェンダーと精神的苦痛の関係」についての論文や、「ネガティブな記憶内のポジティブな側面の発見による記憶の更新」についての論文などが実際の授業で使用されました。
2. 討論
討論は4グループに分かれて行われます。一つのグループが賛成、もう一つが反対、残りの2グループは傍聴人となります。翌週は傍聴人が賛成や反対に分かれ、すでに討論に参加したグループは傍聴人に回ります。「人付き合いにおいて自分と似ている人や違う人、どちらが好ましいか」などのテーマを扱いました。
3.実験
実験は一学期を通して行われます。アンケート調査を基盤としていて、グループ分け、実験内容考案、実験準備、実験(データ収集)、結果分析、発表、報告書提出までが一連の流れです。内容や方法等は自由なので、教授の助言を参考にチームメイトと相談しつつ枠組みを作っていきます。講義では経験できない、東ゼミならではの活動だと思います。
上記以外にも、ゲストスピーカーとして東ゼミOBの方をお呼びし、お話を伺うなどかなり幅広く活動しています。あるOBの方はメンタルセラピストで、私が将来したい職業とかなり似たお仕事をされています。その方の他にも日本や海外の大学院に進み、心理学を基盤として活躍されている方が多数います。東ゼミでの活動や出会いを通じて、心理学の道に進みたいという気持ちがより一層強くなりました。精神疾患の理解という点で遅れをとっている日本ですが、そんな社会が少しでも良い方向に向かうよう精進したいと思います。
 |
This article is written by…
成 リン
|
||||
※この記事は2023年1月時点のものです。
※この科目は毎学期開講されない場合があります。