- Featured Article
Vol.4 教育心理学(1/2)【子どもの心を科学する】生徒・児童の自信を育てるアンガーマネジメント研究 / 本田恵子教授
Thu 27 Jun 24
Thu 27 Jun 24
今回と次回の二回にわたって、早稲田大学教育・総合科学学術院の本田恵子教授をゲストに迎え、「アンガーマネジメント研究」をテーマに、教育心理学シリーズをお届けします。
怒ることを我慢することがアンガーマネジメントではない。自分の感情を認識し、自分と語り合いながら自分自身をマネジメントする方法こそがアンガーマネジメント。
コロナ禍で対人経験を積む時間を逃してしまった生徒・児童たちが抱えるストレスへの対応に注目が集まる中、徹底的な現場主義で生徒・児童に寄り添い、子どもたちの心を研究しているのが、本田恵子先生です。
配信エピソード一覧
ゲスト:本田 恵子
早稲田大学教育・総合科学学術院教授。アンガーマネージメント研究会代表。公認心理師・臨床心理士・学校心理士・特別教育支援士SV。中学・高校の教師を経験したあと、カウンセリングの必要性を感じて渡米。特別支援教育、危機介入法などを学び、カウンセリング心理学博士号取得。帰国後は、スクールカウンセラー、玉川大学人間学科助教授等を経て現職。学校、家庭、地域と連携しながら、児童・生徒を包括的に支援する包括的スクールカウンセリングを広めている。

ホスト:城谷 和代

研究戦略センター准教授。専門は研究推進、地球科学・環境科学。 2006年早稲田大学教育学部理学科地球科学専修卒業、2011年東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻博士課程修了博士(理学)、2011年産業技術総合研究所地質調査総合センター研究員、2015年神戸大学学術研究推進機構学術研究推進室(URA)特命講師、2023年4 月から現職。
- 書籍情報
-
-
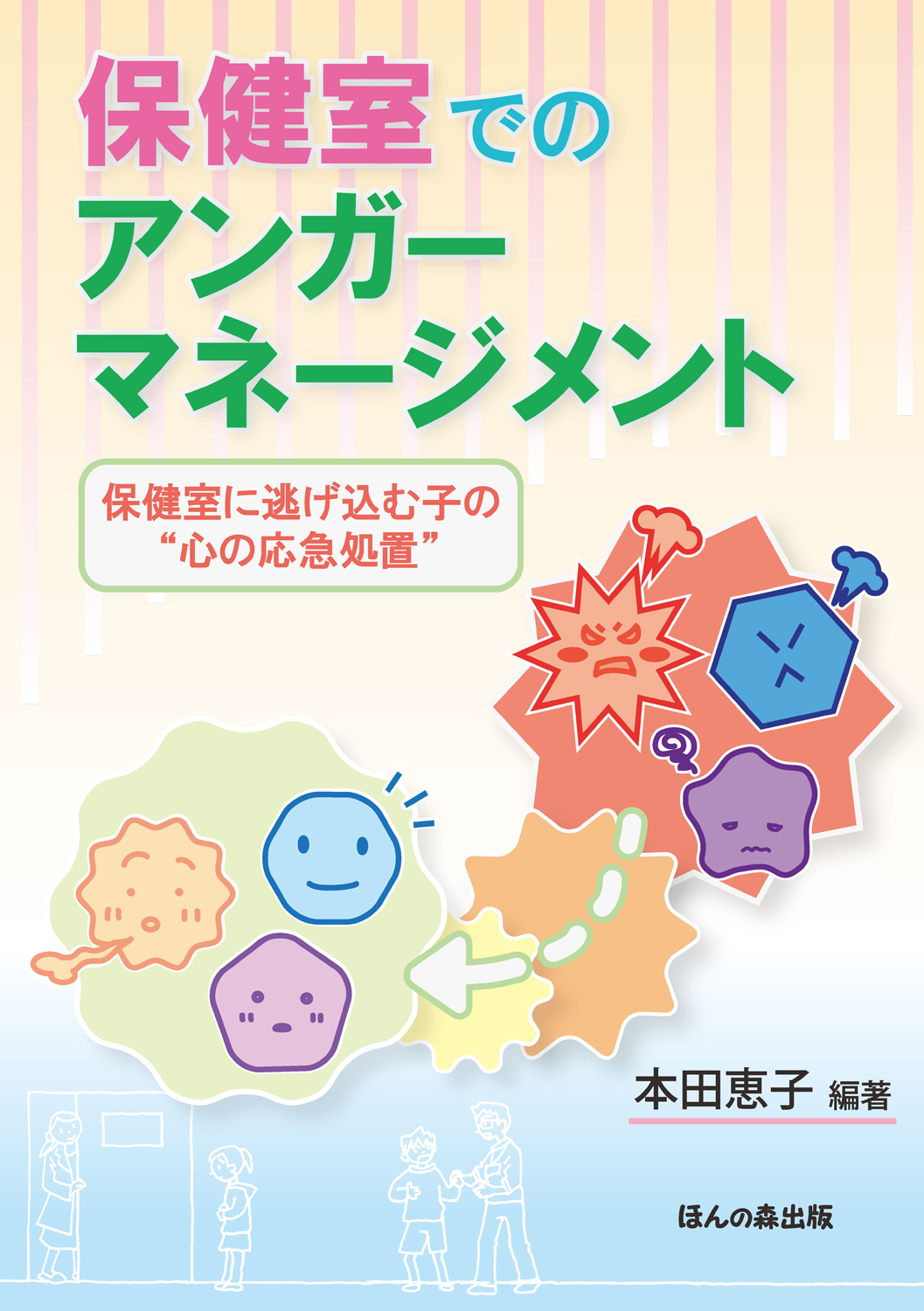
保健室でのアンガーマネージメント 保健室に逃げ込む子の“心の応急処置”
出版社 : ほんの森出版
著 者:本田恵子
発売日 : 2022/1/31
言語 : 日本語
単行本 : 112ページ
ISBN-10 : 4866141247
ISBN-13 : 978-4866141244 -

「8つの知能」をいかすインクルーシブ教育 MI理論で変わる教室
出版社 : 学事出版
著 者:本田恵子
発売日 : 2024/5/22
言語 : 日本語
単行本(ソフトカバー): 140ページ
ISBN-10 : 4761930047
ISBN-13 : 978-4761930042
-
エピソード要約
-アンガーマネジメントとは
アンガーマネジメントは怒りだけでなく様々な感情に対応するスキルを育てるためのもので、学校教育においては、子どもたちが様々な感情と向き合い、学校や社会で健全に成長するためのプログラムとして用いられている。アンガーマネジメントのプログラムは、問題が起こる前の予防教育、危機介入、個別対応の3段階に分かれており、現在は危機介入のニーズが高まっている。
-アメリカと日本のアンガーマネジメントプログラムの歴史
アメリカでは1980年代に学校内の暴力や非行対策として、ゼロ・トレランスやエクスクルージョンといった動きが出てきており、アメリカの学校では行動規範を作り、校内で問題を起こした生徒にはアンガーマネジメントのプログラムを受けさせる仕組みが整えられている。 日本でも1990年代以降のいじめや自殺の社会現象化を受けてアンガーマネジメントへの関心が高まり、保護観察者向けのプログラムを学校現場向けに調整することで適用が始まった。
-本田教授の研究について
本田教授は実践と科学を融合させたサイエンティスト・プラクティショナー・モデルとして、現場のニーズに基づいた研究を行っている。研究は量的データと質的データを組み合わせて行い、実践後も継続的にデータを収集して効果を検証する。行動観察は学生たちと協力し、面接やアンケートを通じて子どもたちの感情や行動の変化を詳細に記録している。
エピソード書き起こし
城谷准教授(以降、城谷)
まず、本田先生のプロフィールを紹介いたします。
中学高校の教師を経験された後、カウンセリングの必要性を感じて渡米。
コロンビア大学大学院にて、カウンセリング心理学博士号を取得されました。
帰国後はスクールカウンセラー、玉川大学人間学科助教授を経て、現在早稲田大学にて教鞭を執られています。学校、家庭、地域と連携しながら、児童・生徒を包括的に支援する包括的スクールカウンセリングを広めていらっしゃいます。
また、学校やカウンセリングの現場における子どもたちのためのソーシャルスキル・トレーニングの教材開発にも取り組まれ、教育現場での実践向けの書籍も多数刊行されています。
先生のご専門であるアンガーマネジメントとは、日常で直面する怒りの感情と上手に向き合うための心理教育やトレーニングとお聞きしていますが、教育現場において、今どのようなことが課題となっていて、その中でアンガーマネジメントはどのような意義があるとお考えでしょうか。
本田教授(以降、本田)
そもそもアンガーとは怒りだけではなく、色々な感情が入り乱れている混沌とした状態なんです。そのため、すごく不安で不登校になってしまうとか、授業中にイライラしてしまうとか、いじめられて自分が傷ついてしまうとか様々な感情を抱えている子どもたちがたくさんいます。
上手に人と関わって、話し合って解決する。そういう力が育ってきていません。特にコロナの3年間の後は。子どもたち自身がちょうど思春期を迎えて、お友達と集団になったりとか、話し合いをしたりとか、文科省が目指している探求の時間とか、グループ学習ができない。今のアンガーマネジメントの中でいうと、学校教育の中で予防教育と呼ばれている第一次予防。色々な問題が起こる前の段階ですね。そこと学校で例えば勉強が嫌い、暴れているとか。そのようなところへの危機介入という二次予防。いじめなど色々な非行もありますが、繰り返してしまう。その場合は三次予防ということで個別の対応。この三段階があります。
アンガーマネジメントそれぞれにプログラムがあって、今一番ニーズがあるのがちょうど危機介入のところ。『保健室のアンガーマネジメント』は、そこのニーズに応えて作った本なんです。
城谷:
アンガーマネジメントは、コロナも踏まえて変わってきているとお考え。
本田:
そうですね。大人も子どももストレス溜まりやすい状況になって、うまく発散できていないなという感じがしてます。
城谷:
ありがとうございます。そもそもアンガーマネジメントという言葉を耳にするようになったのは、日本ではまだ最近のように感じられますが、国内外を含めて、アンガーマネジメント研究の歴史について、教えていただけますでしょうか。
本田:
アメリカからこれは始まって、私がちょうど留学していた頃、相当アメリカも荒れてる時代でした。1980年代、そのちょっと前ぐらいから、虐待、麻薬、非行、学内での暴力がアメリカの中でもあって、バイオレンスフリースクールという動きがアメリカでも出ていました。それと同時にゼロ・トレランスという言葉があって、学校はストレスがない状態で学びを進めるところだと。生徒指導の場じゃないぞ、みたいな。エクスクルージョンという形になりますが、学校は安全で勉強など自分のパフォーマンスができるところ。
生徒指導や虐待、不登校対応という部分はエクスクルージョン、外の専門の機関でやりましょうと。発達障害の子たちもそうだったんです。個別最適化みたいなところで、ADHDの発達障害の子たちの専門の学校ができたりとか。
城谷:
施設自体、場所自体も。
本田:
場所自体も全部外でした。
生徒指導のアンガーについても、校内で例えば暴力を振るったとなると、もう学校にいられません。きちんと外の施設で30回アンガーマネジメントをしてからでないと教室に戻っちゃいけませんという行動規範。ゼロ・トレランスをやるためには行動規範を作って、遅刻したら何点マイナス。授業妨害したらこう。いじめをしたらこうなど。宗教とか国民とか全部違うので、統一した形でみんなが文句を言わないような行動規範を作って、授業が始まる時に親子でそれに従いますとサインする。ダメな時にはちゃんとプログラムを受けますみたいな。そういうことをやっていきました。
城谷:
色々な考え、バックグラウンドがある人がいる中、統一した規範を作るところで誰も文句を言わないという言葉があったと思いますが、それはできるものなんですか。
本田:
学校の中でのシティズンシップ、子どもたちが学校の一員であるというための権利を守るためには、自分たちがきちんと責任ある行動を取らなきゃいけません。
子どもを大切にするという児童憲章もありますが、そういう動きが出てきたんです。
親子できちんとそれに従いますという。
逆にそれがないと、先生によって対応が全然バラバラになってしまったら、一貫性がないですよね。
そこは賛成反対もちろんあったし、アメリカに行って学んだ方が日本に取り入れようとしたこともありますが、なかなか馴染まなくて。私学でいくつかその行動規範を作ろうというところ。大阪府は一部で入れてますね。やっぱり荒れがかなり激しいところではきちんと対応しないと、口頭注意だけではどうにもならないという動きが出てきた。学内では行動規範をきちんと作ったことと同時に、教育だけじゃなくて、教育と司法、それから保健。カウンセリングとその3つが協力した形で子どもを健全に育てないといけない。
罰するためのものじゃないんです。アンガーマネジメントはもう一度きちんと自分のことを理解して教室や学校に戻ってくるバックトゥースクールという動きがとても大きいです。そのためにも子どもに合うプログラムを作りましょうと。
そこで出来上がったものを私は学ばせていただきました。
城谷:
日本に適用させようという動きもあったとお伺いしましたが、そういったものはその国の文化や社会機関に大きく影響しているように思うのですが、日本におけるアンガーマネジメント研究の歴史について教えていただけますか。
本田:
日本の場合は1990年代にいじめによる自殺とか、様々ないじめの問題が社会現象になりました。あの辺りから子どもの暴力とか激しい怒りの感情に大人がどう対応していけばよいのか。こういう子どもたちは大人を信頼していないので相談しません。不登校も増えました。学校現場の話でいくと、生徒指導が今までやっていた口頭注意とかいわゆる説諭が成り立たない。言っても「はい、分かりました」と反省文は書く。でもやっぱりやってしまう。そうなるときちんと本人が自己理解を深めて、新しい行動パターンを身につけるような教育の場所、教育プログラムがいるという動きが出てきてはいたんです。それ以前からいじめ予防のため、ソーシャルスキル教育やアサーションとかが入っていましたが、それはあくまで第一次予防。いじめをしない、暴力を起こさないための教育というところで役に立っていましたが、自分の中でもなかなかコントロールできないという状況で現場対応と繰り返しやってしまう方に対しての個別対応というのはありませんでした。それを作ってもらいたいというのがあって、同時進行で法務省の委託を受けて、保護観察の人たちに対して、アンガーマネジメントプログラムを作ってもらいたいというのがありました。
そちらを先に作っていたので、学校現場にも合うようにと学校現場用のものを6回から8回。刑務所の方は13回とか15回と長かったのですが、そのプログラムとして作っていきました。
城谷:
刑務所の方で作られてたものを同時並行で学校向けに作られる中で、特に学校向けに作るところで意識された点はあったのでしょうか。
本田:
小学校・中学校・高校で発達段階が違うので。刑務所の中は大人の方が対象になるので、自分でも犯罪を起こしているから、何をやったということははっきりしていて、自分で振り返ろうということができますが、小・中学校は日常生活の中でいっぱいあるわけです。だからそこだけに特化すると子どもは嫌がります。だからそこはもちろんやりますが、導入として、「こういうふうにしてあなた辛かったよね」、「授業中に飛び出しちゃったよね」、「友達に物投げちゃったよね」など。そこから入るけど、なんでそうなるんだろうねという自己理解。その自己理解と自己受容に注目できるように、自分の特性について、「こうだから衝動的なんだよね」、「すごく不安だから先手必勝で先に手が出ちゃうんだよね」、「本当はすごく怖がりで暴力振るうのは自分を守るためなんだよね」みたいなことが語れる場面をたくさん作ろうというところで、子どもたちが自分をしっかり客観的に見つめるが、「マイナスだからあんたこれダメよ」とかではなく、「そういう特性なんだよな」、「やっちゃうんだよね」、「どうしたらいいかね」と自分と語り合いながら自分でマネジメントする。アンガーはコントロールではなくマネジメントです。
色々な感情、寂しかったり悔しかったり嫉妬したり。いいんです怒って。だけど「正しく出さないと。物投げたら伝わらないよね」、「物壊したら相手も傷つくし自分も傷つくよね」ということ。そういう感情に気づいて、正しい出し方をする。
城谷:
溜め込まずに。
本田:
そこをすごく大事にしました。
特に日本人は抑圧が多い。海外は出してくれるから、出すところのストレスマネジメントから入ればいいのですが、日本はまず色々な気持ちを出していいんだよというところから。「怒っちゃいけないんでしょ」、「我慢すればいいんでしょ」ということではなくて、「だって怒っているでしょ、怒ったら苦しいでしょ。体が熱くなるよね。だから出したくなって手が震えてるよね。それを緩めてあげるために出していいんだよ」、「ただあなたも傷つかない、周りも傷つかない。そういう方法があるから一緒に考えない?」というスタンスで語りかける。
城谷:
私もお聞きして、そうなんだと思いました。
本田:
そこを言うと「えっ」、「だったらやる」みたいな。
「僕は怒られるから、先生に行けって言われたから来たけど」とか。
「何をしに来ました?」と聞くと、「こういうことで行けって先生に言われました」、「親に言われて来ました」とか。「あ、そっか、苦しかったね」、「よく来てくれたね。ウェルカム」みたいな。
「ここはこういうことをするところだよ」と話をしていくと、「そうなんだ」と自分からどんどん来て、「実はね、こんなことがあってやっちゃうんだよね」、「またやっちゃったんだよね。どうしようかな」、「分かっていたんだけど、この時手が出ちゃうんだよね」といった感じで「分かってるのはどこまでだ」みたいな話をする。子どもとの対話を中心にしながら、自分のパターンを子どもが苦しまずに見つめられる。そういうプログラムにするというところで子ども向けにやっています。
城谷:
先生のご研究の主義やお考えにおいて、実践、教育現場での研究を精力的にされている点がお話いただいたところにつながるかなと思いました。
実際の研究活動を想像しますと、研究対象が生身の人間ということ。ましてや怒りも含めた感情であることを思うと、研究活動の難しさが想像されました。そこで具体的にどのように研究を進めていらっしゃるのか。そのあたりをお伺いしたいと思います。
本田:
私のスタイルはサイエンティスト・プラクティショナーというもので、実践しながら科学していくものなので、現場のニーズに合う研究なんです。
こちらが何かデータが欲しいからと行って、実験計画をするものでは全然ないです。だからそこがすごく難しい。
「今、中学校1年生の学年が荒れてます」となると、「どういうことが起こっていますか」と先生と一緒に相談して、だったら6月くらいからアセスメントを取ってみて、「原因は学級の授業かな」、「それとも対人関係かな」という感じで実態調査をします。
それをもとに先生方もこんなことが起こってるんだと分かれば、予防的な部分がいいのか。それとも繰り返ししている子たちには、ちょっと取り出しでやったほうがいいのかということを一緒に考えながら、その学級がありたい姿をいわゆる研究のゴールに持っていて、それに近づけるためにどういうプランを立てていったらいいか。そこをやってから実践します。
それはきちんとデータに取っていったほうがいい。向こうは困ってますから。助けてくれると思っているので、学校長の許可とかをもらっていくと、「ぜひデータを使ってください」、「他にも役立ててください」と言ってくださる。研究はすごく難しいです。心理系のところは最初に何か実践すると、比較群というものを作って、アンガーをやったところとやらないところで比較しないといけない。それも同じ質のクラスで比較しないといけない。そんなことできないじゃないですか、教育上。倫理的にA組はやったけど、B組はやらないということはできないので、ベース期間というものを作るために、例えば2学期の9月から11月にやりましょうと。じゃあ1学期の間、何もしない状態なんだけど、見守りながら何が起こるか測りましょう。色々なデータを集めながら、じゃあこのプログラムを9月10月にやってみよう。そして事前事後を測りながら、その間ずっと質的にデータを取っていきます。行動観察です。そこは学生たち、公認心理師の育成を早稲田の(教育学部教育学科)教育心理(学専修)でやっていますので、その方たちが一緒に協定を使って入っていって、その中で子どもたちに接しながら行動観察を取ってくる。それが質的なデータとなるし、毎回の振り返りでこういうことが分かったとか、この部分がまだ自分にとっては困るとか。そういう質的なデータと量的なデータを両方しながら、1回のプログラムが終わります。事前のところと事後のところ。1年間でクラスが変わってしまうので、2月ぐらいにもう1回、クラスの状態はどうですかと。そのように測ると、とりあえず自分の中で比較できるので、心理の研究の形にはなる。そんな形で量的なものと質的なものを取っていくところはあります。
城谷:
行動観察ですが、実際にはどのようにされるんですか。子どもたちと面接をするとか、アンケートを取るとか。
本田:
関わりながらの面接です。アンガーは子どもに「今日の気持ちはどうですか」、「なぜそうなりましたか」、「こういう場面の場合にはあなたはどうしますか」、「親に成績が悪いよねって言われた時にどう反応する?」、「自分の考え方って何」というのが5過程あります。その順番に全部で6回、5過程を使いながらやっていきます。
その時、学生さん1人がだいたい6、7人を見て、その子たちとやり取りする。授業終わったら、この子とやったみたいな。録画してるわけではないので。学校場面ではそういう形なんですが、早稲田の教育・総合科学(学術院)の付属に教育総合クリニックというものを作っています。
そこは学生さん育成の場所かつ公認心理師の方の相談の場所でもあるのですが、そこで幼稚園から高校3年生までの方たちの心理相談、心理アセスメント、アンガーマネジメントの10名対象の小学生プログラム、中学生のプログラム、これは6名ぐらいなんですけど、中高生のソーシャルスキル・トレーニング、自己技能トレーニングとか。学習のLDの子たちに対して、そういうのを組んでいます。
そちらの教育総合クリニックの場合、親御さんから許可をいただいているので、録画を撮らせていただいています。行動観察に関して、子どもたちの言葉とか行動とかを一緒にビデオで見ながら、「こういう行動がここで出ているね」、「1回目こうだった子が2回目こんなふうに変わったね」、「ここで切り替えできたね」、「修正できているね」みたいな。そういうことをビデオからデータを集めていく。
クリニックの場合、量的なものより質的な調査なので、アンガー(マネジメント)は小学生だと6回から7回やります。どう変化したのかということと自分でアンガーのマネジメントができるようになるまでにどんなプロセスがあったのかというのは、M-GTAというやり方なんですが、逐語を拾っていきながら、「ここの部分がこう変わったね」という変化のプロセスモデルを作ります。
城谷:
信頼関係というのが非常に重要なのかなと思いました。
本田:
まずは関わってる学生さん。私はそういう時、ポンちゃんって呼ばれます。
城谷:
本田恵子のポン?
本田:
昔からポンポンと呼ばれていて。ポンちゃんポンちゃんと子どもたちも呼びますが、学校の現場に行っても、「アンガーのポンちゃんだ」とか。
子どもにとって信頼できる大人にならないといけないので、まずは自分が「あなたのことを信じてるよ」と。こっちが押さえ込むんじゃなくて、「できるよね」、「君は今荒れてるけど私の声聞こえてるよね」、「あなたどうなりたいの」、「自分でできるでしょ、信じてるよ」、「今待つからってやってみ」といった感じで。できたら「できたじゃん」みたいな。そういう関わりを自分がやりながら、今度は学生にもモデリング。自分が実践するのを見せつつ、学生を育てる。OJTですね。
城谷:
なるほど。
本田:
終わると学生さんはみんな子どもたちに圧倒されて。すごいエネルギーみたいな。すごく学生が育ちますね。だから良いカウンセラーさんになるとか、それこそ矯正教育のところ、今、公認心理師の方たちの合格率がとてもいいです。現場でどんどんやってくれる。病院の療育とか学校の先生にもなるけど、心理教育ができる先生になっていく。
そういう形ができているので、まさにそのサイエンティスト・プラクテショナー・モデルを実践させていただいています。
城谷:
本田先生と児童・生徒、プラス学生さんという中で研究されていると思いました。
特に近年、力を入れて取り組まれている研究テーマはおありでしょうか。
本田:
実行機能トレーニングです。アンガーマネジメントの話に少し戻ると、アンガーは脳の機能が引き起こしています。脳は低次の脳と高次の脳というのがあり、低次の脳が感情と自律神経系と行動なんです。怒るとすぐ行動になってしまうのは、このオートマチック思考の中、刺激反応で行動になってしまっている部分をまずコントロールしないといけない。これはストレスマネジメントなんです。そうすると大人のアンガーはまず深呼吸とよく言われますが、ストレスマネジメントが最初にあって、低次の脳がちょっと落ち着いてきたと。そうすると呼吸も荒いのが少し落ち着いてきて、体、緊張しているじゃないですか。体が緊張しているのを緩めよう。力が抜けたらダンと叩くテーブルもトントンで済むので、体の力を抜こう。そこまで来ると肩から力が抜けるので、心臓から血が上に上がります。そうしたらやっと高次の脳が動きます。
いわゆる人間の脳で言語と視覚が広くなる。一番大事なのが前頭葉という考える脳です。ここに制御機能、車で言えばアクセルとブレーキ。それとこれからどうしようかという計画を組み立てる分野が前頭葉にあります。
ここが動けば自分の行動をアンガーマネジメントできます。どんな感情も持っていいよ、それをまず言葉にしようよ、怒っているとか悲しいとか悔しいとか寂しいとか。それをどうやって出したらいいだろう。寂しいなら泣き喚けばいいのか。悔しいなら相手から物を取ればいいのか。それは違うよねということを前頭葉で考えて、物を取りたいけど手を止めよう。止めたけど相手が持っている物は羨ましい。じゃあどうしようということを頭の中で企画する。そのためにも高次の脳が動かないといけない。
前頭葉の実行機能のトレーニング。ここが発達してないと最終的にはマネジメントできません。
マネジメントができたら、自分で内的制御ができる。
それができないと外からの制御で行動規範があったり、大人がダメでしょと言ったり、物を取り上げたりとか。刑務所なんか最たる例ですよね。
外的制御で縛られてる状況で何もできないからそこではうまくいく。だから刑務所の人たちはプログラムで徹底的に内的制御に変えます。「外からじゃなくて自分で変えるんだよ」、「自分で窃盗しないんだよ」、「自分で暴力振るわないんだよ」、「自分でアルコールの方に行かないようにする」など。制御する前頭葉のトレーニング。自分と語るんです。
「何したいの」、「本当にやりたいのこれ」、「本当に欲しいのこれ」、「これやったら誰か悲しむんじゃないの」。それがセルフトークになります。自分と語り合うから。
語り合っているうちに、「こんなところで物を取っちゃダメだよな」、「ここで物を壊したって一時的にはスッキリするかもしれないけど後で落ち込むよな」、「弁償もしなきゃいけないしな」みたいなことを考える。そのために自己機能の前頭葉トレーニングをする。ここを今やっています。
アンガーマネジメントのプログラムを終えた子たちに自己機能プログラムを紹介して、ちょうどやっている最中です。変わりますね。こんなに変わるんだなというぐらいに。話し合いながら修正、一時停止とか。自己機能は始める・終える・一時停止・修正・いろんな計画を立てるとかがあり、これができるようになります。
そうしたら最後は仕上げになるので、そちらと連動した形で次のプログラムを考えている最中です。
城谷:
自分で抑えられると、本人自身もすごく自信になるんじゃないかなと思いました。
本田:
そこがすごく大事です。その力を周りの大人が信じてあげる。そうすると子どもは「できるよね」、「君はこうだよね」と変わっていきます。ちょっと面白いエピソードがあって、「もうアンガーマネジメントに来たくありません!」と喚いてた子がいたんです。「こんなところ絶対嫌だ」、「なんで土曜日に遊びたいのにこんなところに来なきゃいけないんだ!」と怒っているので、「そうだね」と。「じゃあもう来なくていいですか!」と言うので、「来なくなっていいためには、ポンちゃんが合格出さなきゃいけないんだ」と伝えると、「どうしたら合格になるんですか!」と怒っている。「まずは落ち着かない?その声って合格の声かな」と伝える。すると「ふー」と我慢している。「じゃあどうするんですか」、「次はメッセージだったよね」と言うと、「僕はもう来たくありません」と。「言えたね。じゃあ、2ステップOKだね。じゃあ、理由も言ってみようか」みたいなことをやっていって、「もう嫌です!」とまた座り込むんですよ。座り込むと「座り込んで帰れるかな」、「ポンちゃん信じてんだけどな」とか言うと、立ち上がって「おお、それだね」みたいに言って。そんな感じで頑張ってやっていくと自分でできるんですよ。「その感覚覚えとき」、「ママもこれ応援して」みたいなことになったら、「もう来ないからね」とか言いながら帰っていく。私は「バイバイまた来週ね」とやるんですけど。
自分で本当に自分のことが分かって、自分で何とか悔しいけど立ち上がろうとかできるようになります。そこを信じてあげられるといいかなと思います。
城谷:
やはり子どもの心に寄り添って、その子が自然とやっぱり自信を持てるようになっていくというのがあるのかなと思いました。
前編の最後の質問となりますが、児童・生徒のアンガーマネジメントという研究がもたらす教育現場への変化や期待、可能性について教えていただけますでしょうか。
本田:
まず、学校の現場の先生方がとても大変なんです。発達障害の方とか、コロナの後の対人関係が苦手な子どもたちとか。少子化で兄弟喧嘩とかしてきてないので、話し合って解決するとかしてない子どもたちを対応しないといけない。そのため先生がアンガーになってしまいます。まず先生たちが子どもたちと上手に対応できるという先生自身のアンガーマネジメントの力をつけるようなサポートができるといいかなと思います。
あとはどうしても繰り返しいじめてしまう、暴力が繰り返されるというのもまだまだあります。
ですので、それに対応できるプログラムが学校の中でもできるようになるといいなとは思いますが、そこは生徒指導対応での変化がありますから、そこに向けて何かお手伝いができるといいなと思っています。






