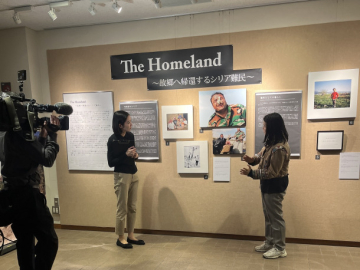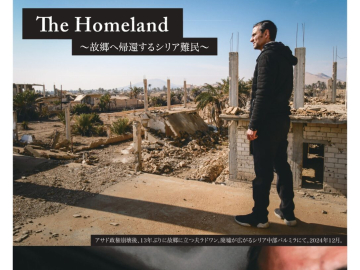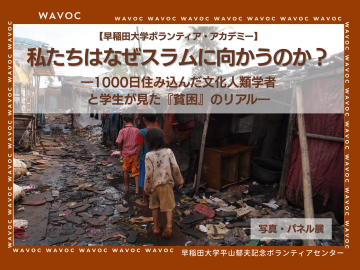相馬 拓也(そうま・たくや)/早稲田大学 高等研究所(WIAS) 講師、博士(農学)略歴はこちらから
日本は台風、地震、津波、火山、地滑り、豪雨、雪害、洪水……と考えられる限りの自然災害がめまぐるしく発生する「被災大国」でもあります。そうした地域の災害事象は 「災害記念碑」として記録されることもあり、たとえば津波について書かれた石碑などは国立民族学博物館で判読・データベース化が進んでいます(http://sekihi.minpaku.ac.jp/)[1]。また高潮や津波で打ち上げられた「台風石」「津波石」などは、その位置・規模・移動方向などの解析により、津波や地震規模の推定にも役立つ貴重な「災害遺物」でもあります [2]。しかし記録資料の乏しい地域や社会、例えばモンゴル遊牧民のコミュニティなどでは、過去の災害経験の記憶の一切は口承伝達によって継承されてきました。被災経験のオーラルヒストリーは、集団的記憶として長くとどめるべき貴重な資料ともなります。モンゴル遊牧民が受け継いできた伝統的な気象予知法や災害対処術には、現代社会の防災・減災思想の原点を垣間見ることができます※。
1. 寒雪害“ゾド”と災害予知の伝統知
| 1 | ガン・ゾド | 乾燥・干ばつによる乾害 |
|---|---|---|
| 2 | トーライン・ゾド | 過放牧による牧草欠乏害 |
| 3 | ツァガーンゾド | 多雪・降雪による雪害 |
| 4 | シレン・ゾド | 凍結融解による氷害 |
| 5 | フイテン・ゾド | 極度の低温による寒害 |
| 6 | シュールガ・ゾド | 強烈な風・嵐による風害 |
| 7 | ハル・ゾド | 雪不足による水源欠乏害 |
遊牧民の直面する自然災害でもっとも激甚被害をもたらす脅威のひとつに、冬季に発生する「ゾド dzud」と呼ばれる気象災害があります。ゾドは一般的には「寒雪害」などと理解されています。しかし、実際には複合災害であり、単純な多雪や寒波などを指すものではありません。そのため、その被害の特性により7種類に分類されています(表1)。いわばゾドとは、極端な豪雪・低温・強風・飼料枯渇などの現象が重層することにより、遊牧民のあらゆる利用資源に破滅的な影響をもたらす気象災害の総体でもあります。モンゴル国では、2001/02年に発生したゾドがもっとも激甚な被害とされています。このゾドにより、1999年には国土に約3,400万頭いた家畜が、2003年には約2,400万頭となり、国家全体のおよそ30%の家畜が死亡したと推定されています[3]。
極限環境に適応した遊牧コミュニティでは、気象推測やゾドの到来を予見する生態学的伝統知(traditional ecological knowledge: T.E.K.)の分厚い積層が培われました。それらはおもに①家畜、②野生動物、③植物(草・木・花など)、④天候・気象、⑤月・星、⑥諺・昔話、の6つの事象に根差しています。モンゴル全国でよく知られた格言のひとつに「西暦が“7”で終わる年はゾドとなる」があります[4]。事実1937年/47年/57年/67年/77年/87年の各年で著しい気温の低下が見られ、かなり正確にこの傾向が見てとれます[5]。さらに「未年/申年は寒くなる」(例えば1967/68,79/80,91/92,2003/04)との認識もあることから[6]、遊牧民は10〜12年周期の厳しい寒波の到来を体得的に理解してきたと考えられます。
家畜の日々の体調や体質の変化からは、「家畜の腹まわりの毛が濃くなると寒くなる」、「家畜を屠殺したとき、胃にたくさん草があるとゾドの予兆」と考えられています。冬季の冷温・寒波の到来は家畜行動にも反映され、家畜群が「朝早く水場に行くとき」、「小屋に入る時間が遅いとき、もしくはなかなか入りたがらないとき」、「早朝から遅くまで草を求めて歩くとき」、「早朝、山のふもと方面に歩き出すとき」は、いずれも寒くなる予兆とされています。これは、家畜たちが寒波に備えてなるべく長い時間を食草に費やそうとする行動と考えられます(図1a-b)。
ほかにも、タンブル・ウィード、シベリアマーモットの冬眠時期、ニガヨモギの生育状態、樹木の紅葉の開始場所、湖の流氷の到達場所、月の動きや形など、モンゴルの遊牧民は生活をとりまく自然現象と森羅を、迫りくる寒波やゾド災害の予知に緻密な観察眼をもって役立ててきました。

図1a 筆者が2年間を過ごした遊牧民の冬の家屋。戸建て式家屋は西部のカザフ遊牧民などに用いられる(バヤン・ウルギー県/2011年11月撮影)

図1b 厳寒期の搾乳風景(バヤン・ウルギー県/2011年11月撮影)
2. ゾド災害への対処術と生存戦略

図2 9月に飼料として再利用される馬糞“シリン・ホモル”。とくに産乳する雌牛や小家畜に与えられる(ウブルハンガイ県/2015年10月撮影)
なかでも家畜防衛のためのさまざまな対処術を、遊牧民は数千年におよぶ草原の暮らしから編み出してきました。モンゴルの遊牧民は弱って斃死(へいし)した家畜を食べることはありません。そのためゾド被害が見込まれるときには、痩せた家畜から先につぶして食用とし、虚弱個体の人為的淘汰が行われます。冬季に牧草や干し草の欠乏時に与えられる救荒飼料(レスキュー・フード)には、特徴的な対処術が見られます。例えば樹木の繁茂地域では、ヤマナラシ、ポプラ、シラカバなどの樹皮が飼料として与えられます。さらに9月に排泄された馬糞は資源とみなされ、濃厚飼料などと混ぜてふたたび雌牛やヒツジ、ヤギに与えられることもあります[7]。この馬糞は「シリン・ホモル」と特別な名称で呼ばれます(図2)。馬は牧草の生長点付近のみを食べるため、糞には未消化でまだ食用可能な牧草資源が含まれると考えられているためです。
極度の冷温が到来すると、家畜の蹄が凍傷になることもあります。そのため、家畜の寝そべる地面に塩をまいて蹄の凍傷を防ぎます(凝固点の降下作用のため)。これは道路の凍結防止剤に、塩化ナトリウムが散布されるのと同じ原理です。また家畜厩舎の床面に1m近い畜糞堆積(“ヒフテル”/“ボーツ”)をすることで、土壌冷気を遮断して家畜の凍死を防ぎます(図3)。

図3 家畜厩舎内に堆積した畜糞の積層“ヒフテル”。冬の前にはがしとり燃料とする(バヤン・ウルギー県/2015年9月撮影)
また災害回避行動の一つに、「(放し飼いの)馬群が移動した場所に、人間も移動して天幕を張る」ことがあります。馬は草原状態の良好な牧草地を自らかぎ分けて移動することから、人間もその特性にあやかって移動する巧みな生存戦略も用いられます。家畜のみならず「遠くから鹿などの野生動物が来たらその冬は暖かくなる」と言われ、冷温を避けて動物が移動した場所が穏やかな冬になることを暗示しています。ゾドとは人間の生活だけに影響を及ぼす気象災害ではなく、ときに生物全体にとっての危機ともなり得るのです。ゾドによる被災は、生態バランスの変化によってレジリエンスの低下した状況下でいつでも起こりうる「常在危機」と言えます。そのため、あらゆるリソースを最大限に活用することで、モンゴル遊牧民は生活の文脈に根差した独自の防災・減災術を発展させてきたといえます。
3. 遊牧民の自然との共生観から、これからの防災・減災を学ぶ
ときに遊牧民の生活を根底から壊滅させることもあるゾドによる被災ですが、「ゾドのあとは草の生育が良く、生き残った家畜が肥る」という肯定的な意見も聞かれます。家畜個体数の減少により、牧草資源が回復し、生存した個体が十分な食草にありつけるためと考えられます。いわばゾドは天然の家畜淘汰のプロセスのひとつであり、遊牧民は自らを自然の一部として認める環境共生観をはぐくみ、生態サイクルに身をゆだねることで災害対処術と精神的強靭さも身につけたといえるでしょう。
しかし近年、地方での若者の遊牧離れと人口流出によるマンパワーの喪失、そして減災の伝統知の継承者の断絶は、コミュニティの災害対処能力にとっておおきな痛手となります。「遊牧」とは実際には、人間と自然相互の絶妙な環境収容力(carrying capacity)の下でしか成り立たない、不安定であやうさに満ちた生業でもあるのです。
地域ごとの脆弱性(ヴァルネラビリティ)と弾性(レジリエンス)を理解することが、防災・減災思想の原点でもあります。どんなにハザードマップや地理情報システムの普及で災害予知の精度が増しても、人類に共通する防災・減災理念とは―遊牧民と同様に―「つねに災害への危機意識をもつ」ことにほかなりません。真の防災インフラとは「自分たちの暮らしを自分たちで守る」という人々の内にある環境共生観を呼び起こした意識と行動にもとづくものであり、加えて災害の記憶の記録と継承が、将来の日本の防災基盤をより強靭なものにしてゆくことでしょう。
※本稿記載の伝統知は、2011年7月〜2017年8月にモンゴル西部バヤン・ウルギー県、ホブド県、オブス県の遊牧民を対象に行った防災・減災の意識調査をもとにしています。
文献
- ^ 国立民族学博物館. 2017. 「津波の記憶を刻む文化遺産−寺社・石碑データベース」
- ^ 野路正浩, 今村文彦, 首藤伸夫. 1993. 津波石移動計算法の開発, 海岸工学論文集. 第40巻: p.176-180
- ^ 神谷康雄, 松本武司, 上原有恒. 2011. モンゴル国におけるゾド(雪寒害)の発生, 畜産の研究. 第 65 巻(8号):859-869
- ^ Soma, Takuya., and Schlecht, Eva. 2018. The Relevance of Herders’ Local Ecological Knowledge on Coping with Livestock Losses during Harsh Winters in Western Mongolia, Pastoralism: Research, Policy and Practice 8(3).
- ^ Jirigalaほか. 2013. ゾド被害を引き起こす気象要因の分析と評価: モンゴル国東部ドルノド県を対象にして, 農業農村工学会論文集. 81 巻 (1号)
- ^ 相馬拓也 2017. 北アジアの遊牧文明をささえた伝統知と環境共生レジリエンスの学際研究, 『髙梨学術奨励基金年報 平成28年度研究成果概要報告』: p. 344-351, 東京: (財)髙梨学術奨励基金.
- ^ 相馬拓也 2016. 北アジアの遊牧文明をささえた伝統知(TEK)の再構築と継承性の民族考古学, 『髙梨学術奨励基金年報 平成27年度研究成果概要報告』: p. 360-367, 東京: (財)髙梨学術奨励基金.
相馬 拓也(そうま・たくや)/早稲田大学 高等研究所(WIAS) 講師、博士(農学)
早稲田大学 大学院文学研究科 博士後期課程(満期退学)。カッセル大学エコロジー農学部 客員研究員を経て現職。地理学、ヒューマンエコロジー、生態人類学を専門とする。主著:『鷲使い(イーグルハンター)の民族誌―モンゴル西部カザフ騎馬鷹狩文化の民族鳥類学』(2018年、ナカニシヤ出版)。NHKドキュメンタリー番組『地球イチバンー地球最古のイーグルハンター』(2015年1月29日22:00~22:50総合G放送)制作協力。