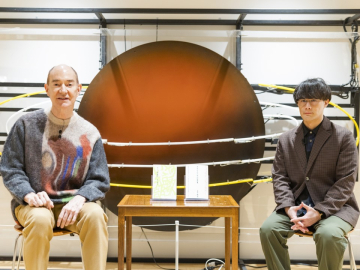田代 桂子さん
KEIKO TASHIRO
未来の地球を救うのは、“地球人”である学生
大和証券グループ本社で取締役兼執行役副社長を務める田代桂子さん。2020年からはSDGs担当を兼任し、グループのSDGsに資する取り組みを牽引している。SDGsが国連サミットで採択されたのは2015年だが、同社では早期より先進的な取り組みが進められてきた。

「転機になったのは2008年。途上国の子どもたちへの予防接種を目的にした『ワクチン債』を、個人投資家向けに販売したことでした。国際機関の要人を招致したセミナーなど、普及に注力したことで、大きなムーブメントを作り出せたと思います。以後、社会貢献意識が全社的に高まり、多様な施策が現場から生まれるようになりました」
同社は、「貯蓄からSDGsへ」をコアコンセプトに、資金循環の仕組みづくりを通じたSDGsの実現を目指す「2030Vision」を策定。グループ全社員が同じ目標を共有することで、ボトムアップでのSDGsを推進している。
「社員一人ひとりの“マインド”を変えていくのが私の役割。海外の優れた事例を共有するなど、アイデアが育まれる組織づくりを心掛けています」
1986年に大和証券へ入社した田代さんは、3年目にスタンフォード大学に留学。以後、各国を飛び回るようにキャリアを積み、キャリア年数の1/3は海外で過ごしたという。多様な価値観を受け容れる精神は、人生を通じて培われてきた。
「幼少期を海外で過ごした経験もあり、人種や民族を隔てる考えはありませんでした。ダイバーシティが重要と実感したのは、留学がきっかけ。さまざまなバックグラウンドを持つ人々の意見を取り入れた方が、人も組織も強くなると思ったんです」
気運の高まるSDGsだが、個人が積極的に取り組まなければ、目標は達成されないだろう。大切になるのは「きっかけ」だと、田代さんは考えている。
「エネルギーを例にあげると、日本はその資源を輸入に頼っており、ヨーロッパにおいてもウクライナ侵攻が起点となり、供給方法が議論されています。困難や苦境とともに、新たな解決策も生まれるのではないでしょうか」
深刻化する地球規模の問題。若い世代はどう向き合うべきなのだろうか。
「SDGsがゴールを設定する2030年は8年後。現在の大学生は働き盛りを迎えます。パリ協定に基づき、多くの国がカーボンニュートラルの達成期限としている2050年には、組織や社会のトップとして世の中に影響力を持つようになっているでしょう。その時に地球を救えるか否かは、学生時代に培った思考力や行動力にかかっています。学生の皆さんには、自分が“地球人”であることを忘れず、好奇心を持ちながら果敢にチャレンジしてほしいですね」
PROFILE
1986年早稲田大学政治経済学部卒業後、大和証券株式会社に入社。1991年米スタンフォード大学MBA。2009年より大和証券執行役員、2013年より大和証券グループ本社常務執行役員、米国子会社会長。現在は同社執行役副社長、海外管掌、SDGs担当、シンクタンク担当、大和証券株式会社代表取締役副社長を務める。