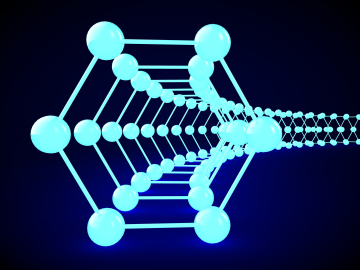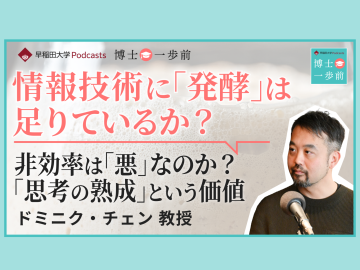2016年4月7日に、文部科学省との共催シンポジウム「早稲田が目指すイノベーションエコシステム ~連携を超えた産学“官”協働の姿~」を開催しました。シンポジウムには100名を超える学内外からの参加者がありました。
人材育成プログラムである早稲田EDGEプログラムでは、理工学術院と商学学術院が共同で運営主体となり、文理融合で多様な人材によるイノベーション創出の場「社会デザイン工房『共創館』」を設置、各種起業教育プログラムを提供することにより、地球規模の視点でビジネス創造し地球市民一人ひとりの幸せの実現に貢献できる人材を育成するとともに、持続的なイノベーションエコシステムのハブ形成に貢献することを目指しています。このEDGEプログラムをきっかけにこれからの産学“官”協働のあり方について、議論を行う試みとして、本シンポジウムが企画されました。


鎌田薫 (早稲田大学 総長)
冒頭の挨拶で鎌田総長は「産業界の第一線で活躍されている方々、文部科学省の皆様、そして本学研究者と共に、“イノベーションをどう創るか”をテーマとして議論する光栄な機会をいただいたものと考えている。企業・行政・大学の各々が目指していること、自らできること・欠けていることを明確にすることで、人材育成と研究成果の社会実装との両面から、大変革時代を迎えているグローバル社会において日本が存在感を示し続けるための、イノベーションエコシステムの構築に向けた産学官協働の新しい姿を描けるのではないかと期待している。」と述べました。
その後の講演で文部科学省事務次官の土屋氏は「アイディアを事業にまで発展させることは容易ではないが、知識・技術・人材・資金を集積し、一体的な価値創造(イノベーションエコシステム)を行うことが重要である。」「早稲田大学でイノベーションエコシステムの取り組みを加速させることで、産学官それぞれのプレイヤーが切磋琢磨、すなわち“インタラクション”を活発化させて新しいビジネス・マーケットを開拓する土壌づくりを、是非、積極的に進めてほしい。」と述べ、続く文部科学省産業連携・地域支援課長の坂本氏も「オープンイノベーションの中心は異分野融合研究であり、今、日本の大学には、それを促進する研究マネジメント体制の変革、また、その体制の中で科学を実証段階にまで展開できる知的生産人材の育成が、社会から求められている。今後も、産業界との積極的な人的、資金的連携によって一層、基盤となるイノベーションエコシステム構築への取り組みを加速してもらいたい。」と述べるなど本学への期待を寄せました。
また、三菱商事の森原氏からは「三菱商事は、組織的な産学連携を推進しており、大学との共同研究や受託研究に取り組んでいるが、産学連携の一層の深化のためには、学界における人材評価の変革や、若手大学教員が企業の研究事業戦略を主導することが必要になってきている。こうした点について議論を進め、企業と大学との間の流動/連動性を高めていくアクションにつなげていくべきではないだろうか」と、企業の視点から、今後の産学連携の在り方について提案が出されました。

左:土屋定之(文部科学省 事務次官)、中央:坂本 修一 (文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課長) 、右:森原 淳 (三菱商事株式会社 地球環境・インフラ事業グループ CTO/東京工業大学 特任教授)

パネルディスカッションの様子
さらに、本学研究者による産学協働事例紹介の後に行われたパネルディスカッションでは、 “産学連携研究開発の中でどのように人材育成を行うか”、“新しい産業を創出することを視野に入れた際の産学連携における研究成果とその活かし方、あるいはそのための人材を育成する体制整備について”、“企業視点からみた人材育成プログラムについて”などを論点として活発な議論が進みました。

橋本 周司 (早稲田大学 副総長)
閉会の挨拶で橋本副総長は、「このようなイベントは早稲田大学で初めてであり誠に喜ばしい。今後もこのような産学官の対話を続け、
産学協働事例紹介をおこなった本学研究者

左:岩田 浩康 (理工学術院 教授)、中央:戸川 望 (理工学術院 教授/理工学術院長補佐)、右:野田 優 (理工学術院 教授)

左:入山 章栄 (商学学術院 准教授)、右:島岡 未来子 (研究戦略センター 准教授)
パネルディスカッション パネリスト
伊藤 匠 (文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課)
濱 健志郎 (文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課)
谷本 順矢 (文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課)
藤井 淳行 (株式会社日立製作所 社会イノベーション事業推進本部 グローバル事業推進本部 EMEA CIS部長)
松田 良夫 (東レ株式会社 技術センター企画室 主幹 担当部長)
他 産学協働事例紹介者
モデレーター
大野 高裕 (早稲田大学 理事(情報化推進、経営企画、本庄プロジェクト担当))
発表資料
プログラム、当日発表した使用した資料はこちらからご覧になれます。