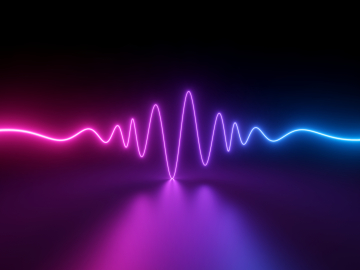筋管細胞の温度変化を蛍光イメージングで計測:実験と計算との間の矛盾解消へ
熱産生が関わる悪性高熱症やメタボリックシンドローム等の治療に期待
早稲田大学理工学術院石渡信一(いしわたしんいち)教授(早稲田大学バイオサイエンスシンガポール研究所長)、重点領域研究機構鈴木団(すずきまどか)主任研究員(研究院准教授)、大学院先進理工学研究科博士課程4年伊藤秀城(いとうひでき)氏(シンガポール科学技術研究庁医学生物学研究所研究官)、重点領域研究機構新井敏(あらいさとし)招聘研究員らの研究グループは、低分子蛍光温度計ER thermo yellowと、蛍光タンパク質の1つであるmCherryの蛍光寿命に、温度依存性(温度が上がるにつれて、蛍光寿命が短くなる)があることを発見しました。さらに、骨格筋様に分化した培養細胞(筋管細胞)をカフェインで刺激した際の、筋小胞体におけるER thermo yellowや、細胞質において発現したmCherryの蛍光寿命変化を観察することにより、それぞれの細胞小器官における温度変化を測定しました。筋管細胞の筋小胞体で温度上昇が見られましたが、細胞質では大きな温度変化が見られませんでした。この結果は、骨格筋での非ふるえ熱産生による温度変化が、筋小胞体近傍の極めて局所で起こることを示唆しています。
我々ヒトを含む多くの生物は、絶えず熱を産生しています。これまでに、細胞レベルでのさまざまなタイプの温度測定実験で、化学物質による細胞への刺激が、1℃程度の温度上昇を引き起こすことが報告されてきました。一方で、これは先行研究である熱量測定装置であるマイクロカロリメトリーによる細胞懸濁液の発熱量測定結果から求められる、一細胞当たりの温度上昇の計算値10-5 ℃と大きな隔たりがあります。しかし、発熱量は細胞の種類によって差があったり、細胞全体に温度上昇がないと仮定したりすれば、このギャップは解消する可能性があります。本研究は、細胞小器官ごとに温度上昇のばらつきがあることを明らかにし、この105ギャップの解消へ一石を投じることができました。
さらに、細胞小器官レベルで温度変化を測定できることがわかったため、この手法を応用して、今後、骨格筋における非ふるえ熱産生に自体の研究を進めるだけでなく、熱産生が関わっている悪性高熱症やメタボリックシンドロームなどの疾患の治療、薬剤評価に貢献することが期待されます。
今回の研究成果は、英国王立化学会(Royal Society of Chemistry)の科学雑誌『Chemical Communications』オンライン版に1月21日(現地時間)に掲載され、3月15日の誌上掲載ではoutside back coverとして採択されました。
論文:Direct organelle thermometry with fluorescence lifetime imaging microscopy in single myotubes
※本研究は、シンガポール科学技術研究庁、シンガポール国立大学との共同研究として実施されました。
(1)これまでの研究で分かっていたこと(科学史的・歴史的な背景など)
我々ヒトを含む多くの生物は、絶えず熱を産生しています。気温が変わったときなど、外部の環境に適応するためには、大きな熱産生が必要となります。その主な発熱源として、褐色脂肪組織や骨格筋が知られています。骨格筋では、ふるえ熱産生が主な発熱メカニズムと考えられていましたが、近年、非ふるえ熱産生も発生していることが報告されました。しかし、これまでの骨格筋における非ふるえ熱産生に関する研究は、個体レベル(1)もしくは分子レベル(2)であったため、両者の橋渡しをする細胞レベルでの研究が必要とされています。
細胞レベルでの温度測定手法は、本研究チームからピペット型(3)、シート型(4)、ナノ粒子(5,6)が発表されています。他の研究グループからも、さまざまなタイプの温度測定手法が開発されています。こうした温度測定手法で、化学物質による細胞への刺激が、1℃程度の温度上昇を引き起こすことが報告されています。この結果は現在、議論を引き起こしています(7–10)。というのは、先行研究において熱量測定装置であるマイクロカロリメトリーによる細胞懸濁液の発熱量測定が行われています。その結果から計算によって求められる温度上昇は1細胞当たり10-5℃程度であると推定されているからです。しかし、発熱量は細胞の種類によって大きな差があったり、細胞全体に温度上昇がないと仮定したりすれば、このギャップは解消する可能性があります。
(2)今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと
C2C12細胞という骨格筋様に分化する培養細胞に外部から刺激を加えたときに、細胞内でどのような温度変化が起きるのかを測定しました。
(3)そのために新しく開発した手法
細胞小器官である小胞体に局在する低分子蛍光温度計ER thermo yellow(11)を用いて、骨格筋における熱産生が行われる場所と考えられている筋小胞体の温度変化を測定しました(図1)。また、細胞質に蛍光タンパク質の1つであるmCherryを発現させ、細胞質内の温度変化も測定しました。これらの測定は、蛍光寿命イメージング顕微鏡法(FLIM)を用いて行われました。FLIMは蛍光物質の濃度変化や測定装置の影響を受けづらいなど、通常用いられる蛍光強度の測定と比べ、正確な結果が得られると考えられています(12)。

図1.低分子蛍光温度計ER thermo yellowと温度依存的な蛍光寿命変化の概念図
ER thermo yellowを細胞培養液に添加すると、細胞内の小胞体(筋管細胞の場合は筋小胞体)に局在する。蛍光による光子放出量は、励起後の時間に沿って指数関数的に減衰する。温度によって蛍光の減衰度合いが変化すれば、逆に蛍光減衰曲線から温度が測定できる。
(4)今回の研究で得られた結果及び知見
まず、ER thermo yellowの蛍光寿命に温度依存性があることを発見しました(図2)。そこで、分化したC2C12細胞(筋管細胞)にER thermo yellowを導入して、筋小胞体の温度変化を測定しました。Caffeine(カフェイン)によって外部刺激を与えると、筋小胞体にあるリアノジン受容体からカルシウムイオン放出が起こり、そのカルシウムイオンを筋小胞体のカルシウムイオンポンプであるSERCA(sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase)が回収する過程(図3)において、温度上昇が観られました(~1.6℃)。一方、thapsigargin(タプシガルギン)で刺激した場合、カフェイン刺激と同様に、細胞質のカルシウムイオン濃度は上昇しましたが、大きな温度変化は観られませんでした(~0.38℃)。これは、タプシガルギンがSERCAを阻害したためで、SERCAが熱を産生するという従来からの説を裏付ける結果です。

図2.ER thermo yellow蛍光寿命の温度依存性
筋管細胞内のER thermo yellowの蛍光寿命と温度の関係(黒丸)。蛍光寿命は測定範囲内で温度に対して直線的な変化を示した(近似直線の傾き:-24 ピコ秒/℃)。温度測定精度は白丸のように求められた(平均値:1.3 ± 0.5℃)。

図3.骨格筋における発熱メカニズム
カフェインは筋小胞体上のリアノジン受容体からのカルシウムイオン放出を引き起こす。SERCAが筋小胞体にカルシウムイオンを取り込む際、SERCAの空回りにより熱が生じると考えられている。タプシガルギンはSERCAを阻害する薬剤で、細胞質-筋小胞体間のカルシウムイオン流が遮断されることで、細胞質内のカルシウムイオン濃度が上昇する。

図4.カフェイン及びタプシガルギン刺激前後のER thermo yellow蛍光寿命の時間変化
カフェイン刺激後、ER thermo yellowの蛍光寿命は短くなった(温度上昇)。一方、タプシガルギンによる刺激は、蛍光寿命に大きな変化を与えなかった。
未分化のC2C12細胞(筋芽細胞)を、カフェインで刺激したところ、大きな温度変化は観られませでした(~0.09℃)。筋芽細胞では、筋小胞体からカルシウムイオンを放出するリアノジン受容体やSERCAの発現量が小さいことが知られており、細胞質内のカルシウムイオン濃度も変化しませんでした。
続いて、mCherryの蛍光寿命にも温度依存性があることを発見し、筋管細胞の細胞質に発現させることにより、その温度変化を測定しました。カフェイン刺激をしても、大きな温度変化は観られませんでした(~-0.07℃)。
以上の結果は、筋管細胞における生理的な熱産生による温度変化は、筋小胞体近傍の極めて局所で起こることを示唆しています。
(5)研究の波及効果や社会的影響
筋管細胞(生体内で熱産生を担う骨格筋様の細胞)において大きな熱が産生されること、それによる温度変化は筋小胞体近傍に局所的であることにより、上述の105ギャップの解消へ一石を投じることができました。
細胞小器官レベルで温度変化を測定できることがわかったため、この手法を応用して、骨格筋における非ふるえ熱産生自体の研究を進めるだけでなく、熱産生が関わっている悪性高熱症やメタボリックシンドロームなどの疾患の治療法・薬剤評価に役立つことが期待されます。
(6)今後の課題
今回の研究対象である骨格筋では、外部刺激により筋小胞体周りでの局所的な温度上昇が観られました。それでは、もう1つの大きな発熱源である褐色脂肪組織における発熱メカニズムは、細胞レベルではどうなっているのでしょうか。また、さまざまな細胞小器官の温度測定を可能とするプローブや、温度感受性の高いプローブを発見できれば、より正確な細胞内の温度マップを描くことができます。
参考文献
- 1. N. C. Bal, S. K. Maurya, D. H. Sopariwala, S. K. Sahoo, S. C. Gupta, S. A. Shaikh, M. Pant, L. A. Rowland, S. A. Goonasekera, J. D. Molkentin and M. Periasamy, Nat. Med., 2012, 18, 1575–1579.
- 2. L. de Meis, J. Biol. Chem., 2001, 276, 25078–25087.
- 3. V. Zeeb, M. Suzuki, S. Ishiwata, J. Neurosci. Methods, 2004, 139, 69–77.
- 4. H. Itoh, K. Oyama, M. Suzuki and S. Ishiwata, BIOPHYSICS, 2014, 10, 109–119.
- 5. K. Oyama, M. Takabayashi, Y. Takei, S. Arai, S. Takeoka, S. Ishiwata and M. Suzuki, Lab Chip, 2012, 12, 1591–1593.
- 6. Y. Takei, S. Arai, A. Murata, M. Takabayashi, K. Oyama, S. Ishiwata, S. Takeoka and M. Suzuki, ACS Nano, 2014, 8, 198–206.
- 7. G. Baffou, H. Rigneault, D. Marguet and L. Jullien, Nat. Methods, 2014, 11, 899–901.
- 8. S. Kiyonaka, R. Sakaguchi, I. Hamachi, T. Morii, T. Yoshizaki and Y. Mori, Nat. Methods, 2015, 12, 801–802.
- 9. M. Suzuki, V. Zeeb, S. Arai, K. Oyama and S. Ishiwata, Nat. Methods, 2015, 12, 802–803.
- 10. G. Baffou, H. Rigneault, D. Marguet and L. Jullien, Nat. Methods, 2015, 12, 803–803.
- 11. S. Arai, S.-C. Lee, D. Zhai, M. Suzuki and Y. T. Chang, Sci. Rep., 2014, 4, 6701.
- 12. X. Wang, O. S. Wolfbeis and R. J. Meier, Chem. Soc. Rev., 2013, 42, 7834–7869.