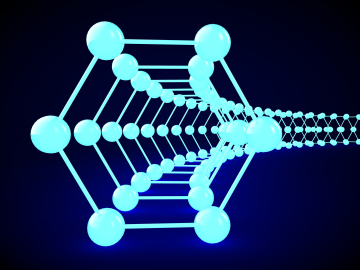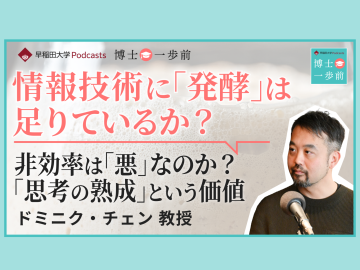Waseda Online に掲載された本学教員のオピニオンから、多様性や共生にかかわる諸問題を扱ったものを集めました。

清国留学生部(春季運動会の万国旗飾り付け)
大学史資料センター 写真データベース B11-04
2008年
谷口真美(商学学術院教授)「ダイバシティ・マネジメント ―経営成果を上げるためには―」

ダイバシティとは、性別、年齢、人種・民族の違いだけと誤解されることが多いようです。しかしながら、正確には、個人の持つあらゆる属性が、ダイバシティの次元となります。例えば、居住地、家族構成、習慣、所属組織、社会階級、教育、コミュニケーションスタイル、マネジメントスタイル、性的指向、職歴、年齢、世代、未既婚、趣味、パーソナリティ、母国語、肌の色、宗教、学習方式、外見、収入、考え方、国籍、出身地、役職、身長、体格、勤続年数、勤務形態(正社員・契約社員・短時間勤務)、服装、社会経済的地位、身体的能力など、人のほとんどの属性がダイバシティの次元に含まれます。
2008年7月
白木三秀(政治経済学術院教授)「外国人留学生の採用活性化を求めて~グローバル競争時代の人材獲得~」

外国人労働者の受け入れ目的については、2002年に厚生労働省「外国人雇用問題研究会」の報告書が出ており、そこでは、これから日本の経済を活性化するには、高いスキルを持った「高度人材」にいかに日本に来てもらうかということが問題意識の底流となっている。このスタンスは現在も同様である。
重要な点は、外国人人材の活用と労働力減少とを直接結びつけてはいけないということである。長期的な日本経済の成長のために生産性を向上させ、日本の経済を支えてもらうべく、基幹的なところに外国人人材に入ってもらいたいというのが外国人人材受け入れに対する筆者の基本的スタンスである。
2008年8月
森本豊富(人間科学学術院教授)「ブラジル移民100周年を迎えて」

1868(明治元)年に「元年者」がハワイのサトウキビプランテーションへ渡り、同じ年にグアムにも労働者として渡航した。今から140年前の話だ。やがて1885年に始まったハワイへの「官約移民」によって本格的な集団渡航が加速化する。しかし、北米での移民制限によって、渡航先はペルー、ブラジル、アルゼンチンなどの南米諸国、フィリピン、オーストラリア、フィジーやニューカレドニアなどの南太平洋にも広がっていった。そして、さらに満州、朝鮮半島、台湾にも多くの「殖民」を送り出した。しかし、1941年の「真珠湾攻撃」で海外への移民は頓挫する。戦後は、サンフランシスコ講和条約を経て1952年末にブラジルへの移民が再開され、パラグアイ、ドミニカ、ボリビアなどに新天地を求めて渡っていった。
2008年9月
植村尚史(人間科学部教授)「外国人看護師・介護士の受け入れ―人手不足の特効薬となるのか―」

日本とインドネシアとの経済連携協定(EPA)によって、日本で資格取得に挑戦することとなるインドネシア人の看護師、介護福祉士の候補者が来日した。協定では、2008年度から2年間で合計1,000人を受け入れることになっており、初年度の受け入れ枠は看護師200人、介護士300人の合計500人であったが、8月7日に来日した第1陣は205人(その後3人が来日)と、当初の予定枠に満たなかった。
2009年3月
鳥越皓之(人間科学学術院教授)「「サザエさん」から地域コミュニティを考える」

サザエさんの4コママンガが朝日新聞朝刊に登場したのは昭和26年です。そしてテレビのアニメとしてそれは今もつづいています。こんなに長く私たちの関心をつなぎ止めたマンガは希有な存在です。長くつづくには、社会の変化にキチンと対応して変貌をつづけてきたはずですが、その変貌を一手に引き受けているのがカツオだと私は思っています。つまりカツオのキャラが時代とともにある方向へ変化してきたのです。
2009年7月
ジェームス・バーダマン(文学学術院教授)「マイケル・ジャクソン」

2009年6月25日、マイケル・ジャクソンの死去にあたり、マスメディアはいわゆる『キング・オブ・ポップス』としての彼を高く評価した人、あるいは非難した人たちの様々な反応について報道した。その謎めいた死、ミュージシャンとしての姿、また彼の私生活について振り返るものだった。私生活に深刻な問題があったことは確かだが、それでもなお彼の音楽は大衆の文化と意識に非常に大きな影響を及ぼしたことも、また確かなことだ。独自のサウンドとボーカルスタイルが、数世代にわたってヒップホップやポップス、R&Bなどの音楽に影響を与えたのと同時に、彼のプロモーションビデオはMTV(アメリカのケーブルテレビチャンネル)の成功に大きく貢献したといわれている。
2010年5月
石原剛(教育・総合科学学術院准教授)「「男性学」―男らしさって何? 男性の多様な生き方を問う」

「男性学入門」という科目を担当してからはや三年程が過ぎた。「男性学」などと聞くと、それこそ男子学生が受講生の大半を占めるのでは、と思う向きもあるかもしれない。しかし、例年、受講生の約半数は決まって女性。「女性学」関係のクラスには男子学生は尻込みする傾向があるようだが、それとは大分様子が違う。一言でいえば、自分と異なるジェンダーについても積極的に学ぼうとする女子学生の意識の高さを反映している。
2010年6月
池岡義孝(人間科学学術院教授)「家族の困難、家族研究の困難」

ここ数年、地味だがわりと大がかりな仕事に取り組んできた。一昨年と昨年の二期にわけて刊行した『戦後家族社会学文献選集』(全20巻・別冊解説・解題1巻、日本図書センター)がそれである。第二次世界大戦が終わった直後の1940年代後半から1970年代年までの家族社会学の主要な文献を、著名な文献だけでなく忘れられた文献も含めて復刻し、各文献の解題と全体の解説をつけたのである。この仕事に取り組んだことで、家族研究者の研究のあり方と実際の家族の関係について、あらためて考えさせられた。
2010年8月
飯野公一(国際学術院教授)「英語公用語化論を再考する―言語政策の国家的議論を」

2010年夏、楽天やファーストリテイリング(ユニクロ)といった企業で英語公用語化を推進するというニュースが話題を呼んでいる。これまでにも、1999年12月に故小渕首相の委嘱による「21世紀日本の構想」懇談会の報告書では英語第二公用語化の議論の必要性についても言及され、当時大きくメディアで取り上げられたり、外国人がトップを務める日産自動車などでは役員会を英語で行ったりという動きはあった。また、来年度より正式に導入されることになった小学校での英語教育など、21世紀に入ってから日本における英語の地位をめぐる議論が目立つようになってきた。こうした議論はしばしば賛成派と反対派に分かれ、あたかもグローバル社会で日本が生き残るには社会インフラとしての英語が不可欠とする「開国派」と、英語崇拝は美しい日本語、日本文化を退廃させる国賊ものであるとする「攘夷派」の両極が感情的な綱引きをするという構図になっているようにも見える。
2010年9月
神尾達之(教育・総合科学学術院教授)「オレオレシュギ・ウイルスにあらがって」

オレオレ詐欺の現場(?)では多くの若者が働いているらしい。高齢者から大金をだましとるためには、ハンドルネームならぬハンザイネームで別人になりすます能力(?)のみならず、オレだけよければオッケーだという能力(?)が必要なのだが、この能力に若者たちはたけているようだ。その一方で、電話やネットのようなメディアを介在させずに、ダイレクトに実名で対面しなければならない場面では、打たれ弱く、ちょっとした言葉の行き違いでも心が折れてしまい、「自室」に引きこもってしまう若者が少なくない。講義では多くの他者と空間をともにしなければならないし、ゼミでは自分の意見を述べそれを他のクラスメートの意見と調整することが求められる。現に、大学に来ることができない学生が増えている。自己肥大(俺)と自己萎縮(折れ)が表裏一体になっているこの心理を、ここでは「オレオレシュギ」と呼んでおこう。
2011年11月
棚村政行(法学学術院教授)「国境を越えた子どもの連れ去りは犯罪か?―急増する国際離婚が生む問題」

米国で離婚訴訟中に長女を日本に連れ帰った日本人女性が、2011年4月にたまたまハワイに行った際に米国司法当局から身柄を拘束されてしまった。彼女に対しては、現在、ウィスコンシン州において刑事裁判が続けられ、来週にも判決が出される予定であるという。(※この事件については、2011年11月23日に米国ウィスコンシン州の裁判所で、30日以内に母親が米国の父親に長女を引き渡すことで正式な司法取引が成立した。)この日本人女性(43歳)は、ニカラグア出身の米国籍の男性(39歳)と2002年にウィスコンシン州で婚姻し、2人の間には長女(9歳)が誕生した。しかし、2人の夫婦関係は悪化し、2008年に男性は同州の裁判所に離婚訴訟を起こしたが、その直後に、日本人女性は男性のDVがあったなどと日本に長女を連れて帰国した。同州の裁判所は、2009年6月に、離婚を認めるとともに、男性に長女の単独親権者とすること、直ちに長女を男性に引き渡すか、日本で男性に長女を渡すことなどを命じ、その裁判が確定していた。これに対して、女性も、兵庫県で離婚と親権者の指定・養育費の支払いを求める裁判、親権者の変更を求める裁判を日本において起こしており、日本では母親に親権が認められ、米国人男性が争っていた。長女は、現在、兵庫県内の親族のもとで暮らしており、この裁判や母親が身柄を拘束されていることは知らされていないようだという。それにしても、両親の間に挟まれた長女にとっては、どのような判断がでようともあまりにも気の毒だ。
篠田徹(社会科学総合学術院教授)「Occupy Wall Street(ウォール街占拠運動)~世界を駆け巡るデモや集会~」

世界をデモや集会が駆け巡っている。北アフリカ、中東、南欧、北米、そして日本。もっともその掲げる主張は、民主化、緊縮経済反対、労組法改悪反対、格差是正、脱原発と様々だ。また夫々の運動作法を仔細に眺めてみると、運動文化、即ち運動の在り様について長年に亘って積み重ねてきた伝統の総体が垣間見られて、こんなとこにもお国柄があると思えて面白い。特にニューヨークに始まり全米主要都市に広がるウォール街占拠運動(Occupy Wall Street)の場合、それが顕著だ。ここでは三つほどその運動文化の伝統を挙げてみよう。
2012年2月
真辺将之(文学学術院准教授)「動物愛護と動物利用の交錯―変わりゆく人間と動物の関係―」

2012年1月、動物愛護管理法の施行細則が改正され、さらに愛護管理法そのものの改正も今年中に国会での審議にのぼる見込みであるという。改正にあたっては、週齢規制や動物実験規制をはじめさまざまな論点があり、昨年末のパブリックコメントでも実に多様な意見が寄せられている。こうした多様な意見が存在する背景のひとつに、人間社会の動物とのかかわり方の複雑性がある。犬や猫への虐待を非難する人が、同時に牛や豚の肉は何の疑問もなく口にし、狐や兎を殺した毛皮を身につけ、動物実験によって開発された薬や化粧品を使用している。そしてこうした動物と人間との一筋縄ではいかない複雑な関係は、過去にさかのぼってみることによって、さらに複雑で変化に富んだものとなる。
2012年4月
牛丸聡(政治経済学術院教授)「世代間の繋がりを大切にした社会保障制度を “分断”招きかねない公的年金議論」

最近、橋下大阪市長が、維新の会の構想として、年金の世代間格差を是正するために積立方式への変換を挙げるなど、国民の年金問題に対する関心が高まっている。このオピニオンコーナーでも「年金の世代間格差」をテーマに執筆してほしいと依頼があった。筆者は最近の国民の社会保障制度のあり方に対する姿勢に一抹の不安を感じていたので、この機会に、私が感じていることを国民にお話したいと思い、執筆を引き受けることにした。
2014年3月
橋本健二(人間科学学術院教授)「「格差社会論」はどこへいった?──長期的視野で対策を」

東日本大震災から、3年が過ぎた。この震災の前後で、日本の社会は大きく変わった。それとともに、人々の関心も大きく変わった。災害と原発の問題に人々の関心が集まるようになった反面、忘れられがちになった問題も少なくない。そのひとつが「格差」の問題である。
後藤雄介(教育・総合科学学術院教授)「大学生に人気上昇中!何故スペイン語が選ばれる? 学んでほしい理由──外国語学習の意義」

日本の大学における英語以外の外国語、いわゆる「第二外国語」教育の勢力図は、大きく様変わりしつつある。かつて主流であったドイツ語・フランス語に代わって相対的に履修者数を伸ばしているのが、中国語であり、スペイン語である。特に中国語は、いまやほとんどの大学で最大の履修者数を誇っているのではないだろうか。
2014年7月
浅田匡(人間科学学術院教授)「英語で話せばグローバル? 幼児教育を考える」

グローバル人材を育成することが学校教育につよく求められるようになった。大学教育においては、9月(秋)入学やクウォーター制の導入、あるいは英語教育の充実、さらには留学の推奨などで騒がしい。また、小学校においても英語活動が導入され、グローバル人材育成イコール英語教育と言わんばかりである。この流れは、幼稚園教育においても少なからずみられるようになってきた。
2014年1月
大門毅(国際学術院教授)「マンデラ後の南アと戦略的重要性」

ケニアやタンザニアなど、アフリカの町を歩くと、「ネルソン・マンデラ大通り」と名づけられた目抜き通りがあちこちに存在することに気づく。マンデラの似顔絵入りTシャツは露店でもよく売れるそうだ。それだけ、マンデラは南アの黒人にとっての英雄であり、アフリカ大陸を超え全人類にとっての偉大な英雄だった。去る2013年12月5日に95歳で大往生したネルソン・マンデラ元南アフリカ大統領(任期1994年~1999年)を賞賛する言葉には事欠かない。バラク・オバマ米大統領は弔辞で「国民を正義へと導き、その過程で、世界中の何十億の人々を感動させた『歴史的偉人』の功績を言葉で言い尽くすことはできない」と賞賛した。確かに、ガンジー、キング牧師などと並び称される偉人には相違ない。しかし、カリスマ的革命家は、得てして政治家には向かない。大衆を感動させる力は、組織を統治・管理する能力と必ずしも同じでないからである。革命成功後、最悪の独裁者になった数多くの歴史的事例がそのことを証明している。
2014年8月
池岡義孝(人間科学学術院教授)「開かれた多様な家族をめざして―血縁・DNAを絶対視する危険性―」

今年の7月17日、最高裁は、DNA鑑定で血縁関係がないことが証明されても、すでに決定した父子関係は取り消せないとの判断を示した。法律上の父子関係の設定は、民法772条の「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」という規定にもとづいて行われているが、夫と子との血縁関係が最新のDNA鑑定で科学的に否定された場合、どう判断するかが争点だった。しかし、最高裁は、科学的に証明された血縁関係よりも子の法的な身分の安定を重視したのである。この血縁か法かという争点は、DNA鑑定による問題にとどまらない。近年の生殖補助医療の発達は、夫以外の精子の使用による受精を可能にしただけでなく、最近では妻以外の卵子の使用による受精や妻以外の子宮による代理出産も技術的に可能にし、父子関係のみならず、これまで出産の事実によって自明のこととされてきた母子関係にも大きな問題を投げかけている。
2014年9月
大月友(人間科学学術院准教授)「発達障害の理解と支援:みんなに心地よい環境を目指して」

「発達障害」という言葉が最初に注目されるようになったのは、小学校や中学校などの学校現場です。2002年に文部科学省が実施した「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査」では、通常学級に在籍する6.3%の児童・生徒に、発達障害の可能性のある特別な教育的支援が必要という結果が示されました。この結果は、学校教育の中で彼らをどのように支援していくのかという課題を教育関係者につきつけました。そして、近年では、いわゆる大人の方々への支援についても議論されています。このように、「発達障害」という言葉が注目されるコミュニティは年々ひろがりを見せ、広く認知されるようになってきました。とはいえ、一般の方々にも知れ渡っているかといえば、まだまだ「言葉くらいは・・・」という状況だと思います。そこで今回は、発達障害とはどのような障害なのか、そして、どのような支援が必要か、簡単に紹介してみたいと思います。
2014年10月
有賀隆(理工学術院教授)「人口減少・高齢化時代に立ち向かう 住み続けるためのまちづくり」

わが国で人口減少と高齢化が社会問題となって久しい。例えば、地方都市のまちなか居住の施策は、中心市街地の地域再生や活性化につながる都市計画と一体的に考えられることが重要であるし、その実践に際しては地域のネットワークを通した担い手の協働が欠かせない。また郊外の土地利用のコントロールと都心への機能の集約化を通したコンパクトな都市像の形成も、そのための市街地再編と一体的に進めることが重要である。
2014年12月
三浦慎悟(人間科学学術院教授)「ワイルドライフ・マネジメントのすすめ 自然から撤退する社会の中の獣害問題」

はなから私事で恐縮だが、先日、勤務地に近い入間市に引っ越した。10月のこと、「イノシシが出没したので登下校に気を付けてください」という市の広報放送に耳を疑った。本当だった。翌日、福生市とあきる野市で「イノシシが突進、通行人6名負傷」が発生した。11月、今度は岐阜県で「クマに襲われ男性死亡」(11月6日付)との新聞記事。環境省の集計によれば今年の全国でのクマによる負傷者は140名をこえたという。クマの「異常出没」はこのところ数年ごとに繰り返され、もはや秋の「恒例」行事となったようだ。そして先日、「シカ増殖、食害列島」(朝日11月7日付)の記事が躍った。シカの農作物被害と森林被害が日本列島を縦貫し、南アルプスや丹沢・奥多摩では土砂崩れの危険さえあるという。
2015年1月
白木三秀(政治経済学術院教授)「グローバル人材とは何者か? 日本人が世界で活躍するための秘訣」

多国籍企業で働くグローバル人材の育成や評価について考察する際には、いくつかの視点が必要かと思います。
2015年4月
天児慧(アジア太平洋研究科教授)「戦後70年と日中韓関係――若者そしてアジアへのメッセージ」

今年は「戦後70年」である。私たちはどのように受け止め考えるべきか。それを考えようとすると、その前にある「長い戦争の歴史」に思いが向いてしまう。まずこれに関して、確かに第二次世界大戦の評価をめぐり「侵略戦争」ではなかったという見方が日本にはある。そしてそのような歴史認識に対して、中国、韓国をはじめとするアジア諸国、あるいは欧米諸国から厳しい批判がなされてきた。70年もの歳月を経ながら、この戦争にたいする日本国自身の態度を明確にしてこなかったことは嘆かわしいと言わざるを得ない。戦争の原因論から見れば、欧米のアジア侵略に対する「アジア解放」の戦いだったとの解釈もありうるが、結果論から見れば、日本がアジア諸国の人々や領土を蹂躙し、強制的に自らの勢力圏に置こうとした「侵略戦争」、さらには無謀にも欧米に戦いを挑み敗れた戦争であったのは疑う余地はない。すでに「村山談話」をはじめ、わが国の指導者はこの事実を直視し、真摯に謝罪を行ってきたが、それに反論する声も大きく、日本の誠意が疑われてきた。この点で「戦後70年」の今年は「安倍談話」を通して日本の総意を明確に世界に示し、この問題に決着をつけねばならない。
2015年4月
檜皮瑞樹(大学史資料センター助教)「早稲田大学最初の留学生」

今から131年前の1884年(明治17)10月、東京専門学校(早稲田大学の前身)は最初の留学生を受け入れる。朝鮮人留学生である申載永(1864-1931)と嚴柱興(1858-1908)の二名である。1882年(明治15)の開校から僅か2年後のことであった。さらに翌1885年(明治18)には金漢琦(生没年不明)が入学している。彼らはどのような経緯をたどって東京専門学校に入学し、そして帰国後はどのようなキャリアを歩んだのだろうか。
2015年5月
都甲幸治(文学学術院教授)「アメリカ文学って英語だけなの?」

アメリカ合衆国の文学と聞いて、どんな作品が思い浮かぶでしょうか。マーク・トウェインの『ハックルベリー・フィンの冒険』ですか。あるいは、アーネスト・ヘミングウェイの『老人と海』でしょうか。J・D・サリンジャーの『キャッチャー・イン・ザ・ライ』という人もいるでしょうね。
これらの作品の共通点はなんでしょうか。そうです。英語で書かれていることです。アメリカ合衆国の作品なんだから、英語で書かれているのは当たり前じゃないか、とあなたは思うかもしれません。でも、それは見た目ほど当たり前のことじゃないんです。
2015年6月
ファーラー・グラシア(国際学術院教授)「「多文化共生」の何が問題なのか?」

日本には200万人以上の在留外国人が住んでおり、その半数以上は永住者だ。多種多様な国籍や文化的背景をもつひとびとがやってくることで、日本人が慣れ親しんできた生活パターンはかき乱され、また「日本文化」や「日本人のアイデンティティ」といったものの構成じたいが揺るがされている。いっぽう、移民を日本社会へと包摂するために、日本政府は「多文化共生」という概念を喧伝し、また地方自治体の政治的指針ともさせている。ここで私が問いたいのは、このような多文化主義は、じっさいに機能するのだろうかという問題である。
マニュエル・ヤン(社会科学総合学術院助教)「「捕らわれ人には自由を」──警察暴力、暴動、アメリカ民主主義の黄昏」

今年、三月三日にロサンゼルスから東京へ引っ越してきた。フェイスブックを開けたとき真っ先に目に飛び込んできたのは、「アメリカのホームレスたちの首都」と呼ばれるスキッドロウに住むカメルーン出身のホームレス、チャーリー・ケウンドゥ・ケウナンをロスの警官が射殺した直後の映像であった。
2015年8月
池上摩希子(国際学術院教授)「目標は「日本語が上手な子ども」を育てることなのか-外国人児童生徒に対する日本語教育の現状と課題-」

日本の学校教育現場には、様々な背景事情から日本語が十分ではない子どもたちが参入してきています。80年代には中国帰国者の子どもたちや海外赴任から帰国した邦人の子どもたちが見られるようになりました。1990年の「出入国管理及び難民認定法」の改正後には、中南米からの日系人の子どもたちも増えました。それ以前からも、多様な言語・文化背景を持つ子どもたちは学校現場に存在していたのですが、増加が認知を進め、「児童生徒に対する日本語教育」が課題だと言われるようになったのです。2014年の文部科学省の調査※1 によれば、日本語指導が必要な児童生徒数は3万人に達しようとしています。
2015年9月
和氣一成(教育・総合科学学術院准教授)「「男性学入門」―男性性の変遷とその背景を学ぶ」

トランスジェンダー(性別越境者)の人々への配慮が高まっている中、米国サンフランシスコの小学校では、男女別のトイレを段階的に廃止する取り組みを始めた。同国ミズーリ州ではトランスジェンダーの生徒が女子用のトイレや更衣室を使用したことに抗議して、生徒のおよそ150人が授業をボイコットするという騒動1があった。フランス通信社(AFP)は2015年6月のある記事2で、映画『40歳の童貞男』になぞらえて、40代で性体験のない日本人男性数が増加していることを取り上げている。(2005年製作。1億7000万ドルの興行収入を上げる大ヒットとなる。主人公アンディ(スティーヴ・カレル)は、人当たりのよいオタク。趣味が高じて40歳にして性体験がない男である。)日本人男性のこういったオクテな性質の背景には何があるのだろうか。ヴァージン(童貞)だということはなぜそもそも不安視され、問題視されなければならないのか。日本のポルノ産業との関係はどうなのか、それが現実世界での恋愛関係に悪しき影響を与えているのか。いわゆる男性の「絶食化」への危惧の背景には、男性は性に対して積極的であれという無意識があることは言うまでもない。今日、これまでにもまして従来のジェンダー観のみならず、とりわけ男性性のあり方が揺らぎ、多様化し、それに付随する諸々の問題が表面化しつつある。
2015年10月
入山章栄(商学学術院准教授)「日本企業がダイバーシティ経営で気をつけるべきこと」

昨今、「ダイバーシティ経営」という言葉が注目されています。これは一般に、企業が女性・外国人などを積極的に登用することを指します。今年8月に政府が、企業の女性登用を促すための「女性活躍推進法」を成立させたのも、記憶に新しいところです。
筆者も、女性の社会参加には大賛成です。しかし一方で、最近の日本では、冷静な議論をせずに「ダイバーシティ」「女性の企業参加」という言葉だけが一人歩きしている印象もあります。メディアなどでは、ややもすれば「女性が企業に入れば、それだけ業績があがる」と言ったニュアンスの主張さえ見受けられます。
しかし実は、経営学の研究成果からは、必ずしもそう話は単純でないことが明らかになっています。そこで本記事では、経営学の知見を紹介しながら、一歩引いた目で、冷静になって女性活用のメカニズムを考えてみましょう。
*職位や論考・評論等の内容は、公開された時点における情報です。
*Waseda Online では執筆者の研究に基づく論考・評論等を紹介しています。これらの論考・評論等は、早稲田大学としての見解を表明するものではありません。