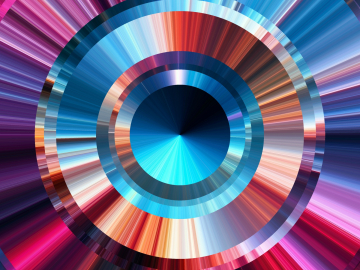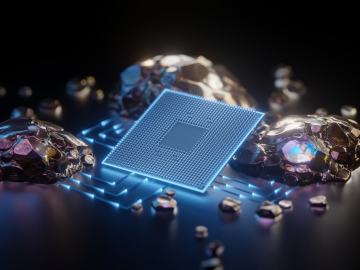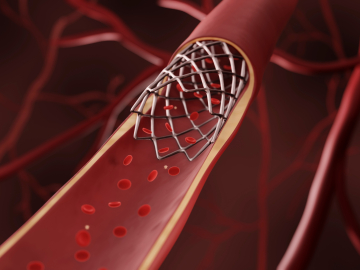早稲田の国際標準化教育
経済産業省国際電気標準課課長らと意見交換

2025年2月26日(水)、経済産業省 イノベーション環境局 国際電気標準課 小太刀課長、同課 前場課長補佐、同局基準認証政策課 安本課長補佐らが、本学リサーチイノベーションセンター内に設けた「国際標準化教育センター」を訪問し、本学研究推進部部長/理工学術院教授の天野嘉春、カーボンニュートラル社会研究教育センター所長/スマート社会技術融合研究機構課長/文部科学省卓越大学院PEPプログラムコーディネーター/理工学術院教授の林泰弘らと、国際標準化活動やそれを担う人材育成について意見交換を行いました。
天野教授からの挨拶のあと、林教授から本学で行われている国際標準化教育について紹介しました。林教授は冒頭、「現在に至るまでに大きな3つの柱がある。1つ目は2014年度にスマート社会技術融合研究機構(ACROSS)を設立し、エネルギーマネジメントに関する国際標準通信規格に基づき国家プロジェクトを産学連携で多く推進してきたこと。2つ目は卓越大学院パワー・エネルギー・プロフェッショナル育成プログラム(PEP)で国公私立13大学連携の博士教育を推進し、この中でこれまでの国家プロジェクトの実績を踏まえて国際標準化教育を構築したこと。3つ目は全学的にカーボンニュートラルの研究・教育・社会貢献を三位一体で推進することを目指す組織として、2022年にカーボンニュートラル社会研究教育センター(WCANS)を設置し、総長主導で早稲田の総合知を結集し、包括的に産学協働する場を築いたこと」と話しました。
PEPの概要説明の中で林教授は「構想段階から国際標準化を念頭にエネルギー領域に係る技術・事業開発を進められる人材の育成を考えており、さらにその中から国際標準化活動に関わる人材が出ることを期待している」と言い、「PEPで行われている国際標準化教育は、研究とひと続き。実際に産学官で社会実装したデマンドレスポンスの国際標準通信制御規格(エコーネットライト)の実験設備を使い、実践演習する科目を置いている。その仕組みや考慮すべき事項などを学んだ上で、学生が自身の専門・研究テーマに落とし込み研究を展開できるように促している。」と話しました。

PEPの紹介をする林教授(右)。左が研究推進部長の天野教授
さらに、PEPの国際標準化教育は、国際電気標準会議(IEC)が設立した次世代電力システムの運用に関する標準化組織(IEC TC 8/SC 8C)初代議長を務めた本学の石井英雄研究院教授が主導して構築・実施したもので、本教育内容はJICAを通じて19か国45名へも提供されたことも紹介されました。
国際標準化に係る活動紹介のあと、実際の研究・教育現場となっているスマートハウスの見学を行いました。スマートハウス内には、ホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS)を国際標準通信制御規格を介して構成する重点8機器(スマートメーター、ヒートポンプ給湯機、蓄電池、電気自動車/PHEV、太陽光発電、燃料電池、エアコン、照明機器)を設置しており、さらに、アメリカのIT企業群が参画する無線通信規格標準化団体が2022年にリリースしたスマートホームのための「Matter」規格も含めて最新のシステムで演習できるように、ブラッシュアップを重ねていることも紹介されました。説明を受けて小太刀氏らからは、知的財産権の取り扱いや大学における標準化活動参画に関する質問があり、見学後も含めて意見交換を行いました。

研究内容についての説明。左から、高野氏、安本氏、前場氏、小太刀氏、林教授

スマートハウス内部のシステム設計についての紹介
本学ではPEPの実績を経て2024年10月から、経済産業省「特定新需要開拓事業活動計画認定制度(Open & Close strategy with Exploiting Academic kNowledge; OCEANプロジェクト)」の認定を2件(東京電力HD㈱との連携、三菱電機㈱との連携)受け、支援をいただいています。
今後、「標準化」はグローバル競争において一層重要な要素となることが予想されます。本学も、これまでの実績をもとに、産学官連携による日本の国際標準化活動に貢献してまいります。