- Featured Article
早大発スタートアップ、更なる躍進
Fri 11 Oct 24
Fri 11 Oct 24
早稲田発スタートアップのエキュメノポリス、さらなる躍進
株式会社エキュメノポリスが「大学発ベンチャー表彰2024」を受賞
2024年8月22日、「大学発ベンチャー表彰 ~Award for Academic Startups~」の受賞者発表が行われ、早稲田大学発のスタートアップ企業株式会社エキュメノポリスと支援機関として早稲田大学が「科学技術振興機構理事長賞」を受賞しました。
JST(国立研究開発法人科学技術振興機構)とNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)が主催する大学発ベンチャー表彰では、大学等の成果を活用して起業したベンチャーのうち、今後の活躍が期待される優れた大学発ベンチャーを表彰するとともに、特にその成長に寄与した大学や企業などが表彰されます。
本記事では、エキュメノポリスで代表取締役を務める松山洋一さん(現在グリーン・コンピューティング・システム(GCS)研究機構客員主任研究員、開発当時主任研究員)と、同社を支援した本学アントレプレナーシップセンター所長の石井裕之教授(理工学術院)、本学GCS研究機構 知覚情報システム研究所所長の小林哲則(理工学術院教授)を取材。早稲田発のスタートアップは、どのようにして躍進を遂げたのか。その軌跡を追っていきます。
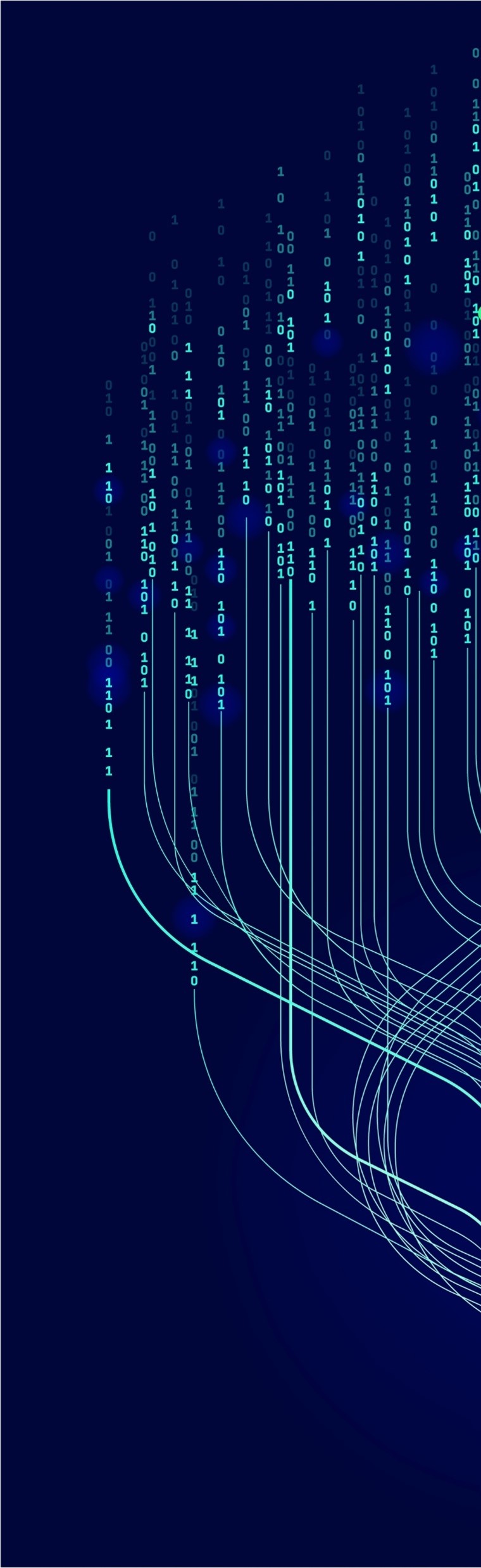
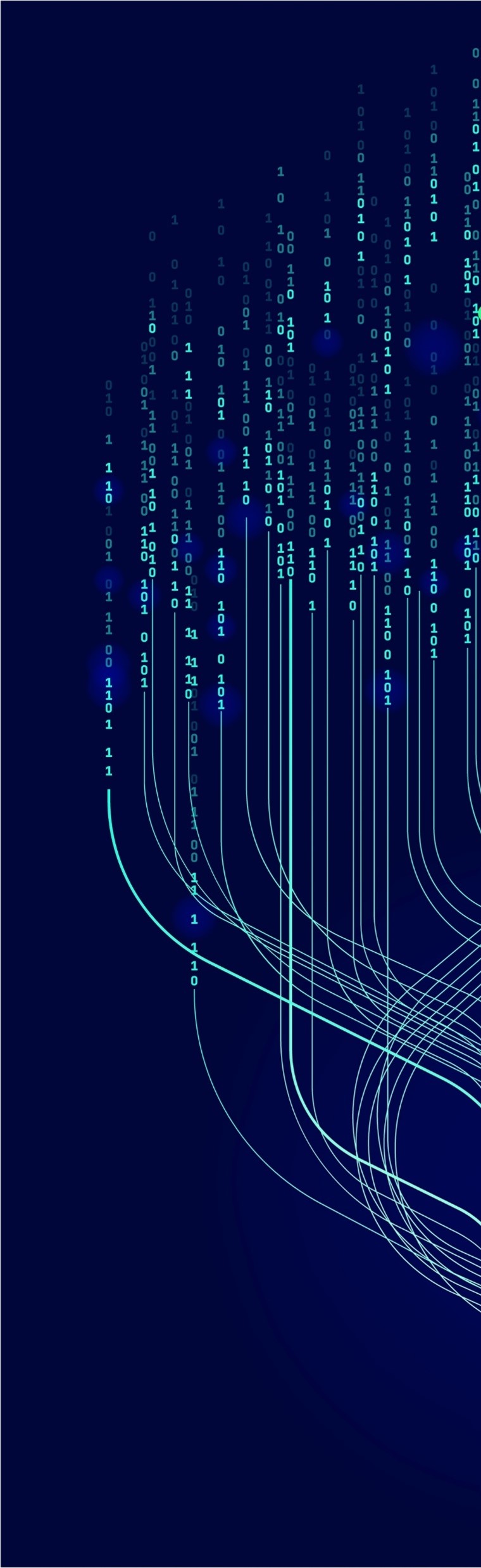
英語教育の革新に寄与する、AI対話システム
人とAIが協調し、共に成長していく社会の創出を目指す、株式会社エキュメノポリス。2022年に早稲田大学発のディープテック・スタートアップとして創業し、翌年には世界的なEdTechイベント「SXSW EDU Launch」に東アジア唯一のファイナリストに選出されるなど、急成長を遂げている。
主力サービス「LANGX Speaking」は、AIによるオンライン英会話レッスンだ。モニターに映し出されたAIエージェント「InteLLA」は、ユーザーとのインタラクティブな会話が可能。学習者のレベルに合わせ、リアルタイムで難易度を調整しながら会話を進めていく。そして一定時間の会話を終えると、学習者の総合的な英会話能力を高精度で診断。評価は世界的な語学能力判定基準である「CEFR(※)」に基づいており、学習者のダッシュボードには、スコアや判断根拠、次の学習課題などがフィードバックされる。

LANGX Speakingは、InteLLAによるインタビューを通して英会話能力を診断する。リラックスした雰囲気で学習者の緊張感を和らげながら、発言できない際は待機してくれる。傾聴動作や話者の切り替えも行い、トピックは簡単な日常会話から社会問題までレベルに合わせてパーソナライズされる

学習者のダッシュボード。各項目が7段階で評価され、上達のポイントも提示される
LANGX Speakingは現在、教育機関を中心に導入が進んでいる。早稲田大学では2023年度より、全学共通の正規英語科目「Tutorial English」の能力判定テストとして採用。九州大学や中央大学などでも試験導入が始まった。事業を牽引するCEOの松山さんは、「個々の能力を精緻に診断できる」と、自社の強みを語る。
松山
「例えば早稲田のTutorial Englishはレベル別のクラス編成が特徴ですが、LANGX Speakingの導入によってスピーキング能力に基づくクラス分けの精度が向上したことが、運用2年目にして明らかになってきました。自分のスキルの正しい把握は学習の基本となるため、英語能力の向上に貢献できると考えています」
このアプローチは中学や高校でも有効で、昨年には千葉県の県立高校で実証事業が行われた。今年度は千葉県に加えて岐阜市にも展開している。生徒の特性が学校や自治体に共有され、授業の最適化や教科書との連動に応用できれば、英語教育全体のアップデートが見込める。またLANGXのコア技術は、企業研修や英会話スクールなど、さまざまな英語関連産業にも応用可能だ。企業向けに技術を提供すれば、事業領域も大幅に広がる。
松山
「“対話”と“診断”の両方を備えた当社の技術は、世界的に見ても独自性が高いと思っています。英語は国境を超えた需要がありますし、人材不足といった課題の解決にも貢献できます。次のステップでは、カリキュラム提供などの機能拡張、技術の知財化や標準化を進めます。そしてグローバル市場で一勢力を成すプラットフォームへと、事業を拡大するつもりです」
壮大なビジョンを描く松山さんは、どのようにしてエキュメノポリスを立ち上げたのだろうか。次に創業に至るストーリーを見てこう。

週刊東洋経済「すごいベンチャー100」2023年最新版にも選出された、株式会社エキュメノポリスCEOの松山洋一さん
※CEFR…「Common European Framework of Reference for Languages」。国際的な基準であるヨーロッパ言語共通参照枠として、2001年に欧州評議会が公開した
GCS研究機構の研究者として、創業を準備した3年間
松山さんは早稲田大学の基幹理工学研究科で博士号を取得後、米国・カーネギーメロン大学に在籍。ダボス会議公式パーソナルアシスタントプロジェクトや、GAFAMを含む複数の産学連携で会話AI研究開発のプロジェクトを率いるなど、ポスドクの研究員として経験を積んだ。AIによる英会話サービスを事業化しようとしたのは、2019年に帰国したタイミングだ。着想の源泉は、学生時代の経験だった。
松山
「私自身、早稲田大学の在学中にTutorial Englishを履修していたんです。当時、白井克彦先生(元早稲田大学総長)や中野美知子先生(元教育・総合科学学術院教授、名誉教授)らが、ITインフラ整備や英語教育改革を進めており、同じ頃に欧州評議会からCEFRも公開されました。そうした中で会話志向型かつレベル別のTutorial Englishが始まり、私は第一世代の受講生だったわけです。その後、研究者としてのキャリアを歩む中で、AI対話システムを英語教育に活かせると直感的に思いつき、起業を決意しました」

実際の人間をモデルに、InteLLAの動作をアップデートする作業。エキュメノポリスの研究所にて
帰国後、松山さんは中野名誉教授とTutorial Englishを企画・実施しているグローバル・エデュケーション・センターおよび早稲田大学アカデミックソリューションに対し、英語教育の状況についてヒアリングを重ねた。その結果、読み書きを中心とするペーパーテストに偏る英語能力の判定が、大きな課題として浮上。AI対話システムによる能力判定という、技術開発の方向性が固まっていく。中野名誉教授の紹介など、松山さんを全面的にバックアップしたのは、知覚情報システム研究所にいた小林哲則教授だ。
小林
「帰国後の松山くんには、GCS(グリーン・コンピューティング・システム)研究機構の主任研究員に就任してもらいました。当時の松山くんは100を超える事業案を考えていて、英会話とは別の事業でJSTの『研究成果展開事業 大学発新産業創出プログラム(START)』に、2019年に採択されています。LANGXにおいて松山先生のセンスが優れているのは、能力判定に注目したことでしょう。当時のAI対話システムはまだ技術水準が低く、診断という別のアプローチで攻めるスタンスは画期的でした。社会的ニーズを見極めながら、付加価値を明確にする力は、研究資金の獲得などでも発揮されたのではないでしょうか」
松山
「中野先生ら多くの方々の協力を得て、2020年にNEDOの事業に採択されたことは、STARTにつづく大型の資金となりました。ただし創業準備期の私にとって一番ありがたったのは、小林先生にGCS研究機構のポストをいただけたことです。帰国しても働き口がなかった私は、故郷の東北で妻と畑仕事をしながら、起業準備をしようと思っていたくらいでしたから(笑)」

松山さんの師にあたる小林哲則教授。音声・画像処理などを用いたコンピュータ・ヒューマン・インタラクション、知能ロボット、音声の生成・知覚、インタフェースの開発パラダイムなど、幅広い研究に興味を持つ
アントレプレナーシップセンターで、経営のインフラを整える
獲得した研究資金で応用研究を進め、3年の準備期間を経て起業に踏み出した松山さん。創業前後に支援を受けたのが、早稲田大学のアントレプレナーシップセンターだった。
松山
「アントレプレナーシップセンターの住所で法人登記をさせてもらったり、弁理士さんを紹介してもらったりと、インフラ周りを整えられたのは、アントレプレナーシップセンターのおかげです。コンサルタントには、人事・労務から知財ビジネスの闘い方まで、会社経営のノウハウを教わっています。また、大学主催のイベントへの参加がきっかけとなり、早稲田大学提携ベンチャーキャピタルであるBeyond Next Ventures株式会社より出資を受けることもできました。現在はPR面でのバックアップをしていただいており、大学を通した広報のリリースが起点となることで、メディア露出が増えています」
現在アントレプレナーシップセンターの所長を務める石井裕之教授は、起業を志す多くの研究者と接する中、松山さんの事業推進力に注目してきた一人だ。

ロボット工学や知能機械学を専門とする石井裕之教授。次世代型全自動歯ブラシを手掛ける大学発ベンチャーの株式会社Genicsでは、テクニカルアドバイザーを務める
石井
「アントレプレナーシップセンターとして大切にしているのは、失敗を許容する環境です。やはり新たなイノベーションを育む以上、時間をかけて支援する姿勢は欠かせません。大学発のスタートアップを見ていると、創業までは順調なものの、シード期を抜けた後に停滞してしまうケースが多い。エキュメノポリスのスケールアップは、かなりスピーディーだと感じます」
松山
「私たちもベンチャーキャピタル50社ほどに出資を断られるなど、順風満帆に進んだわけではありません。それでも大切にしていたのは、小林先生の『筋の良いことをやれ』というアドバイスでした。『誰が困っているか』『課題に対してベストな技術は何か』『どのようにスケールするか』をロジカルに説明できる時は、事業もスムーズに進むと感じます。例えば公的な助成金の獲得においては、社会全体のマクロな文脈の中で、自分の立ち位置を説明しなければなりません。創業前の3年間、片端から申請書を作成した経験は、事業価値を問い直す上でもプラスに働いたと思います」

大学発スタートアップを増やすため、早稲田が進めるべきアプローチ
大学のリソースを最大限活用し、スケールアップを実現したエキュメノポリス。今回の「大学発ベンチャー表彰」の受賞には、どのような意義があったのだろうか。
松山
「もちろん社会的な信頼獲得といった効果を期待しますが、何よりも嬉しかったのは、お世話になった皆さんにお礼を言える機会をいただけたことでした。小林先生をはじめ、学内関係者に改めてこれまでのご報告ができたことは良かったと思います」

「大学発ベンチャー表彰」授賞式の様子。支援機関向けのトロフィーには松山さんの希望で、小林教授の名前が刻まれた
石井
「松山先生の飛躍により、アントレプレナーシップセンターのプレゼンンスも向上し、後続する若手の刺激にもなったと思います。創業の裏側には、師匠にあたる小林先生の支援があったことも、今日の鼎談でわかりました。大学としても縦のつながりを強化するなど、支援体制をより強化したいと思います」
小林
「エキュメノポリスの成長を“特例”にせず、そこに内在する要因を分析しながら、大学として欠けているピースを埋めていくべきでしょう。ギャップファンドやアントレプレナーシップセンターで満足せず、客観的で冷静な指導にあたる人材を確保するなど、よりシステマティックな支援体制を整備していく必要がありますね」
松山
「早稲田の大学院時代、私はアントレプレナーシップ関連の授業を受けていましたが、今になってその効力を感じます。教育や人材育成は、時間差で効果が現れるものなのでしょう。本当に次世代を育てるならば、10〜20年スパンの継続的な支援も重要です。私の場合は30代の最後に大きな勝負に出たわけですが、それより早くても遅くても、上手くいかなかったかもしれません。若手人材にとって大切なのは、ベストなタイミングでチャンスを掴めるように、素地を養っておくこと。そして機が熟した時に、自由に挑戦させくれるのが、早稲田という環境の強みでもあります。世の中を変える大学発スタートアップは、もっとたくさん生まれるはずです」

撮影=早稲田大学グリーン・コンピューティング・システム研究センター エキュメノポリス研究所


