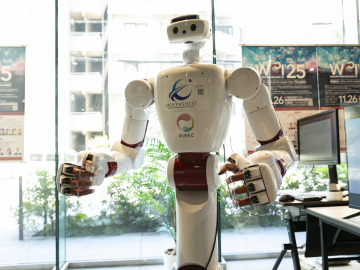2024年6月12日、泉谷満寿裕珠洲市長が東京での多忙な公務の合間を縫い、早稲田大学へお越しになられました。1月1日に発生した能登半島地震の状況について、当日海外校務のため不在であった田中愛治総長に代わり、萬代 晃常任理事(校友連携)・校友会代表幹事、松居 辰則平山郁夫記念ボランティアセンター(WAVOC)所長、荻原 里砂教務部教育連携課長に情報の共有をいただきました。

珠洲市の現状
冒頭、泉谷市長から「現在珠洲市は、水道の復旧率が79%で、全4,800世帯のうち994世帯が断水している状況です。一部の地域では下水管が機能不全に陥っており、復旧の見通しが立っていません。仮設住宅は1,600戸が必要であるのに対し、完成しているのは854戸です。用地手配の目処が立ち、需要に追いつく予定ですが、避難所におけるエアコンの設置が追いつかないなど課題も多い状況です」と珠洲市の現状について説明がありました。
「早稲田」の校友ネットワーク
泉谷市長は1987年に政治経済学部を卒業されている事もあり、能登半島地震の発災直後に、田中愛治総長と電話で現地の情報共有をしたというエピソードの紹介がありました。
「発災直後に田中総長よりお電話があり、必要な支援について質問をいただきました。避難所の水不足が想定されたので、水道のない場所でも使用できる、循環式の手洗いスタンドやシャワーが必要であることを伝えました。さっそく田中総長より日本財団を通じてWOTA社の移動式シャワーボックス55台、手洗いスタンド28台を届けていただきました。自分が早稲田大学の卒業生であることを、改めて強く感じた瞬間でした。
また、特定非営利活動法人『難民を助ける会』からは非常用携帯トイレなどの物資支援をいただいておりますが、現在会長を務められている長 有紀枝さんは、学生時代は私のクラスメイトでした。他にも多くの校友の皆さまにご支援・ご協力をいただいています。早稲田大学の校友の皆さまに、心から感謝申し上げます」
早稲田大学としての取り組み
WAVOCではこれまでに6回、学生ボランティアが能登エリアで支援活動をしてきました。また本学では2020年より珠洲市との「地域連携ワークショップ」を継続して実施してきました。こうした関係から多くの学生が珠洲市での活動を希望していること、参加した学生が住民の方々に温かく迎えられたことが、松居所長と荻原課長より泉谷市長へ伝えられました。
「ボランティアに関しては、珠洲市はたくさんの方々にご協力いただいてきました。今後も家屋からの家財の運び出しなど、多くの支援が必要になりますので、ぜひご協力をお願いします。また、地域連携ワークショップに関しては、今年度は能登半島地震に関する支援で来られている方々へのヒアリングや資料収集を予定されていると伺っています。珠洲市でも多くの支援団体の皆さんが活動しており、その内容を知ることは、学生の成長の助けにもなるはずです。ぜひ交流を深めていただきたいです。
早稲田大学の学生の皆さまには、ぜひ“自分事”として、各活動にご協力いただきたいと考えております」
泉谷市長より「早稲田大学」へのメッセージ
最後に、泉谷市長より早稲田大学に対して、次の通りメッセージが述べられました。
「いろいろな方にご支援をいただいたことを、本当にありがたく思います。珠洲市では多くの建物が壊れてしまいましたが、これまで培ってきたネットワーク、取り組みは壊れることはありません。それを希望の光として、一歩ずつ復興に進んでいきたいです。そして、私自身も早稲田の卒業生として恥ずべき行動はできませんので、全力で使命を果たしてまいります。校友や学生の皆さまにも、引き続きご支援をいただけますと大変ありがたく存じます」

左から荻原教育連携課長、松居WAVOC所長、泉谷珠洲市長、萬代常任理事、菊池理事
早稲田大学では卒業生を含め被災地域で生活されている方々に向けて物心両面からの支援、特に被災地域を出身とする学生や入学支援者の皆様に対して在学・受験上の経済援助などできうる限りの支援を行って参ります。