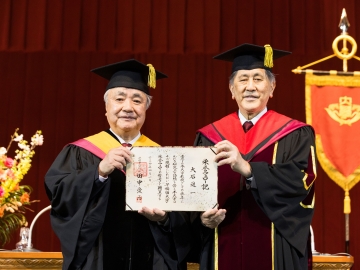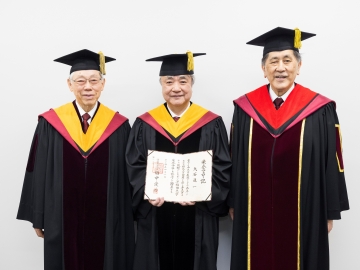栄誉フェロー 大石 進一 理工学術院 元教授

皆様、ご入学、ご進学おめでとうございます。只今は栄誉フェローの贈呈を頂きまして誠にありがとうございました。
私が早稲田大学理工学部電子通信学科に入学したのは1972年の春ですので、52年も前のことになります。1980年に博士3年生で助手に奉職して以来44年間早稲田大学で教育研究をおこなってきました。一言で言えば、自由に好きな研究を思う存分にさせていただきました。早稲田大学には感謝の言葉しかありません。
本日は私の研究の歴史をお話しさせていただいて、皆様の学生生活の参考にしていただければと思います。わかりやすいように、格言のような表現をさせていただきます。
最初の格言は「大学生時代、集中して勉強すると驚くほど頭が良くなる」です。大学2年生になり、化学(ばけがく)で量子力学に基づく原子論を習いました。そこで当時刊行開始された岩波講座「現代物理学の基礎」(全12巻)の中の一冊「量子力学II」を読むことにしました。夏休みを使って、行間を埋め、計算を再現しながら、息を呑むように読み進めました。読了には夏休みいっぱいかかりましたが、ずいぶん頭が良くなった感覚がありました。大学生時代集中して勉強すると驚くほど頭が良くなるものだという体験になりました。今日、皆様にお伝えしたい第1のことです。
第2の格言は「教室で学ぶのはとても役立ち効率的ではあるが、入門であり、深く学ぶには教室で教えられないことまで学ぶことが大切」ということです。12巻からなる「現代物理学の基礎」シリーズは、日本全国の物理の先生が物理をまるで冒険譚のように語ってくださるので、恐ろしく面白く、次々に読み進めていきました。「古典物理学II」の巻では量子力学の逆散乱問題を使って非線形方程式を厳密に解くという奇想天外なソリトン理論の紹介に出会いました。
3年生の終わり頃には「ソリトンを使った通信理論」を卒論でやろうと思いました。非線型光ファイバの基礎方程式である非線形シュレーディンガー方程式を拡張した広田方程式がまだ解かれていないということでこれを解くことにしました。すぐに解けて初めて学会で発表しました。修士に入ると、とても不思議な広田の双線型ソリトン方程式を調べてみました。すぐに、ある形の双線型方程式のクラスには皆2―ソリトン解が存在することを発見しました。これを発表するとソリトン理論の開拓者の一人である戸田盛和先生に大変褒めてもらえました。博士課程に進学し、今度はそのクラスの双線型方程式にはFredholm行列式でかけるある意味一般解があることを発見しました。博士2年生の時です。これ以降、毎月1つずつ論文を書くことができ、結局8編の論文をまとめて博士学位を頂くことができました。さて、Fredholm行列式は独学で勉強していました。大学2年生の時の数学の講義で武田二郎著「工業数学の基礎<上>」(槇書店)が教科書に使われました。<上>があるなら<下>もあるはずであり、それはどんなことが書かれているのだろうと思い、買って読んでみました。すると、Fredholmの積分方程式論が書かれていて、有限次元の行列式の無限次元への拡張としてFredholm行列式が導かれていました。これが博士論文につながりました。習った先に何があるか、関心を持つとよいという体験談です。
第3の格言は「流行り分野をやるのではなく、流行りの分野を作り出せ」です。砕いていうと、天才の裏をかけです。
博士3年生になると京大数理研によく呼ばれ、研究集会で発表しました。書き上げたばかりの論文のコピーを日本発の超関数論で名高い佐藤幹夫先生のグループに差し上げました。その年、佐藤先生はソリトン解の全体がグラスマン多様体をなすこと、そして、その多様体上で成立する恒等式群のプリュカー座標系での表示が双線型方程式になることを示しました。また、ソリトン方程式は無限次元のリー環で分類でき、私がやったのはA型のリー環の双線型方程式の一般的な解を求めていることになることが示されました。佐藤グループは私の解の相互作用項に着目していました。私はこの項を不思議な行列式の恒等式を駆使して導きました。これがA型リー環の代数構造の本質的な部分でした。佐藤理論によってあれほどミステリーだったソリトン方程式の代数構造が一夜にして解き明かされてしまいました。佐藤先生はものすごい天才であったのです。この人を超えられるのかというのが次のテーマになりました。そこで「ソリトン」という流行りの分野ではなく、新しい分野自体を開拓しようと思い、ソリトンの研究から離れることにしました。そして、「佐藤先生の嫌いそうな」代数構造のない非線型偏微分方程式の厳密解を求めることにテーマを変えました。具体的にはコンピュータで面白そうな近似解を見つけその近くに真の解が存在することをコンピュータを使って証明する計算機援用解析の研究をすることにしました。それは、四捨五入をする計算機の四則演算の誤差など、計算機で発生する誤差を全て把握する「精度保証付き数値計算」を用いて非線形方程式の厳密な解を求める方法です。この方向で、やってみるとすぐに色々な成果が出ました。そして未解決問題であるローレンツ方程式のカオスの存在の厳密証明をしようとして、当時の精度保証付き数値計算の研究レベルが不十分であることに気がつきました。80元ぐらいの連立一次方程式の解の精度保証が限界だったのでした。この問題の解決が最優先であると思い、追求していると、コロンブスの卵的発想で、行列単位に浮動小数点数の演算の丸めの向きを変える方式により、近似計算の2倍の手間で連立一次方程式の解の精度保証ができることに気がつきました。一気に1000万次元ぐらいの連立方程式が場合によって解けることがわかったのです。そして、数値計算のほぼ全ての問題がこの方法論によって効率よく解けることを示すことができました。新しい分野を体系的に開拓できたのでした。非線形方程式を計算機を使って厳密に解くという、綺麗に解きたがる天才の裏をかく作戦が成功したといえるでしょう。
以上3つの格言を申し上げました。今、理工学術院では素敵な校舎の増設が進んでいます。総長をはじめとして実現してくださっている方々に深く感謝します。皆さんにとって一層快適な勉学と研究の環境が整うことと思います。
改めまして皆様、ご入学おめでとうございました。