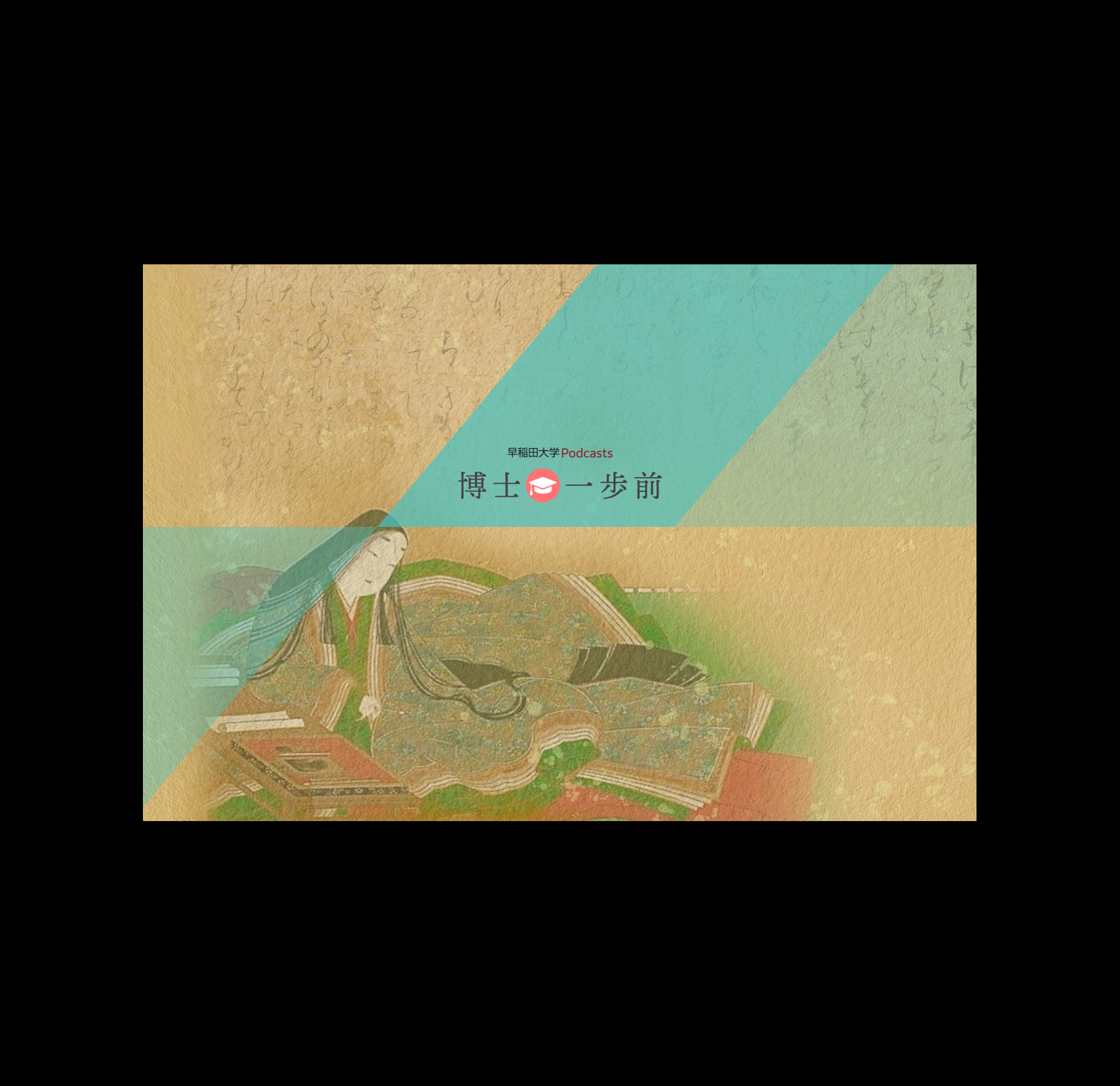- Featured Article
Vol.2 国文学(3/4)【平安に栄えた日記文学】宮仕え女房の 役割と実相 / 福家俊幸教授
Tue 21 May 24
Tue 21 May 24
国文学シリーズの第3回目では、平安時代の宮仕え女房たちの生活とその文化的役割に焦点を当てます。
紫式部の日記から垣間見える、宮仕えのリアリティ。宮中生活の中、各々が抱えていた社会的役割と個人的な感情の狭間で、女房たちはどのように文化を形作っていったのでしょうか。福家教授の日記文学研究への想いとともに伺います。
配信エピソード一覧
ゲスト:福家 俊幸
教育・総合科学学術院教授。専門は平安時代の文学・日記文学。
1962年香川県生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。博士(文学)。早稲田大学高等学院教諭、国士舘大学助教授、早稲田大学教育学部助教授を経て現職。著書に『紫式部日記の表現世界と方法』(武蔵野書院)、『更級日記全注釈』(KADOKAWA)、共編著に『紫式部日記・集の新世界』『藤原彰子の文化圏と文学世界』『更級日記 上洛の記千年』(以上、武蔵野書院)、『紫式部日記の新研究』(新典社)、監修に『清少納言と紫式部』(小学館版・学習まんが人物館)など。

ホスト:城谷 和代

研究戦略センター准教授。専門は研究推進、地球科学・環境科学。
2006年 早稲田大学教育学部理学科地球科学専修卒業、2011年 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻博士課程修了 博士(理学)、2011年 産業技術総合研究所地質調査総合センター研究員、2015年 神戸大学学術研究推進機構学術研究推進室(URA)特命講師、2023年4 月から現職。
- 書籍情報
-
-
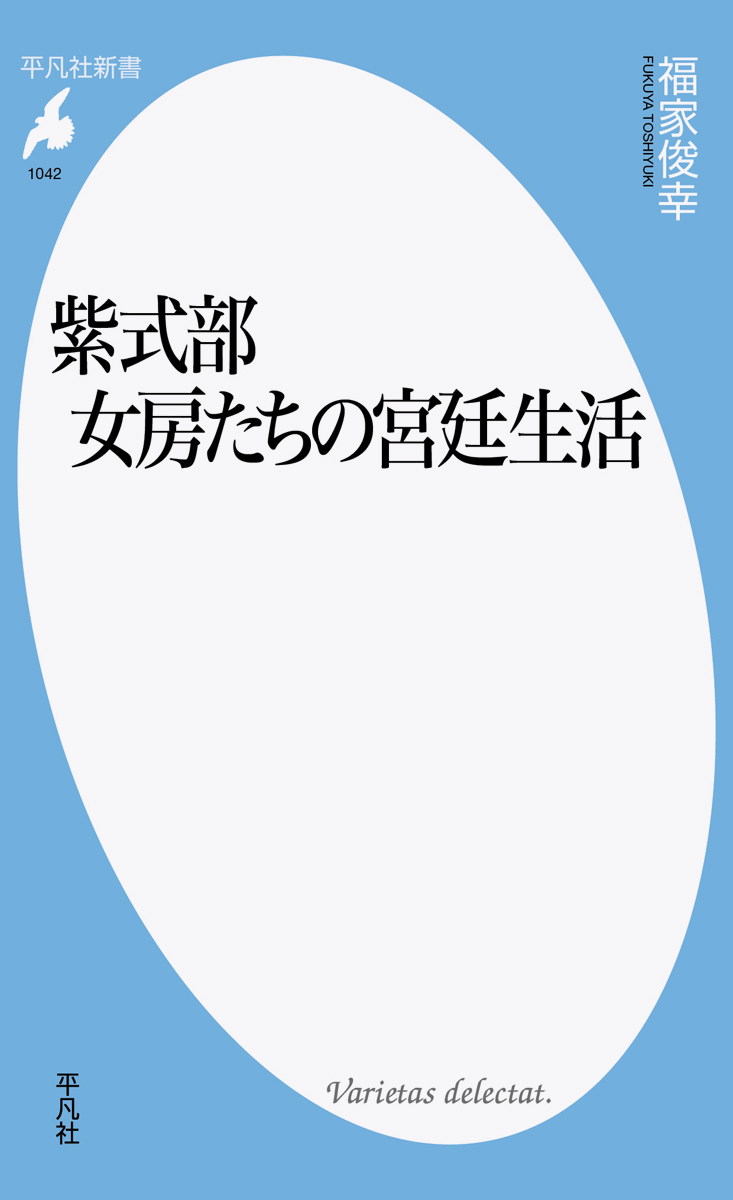
紫式部 女房たちの宮廷生活
出版社:平凡社
発売日:2023/11/15
言語:日本語
単行本:264ページ
ISBN-10:4582860427
ISBN-13:978-4-582-86042-9
-
エピソード要約
-平安文学の魅力
平安時代の女性、特に女房たちはその時代の日常や感情を反映した作品を残しており、紫式部の日記などの記録は、宮仕えの厳しさや文化的なステータスを上げるための役割など、当時の女房の生活のリアリティを伝えている。
『源氏物語』や平安時代の文学作品は、登場人物の生き生きとした描写と共感できるキャラクターにより、読者の関心を引きつけ続けている。
-宮仕え女房の光と影
宮仕え女房は知的で教養深い女性が選ばれ、宮中の進んだ文化に触れる機会を得ていたが、同時に権力的な側面もあり、自分の親族を売り込む役割も担っていた。一方で、女性は顔を見せないことが嗜みとされていた時代に、立場上顔が知られている女房を奥さんに迎えることに抵抗感を持つ保守的な男性もいたとされている。紫式部の娘が天皇の乳母になるなど、宮中で活躍した女房が高い地位を得ることもあり、これは大きな栄光と見なされた。
-福家教授の研究について
国文学の研究者として、特に日記文学、仮名文学を中心に研究している。仮名日記は基本的に女性が主体となって書かれ、特に平安時代のものは書き手の個人的な思いや人間くささがより表面に出ており、これが福家俊幸教授の研究における関心の一つである。
教授の研究への情熱は、古典に関する様々な議論と教育を通じて育まれ、特に『紫式部日記』との出会いが研究の方向性に大きな影響を与えた。福家教授は研究者として早い段階で論文を執筆し、外部の厳しい評価を受けることを通じて学び、成長してきた経験を持つ。
エピソード書き起こし
城谷准教授(以降、城谷):
2024年、大河ドラマで『源氏物語』を扱っているという段階ですが、それからしてもかなり関心が高いと感じているところです。
今、改めまして先生は、紫式部ですとか『源氏物語』、世の中の関心について、どのように感じていらっしゃいますでしょうか?
福家教授(以降、福家):
『源氏物語』の作者・紫式部は、平安時代の中期を生きた女性なわけですよね。宮仕え女房だったわけですが、例えば戦国時代の女性たち、お市の方とか、前の大河(ドラマ)でいうと築山殿ということになるんでしょうか。こうした人たちももちろん懸命に生きていたと思うんですけれども、結構実際彼女たちが語ったことというのは残っていないです、ほとんど。記録にはあまり残っていない。辞世の歌なんかはお市の方など残っているかと思いますけれども、本人が本当に詠んだかどうか、またいろんな議論もあるところです。そうした女性たちの声って結構残っていないんですけれど、平安時代はそうした人生がかなりわかっているわけです。書いたものも残っているし、物語だけではなくて日記も残っているし、詠んだ歌も残っているわけです。紫式部に限らず、例えば赤染衛門だとか、和泉式部だとか、あるいは清少納言とかですね。それぞれもうキャラクターが結構はっきりわかりますよね。赤染衛門ですと良妻賢母だとか、和泉式部だと恋多き女性とかですね。清少納言だとちょっとなんか高慢な人みたいな感じですね。実はそんなことなかったかもしれませんけれども、イメージみたいなものがあって、大河ドラマの中にもそういったイメージが反映している部分も、清少納言なんかも出てますけれども、ありますよね。
そうした現代人にも共感しやすいキャラクター、特に女性たちのキャラクターが出てきているところがあって、もちろん『源氏物語』への関心もずっと継続的に高まっているわけですけれども、特にやっぱり紫式部とか、そういった周辺にいた女房たちの、そうした個性豊かな人物像と言っていいだろうと思います。また女性に限らず男性貴族たち、藤原道長や公任、あるいは斉信とか、行成だとか、源俊賢とか、そういった男性貴族たちもいずれも個性豊かでいろんな逸話も伝わっていて、そういったところが、今は結構若い人たちはキャラクター的なものって好きですよね、そういうキャラクター的なものの共感もあるんだと思います。
また『紫式部日記』を読んでみると、宮仕えの辛さというか、自分の主人筋からあまりによくされていると、周りからいろんな軋轢といいますか、実際紫式部が車に乗ろうとしたら、当時車に乗る順番は決まっていて、偉い順から乗っていくわけですけれど、ちょうどたまたま一緒に乗ろうとした馬の中将という女房が、なんで私と一緒に乗るの? みたいな。そんなような反応をされたということを、彼女は日記に書いていたり、そういう結構宮仕えの辛さというのも、現代人の共感を得るところもあるんじゃないかなと思ったりするんです。
城谷:
平安時代のものが残ってるというのが、それだけでも魅力的かなと思うのと、あといろいろな登場人物がそれぞれのキャラクターで、まず生き生きと読み手に入ってくるっていうところの面白さがあると思います。かつ共感できるというところが、一層関心を持っているのかなというふうに思いました。
現代人との共通点とか、またその違いであるというところについて、紫式部とか、彼女が職業として職場にいた女房の世界とか、宮廷生活のところから、先生にいろいろ共通点、違いなどをお伺いできればなと思います。
福家:
この時代の宮仕え女房というのは、基本的には雑用などをあまりすることはなくてですね。むしろ主人と主人の文化的なステータスを上げるという。
城谷:
プロデューサーみたいな感じですかね。
福家:
主人をいかにプロデュースしていくのかという、そういう一翼を担っているという感じになっているわけですよね。主人のもとに歌を詠んだり、場合によっては物語を作ったり、日記を書いたりといったような知的な作業に従事していくんですけれども、そういう意味では非常に知的な、教養深い女性が選ばれてきたということはあるわけですね。
階層的には、ちょうど紫式部と同じような中流貴族、いわば地方の国主を歴任していく、今でいうと県知事などを歴任していくような階層の娘たちが選ばれることが多かったんですね。そういった人たちが幼い頃から教養を身につけて、そして宮仕えに上がって、宮仕えに上がっていくということは一つのステータスになるわけですし、より高度な文化といいますか、宮中の進んだ文化に触れることができるということです。
一方では、これも権力的な問題と関わってきますけれども、仕えている主人は当然身分が高いわけで、そのお父さんなんかは当然高位高官なわけで。当時、女房たちは自分の仕えている主人に対して、自分の親族、例えば父親とか、あるいは弟とかお兄さんとか、そういった人たちを売り込むってことをよくやっていたわけです。これは『枕草子』にも書かれていますけれども、除目という人事異動の、年に2回あるんですけれども、その人事異動の儀式が近づくと女房たちが自分の主人に向かって一生懸命自分の親族を売り込んでいるという話が出てくるわけで。そういう意味では、一家に一人ですね、女房に出ているとそういう役に立つという部分もあったわけです。
そういうのは現代と違うところですけれど、また同時に、女房たちは、儀式に参加していくことも重要な仕事で、そうなると男性貴族たちの視線をかなり浴びるということになりますよね。実はこの時代は、絶えず女房たちは、女性全般ですけれども、貴族女性全般なんですが、御簾や几帳と言われる、カーテンのようなところの陰にいて、男性の視線から見えないようにしている。
城谷:
非常に想像力をかきたてられるという。
福家:
そうなんですよね。本当に見せない魅力というんですかね。そういうところでいたわけですけれども、一方で男性の方からすると、顔を見せないのがいいと、嗜みなんだという捉え方があって、一方であの女房というのは、男性から直接顔を見られてしまう機会も結構あるわけです。
城谷:
立場上というか、その動きというか。
福家:
そうですね、動きの中でですね。中には部屋にいた時に、覗きに来る輩もいるわけですよね。現在だったら大変な問題ですけれども、当時は割とそういうことがあったようです。そういった女房たちを、むしろ男性たちは、一方では結構はしたない存在だと思っていたところもあるようなんですね。女房を奥さんに迎えるというのは、なんかその顔が周りの連中に知られているので、どうも抵抗があると。そんなようなことがあって、『枕草子』で清少納言が書いてますけれども、そういうように女房を奥さんとして迎えるのを嫌がる男性がいるけれども、清少納言はそれに対して反論していて、当時の宮仕え女房は宮中のことをよく知っているので、そういう奥さんを迎えたら、旦那が宮中に出て行った時にむしろいろんなアドバイスをしてくれると、役に立つよってことを強調して言っています。一方ではそうした宮仕え女房に対する厳しい目といいますか、やっぱり家にずっといる女性の方がいいんだみたいな保守的な見方をする男性も結構いたようなんですね。
城谷:
自分に対して見せる一人という、いろんな人には晒されていないっていうことに、ちょっといいかなと思うところがあったんですね。
福家:
ですから宮仕え女房は学校とか行くこともないですから、家では中流貴族の娘といってもですね。
城谷:
お姫様ですね。
福家:
お姫様ですもんね、本当にそうで、外泊とかしたことないわけですし、また集団で寝たこともないわけです。『更級日記』の作者の菅原孝標女は、初めて宮中に行った時に、他の女房たちとの間に挟まって寝て、もうまんじりともできなかったというふうに書いていますけれども、それが実際実感であって、結構女房にもつらいところがあったと。光と影の部分とですね、両方あったということだろうと思うんですね。
城谷:
親族を宣伝できる、売り込めるっていうところも一つ、多分それは本人自身よりも、周りの親族が期待してるというところも大きかったと思うんですけど、やっぱり宮中に入った女房自身にとってはなかなか慣れない面もあるけど、いろいろな上流の文化に入り込めるというのは、非常に魅力的だったっていう。
福家:
そうですね。これは紫式部の宣孝との間の、賢子という名前の娘ですけれども、彼女は後に宮仕えに出まして、『百人一首』の中で大弐三位という名前で歌もとられているので有名ですけれど、娘・賢子、大弐三位は、後に後冷泉天皇となります天皇の乳母(めのと)になるんですね。この時代は、そうした宮中で活躍した女房の、ある種の最高の立場が、天皇になるような皇子の乳母(めのと)になること、乳母(うば)になるということでもありましたので、そういう栄光の座を掴むということにも繋がっていたわけでした。また、おそらく、これは推測になりますが、なぜ紫式部の娘が天皇の乳母になれたかといえば、これは紫式部がお仕えしていた中宮彰子が、長年『源氏物語』を元としながら、自分に親しく仕えてくれた紫式部に対する、お礼の意味を込めて、娘をそういう立場に置いたんじゃないか、というふうにも考えられまして。
城谷:
すごい物語があって、いいですね。
福家:
そういうサクセスストーリーにも繋がってくるということでもあったかと思います。
城谷:
平安時代の宮中生活での女房の切り口から、共通点だったり違いだったりをお話いただいたところですけれども、そういったところが現代との比較とか、その時代を研究するという部分、学術的な、先生のご研究が注目されている点かなと思います。
ここから先は、先生のご研究について色々お聞きしたいと思っております。まず、福家先生が国文学という研究分野に対して抱く研究への情熱とか、思考の一端について、聞いていきたいと思います。突然ですけれども、研究者としての道のり、先生が、やはりこの時代、先生のご著書というのは、今回紹介させていただく『紫式部 女房たちの宮廷生活』以外にも、この時代の女性といったところの切り口での著書が多数あると思っておりまして、そのあたりについて先生のお話を伺いできればと思います。
福家:
私は早稲田大学の教育学部の国文科の出身で、入学は1982年ですが、私一浪しておりまして、今は予備校の先生って結構専門的な予備校の先生が普通じゃないですか、専属の先生みたいな感じですよね。実は当時は大学の教員が教えに来ていまして、早稲田の先生も来てはいたんですが、国文の先生は、古典の先生は早稲田の先生はいなかったんですが、ただ、他大の先生がいらしていて、もうお亡くなりになられた先生ですけど、『古今集』の権威的な存在であった村瀬敏夫先生とか、『伊勢物語』の同じく権威的な存在であった山田清市先生とか、そういった先生方が予備校の授業をやってたんですね。丸々1時間潰して源氏の話をするとか、ある意味その予備校で古典を手ほどきをしていただいたというか、答えがないといいますか、予備校って答えを教えるものだと思うんですけど、答えのないものを教えていただいた、国文学でもいろんな議論があることを教えていただいて。
教育学部に入りまして、大学では私は卒業論文が、在職中にお亡くなりになった、津本信博先生という先生に指導していただきまして、そこで『紫式部日記』と出会いました。先生は決して断定せず、学生の意見を非常に面白がってくださったというところがあって、日記文学への目覚めをさせていただいたと思います。それから大学院の指導は中野幸一先生にしていただきまして、中野先生は『源氏物語』や紫式部研究の権威で、大変有名な先生でいらっしゃるんですけれども、「役者は舞台で磨かれる」というのが持論で、実は修士課程の1年生の頃からもう論文を執筆する機会をいただいて、『中古文学論考』という雑誌を、先生のポケットマネーで出してくださっていたんだと思うんですけれども、そういったことで発表の機会をいただいて。実は中野先生は今もう卒寿を過ぎておられるんですけれども、今だ現役でバリバリで、昨年『深掘り!紫式部と源氏物語』という本を上梓なさるなど、第一線で今も活躍されているということで本当に頭が下がります。
そういった、いわば早稲田大学の、私にとっては非常に理想的な環境で学ばせていただいて、非常に自由に勉強させていただいたという思いが非常に強いですね。いきなり外に発表して、外の評価を受けなさいというのが中野先生の持論でしたので、ある意味早い段階で発表するとその部分、厳しいご意見をいただいたりする部分もあるんですけれども、それがやっぱり自分の糧になるといいますか、ある意味指導教員とはまた別の見方を教えてもらえるということになり、非常に有意義だったと思います。
城谷:
そういった中で先生が学生の頃から学部生、院生、で先生になられてというふうに、ずっと研究されてこられた中で、共通して持たれているリサーチクエスチョンといいますか、日々向き合っている問いというのはどういったところになりますでしょうか。
福家:
私自身は平安時代の特に日記文学、仮名日記を中心に研究しておりまして、そういった中に『紫式部日記』も入ってきますし、『更級日記』、『和泉式部日記』や『蜻蛉日記』など、いくつか有名な作品が平安時代でございますよね。日記文学は平安時代以降も書かれ続けてはいくんですけど、ただそんなに読者を得ているとは言えないと思うんですよね。鎌倉時代にも行事を中心とした日記がありますし、最近は再評価も進んでいるんですけれど、ただ平安時代の日記ほど少なくともネームバリューはないと思うんですよね。もちろん『とはずがたり』といったような作品もあるんですけれど、平安時代の作品の方が人口に膾炙していることは間違いないだろうと思うんですね。