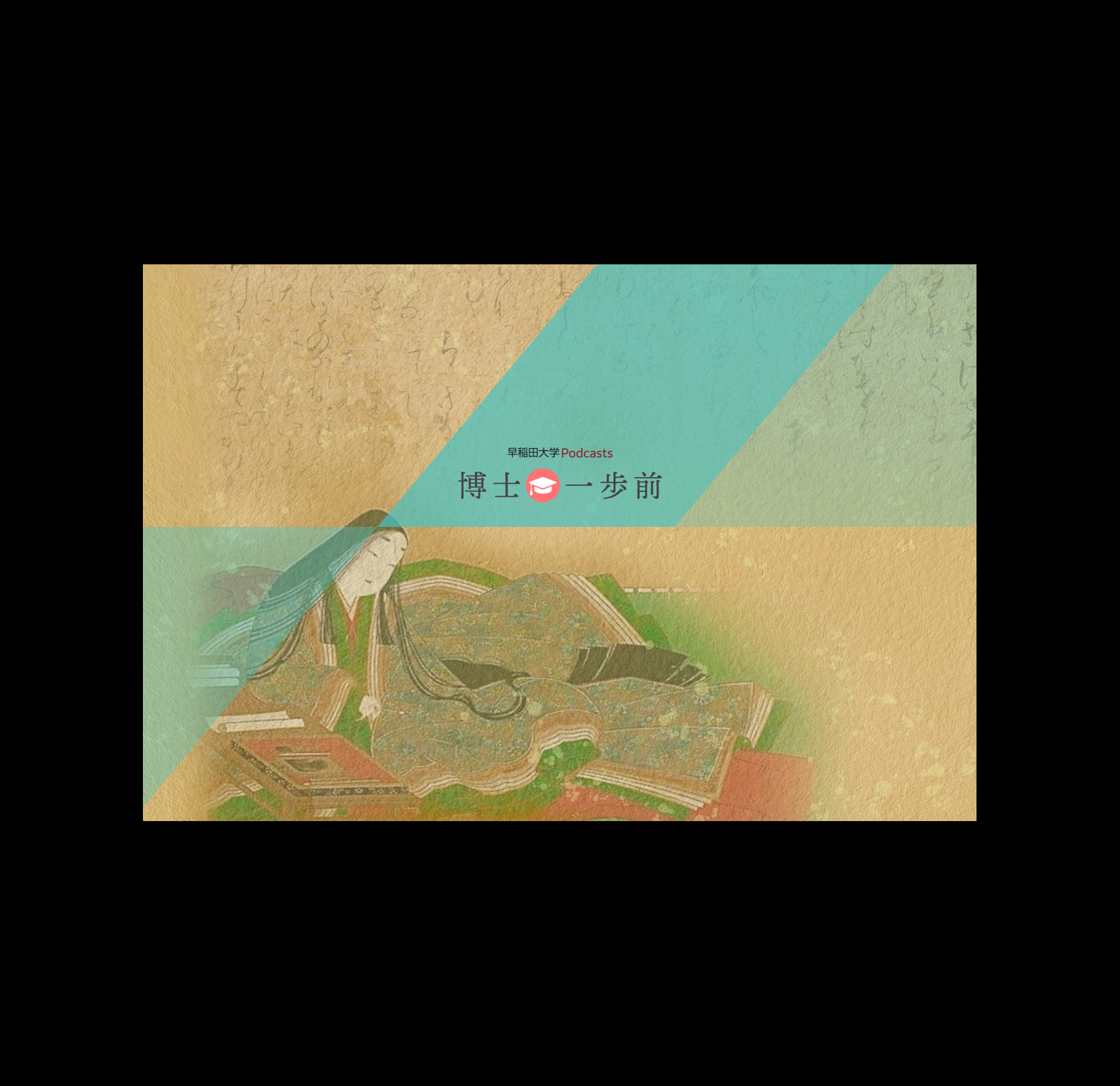- Featured Article
Vol.2 国文学(2/4)【紫式部と中宮彰子】源氏物語を支えた政治と文化が交わる宮中 / 福家俊幸教授
Tue 14 May 24
Tue 14 May 24
教育・総合科学学術院の福家俊幸教授をゲストにお迎えする国文学シリーズの第2回目では、紫式部と中宮彰子の関係性について深掘りします。
紫式部が『源氏物語』を書き続けるうえで、彰子や彼女のサロンが果たした役割は大きなものがありました。中宮彰子の存在は、紫式部の執筆活動にどのような影響を与えたのでしょうか。また、紫式部の宮中での振る舞いと内心の葛藤、そして『源氏物語』が持つ政治的・社会的意味合いについても考察します。
配信サービス一覧
ゲスト:福家 俊幸
教育・総合科学学術院教授。専門は平安時代の文学・日記文学。
1962年香川県生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。博士(文学)。早稲田大学高等学院教諭、国士舘大学助教授、早稲田大学教育学部助教授を経て現職。著書に『紫式部日記の表現世界と方法』(武蔵野書院)、『更級日記全注釈』(KADOKAWA)、共編著に『紫式部日記・集の新世界』『藤原彰子の文化圏と文学世界』『更級日記 上洛の記千年』(以上、武蔵野書院)、『紫式部日記の新研究』(新典社)、監修に『清少納言と紫式部』(小学館版・学習まんが人物館)など。

ホスト:城谷 和代

研究戦略センター准教授。専門は研究推進、地球科学・環境科学。
2006年 早稲田大学教育学部理学科地球科学専修卒業、2011年 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻博士課程修了 博士(理学)、2011年 産業技術総合研究所地質調査総合センター研究員、2015年 神戸大学学術研究推進機構学術研究推進室(URA)特命講師、2023年4 月から現職。
- 書籍情報
-
-
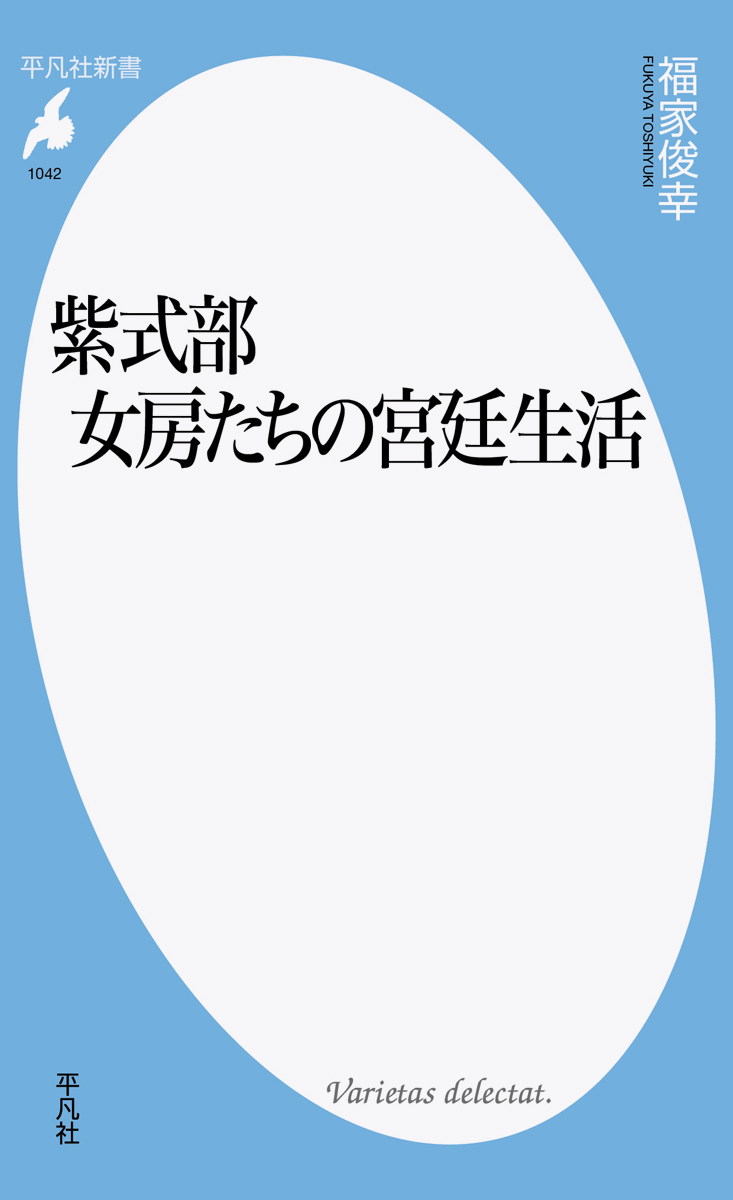
紫式部 女房たちの宮廷生活
出版社:平凡社
発売日:2023/11/15
言語:日本語
単行本:264ページ
ISBN-10:4582860427
ISBN-13:978-4-582-86042-9
-
エピソード要約
– 紫式部の宮中での立場
宮中での紫式部の立場は当初困難であり、高慢な周囲からの反感を買い、一時は宮仕えを逃げ出したこともあったが、中宮彰子の心配やサポートが彼女にとって心強かった。紫式部は中宮彰子の配下の女房として『源氏物語』を書き続けることで、彰子やその周囲の後宮文化に親しむ人々に直接作品を届けることができ、これは彼女にとっても特権的な立場を意味していた。
– 『源氏物語』が持つ政治的・社会的意味合いと紫式部の心情
紫式部の活躍によって教養豊かな一条天皇を彰子のサロンに招けば、彰子が妊娠する可能性が高まる。これは、道長が政治的権力を強化する戦略の一環だった可能性がある。
紫式部は自分が必要とされていることを認識していたが、その地位を鼻にかけることなく、日記においても謙虚な態度を保ち続けていた。彼女は教養をひけらかさないよう努力していたが、日記の中で漢籍を教えていることを隠していることや、一条天皇からの賛辞を控えめに書き記していることから、内心では自分の才能を認めていたり、それを伝えたい一面もあった。
-権力獲得の手段としてだけではない『源氏物語』
『源氏物語』の物語自体は権力獲得の手段として使われていた可能性があるが、物語の中身は光源氏の栄華だけでなく、人間の複雑な感情や道徳的ジレンマをも描き出しており、紫式部の深い人間理解と表現力が現れている。
エピソード書き起こし
城谷准教授(以降、城谷):
宮中の女房となった時に、これから『源氏物語』をさらに書いていくという喜びもあったと思うんですけど、一方でこの先生が書かれた本の中には、はじめのうちはちょっと逃げ出したと、女房を逃げ出したというところもあったと思います。そのあたり紫式部の心の持ちようですとか、気持ち的なところはどんな感じだったんですか?
福家教授(以降、福家):
これも日記の回想の中に書かれているんですけれど、彼女が宮仕えを始めた頃は、周りの人たちは、(式部が)非常に高慢ちきで人を人とも思わないで歌ばかり詠んで、物語をひたすら好んで自分たちを小馬鹿にするような人だ、というふうに思って憎んでいたと、当時はそう思っていたと。でも、今こうやって仲良くなってみると、紫式部さんって本当におっとりとしていて、本当に付き合いやすい人だわと言っていたというように彼女は書いています。裏を返せば彼女が宮仕えに出ていた頃には、そういった悪い評判といいますか、今でも中途採用の人が鳴り物入りで入ってきて、会社の社長とか幹部から蝶よ花よと言われたりすると、結構周りから反感を買うこともあるだろうと思うんですけれども、それに近いようなことが紫式部にあったのではないか。それが宮仕えに出た初めの頃すぐ彼女は実家に戻ってしまったと、中宮彰子もすごく心配してどうなってるのと手紙をくれたとかですね、そういったエピソードが歌集にも残っていますけれども、それだけ紫式部が鳴り物入りで入ってきたことに対する、ある種やっかいものが来たみたいな目があったということだと思います。
城谷:
彰子が気にかけてくれてることは紫式部にとって心強かったところはあったんですかね。彰子は本心は心の優しい人物で、そういう気持ちを出したこともあるだろうし、もう一つは『源氏物語』をずっと書いておいてほしい、そういったところは実際はどうなったんですかね。
福家:
それも確かにあるかもしれないですね。
『源氏物語』を自分のいわば所属の、自分の配下の女房が書くことは、もちろん続きを読みたい、真っ先に読めるわけですよね、ある意味。『源氏物語』を真っ先に読めるという特権的な立場にあるということになります。
これは道長が紫式部を招聘したこと、自分の娘の女房として呼んできたことにも関わるんですけれど、自分の娘のサロンで物語を書くというのは、一条天皇という天皇は大変文学好きな天皇としても知られていて、非常に教養豊かな人でもあったわけです。またこの時代の天皇は結構幼く即位する人が多く、一条天皇も幼年期に即位して、その幼い天皇の近くには母親が常に近くにいるわけですね、これが道長の姉の詮子という人にもなるんですけれど、一条天皇のお母さんですね、この詮子が絶えず一条天皇の近くにいて、詮子の周りもいっぱい女房がいて、いわば後宮文化といいますか、物語とか和歌とかに非常に親しみながら天皇も過ごしていくわけです。ですから当然『源氏物語』のような物語にも、また和歌にも非常に教養もあるし、関心も強いわけです。そういった天皇を自分のサロンに呼び寄せることは彰子が妊娠する機会が高まるわけです。
この時代は后が皇子を生んで、その皇子が即位することによって后の父親が、いわゆる外戚政治といいますけれども、権力者となって政治を動かせるという大きなシステムがありましたので、そうした権力を掴む手段としても、道長は紫式部を彰子の元に呼んでいたと、大切にしたということです。その気持ちはおそらく彰子も理解していたでしょうから、続きを見たいという部分もあるでしょうし、やっぱり紫式部にそばにいてもらって、自分のサロンを盛り上げてほしい思いもあったと思います。
城谷:
紫式部はそうすると本当に必要な人なんだなとすごく思うところですけど、彼女自身それは気づいていたんですかね?
福家:
おそらく気づいてたんですかね。
城谷:
その中でも、自分は必要な人間だからと偉ぶるわけでもなく、さっきの既にいた女房たちからも実際付き合ってみたらすごく大人しいし、ゲスゲスしてないと言っていた、と日記には書いているところで、紫式部は賢いと思うので、そういうふうに演じてたという部分はあるんですか?
福家:
彼女はこれも日記の中に書いてるんですけれども、「一」という漢字も読めないふりをしたと言っていまして、ちょっとこれはやりすぎじゃないかと思うんですが、自分の学才を表にひけらかさないように、一生懸命一生懸命努力していたと言っているんですね。実際日記の中に中宮彰子から頼まれて漢籍を、新楽府という『白氏文集(はくしぶんしゅう・はくしもんじゅう)』を書いた白居易が書いた漢詩集ですが、その新楽府を中宮彰子に頼まれて教えているけれど、実は誰にもそのことは言ってなくて、隠れてやっていると。そんな私が学才を外にひけらかすなんてことはないと。実は彼女は、悪意ある女房によって、一条天皇が『源氏物語』を読んで、実際は朗読を聞いてでしょうけれど、朗読を聞いて絶賛して「日本紀の御局」と日本書紀の講義もできるすごい学才のある人なんだと言った、ということが日記の中に紹介されているんですが、そのエピソードを日記の中に紹介するときに、私はいま中宮彰子に漢籍を教えているのも隠しているのに、そんな「日本紀の御局」なんて言われるような学才をひけらかすようなことは絶対しないだろうと、そんなことするわけがないんだと言って、書いているわけです。もちろん、書いてるわけですのでそこでもう言ってるわけですけれども、実際ひけらかさないように苦労していたわけですけれど、どこかで言っておきたかったという部分はあったんじゃないかなと思います。
城谷:
そこが私は人間味があっていいなと思って、そういう人間味というのが、『紫式部日記』もそうですし、『源氏物語』にも表れていたりするんですか。
福家:
そうですね。『源氏物語』はもちろん、ある意味言わば権力を手にするための一つの手段のように使われているところがあるわけです。特に道長はそういった目的を持っていたと考えられると。ただ、あの『源氏物語』を読んでいきますと、必ずしも『源氏物語』自体が光源氏の栄華だけを語っている物語であるかというと決してそんなことはないわけです。
藤壺との道ならぬ、密通ですね、自分の父親の桐壺の、帝の后と密通してしまうということが『源氏物語』の大きなテーマになっていて、その結果、彼は一時期、准太上天皇という、天皇に準ずるくらいにまで登り詰めるんですが、その後しっぺ返しを喰らうように、女三宮という若い妻が、柏木という貴公子と逆に密通をしてしまって、そこで薫という子供が生まれ、光源氏は自分の子供ではないことを知ってるんですね。自分の妻の密通に気づいてしまっているんですけれども、もうすでにこの時、光源氏は中年期で、もうおじいちゃん一歩手前みたいな年齢になって、その時に自分の子供でないことを知りながら、光源氏は薫という生まれてきた子供を抱くんですが、そこでひょっとしたら自分のお父さんの桐壺の帝も、かつて自分の后と光源氏が道ならぬ恋をして子供が生まれて、それは自分の子供ではないことを知っていたんじゃないかと思うんですね。ふとそう思ったりして。いわば因果往報というふうに、かつての罪が自分に戻ってきたことを痛感していくことになります。
また『源氏物語』の最後のヒロイン浮舟という人は、実はお母さんがいわゆる召人と言いますけれども、女房であるけれども愛人という立場の人で、この人と八の宮という、皇位継承権に破れた宮との間に生まれたのが浮舟で、身分的には紫式部とそんなに変わらない身分の人が最後のヒロインなんです。彼女は最後出家するんですけれど、その前に宇治川に入水を図るという有名な話なんですが、実は浮舟をめぐって争っている二人の男性、薫と匂宮という二人の男性がずっと浮舟のことを忘れきれずに、この浮舟をめぐって、浮舟は出家してそういう愛執の世界、愛と執着の世界から離れてしまっているんですが、二人の男は未だに争っていて、ひょっとしたら何か諍いが起きるんじゃないかなと。そんなところで宇治十帖、『源氏物語』の最後の巻はプツンと終わってしまうんですね。ですから、いわば男たち、身分の高い御曹司たちはいつまでもそうした愛と執着の世界から離れられずにいて、そして身分の低い浮舟はそうした世界から浄土へ救いを求めて宗教的な救済の道にも入っていくというふうに書かれているわけで、ちょっと長々と申し上げましたけれども、そうした政治の手段となるような物語とまたかけ離れた世界にまで『源氏物語』最後到達していっているわけです。
城谷:
それぞれの人物の、それぞれの生き方というところまであるということで。そうすると、福家先生は登場人物の中で誰になりたいとかそういうのありますか?
福家:
『源氏物語』の人物ですか?それはあんまり考えたことはなかったんですけれども、そうですね、よく学生を引率で京都に連れて行ったり、宇治の源氏物語ミュージアムというところに源氏物語占いというものがありまして、これイエスノーで答えていくと『源氏物語』の中のある登場人物と同じだとか、あなたは似てますよという形になるんですね。私は学生さんからちょっとやってみてなんて言われて、イエスノーで答えていって、結局夕霧という、光源氏の息子で、一時期ヒーローみたいに登場するんですが、ヒーローになりきれずに、ただひたすら真面目に、最後、官僚としては出世するんですけれども『源氏物語』の主人公にはなりきれないような人物になってしまって、ちょっとがっかりするようなところがあるんですが。