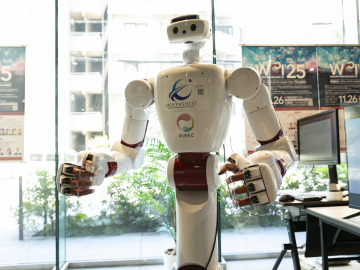特別対談 京都大学iPS細胞研究所 所長・教授 山中伸弥さん × 早稲田大学総長 田中愛治~未来の研究者に贈る言葉 Message to Future Researchers~
2019年9月、山中伸弥京都大学iPS細胞研究所 所長・教授と田中愛治早稲田大学総長が対談。再生医療と政治学の分野で世界をリードしてきた二人が、研究・教育の課題、そして展望を語ります。
心の底から楽しいと思える研究や仕事に出合ってほしい

山中 私が最初に目指していたのは、研究者ではなく整形外科の臨床医。しかし残念なことに、手術の才能がなかったのです。どのように医療の世界に貢献ができるかと悩む中、腕の良い臨床医でも治せない病気やケガを目の当たりにし、研究医を志すようになりました。臨床医は目の前の一人一人の患者に貢献できますが、研究医は10〜20年先に成果が生まれるかどうかです。しかし、その成果が患者の役に立てば、一気に何千人、何万人に貢献できるわけです。
田中 研究のそこに面白さや魅力があるということですね。
山中 魅力的だと感じたのは、臨床医が働いている病院の中で競い合うのに対して、研究医は世界を相手にすることです。また、臨床医は研修中に上の人に従うように指示されますが、研究医は好きなことをやれと勧められます。このように180度違っていて、私には研究医が向いていたようです。
田中 最初は研究者を目指していなかったという点では、私も同じですね。早稲田で学ぶ中で政治学に興味を持ったきっかけは、国民が政治をどのように見ているのかということへの関心でした。そのことを知るには世論調査の手法を学ぶ必要があり、アメリカに留学しました。そして大学院時代に、ある研究で私の仮説通りの調査結果が出たんです。興奮して徹夜で論文を書いたことを覚えています。誰も考えていない仮説を立て、それを検証する楽しさを知り、そんな仕事にしたいと思ったのが、研究者としてのスタートですね。
山中 寝食を忘れて研究に没頭するのは楽しいことです。心の底からやりたいと思えるものに出合え、仕事にできるのはやはり幸せですね。
田中 ですから私は学生には、自分が楽しいと思う研究や仕事を追求してほしいと言っています。
セオリーや理論にとらわれず新たな挑戦を

山中 ただ、近年の日本では短期間で成果を求める風潮があり、その点が心配です。
田中 研究の評価が定まるまでには30〜40年と時間がかかるのが普通です。それはノーベル賞の受賞者を見るとよく分かります。短期間で評価されるような研究はなかなか生まれません。山中先生は例外で、若くして評価された稀代の天才です。
山中 iPS細胞も、ノーベル賞を一緒に受賞したケンブリッジ大学のジョン・ガードン先生が1962年に行った細胞の初期化の実験から計算すると、実は50年以上になります。研究は失敗の積み重ねであり、失敗の数が多いほど、すごい成果が生まれます。若い研究者には、失敗を恐れずチャレンジしてほしいし、チャレンジできる環境を用意するのが、私の仕事の一つだと考えています。
田中 もっとおおらかに研究を見守る心構えが重要ですね。大隈重信も学生に向かって、「諸君は必ず失敗する」と言っていて、失敗を糧にする必要を説いています。
山中 あのイチロー選手ですら、生涯打率では約3割しかヒットを打てなかったわけです。研究の成功率はもっと低く、1割に届くかどうかですよ。
田中 イチロー選手の話が出ましたが、スポーツといえば、私は中高と陸上部で、大学は空手部でした。スポーツではあきらめずに粘り強く取り組むことが大切で、それは研究でも同じであるため、私は「たくましい知性」という言葉をよく使います。
山中 私も学生時代は柔道、ラグビー、最近ではマラソンに打ち込んできましたが、スポーツも研究も失敗が多いことは共通しています。大切なのは失敗から学ぶことができるかどうか。失敗した研究のデータをまとめ、原因を解析する中で、発見があったりします。同様にスポーツからも失敗を生かすことを学びました。失敗を楽しむことを後輩たちに伝えたいと思います。
田中 どの競技も、戦う相手や状況は毎回異なります。その中で勝つには、仮説を立てることと、検証すること、そしてあきらめないことが重要ということですね。
山中 そうです。スポーツにはセオリーがあり、研究には理論があります。つまり過去から学ぶことが大切です。しかし、必ずセオリーや理論通りにする必要があるかというと、それはちょっと違う。理論通りだと大きな失敗はないかもしれませんが、ブレークスルーも生まれません。
田中 基礎ができていなかったり、ただの無鉄砲なトライだったりというのは論外ですが、新しい道に挑戦することは大切ですね。
山中 前回2015年のラグビーのW杯イングランド大会で、日本は南アフリカに逆転勝ちしました。あの瞬間、残り時間がわずかな状況で負けていた日本にとって、ペナルティキックで同点を狙うのがセオリーだったと思います。しかし、選手たちは逆転するためにスクラムを選択したわけです。私も年を取って、安全な道を選ぶようにと、どうしても言いたくなります。若い人に失敗してほしくないからですが、それではそこそこの成功しか得られません。先生の言うことを無視してでも、挑戦することが許される環境づくりが必要です。
田中 従来の理論や慣習といったものから抜け出して、チャレンジするのを促すのが教育であり、若い人を後押しする社会であってほしいと思います。
現在の大学に共通する課題とは

山中 私が大学院生だったのは、平成元年から5年ころにかけてで、当時の研究生活には難しい課題にじっくり取り組めるという利点がありました。しかし現在は、競争原理の影響か、時間をかけて研究することが困難になっています。研究費も高額になっていて、私の時代は医学の基礎研究で年間100万円から200万円でしたが、今は基礎研究であっても年間1,000万円が必要です。こうした課題は全国の大学に共通するものでしょう。
田中 競争原理はもちろん大事ですが、アカデミックで意義のある研究をしている人を盛り立てることも、自然科学系、人文社会系を問わず大切です。中でも基礎研究は、丁寧に支えていくことが求められます。よく知られているように、日本のGDP比の教育予算の割合はOECD諸国の中で最低ですからね。
山中 大学の使命は、何もないところに水を撒くことなんです。研究において、どこに水を撒くと芽が出るかは、やってみないとわかりません。これを企業が担うというのはなかなか難しいと思います。たとえ芽が出なくても、使命を果たすという点では大学にはできるわけです。短期間や局所的に見ると芽が出ないかもしれませんが、10年や20年という長い視点で見れば必ず芽が出ます。
田中 私たちも人材育成に関しては、すぐに結論を求めるのではなく、長期的な視点で芽を育てていくことが必要と考えています。
山中 そして芽が出たら、水や肥料を与えて大きく育て、最後は企業に渡します。ただし、どの段階で企業に渡すかということにセオリーはありません。iPS細胞は、偶然にも私たちの畑で芽が出たので、企業に任せるまでは、きちんと育てる必要があります。この10年で大きく発展しているなか、どこで企業に渡すかを考えてきましたが、私たちの判断ではまだ企業に渡す時期ではない。最も早く、明確な結果が生まれるタイミングが適切だと考えています。最初は好奇心で始めた研究も、芽が出ると責任も生まれます。そして芽を育てると同時に、新しい芽を探すことも考えたいですね。
田中 早稲田大学も、工学系などでは産学連携を推進する後押しを積極的に行っています。一方、人文社会系では、論理的な文章をつくる力、論理的な英語文章作成力、データでエビデンスを示す方法など、研究でも、実社会に出ても、必須となるアカデミック・リテラシーを身に着ける教育を学生に提供しています。そうした礎があってこそ、優れた研究も生まれると考えています。
——-

やまなか・しんや/1987年神戸大学医学部卒業。93年に大阪市立大学大学院医学研究科修了、医学博士。米国グラッドストーン研究所博士研究員、奈良先端科学技術大学院大学教授、京都大学再生医科学研究所教授などを経て2010年より現職。06年、人工多能性幹(iPS)細胞を発表し、12年ノーベル生理学・医学賞受賞。(写真右)
たなか・あいじ/1975年早稲田大学政治経済学部卒業。85年オハイオ州立大学大学院修了、政治学博士(Ph.D.)。東洋英和女学院大学、青山学院大学、本学政治経済学術院教授などを経て2018年より現職。06年から本学の教務部長、理事、および世界政治学会(IPSA)会長などを歴任。(写真左)
—–
対談の様子は以下の動画でも視聴いただけます。