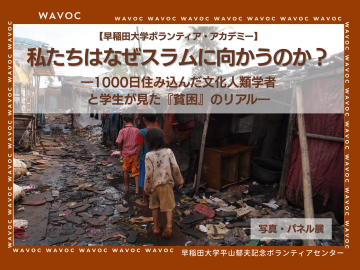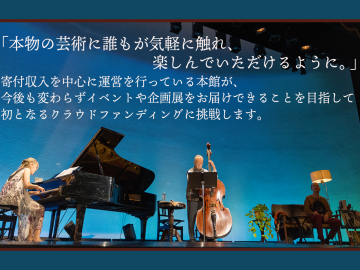早稲田小劇場どらま館が竣工
5月7日 平田オリザ氏公演でこけら落し
早稲田キャンパス近くの南門通りに建設中であった「早稲田小劇場どらま館」が3月23日、竣工しました。本学には本格的な劇場設計・運営・管理のノウハウはありませんでしたが、幸いなことに設計段階からかつてのどらま館を利用し今や演劇の第一線で活躍する多くの舞台スタッフにご意見・ご協力をいただくことができ、この度の竣工にこぎつけることができました。今後、グランドオープン(4月30日)に向け検証を兼ねたプレオープン公演等を経て、5月7日(木)のこけら落とし公演を平田オリザ氏に託します。

客席はわずか72席と小さな劇場であり、スペースは限られているものの、各フロアのレイアウトや、舞台、客席、楽屋、受付まわり、ブース部分等、ほぼ全てについて、舞台関係者の方々と細かく議論し、国内外で評価の高い劇場との詳細な比較分析を重ねてきました。安全面など細部まで使用する学生への配慮がなされており、舞台床面に最適な厚さに調整された2枚の板を使用することで、舞台の仕込みがしやすく、床材の交換も容易にできるようにしたほか、舞台から天井までの高さを4メートルとし、小劇場としては十分な空間を確保しました。場内の誘導・機材の運搬もしやすく設計されており、「大学の劇場とは思えない完成度の高さ」という舞台関係者の感想も耳にすることができました。

正面外観は、舞台の緞帳(どんちょう)をイメージし、職人が板を1枚1枚手作業でひねりを加え制作しました。カラーは黒一色であくまでも建物は「黒子」の役回り。学生の力でそれぞれの公演を色付けていくよう願いが込められています。

通常のキャンパス内の教育設備と大きく異なる点は、劇場で学生たちが料金をとって経済活動を行うことです。自分たちで演劇を創造し、社会に問うた結果である公演収入を蓄積していくことは正規の授業では得られない経験となり、学生たちのモチベーションを高め、主体性・実行力を養っていくうえで、計り知れない効果が期待できます。学生は劇場使用料が無料であり、さらに教員や一線で活躍する校友、そして一流の演劇人のサポートが加わる大学の劇場であるからこそ可能な、壮大な教育プロジェクトになっていくと考えられます。
竣工式には多くの大学関係者・建築関係者が訪れ、学生時代、自らも演劇活動に励んでいたという鎌田薫総長は「学生の成長、街の活性化につながる。早稲田だけでなく、東京、そして日本の演劇の中心になってほしい」と期待を込めました。
5月7日-10日の3日間には平田オリザ氏によるこけら落とし公演「アンドロイド版 変身」が開催されます。
【建物概要】
名称:早稲田小劇場どらま館
住所:新宿区戸塚町1-101
構造:鉄骨4階建て、敷地面積約122㎡、延べ床面積約210㎡、観客席72席
その他:事務所、売店、エレベータ、トイレ、バリアフリー
使用資格:学生演劇サークルなど
設計・監理/ 施工:株式会社竹中工務店
【今後の主なスケジュール】
4月8日(水)~27日(月) 3劇団による3つのプレオープン公演・
4月23日(木) 平田オリザ氏×鎌田薫総長 開館記念トーク
4月29日(水・祝) プレオープン公演3劇団によるスペシャルイベント
4月30日(木) グランドオープン
5月7日(木)~10日(日) こけら落とし公演 「変身」アンドロイド版(作・演出:平田オリザ)
※イベント詳細:http://www.dramakanfes.link/
【どらま館について】
かつて、早稲田キャンパスに沿った南門通りには、世界的に活躍されている演出家・鈴木忠志氏(1966年・政治経済学部卒)らが創設した劇団「早稲田小劇場」と同名の小劇場がありました。「早稲田小劇場」は1960年代の小劇場運動の中心的な劇場として数々の名作を世に送り出し、1976年に鈴木氏が活動拠点を富山県利賀村(現・南砺市)に移されたあとは、「早稲田銅鑼魔館」という民間の貸劇場として運営されてきました。同施設はその後本学の所有となり、2012年10月に解体されるまで、演劇サークルの活動拠点として利用され、多くの演劇人を輩出してきました。早大学生演劇の拠点を求める声は多く、「Waseda Vision 150 Student Competition」では、学生からのも劇場再建の提案をありました。鈴木氏承諾のもと、このたび「早稲田小劇場」の名称を冠した「早稲田小劇場どらま館」(72席)を再建する運びとなりました。