- Featured Article
Vol.4 教育心理学(2/2)【セルフトークで助ける怒りの表現】生徒・児童の自己理解を支援する教育心理学の役割 / 本田恵子教授
Thu 04 Jul 24
Thu 04 Jul 24
早稲田大学教育・総合科学学術院の本田恵子教授をゲストに迎え、「アンガーマネジメント研究」をテーマにお届けする、教育心理学シリーズ。
後編のエピソードでは、怒りのメカニズムを理解し、自分の中の怒りを正しく表現するためのプロセスとして、怒りの方向、質、量を理解し、自己対話を通じての解決策を見つけるセルフトークについてのお話をお届けします。
「子どもの元気なところをより活かし、苦手な病んでいるところを包み込んでいく」
アメリカ留学で学んだダイナミックアセスメントとガイダンスカウンセリングを、どのように日本の教育現場へ導入してきたのかを伺いながら、教育環境において教育心理学が果たす役割の重要性について深掘りします。
配信サービス一覧
ゲスト:本田 恵子
早稲田大学教育・総合科学学術院教授。アンガーマネージメント研究会代表。公認心理師・臨床心理士・学校心理士・特別教育支援士SV。中学・高校の教師を経験したあと、カウンセリングの必要性を感じて渡米。特別支援教育、危機介入法などを学び、カウンセリング心理学博士号取得。帰国後は、スクールカウンセラー、玉川大学人間学科助教授等を経て現職。学校、家庭、地域と連携しながら、児童・生徒を包括的に支援する包括的スクールカウンセリングを広めている。

ホスト:城谷 和代

研究戦略センター准教授。専門は研究推進、地球科学・環境科学。 2006年早稲田大学教育学部理学科地球科学専修卒業、2011年東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻博士課程修了博士(理学)、2011年産業技術総合研究所地質調査総合センター研究員、2015年神戸大学学術研究推進機構学術研究推進室(URA)特命講師、2023年4 月から現職。
- 書籍情報
-
-
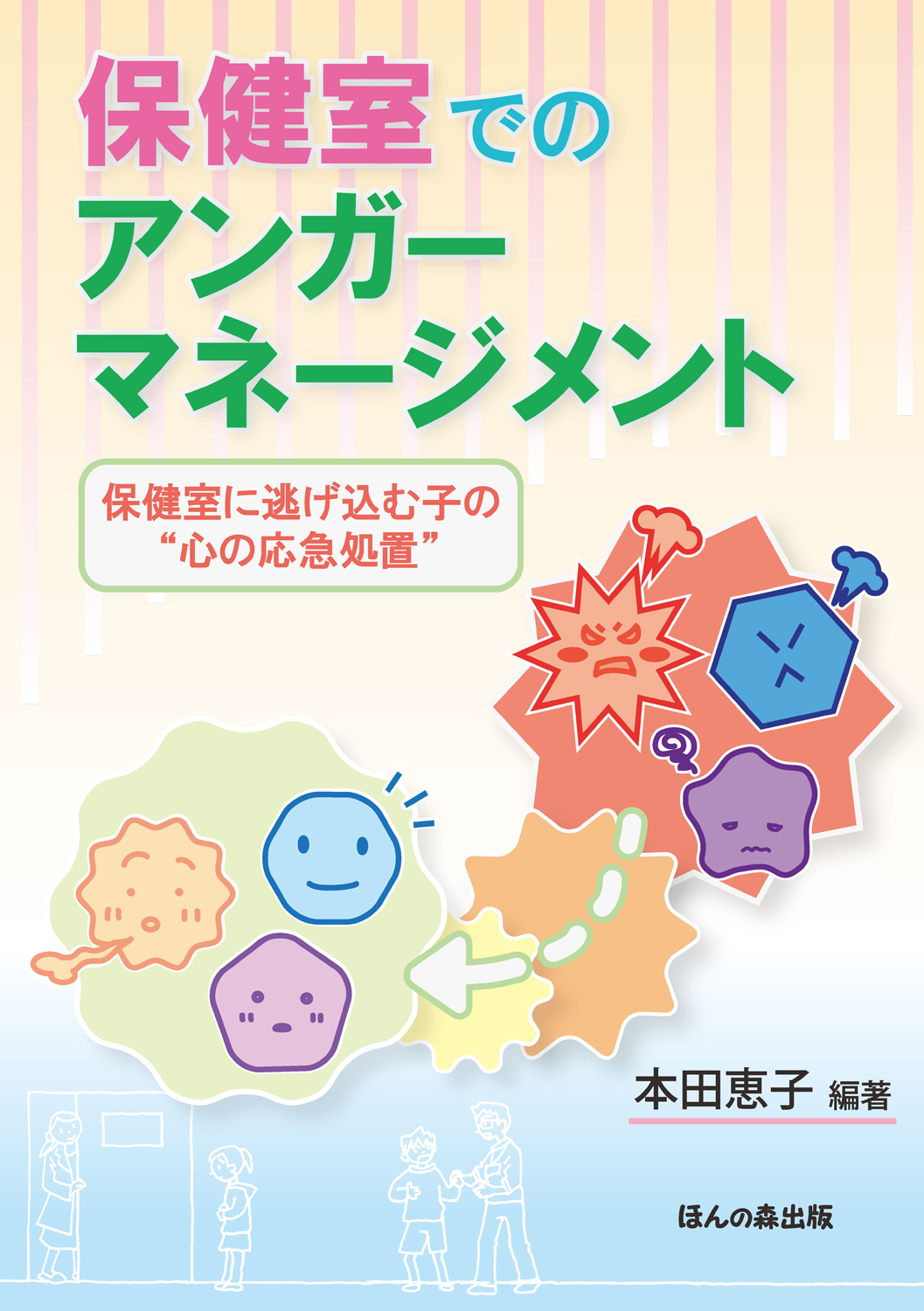
保健室でのアンガーマネージメント 保健室に逃げ込む子の“心の応急処置”
出版社 : ほんの森出版
著 者:本田恵子
発売日 : 2022/1/31
言語 : 日本語
単行本 : 112ページ
ISBN-10 : 4866141247
ISBN-13 : 978-4866141244 -

「8つの知能」をいかすインクルーシブ教育 MI理論で変わる教室
出版社 : 学事出版
著 者:本田恵子
発売日 : 2024/5/22
言語 : 日本語
単行本(ソフトカバー): 140ページ
ISBN-10 : 4761930047
ISBN-13 : 978-4761930042
-
エピソード要約
-セルフトークとは
セルフトークは、自分の中の怒りを正しく表現するためのプロセスで、怒りの方向、質、量を理解し、自己対話を通じて解決策を見つけることを目指す。またセルフトークには感情に働きかける言葉、認知に働きかける言葉、問題解決に向けた言葉があり、それらを用いて自分の感情や欲求を可視化し、解消していくことを目的としている。
-本田教授がカウンセリングを学ぶことになったきっかけ
本田教授は中学高校の教師を経て、教育心理学の研究者となったが、教員時代に教育実習校の荒れた状況に直面し、日本の子供たちを支える必要性を感じた。そのため、本田教授はコロンビア大学での実践的なカウンセリングやストレスマネジメント、グループ・ダイナミクスなどを学び、その経験を日本に持ち帰り、導入しようとした。
-本田教授が教育環境について思うこと
本田教授は、生徒の個性に応じた学び方を推奨し、学びやすい教室設計が重要であると考えており、冷房や環境音が学習に影響を与えることがあるため、自然に近い環境での学習環境の改善が必要だと考えている。また新しい学校の形として、子どもがほっとできるような学校環境を目指し、環境改善が子どものストレス軽減に役立つと述べている。
エピソード書き起こし
城谷准教授(以下、城谷):
はじめに私ごととしてお伺いしたいことがあります。怒ってしまうと後悔することがあり、
できるだけその後悔をしたくありません。自分自身に向き合って、それを防げるなら防ぎたいと思うのですが、どうしたらいいのかなと思うこともあります。前編のお話の中で、少しセルフトークについて触れていただいたかと思いますが、セルフトークについてお聞かせいただけますでしょうか。
本田教授(以降、本田):
セルフトークは簡単に言うと、自分の中で怒り玉が出ます。それが体に色々なオイタをしているわけです。心臓をバクバクさせたりとか、行動化させたくなったりとか。何も出してあげないと身体化するので、お腹が痛くなる、頭が痛くなる。だんだんに激しくなると鬱になることになるので、上手にこのアンガーに「あなた何したいのよ」、「誰に怒ってるの?」と語りかける。怒りの方向と質と量ですよね。この3つを分かってあげると「誰に出したいの?」、「どのぐらい怒ってるの?」、「それをどう解決すればいいの?」と自分と対話しながら、この人をちゃんと正しく出してあげる。そのためのプロセスです。怒ってOKです。ただ「正しく怒ろうね」、「落ち込まないように正しく怒ってすっきりしようね」ということ。
城谷:
例えば、日常でそれをする簡単な実践方法はありますか?
本田:
言葉が働くようにする必要があるので、まずは第一ステップとして、ガーって怒ってる、あるいは不安になって固まっている状態を、ストレスマネジメントでほぐすのは必ず必要です。少し呼吸が整ってきたり、体がリラックスしてきたら、そこで言葉が出る。書いた方がいい人は書いていきます。自分の中で一連の流れを整理するシートもありますが、使うのがアンガーチャートというものとその一連の流れで整理するのと2つあります。一連の流れの方が分かりやすいのは、何が起こったということを相手のセリフと自分の行動と順番にやっていきます。こういうことがあって自分はこうした、そうしたら相手がこう言った、自分はこうやった、その結果相手がこうなって、最終的にこうなってしまったみたいな。その一連の流れで言うと、その途中で言葉にしていない自分の気持ちとか、本当は伝えたかった欲求とか、そういうものがあります。それをちゃんと書いてあげます。そうすると見える化するじゃないですか。「そうだよねこの時こういうこと言いたかったよね」と気持ちを受け止めてあげて、「我慢しちゃったねこの時」、「なんで我慢しちゃったんだろうね」と自分で話し合いをしながら、セルフトークの言葉集というのもあるのですが、「頑張ったね」と言って、自分にかけてあげる。感情にかけてあげる言葉もあれば、認知に働きかける言葉というのもあって、「なんでそんなふうに思ったの」とか。あと問題解決に働きかける言葉で、「できることをすればいいんだよ」、「大丈夫だよ、明日は周りに誰か助けてくれる人がいるよ」とか。そういう見通しを立てる、解決策に行く、セルフトークの中にも感情にかける、考え方にかける、問題解決の行動にかける言葉など。そういうのをうまく使いながら自分のアンガーと語り合います。手の平に自分のアンガーを乗せながら、「あなた、何に怒ってんの」、「悔しかったよね」と受け止めて、「本当は何が言いたかったの?」、「こういうことだよね」、「なんで我慢しちゃったの?」、「なんでそこでキレちゃったの?」、「だってこうだったんだもん」、「じゃあ、次は言葉で相手を責める前にちょっとタイムアウト取るといいかな」とか。そういうところをやり取りして、自分の気持ちを解消してあげる。セルフトークはそんなことができる言葉です。
城谷:
お聞きしてると、難しいことではないことが分かり、実践しやすいかなと思いました。いい意味で慣れていくことかと思うので、ちょっと心がけていきたいと思いました。
ここからは本田先生の研究者人生にフォーカスを当てて、お話をお聞きしていきたいと思います。本田先生は中学高校の教師をされた後、研究者としてのキャリアを歩まれていますが、どのような転機があって研究者を志すことになったのでしょうか。
本田:
私は大学4年を出た時に中高の教員になったのですが、その当時、教育実習校も大荒れでした。非行、不登校とか。本当は開発教育をやりたくて。私のスーパーバイザーがユネスコの方だったので、アフリカに行く予定でした。アフリカで教育系の開発教育をやろうと教育実習に行ったら、とんでもない、日本の方が大変じゃないかと。日本の子どもたちをなんとかしないと、今後大変だぞということで、日本に残って教員をする。80年代、学校大荒れみたいなところの中で、とにかくありとあらゆる場面に出会いました。自分一人でやれと。その当時の教職課程、カウンセリングのカの字もありませんでした。カウンセラーも現場にでない。教育心理で何をやったかというと、喃語のバパパパブブブブくらいしか教えてもらってなくて。
城谷:
(喃語のバパパパブブブブとは)どういうことですか。
本田:
発達心理学という授業があって、その中で喃語という赤ちゃんが初めて喋る言葉です。それ一個しか習わなかったんですよ。学校現場に行って、子どもたちとどう対応するのか、全くわからない。現場の先生たちもベテランがいっぱいいますが、「こんなもん経験だよ」と。40代、50代、そこまで待っていられないので、色々体当たりでやりました。勉強嫌いだったら、いろいろ体験学習しようとか、キレてる子たちがいたら、授業の前に一緒になんだかんだ言いながら、ストレスマネジメントとかやっていましたが、無理だなと。なにか理論とかよりどころがなかったら、もうこのままだとやっていけないなと。
城谷:
経験と理論。
本田:
そうですね。それで思い切って「ゼロから学び直します」と言って、どうせ行くなら、一番荒れているところでと。そういう性格なので、アメリカであちこち、カウンセリングのロジャースさんのところとかも回りましたが、これはニューヨークのハーレムだなと。ハーレムの中に住んで、それこそボランティアとかもしながら、虐待の対応とかを一緒にしながら学ぶことができたのがコロンビア大学でした。
そこで最初は修士だけで終わろうと思っていました。しかし、「日本に帰ってどうしたいの」と言われたので、「日本にカウンセリングがないから、それを学校現場に入れたい」と答えると、「だったらドクターまで取らなきゃ無理でしょ」、「人を指導できる状態まで全部学んでこい」と言われて。修士とドクターで120単位ぐらい取りました。もう全部やれと。コンサルテーションから企業に行って、スーパーバイズの仕方、危機介入、もう全部行けと。その一環で、刑務所にも行ってらっしゃい、少年院にも行ってらっしゃい、産業のところで荒れている人たちのストレスマネジメントもできるようになってらっしゃい、あの工場のラインの組み立て直しもしてきなさい。それを3ヶ月でやってこいと。それができると、荒れている学校に入って、その学校が何に悩んでいるかが分かって、学校と一緒にプログラムを組んで、変えられる。授業なのか、ソーシャルスキルなのか、教員集団なのか。それでもありがたかったです。アメリカの先生たちはアメリカに残ると言ったら、自分のライバルになるから教えてくれません。しかし日本に帰りたいんだと言ったら、これも持っていけ、あれも持っていけ、あれもこれも広めて来いと。次々にちょっとおいでと研究室に呼んでくれて、こういうことをやるけど実践しないか、みたいな。そういう意味ではすごく恵まれていました。
城谷:
密度の濃い。
本田:
その分、色々やってもいいけど、日本に合うようにしないと横文字を縦文字にしたらダメだよということで帰ってきて。ちょうど90年代、95年のいじめのところから始まったので、学んだことを現場に合わせながら、自分なりに組んでいくところではありました。
城谷:
コロンビア大学時代、周りのクラスメイトはアメリカの方が多かったんですか。それとも先生のように海外から留学されている方は結構いらっしゃったのでしょうか。
本田:
アジアから結構来てました。韓国、中国、タイ。カウンセリングがないから学びたいということで、最前列に座って。英語がわからないので、「スペリング」とか書いてもらわないと聞いても辞書も調べられない。そこはすごく先生たちは丁寧で、「分からなかったらどんどん聞きなさい」と言って、やっていただけました。向こうの大学院は、(学生は)仕事を持ってきています。だから夜が多い。昼間は学部の授業や実践に行ったりしながら、夜、みんなで学ぶので、現場の内容をガンガンできて、非常に実践的な内容。精神分析もやりましたし、カウンセリングとか、グループ・ダイナミクスとかも学ばせていただいていたので、大人の方たちと現場の理論と一緒に合わせてできたところは良かったです。
城谷:
教師陣とクラスメイトからたくさんの刺激を受けたと思います。その期間に先生が一番刺激を受けたこと、これは日本に持ち帰ろうと思ったことはありましたか。
本田:
やっぱりアメリカの制度が、非常に包括的なんですよ。私はガイダンスカウンセリングということで学校現場にもインターンで入ってやっていきますが、例えば、不登校、学校に来ないとなると、もうスクールサイコロジストというのが行って。日本だったら教育相談室とかに説得して行かせないといけませんが、カバンを持ってきて、なぜ不登校になるのかをアセスメントします。そういうところで不登校の原因は、「じゃあ、この人は学習だね」、「いや、発達障害じゃない」、「家の問題とか身体的なものだよね」というのをアセスメントして。この仕方はすごいなと思って。ただデータを集めるだけではなく、ダイナミック・アセスメントというやり方があって、その人と関わりながら、どうやったらこの人のいい行動が出るか、学びが出るかを見せていきます。先生がアセスメントしながら。このやり方はしっかりと学校現場に持ち帰りたいなと。要するに「あなたダメよ」、「スクリーニングで特別支援よ」というためのアセスメントではなくて、どうやったら、このいいところを活用できるかというのがあったので。いわゆるガイダンスカウンセリングというのは臨床モデルではなくて、健康モデルなんです。子どもの元気なところをより活かしていって、苦手なところを包み込んでいくみたいな。このやり方はぜひ持っていきたいなというのと、包括的にアセスメントをする方法はぜひ持ち帰りたいなと思いました。
城谷:
その考え方とそれに対するたくさんの研究実績がアメリカでは蓄積されていたということで、先生もその刺激を受けて、日本でさらにご活躍されていると。
本田:
本当に最先端を先生方がこれでもかと出してくださったので、学び甲斐はありましたね。
城谷:
次に本田先生の研究活動におけるこだわりについてお伺いしたいと思います。
そもそも児童・生徒の感情という研究対象がとても繊細で変化も著しく、ときに研究活動以上に生徒・児童の心に寄り添う必要がある分野だと思います。その一方で、研究活動のゴールもあって研究機関という制約もあるかと思います。これまでの先生のご研究の中で、乗り越えられてきた苦労や心がけ、リサーチクエスチョンについて教えていただけますでしょうか。
本田:
一番心がけているのは、とにかく現場の役に立つことをすることです。
城谷:
それは先生が日本で高校・中学の先生になった時、またアメリカに留学された時、そしてこちらに戻られてきた時、ずっと一貫してお持ちになられてた。
本田:
そうですね。東日本大震災とか、そういうところでもすぐ駆けつけていろいろやるとなると、今度は先生方が病んでしまう。違う意味でのアンガーなんですよね。そういう危機介入の場面でいうと、新しい場面で何が必要だろうということを、データ収集をその場でしながらインタビューして、こういうことだなと思ったら、それに対応できるようなものをプロジェクトとしてやっていくので。割と早稲田と県レベルでの連携事業を向こう側も仕込んできて、自分たちでは難しいが、大学の研究としてやってもらいたいからと言って、それを3年計画でやっていくところはすごくあります。だから手探りが多いです。一番前のところをやりながら、これなんだろうと。理論がないところを実践しながらそこで理論を作っていって、「きっとこうなんだよねー」とプログラムを作って、効果検証していくところなので、とてもやりがいはありますが、先駆者がいない分、常に不安ですね。本当にこれでいいのか、みたいな。論文で学会誌とかに出しても、「根拠は?」と言われたら、「私がやってます」みたいなことなので。そうすると「却下」になりますから、理論化していくところで、これからそれこそ博士の方たちにがんばって理論化を手伝っていただけるとありがたいなと思います。
城谷:
先生の研究は実践、現場というところが非常に特徴だと思います。
今後、児童・生徒のアンガーマネジメント研究をしていく中で、異分野との連携や展望についてお聞かせいただきたいと思います。例えばアンガーマネジメント、既に出てきていますが、アンガーの状態の予防というところもあるかと思います。特に子どもの特性を理解するなど、そういったところでの異分野連携、展望について、お聞かせいただければと思います。
本田:
特性、見立てになりますが、ここが実は一番難しいです。先生方は心理の専門ではないので、現場で対応しないといけない先生方がある程度、パターンが類型化できるようになると、限られますが、AIの活用とかができるようになったらだいぶ楽かなと。例えばデータベースを組んでいきながら、イントラネットで全部やらないといけないと思いますが、キーワード検索ができたりすると、こういう場面の時にはこのようなことが起こりそうで、最低でもこんなことを押さえておくといいんだな、みたいなことが先生の中でソーティングできるような。それが永遠のプロジェクトの中でできたらいいなと。もう一つは、子ども自身が自分と対話できる、子どもがキレた後に、ちょっと落ち着くまでは時間かかりますが、その後、「どうなの」という対話をコンピューターとしながら、「何があったの」と優しい声で。それこそ本人の好きなアニメーションとかで、キャラが出てきて、「大変だったね」とか言って、「何があったの」とか聞いてくれて、「こんなことやったんだよ」とか言葉で言ったら、それが出てきてみたいな。そんなやり取りをしながら、「どうする」、「次の授業こうする」みたいなものを長くても15分ぐらいでクーリングダウンできるようなシステムのプログラム開発ができるといいなと思います。あと一個は教室環境論です。
城谷:
そこもお聞きしたいと思います。
本田:
今の学校は何十年前の学校と同じような教室環境じゃないですか。スクール形式でみんなが並んでいて、ドアが閉まっていてみたいになると、やっぱり学びにくいです。自分の個性に合わせた学び方ができるような。ゴールは一緒だけど少し動き回ってもいい、話し合った方がストレスを発散できる、あるいは一人の方がいいとか。学びやすい教室の設計、キレない教室というのができるといいかなと。天井の高さも低いし、隣のクラスの音は聞こえてくるし。聴覚過敏の子たちだったら音楽が入ってくるとすごい気になります。
城谷:
冷房が入ったのは良かったと思いました。昔、暑い中でやっていたので。
本田:
冷房はだいぶ入るようになりましたが、冷房自身もあの音が気になってしまう子がいる。風の当たり方というのもあるので、自然に近い状況。あまり冷房暖房をやりすぎると、今度は自律神経にダメなんです。キレやすい子がとても多いです。
城谷:
そういうこともあるんですね。
本田:
エレベーターの世界ですから。動いてない、床掃除とかしてないから、体動かしてない、肩がガチガチ凝るということなので。自然に近い環境、木でできているとか、床下のところで空気が通っていて、自然な音が出てくるとか。学校の中で子どもがほっとするような、そういうキレにくい教室環境や学校環境論とか、そういうところと一緒に何かできることがないかなと。新しい学校の形を作っていっていただけるところがあったら、子どもたちが喜んでくるだろうなと思います。
城谷:
最後に、アンガーマネジメント研究や教育心理学という分野を志す、将来の研究者の皆さんへメッセージをいただけますでしょうか。
本田:
教育心理は文字通り、人を育てる心理学です。ですので、健康モデルとして人間そのものをしっかり理解していただいた上で、感情・心の部分、思考・考え方の部分、それから行動というソーシャルスキル。この部分を自分で理解した上で自己調整の学習ができるマネジメント。自分をありのままの自分としてどう自己実現していけるか。そういうところをターゲットにした研究や教え方を研究したいという方がたくさん増えてくださるといいなと思っています。
城谷:
ありがとうございました。
本田先生とお届けしてきた早稲田大学ポッドキャスト博士一歩前。後編のエピソードもエンディングの時間となりました。
最後に先生はアンガーマネジメント研究の他にも、インクルーシブ教育のご研究もされていらっしゃいます。近日2024年5月に『「8つの知能」をいかすインクルーシブ教育』という書籍を学事出版から出版されました。ぜひ本田先生に本のご紹介をいただけますでしょうか。
本田:
この8つの知能というのはMI理論と呼ばれていて、マルティプルインテリジェンスの略なんです。ハーバード大学のハワード・ガードナー教授が開発された理論で、子どもの右脳と左脳、脳のバランスを8つに分けていって、一番本人が得意、好きなやり方を使って学んでいく。当然、苦手なところもありますが、得意な分野で苦手なところもカバーしていくという理論なんです。例えば左脳の場合だと、言語、論理性、自分のことを内省する力、博物学といろいろ整理整頓していく、情報収集する。右脳の場合は、目で見るという視覚の知能、体を動かす運動知能、人と対話する対人知能、あとは感情を理解したり、音楽と抑揚という8つがあるので、この組み合わせを使いながら、本人たちが好きで得意なところを使って、例えば国語を学んでいこう。国語を学んでいくにあたって、心情理解は言語だけだと難しいじゃないですか。そうなると、もう読んでいて、「あーつまんない」、「わかんない」となるのを、「じゃあこのセリフ言ってみようか」と対人が好きな子だったらロールプレイしてみるとか。視覚が好きな子だったら、「この子のこの気持ちを色にするとしたら何色」とか、整理整頓とかが得意な子だったら、「気持ちの動きを言葉で表にしてごらん」とか、数字が好きだったら、「グラフにするとしたら、どんなグラフが書ける」とか。どれも心情理解としては表現でOKなんですよ。しかしそれを言葉だけでやってしまうと、言葉ができる子、言葉が書ける子以外は点数が取れないです。分かっているのに表現できないことで成績につながらない。こういう子たちが実はアンガーになっています。キレている子たちをよくよく見るともう八割方勉強みたいなところだったりする。やっぱり自分の脳のバランスに合わない授業になってるので、ゴールは一緒。だけど学び方はそれこそ一人一人違っていい。
城谷:
得意なことに落とし込んで。
本田:
そうですね。それができる教室環境があれば、今、UDLということで海外ではどんどん進んでいますが、学びのユニバーサルデザインというところですね。そこを実践できるというので理論と実践が入って。今回の本は小学校と中学校で既に実践してきた内容を紹介しています。
城谷:
ありがとうございました。






