
木村 佳菜子 KIMURA Kanako
建築科2年在籍
東京大学理学部卒業、新領域創成科学研究科修了
不動産再生を手がける企業にて時短勤務
私にとって建築は、節目節目で気になりつつもずっと踏み込んでこなかった世界でした。大学では地学、大学院では社会学を専攻し、就職後はクラウドファンディングや不動産再生に携わってきました。脈絡なく見えて、人の居場所について考え続けてきたのだと思います。
建築に触れ始めたのは、建築界の周縁からまちや社会構造を変えていこうとする人々がきっかけでした。しかし、職業人としての立ち位置を考えるうちに、労働力を売るのではなく制作や技術で身を立てたい、考えを形にする腕を磨きたいという思いが強まり、芸術学校へと飛び込んだのでした。
芸術学校のカリキュラムは、「ASSEMBLE」を掲げるだけあって様々な分野や背景、アプローチの先生から教わることができます。異なる授業の学びが自分の中で化学反応を起こしていく様はとても愉快です。
その中でも、各授業での学びを統合するような位置付けで存在感を放つのが設計課題です。設計に正解はないとはいえ、建築的な表現作法や評価軸はあり、時に知らない試合に出場していたかのような切迫感を覚えます。現に私も2年生に上がってその世界観とスピードに振り落とされそうになり、塞ぎ込むことがありました。
入学動機や設計テーマが切実であるほど、苦しいこともあると思います。ですが、困った時に助けを求められる先生や仲間も多くいるのがこの学校です。自分の創造性を慈しみ守ること、小さな成長を祝い合うこと、うまくいかない時だってあること、上手に飲み込めない所こそ個性であること…。設計を学んでいるようでいて、それ以上のことを学ばされています。
他にも、建築セミナーや作品展といった学校行事、学生有志による見学会・勉強会、2年生からはスタジオ(作業場)など、学びと繋がりが豊かになる場が多くあります。それらを通して私は、互いの資源を持ち寄ることで全体がより豊かになるような環境を作る、それも設計なのだと思うようになりました。
芸術学校での学びは、生涯学習と言うには肉体的にも精神的にもハードです。新しい物事の習得は現状の否定と隣り合わせでもあります。ですが、ここでの学びと仲間との時間が私の生活を彩っているのは確かで、苦しい時はその存在が私を繋ぎ止めてくれます。そんな学びの場を一緒に作りたいと思ってくれる新たな仲間の入学をお待ちしています。

太田 涼介 OTA Ryosuke
建築都市設計科2年在籍
慶應義塾大学文学部卒業後、入学
「表参道ヒルズ」(2006 , 安藤忠雄)は当時中学生だった私に建築の魅力を教えてくれました。スロープがつくる巨大な吹き抜け空間や、反対側にいる人の動きを見ながらスロープを移動する体験は、とても衝撃的で言葉にならないほど感動しました。感動のあまり何度もスロープを行き来した覚えがあります。この時から建築に興味を持ち始めたのだと思います。
大学は文学部への進学を決めましたが、美学美術史学を専攻し、その中でも建築史学を中心に建築について学び、卒業論文ではアントニオ・ガウディについて建築史的視点から書きました。趣味であった建築は大学では学問として関わることができ益々建築に惹かれていきました。建築物をめぐりながら、建築の歴史を学んでいく中で、この建築が良いと評価されている事と自分が良いなと感じた事との差異について、様々なことを言語化できるようになりました。その作業がとても楽しく、同時に建築を俯瞰するだけでなく、自分も建築に直接携わっていきたいと感じるようになりました。
それに気づいたのが大学4年生の時でした。周りは就活を進めている中、自分は建築家になるか、企業に就職するか悩みました。その最中、この芸術学校を見つけました。個性を伸ばしながら、総合芸術としての建築を目指す理念に共感し、ナイトオープンキャンパスにすぐに応募しました。学校の概要の説明を受けた後、実際に授業の様子を見た際、設計課題に対して先生と生徒はもちろんのこと、生徒同士も熱心に話し合っている姿はとても楽しそうに見えました。そこで大学卒業後この学校に進学する事を決めました。
実際入学して一年が経ちましたが、想像以上に楽しく充実した学校生活を送ることができています。大学では同じ年代の人たちと一斉にスタートしますが、芸術学校では年代やバックグラウンドが異なる人たちが同級生になります。それぞれが異なる価値観を持っていて様々な方向から、色々な意見を交換しあえています。それが私にとって、とても居心地が良く感じています。お互いに刺激を与え合いながら、会話を重ねることによりそれが深みを増していく…この一年が密度の濃い時間であったのは、互いに切磋琢磨し合いながら建築について真剣に向き合ってこれたからだと思います。
趣味であった建築に学問として向き合い、今は作り手として向かい合っている。この経験は私だけの個性であると自信を持つことができます。芸術学校で3年間勉強することは今後の設計活動にとって大きな財産となるだろうと感じています。

秋庭 敦子 AKIBA Atsuko
建築科2年在籍
早稲田大学法学部卒、仏・INSEAD MBA
金融機関勤務を経て現在学生
転勤族の父と築いた私の引越記録は、私自身が金融の世界に進んだことで更新を続け、日本を含む計4か国19回に及びます。子供の頃から音楽や写真に関わっていたこともあり、各地のコンサートホールや美術館、教会等を訪れる機会も多かったのですが、長い間、「〇〇が行われる場所」に過ぎなかった建築物が突如主役に躍り出たのは、学生時代訪れたバチカンのサン・ピエトロ大聖堂に足を踏み入れた瞬間でした。打ちのめされたような感覚で何時間も教会の内外を歩き回ったことをきっかけに、国内外で移り住んだ数々の場所で、家、学校、鉄道の駅舎、教会等々、周囲に存在した建物の数々が、必ずその土地の人々の生活…気候や文化、宗教、等々…と深く関わっていたことに思い至り、強烈な興味が湧いてきました。
長く続けた仕事に区切りが見えた時、建築か写真かと悩みましたが、写真は手段として建築と関わりたい、それにはまずきちんと建築を学びたい…あちこち学校を探す中、オープンキャンパスやワークショップに参加して芸術学校への入学を決めました。
芸術学校の一番の「推し」は、何と言っても多彩なキャリアをお持ちの先生方による授業です。ご自身主宰の設計事務所における受賞経験、大手ゼネコンで誰もが知る大プロジェクトへの参画実績、学部/大学院で教鞭をとられるほか学外での専門家としての活動、等、数々の「生の」経験談は非常に興味深く、「理論」と「実践」を同時に学ぶ貴重な機会です。設計課題では学生1人ひとりと真剣に向き合って作品にコメントして下さり、更には大学院生等がTAとして細かな面でサポートして下さる…資格試験予備校は勿論のこと、他校に類を見ない贅沢な環境だと思います。
2つ目は早稲田大学との繋がり。学部との交流授業や大学院進学への道があることもそうですが、まずは膨大な資料を持つ図書館をはじめとするキャンパス内の様々な施設を学部生/院生と同様に使えること、2,3年生専用の部屋「スタジオ」では各人が席をもらえ、遅くまで作業できること、などは非常に魅力です。
そして、幅広い年代かつ多種多様なバックグラウンドを持つクラスメイトと一緒に学べる事。異なる価値観や感覚に基づく斬新な着眼点や発想には常に新鮮な驚きと学びがあり、ほとんど最年長に近い私は日々刺激を貰っています。各地の建築を訪れ、その建築に関わられた先生自らがレクチャーして下さる「建築セミナー」や、発表の場でもある芸術展への参加、先生の事務所を見学させていただいたり、と充実した日々です。

©長浜功明
鈴木 蒼平 SUZUKI Souhei
建築都市設計科2年在籍
早稲田大学人間科学部 卒業
早稲田大学大学院人間科学研究科 在学中
「入学した経緯」と「入学してからの話」、「ダブルスクール生としての話」の3点に関してお話しさせていただきます。
私が建築の道を志した原点は、建築士である両親の元、住居兼設計事務所という環境で育ったことにあります。幼い頃から両親の仕事現場に同行し、全国各地の建築や多くの専門書に触れる中で、建築はごく自然に私の日常の一部となっていました。しかし、5歳からテニスに打ち込んできたこともあり、建築への興味は抱きつつも、それを専門的に学びたいという意識は大学進学時まで明確ではありませんでした。早稲田大学進学後も体育会庭球部に所属し、テニスに明け暮れる日々でした。建築学科ではなかったため、学問として建築を学ぶ機会はないと思い込んでいました。
転機が訪れたのは大学3年生の時です。所属する人間科学部で建築設計に触れる授業を履修した際、その奥深さと創造する楽しさに心を掴まれ、建築への熱意が再燃しました。この経験から、大学では建築人間工学というソフト面からアプローチしつつ、実際に「形にする力」を養いたいという思いが強くなり、実践的な設計スキルを夜間でも集中的に学べるこの芸術学校への進学を決意しました。
芸術学校での日々は、まさに挑戦の連続でした。大学での卒業研究や、引退までは庭球部主将としての活動と並行し、設計課題や製図に没頭する毎日。特に芸術学校の1年生の時(大学4年生)は、卒業研究と主将の重責も担っており、時間的にも体力的にも極限に近い状況でしたが、休む間も惜しんで取り組みました。設計課題では、コンセプト立案からディテールに至るまで、先生方や学友たちと徹底的に議論を重ね、自らのアイデアが少しずつ形になっていく過程に、大きな達成感と喜びを感じました。
この大学と芸術学校でのダブルスクールという環境を乗り越えた経験は、私を大きく成長させてくれていると実感しています。建築の知識やアイデア力だけではなく、何よりも困難な状況でも諦めずに目標を追求する精神的なタフさが鍛えられました。
現在、大学院で建築人間工学の研究を進める中でも、芸術学校で培ってきた設計の知識や空間を捉える視点が、研究を多角的に深める上で大いに役立っています。今後も、この芸術学校で学ぶ実践的な「ハード」のスキルと、大学院で探求する理論的な「ソフト」の知見、この両軸を大切にし、建築への理解を深め、将来社会に貢献できる力を養っていきたいと考えています。

三浦 翔太 MIURA Shota
建築科2年在籍
千葉大学園芸学部緑地環境学科卒
団体職員
私が建築を学びたいと考えたきっかけは、とある公共の水族館建て替えに関するパブリックコメントを見たことでした。類似施設の維持管理を担う会社に勤めていたこともあり、水族館という用途や社会的な役割も理解していた自負もあり、新しい水族館ができることをうれしく思っていました。しかし、このパブリックコメントでは、既存の建築を取り壊すことに対して批判する文言が並んでいました。その際に改めて建築という領域を知り、意識するようになりました。建築物の利用用途だけでない社会的な存在意義のようなものがあると分かりました。このような背景があり、よりアカデミズムに近い領域で建築を学びたいと思うようになり、芸術学校に調べあたりました。
その後、生活上ある程度時間的な余裕ができたことから、半ば衝動的に芸術学校への出願を決めることになります。1月末、年度最後のナイトオープンキャンパスに参加した際に、住宅設計課題の講評回で、先輩である当時の1年生がすごく楽しそうに発表されていたのをおぼえています。
建築とそのデザインを専門的に学ぶことは初めてのことです。とくに、設計課題のなかで行われるエスキスという過程はまったく新しい体験でした。自分の“考え”を言葉と目に見える資料にし、人の意見を仰ぐ、これだけのことですが、体系的にこなしたことはなかったかもしれないなあと思い返してます。
日中の仕事と夜の学校、課題の分量も多く、現在は決して自由時間を十分に取れる生活ではありません。しかし、授業中は仕事のことをさっぱり忘れることができ、入学前に比べると精神的には安定したように思います。社会に出て業務上の技術向上や資格の習得を進める段階になると、自学自習の割合が大半になっていきます。そんな中での学校の時間というものは、人から何かを教わる楽しみを感じさせてくれます。生涯学習という言葉がありますが、その言葉の意味をまさに体感しているところです。

小林 稚菜 KOBAYASHI Wakana
建築都市設計科2年在籍
横浜国立大学経営学部国際経営学科卒業
コンサルティング会社勤務を経て現在ダブルスクール
建築を強く意識するようになった契機は、留学でドイツを訪れた際、日本とは異なる都市の在り方、人の住まい方を目の当たりにしたことです。元々、地勢・社会・歴史・文化と人の行動・生活の関係性に関心がありましたが、海外での生活を通して、その興味が自然と都市・建築に向けられるようになりました。
未経験の領域に飛び込む最初の一歩は勇気がいると思います。特に、自分の生活・キャリアを変える場合には相応の覚悟が必要ではないでしょうか。
私も以前は建築の道に進むべきかとても悩みましたが、やりたいことをやらずに後悔したくないと思い、芸術学校への入学を決意しました。1年半が経ちましたが、以前では想像できないほど充実した生活を送っており、自分の決断に後悔したことは一度もありません。
芸術学校の先生は前線で活躍されている先生方ばかりですが、どの先生も親身になって指導してくださり、何も知らなかった私でも一つずつ身になっていると感じます。実践の場のお話も聞くことができ、とてもワクワクする時間です。
課外では建築セミナーという、半日~1泊程度で行われる特別講義があります。先生方と学生で建築を訪れ、個人では見られない建築・空間を鑑賞したり、所縁の方からレクチャーを受けられたりと、貴重な経験ができます。クラスメイトと一緒に建築を鑑賞し、議論できるのはとても楽しいです。
年に2度開催される、作品展(芸術展及び卒業設計展・学生作品展)では設計課題の作品を外部に公開します。最初は「初心者の私の作品を公開するなんて」と躊躇いましたが、公開することで様々な方から講評を受けられたり、学年を越えた優秀作品を目にすることができたり、非常に刺激的で価値のあるイベントであると体感しました。
最後に、芸術学校での学びを充実させつつ、働く/他校に通うとなると毎日が非常に忙しくなります。自己管理ができていないと体調を崩したり、満足のいかない結果になったりすることもあります。ただ、様々な年代・バックグラウンドの学生がいることで、お互い刺激し合いながら切磋琢磨できる、素敵な環境だと感じています。
芸術学校で学び始めてから、これまで経験したことの一つひとつが建築を志す上で価値あることだと思うようになりました。今後も色々なことに挑戦し、楽しみながら日々精励していきます。

寺島 慧美 TERASHIMA Satomi
建築科2年在籍
獨協大学外国語学部言語文化学科卒業
家具インテリアメーカー~IT企業を経て学業専念中
「入学を決心するまで」「在学中の出産」についてお話させていただきます。入学を検討されている方の参考になれば幸いです。
以前勤めていた家具インテリアメーカーで店舗レイアウトを担当していたときのことです。日本ではあまりないのですが、中国のショッピングモールはテナントの壁面に曲線が多用されており難しいレイアウトを強いられることがよくありました。そのうち、与えられたテナント範囲を超えて、建築物そのものの形が気になりはじめ、設計者の意図を知りたいと思うようになりました。これが建築に興味を持ったきっかけだったと思います。
そういう建築への思いに気がつきつつも一方踏み出せないまま、転職をして住宅やインテリア関連サービスのインターネット販売促進をしたり、また長期休暇には国内外問わず建築旅行をしたりしていました。そんな中、コロナウイルスの流行を機に、やりたいことを後回しにするのは辞めようと決心がつき、退職して職業訓練校の建築CAD科へ入学を決めました。朝から晩まで建築に浸り充足した時間を過ごせたことで、ようやく建築への道に進みたいという気持ちに確信が持てました。ここまで約6年かかりました。
そしていざ4月の入学に向け入学試験を受けたのですが、当時私は妊娠中でした。妊娠中に夜間学校に通い、そして出産後も通い続けることはムリだと何人にも言われました。私自身も不安はなかったと言ったら嘘になりますが、迷いはありませんでした。実際に通い始めてから思ったことは、多様な先生・生徒が通う芸術学校だからこそ、人との違いはハンデにならないということです。Wスクールや仕事と両立されている方など忙しい方がほとんどです。皆がお互いの立場を理解し、助け合いながら勉強していますし、学校側も個別にサポートしてくれます。出産間際は約2か月間学校に通うことができなかったのですが、クラスメイトのフォローアップのおかげでなんとか乗り切ることができました。通学というのはオンラインと違い時間的身体的ハードルが上がりますが、助け合い切磋琢磨し合えるクラスメイトと出会えたことは想像以上のメリットがあると感じています。出産後の現在は家族の助けやベビーシッター・大学構内にある託児所などをフル活用しながら通学しています。目が回るような忙しさですが、これ以上ない充実した時間を過ごしています。

上村 真次郎 UEMURA Shinjiro
建築科2年在籍
BBT大学大学院 経営学研究科 経営管理専攻修了
機械メーカーにて技術営業職として勤務後 主夫
子供のころから父の仕事先の建築現場に連れていかれ自然と建築に触れていました。父は私に建築家になれと口癖のように言っていましたが、中学卒業と同時に高専の寮に入り卒業後は専門の機械エンジニアとして働いていたので次第に建築が遠くのものになっていきました。父が年をとり介護をしている際に私が建築に興味が出てきた事を話した時にとても喜んだのがきっかけになり少しずつ自分で勉強を始めたのですが、独学での勉強はなかなかうまくいきませんでした。そのような時に芸術学校のワークショップに参加して、学校や先生、授業の雰囲気が分かり本校へ入ろうと決意しました。詳細なカリキュラムや先生方の熱意と経験に裏付けられた指導方法を体験して、これなら経験も知識もない私でもついていけると感じたからです。
近年さかんに生涯学習とかリカレント教育といわれますが、実際にはそれほど簡単ではないと思います。もちろん学ぶものやレベルにもよりますが…。現在62歳の私が一番気を付けていることは健康です。徹夜などの無理はもう体力がなくできなくなったので、コツコツと少しずつ毎日課題やレポートをこなすようにしています。瞬発力や馬力は若い時のようにはないのでマイペースでやるように心がけています。
しかしながら、1年から2年になって授業や課題の密度が急に増しました。また、それと共に勉強の内容も全く異次元という程の難しさであり、特に考えて行う作業がほとんど全ての科目に必要になってきました。毎日のように課題やレポートが間に合わないのではと焦る反面、勉強を通して今まで気付かずに過ごしてしまった事の発見もたくさんあり、それが楽しくも感じられます。また芸術学校では多様な職業や年齢の学友が学んでおり、ダブルスクールや仕事の忙しさなどフラットな関係で様々なことについて話すこともできます。授業以外のそうした会話からも、もし自分がここで学んでいなかったら、今までの限られた自分の生活からは想像できないような建築のとらえ方や考え方などを知ることができなかったのではと有意義に感じます。「60の手習い」ということわざがありますが、入学に迷っていたらとにかく学校の門を叩いてみてください。そこには必ず今まで感じることのできなかった建築の世界が見えると思います。

永原 和奈 NAGAHARA Kazuna
建築都市設計科3年在籍
早稲田大学人間科学部卒業
損害保険会社勤務を経て現在学業専念中
学生時代から漠然とした建築への興味がありましたが、全く別の業界に就職し働いていました。安定はしているが刺激のない日々…一度きりの人生、せっかくならばやりたいと思っていたことにチャレンジしてみよう、そんな勢いと単純な興味でこの学校に入学しました。
私が考える芸術学校の魅力は大きく二点です。
一点目は、建築を多角的に考える視点を学べる事です。設計課題のエスキスでは、学生と先生方の熱量がぶつかり合います。どうしたら自分が表現したいことをカタチにできるか、よりよい建築になるかを、先生方は学生と一緒になって真剣に考えて下さります。いただけるアドバイスは設計の技術に直結するものだけでなく、そこから派生して歴史や社会・文化や芸術など多岐の分野にわたります。先生方の知見の広さに圧倒されると同時に、建築というものがそれ単体で存在しているわけではなく、社会や文化の一部として存在していること、あらゆる分野を横断して考えなければならないものであることを実感します。座学においても同様で、様々な分野の断片的な知識が、建築という世界を通して繋がっていく感覚が得られるのも、芸術学校で学ぶ面白さではないでしょうか。
二点目は、個性豊かな仲間から気づきを得られる事です。同一の設計課題に取り組んでいても、出来上がる作品はひとつひとつ全く違います。各々の学生が、どんな過程を経て何を意図して設計したのか、その“解き方”の説明を聞くたび、自分にはない発想や視点に気づかされます。そしてその多岐にわたる視点は、学生が持つバックグラウンドに裏付けされたものであるとも感じます。得られる気づきと刺激の多さは、多種多様な背景を持つ人々が集っているこの学校ならではの醍醐味です。
また、建築とは全く別の業界からこの学校に飛び込んだ私ですが、遠回りのように思える今までの経験も、無駄なことではなかったのではないかと思えています。毎日仕事をしてから授業に向かい、課題をきちんとこなすことは、想像していた以上に大変です。しかし、その大変さ以上に、社会人になってから学べることの楽しさを毎日実感し、充実した日々を送ることができています。

大塚 明将 OTSUKA Haruma
建築都市設計科3年在籍
香川県立善通寺第一高等学校デザイン科卒
学生
私は高校で広く浅く、多種多様な芸術やデザインを学び、その延長線上で「建築」という分野に興味を持ち、この芸術学校に進学しました。高校卒業後すぐに入学したので、年齢的には同世代の大学生と変わらないですが、ここでは本当にいろいろな年齢、職業、背景を持った人たちと一緒に学んでいます。
この学校に入って一番良かったと感じているのは、そういった多様な人たちと関わることができる環境に身を置けたことです。昼間は仕事をして夜に学校へ来ている方、すでに社会経験のある方、大学を卒業してから再度学びに来ている方…。普通の大学に進学していたら、出会えなかったような人たちばかりです。最初は年上の方々と話すことに少し緊張もありましたが、話してみるとみなさんとてもフランクで、建築に対する思いや人生の話など、毎回新しい発見があります。授業以外のこうした交流が、自分の視野を広げてくれているのを実感します。
もちろん、建築の専門的な学びの場としても、とても充実しています。夜間でありながら、課題や授業内容の質は高く、真剣に取り組むことで自分の力になっていくのが分かります。模型制作や図面の作成など、手を動かしながら考える時間が多く、最初は大変に感じたこともありましたが、今ではそのプロセスが楽しくなってきました。
この学校に入る前は、「夜間専門学校」ってどんな雰囲気なんだろう…と少し不安もありました。でも実際に入ってみると、建築に本気で向き合う仲間が集まっていて、お互いを高め合えるとてもいい環境です。高校卒業してそのまま入学した自分にとって、ここはただ「建築を学ぶ場所」ではなく、「人として成長できる場所」でもあると感じています。
将来は、ここで学んだことを活かして、自分らしい建築を形にしていきたいと思っています。まだまだ知らないことも多いですが、この学校での日々が、確実にその一歩になっていると感じます。

井上 真緒 INOUE Mao
建築都市設計科3年在籍
立教大学社会学部4年在籍
私は、芸術学校への入学を決めた理由、大学生活との両立、そしてこの学校での学びを通じて得たことについてお話しします。
入学を決めたきっかけは、幼い頃からの建物への興味でした。建築学部を卒業した父と街を歩く中で、建物の形に目を向けたり、旅行先で建築を見に行ったりする体験を重ねるうちに、「建物を見るとワクワクする」という気持ちが自然と育まれていきました。高校時代は理系科目への苦手意識もあり建築とは無縁の文系学部に進学しましたが、大学生活を送る中で「建築を“つくる側”」に興味を抱くようになりました。そこで、文系出身の自分が建築を学べる環境を探し、実際にいくつかの学校を体験したうえで、設計だけでなく多様な授業を通じて幅広く学べるこの芸術学校に魅力を感じ、進学を決めました。今振り返ると、設計の知識も経験もなかった私が入学を決意できたのは、家族や友人の支えと勢いだけだったと思います。
実際に入学してみると、自分の興味があった分野について学べるという充実した日々が過ごせる反面、大学と芸術学校の両立は想像以上に忙しく、特に大学の期末試験と設計課題が重なる時期は大変で、あっという間に1年が過ぎました。しかし、クラスには仕事や子育てと両立して通う方も多くいらっしゃり、自分以上に努力を続ける人たちの姿に刺激を受け、頑張ることができています。設計課題では何度も厳しい講評を受け、周囲の完成度の高さに劣等感を抱いたこともあります。それでも、自分の中で、「楽しむ」という気持ちを忘れず、同級生や先生に支えられながらなんとか頑張っています。現在も設計課題に苦戦中ですが、後悔しないように卒業まで頑張りたいと思います。
芸術学校での学びを通じて得たものとしては、建築への知識は勿論のこと、人との出会いだと感じています。この芸術学校に入っている人は、自分で何かしらの大きな決断をして入った人が多いように感じます。年齢は違えど、夢を持ち、努力し続ける同級生に沢山出会えたことは、自分の人生にとってとても刺激になりましたし、普通の大学生活では絶対に出会うことのできなかった方々に芸術学校を通じて出会うことができたと感じています。芸術学校には、圧倒的な才能や表現力を持ち、夜遅くまで作業を続ける努力家が沢山おり、世の中にはこんなにもかっこいい人生の先輩が沢山いるのだと自分の人生にとってとても刺激になりました。本当に心から充実した大学生活を過ごせています。
もし自分のように建築に興味がありながらもダブルスクールに不安を感じる方がいらっしゃいましたら是非、勇気を出して挑戦して欲しいと感じています。

北 真奈美 KITA Manami
建築都市設計科3年在籍
神田外語大学外国語学部国際コミュニケーション学科卒業
ワイン商社〜総合建築会社(家業)勤務
社会人経験後、建築を学び始めた私の人生は、遠回りしているように見えますか?
家業が建築関係ということもあり、幼いながらに、この業界で働くということは、知力と体力の両方を必要とする、大変なことであると認識していました。そのため、当時自分に自信がなかった私は、建築に興味があったものの、好奇心だけでチャレンジできるほど強くはなく、賃貸チラシの間取りに家具レイアウトを描くだけ、それだけで満足したかのように、自分の気持ちに蓋をしていました。
月日が経ち、得意だった文系の道を歩み続けた私は、好きなことに全力で挑み続け、大学を卒業。新卒で入社したワイン商社では、食事とのペアリング、歴史や栽培方法等あらゆる角度からワインに向き合い、充実した毎日を過ごしていました。そんなある日、ふと「ワインを楽しむ空間は、人それぞれ違う。その空間の違いによって選ばれるワインも異なる。では、その空間とはどんなものか。」と疑問に思い、それと同時に、胸の奥にひっそりと隠していた建築に対する想いが芽吹いた、そんな気がします。
それから先は、今思えばあっという間でした。父に紹介され、先ずはナイトオープンキャンパスに参加。そこで聴講した前校長・古谷誠章先生の「建築は、人間が衣類の次に身に着けるものである」という言葉に、「私の抱く、空間に対する疑問や建築の在り方を考えるためのヒントはここにある」と直感し入学を決意しました。
何度考えても、普通だったらこれまでの道のりは遠回りです。しかし、入学してみるとその概念は壊れます。なぜなら、過去の経験がなければ、私が今まで創造してきた作品は生まれなかったからです。
設計課題で行われるエスキスという過程は、自らのバックグラウンドから沁みだした意見や考えが建築言語に変換する時間です。先生方は多種多彩な生徒それぞれにあわせて、つたない変換でも理解し、あらゆる可能性を見つけ、広げてくださいます。また年2回ある外部公開型の作品展(芸術展/卒業設計展・学生作品展)では、多角的な意見や講評に刺激され、作品づくりに対する熱意や建築に対する考え方が洗練されていきます。そしてまた、建築の面白さに魅せられます。
恐れず、思いのままに踏み出してみると、案外気持ちよくことが進むかもしれません。私は、今このタイミングで建築を学んだことで、自分らしさを見つけた気がします。

竹内 孝明 TAKEUCHI Takaaki
建築都市設計科3年在籍
米国マサチューセッツ工科大学 技術&政策大学院修了
事業創造コンサルティング会社経営
小学生の頃、自宅を手掛けた大工さんの手仕事に感動して以来、大学入学時まで「建築家」を志していました。ふとした縁で専攻をコンピュータサイエンスに変え、その後ビジネスの世界へ。この20年ほどはベンチャーや事業創造のコンサルティングに携わっています。最近「まちづくり」や「地域材を活用した都市の木質化」など、建築に関りのあるプロジェクトが増え、建築家に憧れる気持ちが再燃し、意匠デザインに強みのある芸術学校への入学を決めました。
私個人にとっての芸術学校の魅力を大きく3つ挙げます。
①「理論を伴った実践的な設計感覚」を磨くことができる
殆どの先生方が、ご自分の設計事務所を持ち、研究もされつつ教壇に立たれ、エスキスでアドバイスをくださいます。これは私たちにとっては「体系だった理論」と「実践で考えるべきこと」、「オリジナルであることの大切さ」を同時に学べるということ。設計課題を解く際にも、常になぜそのカタチでなきゃいけないのか、周囲の環境との関係をどう考えているのか、即答が求められます。原理原則を踏まえつつ、自分ならではの実社会を動かすような設計を考えるよう、日々鍛えられています。
②文化教養を身に着けることの建築設計にとっての大切さに気付かされる
理科系出身であることを言い訳に、これまで文科系の勉強を疎かにしてきた私にとって、世界や日本の歴史、文化の変遷を、建築や技術と結びつけながら学んでいくことは、様々な要素が面的に繋がっていくようで、驚くような発見があります。私の好きなアートの世界も、建築と隣り合わせ。そういった要素を建築設計に取り込むことの本質的な意味に、今更ながら気付かされています。
③クラスメイトが多様性に富んでいて、互いに刺激し合える
私はクラス最年長。経験や常識にとらわれて、枠を超えたハッとする様な発想が湧かずに苦しむこともしばしば。クラスメイトはバックグラウンドも年齢層も本当に多様で、斬新な着眼点や発想を披露してくれるので、他に類を見ないような互いの学びと刺激の場になっています。自身のアウトプットに1年生の頃よりも何かしら変化、進化を感じるのは、クラスメイトからの刺激が少なからず影響しているように思います。
仕事との両立は想定していた以上に厳しいです。特に設計課題の実習は、行動と思考と作業の度重なる繰り返し。常にタイムマネジメントに悩まされます。私のやり方は、「途上でもよいから、少しでも考え進化させたものを必ず期限内に提出し、何かしらアドバイスをいただく」ということを自分に課してきました。その結果、ハードルは期を重ねるごとに高くなっていきますが、それを超えるための力も徐々に育っているような気がしています。
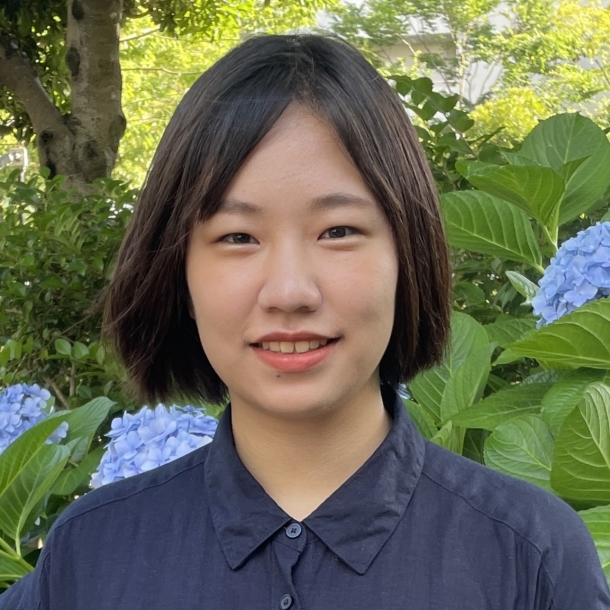
橋本 果歩 HASHIMOTO Kaho 建築都市設計科3年在籍 東京家政大学家政学部造形表現学科4年在学
芸術学校への入学は、今思い返すと興味と勢いだけでした。
大学は家政学部内の芸術系学科。大学1年生の時、デザイン史の授業で初めて建築を学問として認識しました。その時に「建築ってもしかしたら1番生活に直結したアートかもしれない。」と感じたことで建築を自分の専門にする事を決め、数ヶ月後には芸術学校を受験していました。
芸術学校の1番の魅力は、多種多様なバックグラウンドを持った仲間を得られる事です。大学や専門学校の多くは、同年代のクラスメイトと学ぶことになりますが、ここではみんなバラバラ。そのような仲間と一緒に学ぶことができる環境は、自分が経験したことのない体験や、自分とは異なる感覚、知らない知識などで溢れており、先生だけではなく、クラスメイトからも学べることがたくさんあります。
3年生になってみると、座学はアセンブルデザイン特論という週2回の授業のみ。オムニバス形式で、現在、建築界で活躍されている様々な先生方の講義が行われます。この授業は、技術を学ぶというよりも先生方の経験や考えを知る講義です。毎回講義後の帰り道は、2年生までに蓄えた知識を自分はどの様に活用し、力を伸ばしていくかを考え、自分の未来を想像する貴重な時間になっています。
芸術学校生の多くは仕事や学業と芸術学校を両立しながら生活しています。私も大学と芸術学校を両立していますが、両立は結構大変です。私の場合は、大学と芸術学校の講義時間が被ってしまい週に2、3度はどうしても遅れてしまう時期がありました。そんな時は講義について行けなくなる不安や悔しさを感じましたが、クラスメイトや大学・芸術学校の先生方の理解や助けもあり、学び続けることができています。
設計課題も多くの時間を費やしじっくり考えていくものなので、計画的には進まない場合が多々あります。そのため、入学当初は両立を困難に陥れる要因でした。しかし、課題をこなしていくうちに自分の躓く所、進みが早い所が理解できタイムマネジメントが上手くなり、今は少し余裕ができました。
今年はいよいよ卒業の年。国際コンペや卒業設計とワクワクする課題がまだまだ続きます。卒業まで気を抜かず頑張っていきたいと思います。

浅野 秀矢 ASANO Hideya
建築都市設計科3年在籍
早稲田大学人間科学部卒業
建築設計事務所勤務
建築や空間について、興味を持ったきっかけは⼤学時代の経験です。私が在学していた早稲⽥⼤学⼈間科学部は幅広い分野を学べる学部であり、その中に建築に関する分野もありました。所属していた研究室では、実際に建築を⾒に⾏く機会等もありました。そこで設計の課題を少し経験しましたが、もっと建築について知⾒を広めたいという思いが⽣まれ、芸術学校への⼊学を決断しました。
私が数ある学校の中で芸術学校を選択した理由は、学習する⽣徒の多様性と 充実した学習環境です。まず芸術学校には様々なバックグラウンドを持つ学⽣がいます。⾃分と同じように⼤学を卒業して⼊学する⼈や⼤学で異なる分野を学びながらダブルスクールで通う⼈、会社に勤めながら通う⼈等、年齢層も幅広く様々な学⽣がおり、芸術学校で学ぶ⽇々は毎⽇充実しています。また、設計課題ではそれぞれのバックグラウンドを活かした作品を⾒ることができ、⾮常に良い刺激となっています。
次に、充実した学習環境があるという点です。芸術学校は資格試験対策だけに留まらず、建築に関する歴史は地理等も学ぶことができ、建築についての幅広い理解や教養を深めることができます。設計課題でのエスキースでは、第⼀線で活躍する先⽣達が⾃分のやりたいことに熱⼼に向き合ってくださります。⾃分の考えとは異なる⾓度でアドバイスをいただき、そこから新たな気づきを得ることで作品の質を上げることができるので⾮常に有意義な時間です。
振り返ると、1年次は線の描き⽅や模型の作り⽅もわからず、課題を期限通りに出すのに精⼀杯でした。2年次は設計課題でより多くのことが求められ、中々上⼿くいかず、悩みながらもなんとか⾷らいついていった1年だったと思います。仕事と学校の両⽴をすることも⼤変で、様々な困難があったと思います。しかし、それを上回るほどの楽しさが建築にはありました。建築と向き合っている時間は何よりも楽しく、考え続けたその先に⾃分にしかできない作品をつくり上げることができ、向き合い続けた達成感を得られると⽇々感じています。
卒業後は実務を経て1級建築⼠の資格を取得し、将来的には独⽴するのが⽬標です。今後も建築を学べているということに感謝して、設計を楽しみながら、⽇々精進していきたいです。
※掲載内容は、取材当時のものです。
(最終更新日:2025年10月16日)