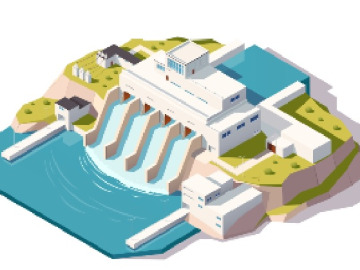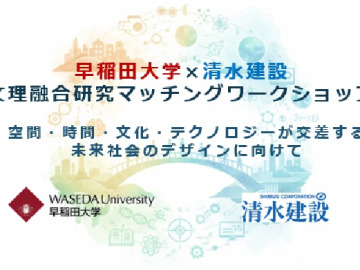早稲田大学ガバナンス&サステナビリティ研究所では「第16回 早稲田大学ガバナンス&サステナビリティ研究所研究会」を下記のように開催することとなりました。世界で最も影響力のある研究者の上位にランクされている著名な講演者が参加します。
概要
■ 日時:2024年 4月11日(木)19:00 ~ 20:30
■ タイトル: 『環境DNAを用いた生物多様性モニタリング法:持続可能な地球環境の利用に向けて』
■ 講演者: 宮正樹様
千葉県立中央博物館 主任上席研究員・九州大学大学院客員教授
■ 開催方法:対面およびオンライン
対面の会場:早稲田キャンパス26号館8階
オンライン:お申込みの際にZOOMのURLをお知らせいたします
■ 参加費:無料
申込URL
https://forms.gle/dStRbhgZqwXqLS8A6
講演概要
科学技術が急速に発展した今日においても,「どこにどんな生きものがいるのか?」というシンプルな問いに答えるのは容易でない。水生生物である魚の場合には,魚を潜水観察したり漁具で採集したりなど,多大な労力と費用がかかるうえに長期間の調査が必要となり,種を特定するためには高度に専門的な知識や経験も欠かせない。近年,魚が粘液や糞を通じて水中にDNAを放出していることが明らかになり,この水中を漂うさまざまな種類の魚のDNA(環境DNA)を分析することで,そこにどんな魚が棲んでいるのかわかる技術が開発された。本講演では,環境DNAを用いた生物多様性調査法の概要と実際について最新の研究成果に基づき解説するとともに,この調査法が持続可能な地球環境を維持していくためにどのような貢献ができるのか論じる。
講演者略歴
千葉県立中央博物館 主任上席研究員・九州大学大学院客員教授
1959年東京都杉並区生まれ。1986年3月東京大学大学院農学研究科博士課程修了 (農学博士)。1995年に分子生物学実験の基本技術を習得して以来,新技術の開発を突破口に大規模データを取得して新分野を切り拓くスタイルで研究を進めてきた (データ駆動型・仮説発見型研究) 。専門は魚類を主体とする分子進化系統学と分子生態学。前者の分子系統学については,ミトコンドリアゲノム全長配列 (約16,500塩基対) の高速決定法を開発。大規模データに基づく大系統解明の先駆けとなる一連の研究を行った。後者の分子生態学については,魚類環境DNAメタバーコーディング法 (同時並列多種検出法) の技術を開発。「バケツ一杯の水で棲んでいる魚がわかる技術」として注目を集め,テレビ,ラジオ,新聞,雑誌等の各種メディアで大きく取り上げられた。この環境DNA分析技術は世界の海洋・淡水・汽水で用いられるようになり,魚類群集研究の標準法としての地位を築きつつある。公表済みの原著論文は190篇で通算19,316回引用されている。2022年版“世界で最も影響力のある研究者トップ2%” では,上位2%にランクされた210,199人の世界の研究者の30,994位 (日本のみでは497位)に位置づけられた。
奮ってご参加ください。