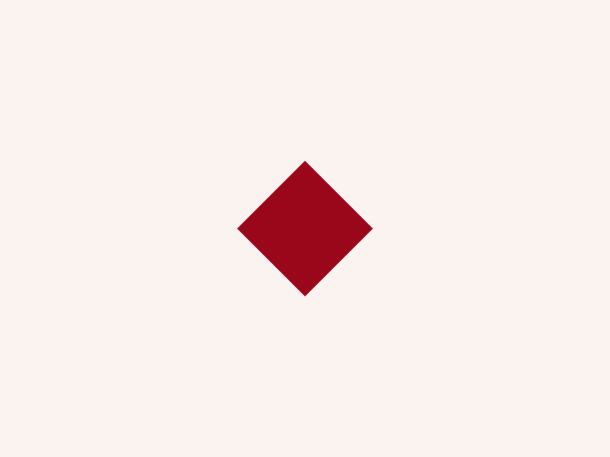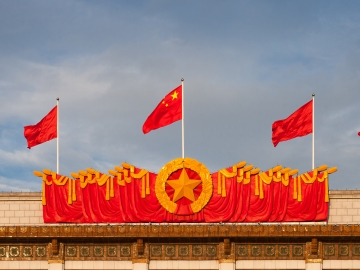Research Theme 研究テーマ
2005 年 4 月に設置された建築学研究所は全建築学専攻教員を構成員として研究活動・情報発信を続けている。
近年の各種災害の発生、地球環境・都市環境の大きな変化をはじめとして、建築および建築学を取り巻く状況は大きく変化してきている。このような変化に対応した研究体制の構築、積極的な情報発信を目的として、「建築学研究所」は理工学術院・建築学教室と表裏一体となった活動を行う。
建築史、建築計画、都市計画、構造、環境、生産の各分野での実績を有する個々の研究所員の活動や複数研究所員による共働研究活動を、「人・建築・都市・自然をつなぐ総合的デザインの実践研究」として統合し、その成果を各年度に発行する『早稲田建築学報』として発表する。また、各分野の著名研究者を招聘し、先端建築学セミナーを年に 4~5 回開催する。
Research Director 所長
Member メンバー
- 有賀 隆 理工学術院創造理工学部教授
- 石田 航星 理工学術院創造理工学部准教授
- 小岩 正樹 理工学術院創造理工学部准教授
- 輿石 直幸 理工学術院創造理工学部教授
- 後藤 春彦 理工学術院創造理工学部教授
- 小林 恵吾 理工学術院創造理工学部准教授
- 高口 洋人 理工学術院創造理工学部教授
- 田中 智之 理工学術院創造理工学部教授
- 田邉 新一 理工学術院創造理工学部教授
- 中谷 礼仁 理工学術院創造理工学部教授
- 中溝 大機 理工学術院創造理工学部准教授
- 早部 安弘 理工学術院創造理工学部教授
- 伯耆原 智世 理工学術院創造理工学部准教授
- 宮本 佳明 理工学術院創造理工学部教授
- 矢口 哲也 理工学術院創造理工学部教授
- 山田 宮土理 理工学術院創造理工学部准教授
- 吉中 進 理工学術院創造理工学部教授
- ラムサル ビカス 理工学術院創造理工学研究科准教授(任期付)
- 渡邊 大志 理工学術院創造理工学部准教授
研究キーワード
建築史、建築計画、都市計画、建築構造、建築環境、建築生産、建築材料、防災、地球環境問題
研究概要
建築学専攻の教員が中心となり、新たな建築学の創造に向けた研究体制の構築と積極的な情報発信を目的として、2005 年に建築学研究所を発足した。以来 4 期にわたり継続した研究活動、広報活動、出版物の刊行を続けている。
これまでの活動は、「早稲田建築学報」の発行と先端建築学セミナーの開催で、情報発信と交流が中心であったが、2022 年に拠点なる内藤多仲記念館 建築学研究所を整備し、研究スペースを確保した。2023 年からは第一弾となる産学連携研究「解築学の構築」を開始し、分野横断型研究にも着手できた。第 5 期では研究所名も継続しこれらをさらに発展させる。第 5 期では引き続き建築学教室の活動、研究のアウトリーチを目的とした「早稲田建築学報」の発刊、先端建築学セミナー等の開催、分野横断型の研究推進に務める。日本の近代建築学の創世記において、早稲田大学建築学科は当初から民の立場、すなわち市民社会と実業の側から、近代建築の理想を追求することを自らの使命として出発した。そのことが、本学における建築学が、実学としての技術に基礎を置きながら、市民社会の側につく志の追求という色彩を強くしてきたことにつながっている。2023 年から始まった解築学は、新築偏重だった建築学を、ストックの活用にシフトし、不動産ファイナンスとの連携、解体方法の開発、建設材料のリユース、リサイクル、特にアップサイクル方法の開発に展開するもので、本学の建築学の伝統から生じた分野横断型研究であり、時機にもあったものと引き続き推進する。
第 5 期では、解築学の研究をさらに発展させるとともに情報発信に務める予定である。また内藤多仲記念館 建築学研究所を活用し、外部資金・外部人材を活用した新規分野横断型研究にも取り組む予定である。新規分野としては、デジタル時空間マネジメント(2025 年度に研究重点教員を採用予定)、防災分野を予定している。