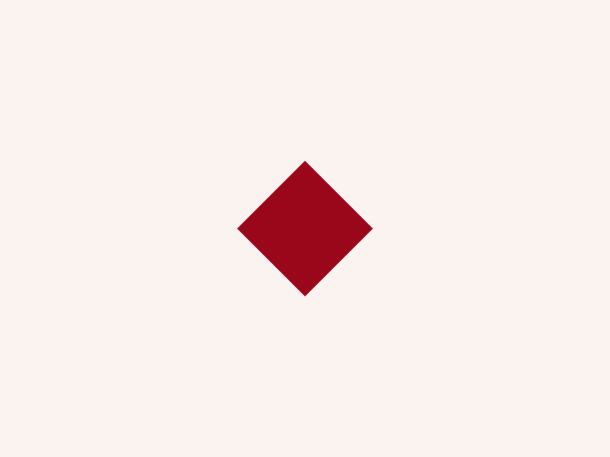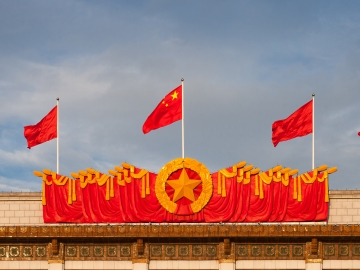Research Theme 研究テーマ
社会システム、とりわけ経済、経営、教育分野のシステム・組織の競争力について検討し、その動態メカニズムを明らかにする
Research Director 所長
熊谷 善彰
くまがい よしあき
教育・総合科学学術院
Member メンバー
- 楠元 範明 教育・総合科学学術院教育学部教授
- 熊谷 善彰 教育・総合科学学術院教育学部教授
- 野口 穂高 教育・総合科学学術院大学院教育学研究科教授
- 矢口 徹也 教育・総合科学学術院教育学部教授
- 吉田 賢史 高等学院教諭
- 大木 裕子 総合研究機構客員上級研究員(研究院客員教授)
- 大塚 耕平 総合研究機構客員上級研究員(研究院客員講師)
- 戸崎 肇 総合研究機構客員上級研究員(研究院客員教授)
- 森 玲奈 総合研究機構客員上級研究員(研究院客員教授)
- 大野 貴洋 学校法人三幸学園講師
- 川内 康裕 株式会社リビングロボット
- 姜 元馨 SNK POLYTEC,.LTD GROUP代表取締役会長、NPD CO,.LTD GROUP代表取締役会長、CAP CO,.LTD GROUP代表取締役会長
- 工藤 洋一
- 齋藤 大輔 高千穂大学経営学部准教授
- 佐藤 勝彦 淑徳学園監事、日独協会理事
- 武沢 護
- 田村 琢実 埼玉県議会議員
- 崔 岩 大連諾克科貿有限公司
- 崔 彰完 カトリック大学校日語日本文化学科
- 長島 啓記 早稲田大学名誉教授
- 中西 正文 株式会社Kids Smile Holdings代表取締役社長
- 浜崎 祐一郎
- 樋口 清秀 早稲田大学名誉教授
- 藤井 浩司 早稲田大学名誉教授
- 幕 亮二 株式会社MK総合研究所代表取締役社長
- 村上 明男 ナノ・ライフ創新研究機構ナノテクノロジーフォーラム研究戦略監
- 森 康郎 元早稲田大学システム競争力研究所客員研究員
- 山中 脩也 明星大学情報学部情報学科准教授
- 山本 訓史 リベラグループ株式会社代表取締役社長
- 米持 賢治
研究キーワード
教育・人的資源研究、戦略・社会システム研究、社会基盤研究
研究概要
概要を、部門・部会別に列挙すると以下の通り。
Ⅰ.「官学共同研究部会」
Ⅰ-1.内閣府SIPスマート物流サービス「荷物データを自動収集できる自動荷降ろし技術」の研究開発
Ⅰ-2.経産省「未来の教室」の遠隔教育・在宅教育普及促進事業の展開
「金融経済・投資教育」STEAMコンテンツ作成事業
Ⅰ-3.文科省等
公的機関との研究・事業の展開(コンテンツについての具体的意見交換等、準備進行中)
Ⅱ.教育・人的資源部門
Ⅱ-1.「教育システム部会」
- 東日本大震災の被災地(教育委員会等)との討議・検討を通した学習支援システムの構築(地域連携システム部会と共同研究と事業実施)
- 小学校導入予定の「プログラミング教育」のための養成を各教育委員会と連携して実施(出張授業)。
荒川区教育委員会、学力向上研究所及びシステム競争力研究所と連携しプログラミング教育の出張授業を実施。
荒川区立中学校では自立継続型の教員育成の傾向が拡大しつつある。
- 文科省の教育改革、特に新学習指導要領を視野に置いたプログラミング教育・「金融・投資教育」のための人材養成(金融システム部会との共同研究)
Ⅱ-2.「人的資源システム研究部会」
- リーダーシップについての事例収集と理論化、講義実施と早稲田ウエイの検討。
- オリンピック・パラリンピックについての選手強化事例収集と講議実施。
- 「しごと能力研究学会」との研究・国際会議開催等に関するコラボレーション
- 荒川区自治総合研究所との共同研究。
第四次産業革命ともいわれているAIと求められるしごと能力について継続的にとりあげ、研究と報告を重ねたしごと能力研究学会との共同研究実施。
基礎自治体の運営と人的交流についての研究(荒川区自治総合研究所との共同研究所)
Ⅲ.戦略・社会システム部門
Ⅲ-1.「金融システム研究部会」
「投資教育とそれに関わる人材育成」に関する事業の実施。
主な実施校は以下の通り
- 宮城県 気仙沼市立新月中学校/南三陸町立志津川中学校 /東松島市立矢本第一中学校
- 東京都 荒川区立第四中学校/早稲田実業高校
- 埼玉県 早稲田本庄学院高校
- 神奈川県 県立平塚商業高校
- 広島県 呉青山中学校・高等学校
- 福岡県 宗像市立自由ヶ丘中学校 /宗像市立日の里中学校/宗像市立城山中学校
- 佐賀県 早稲田佐賀中学・高校
Ⅲ-2.「地域システム研究部会」
- 地域活性化と地域競争力についての研究推進と成果の発信。 被災地における普及・復興状況の分析と支援活動。
- 観光・観光教育の分析と支援活動
IV.社会基盤研究部門
「未病産業の研究」を通した産業創造の研究
Ⅴ.東アジア研究部門
韓国・台湾との政治経済交流を中心とした調査研究の実施