最適化計算・統計推測・機械学習などの技法を導入し、出力が天候に左右される太陽光発電をスマートに活用するための様々な技術を開発し、環境に優しく再生可能であるという太陽光発電の価値を最大限に引き出します。太陽光発電の価値向上を通じて、カーボンニュートラルの実現に貢献します。
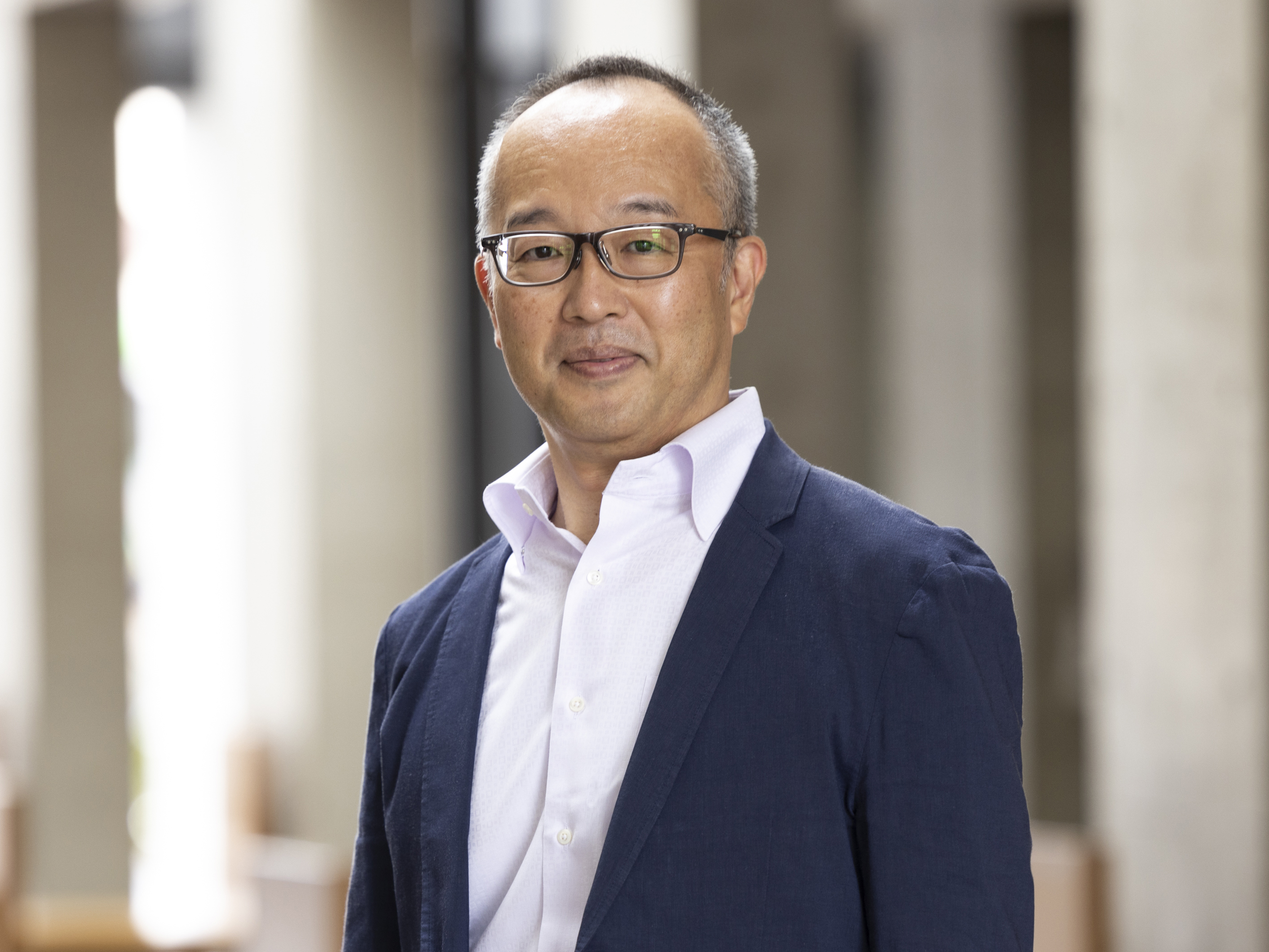
自然エネルギーをはじめとする化石燃料の代替エネルギー開発は、持続可能な社会の実現に不可欠な最重要課題です。また、東日本大震災のような広域災害時におけるエネルギー供給の役割も自然エネルギー利用の重要な目的の一つですが、近年の大風・大雨などの異常気象による災害の激甚化に表れているように、環境問題がますます深刻化する現在では、太陽光発電(PV:Photovoltaics)に対し、カーボンニュートラルの実現に向けてどのような貢献ができるのか、議論が活発化しています。
これまで太陽光発電に関しては、発電効率の向上に代表されるような、太陽電池自体、すなわちデバイス分野における技術開発が中心的な位置を占めていました。これは、日射エネルギーの密度の低さから、まとまった量の電気エネルギーを生み出すためには大面積を要するという難点が根底にあります。その他に、一般に自然エネルギー特有の難点として、気象条件により発電出力が変動することが挙げられます。今後のPV大量導入を想定した場合、後者の難点が及ぼす影響がより深刻なものとなります。発電した電気エネルギーを負荷に届けるためには電力ネットワークを介することとなりますが、時々刻々と変動する負荷のみならずネットワーク上に出力制御に難がある太陽光発電の割合が増えるにしたがって、電力の余剰・不足の不確定性は増大の一途を辿り、電力品質の低下や保護・保安上の問題等が深刻化するからです。自然エネルギーから電力を生み出しても、それを負荷まで安定性と経済的合理性を備えつつ輸送できなければ、環境に優しく再生可能であるという価値は半減します。このような背景のもと、電力ネットワークにつながる制御可能なものを総動員して、ネットワークシステム全体でバランスを取り、太陽光発電の出力不安定性をカバーしようというシステム分野の研究開発の重要性が、急速に高まっています。
本研究所では、分散型太陽光発電を含むエネルギーネットワークシステムの最適化設計技術の開発、日射量予測も組み入れたエネルギーマネジメント手法の開発、自然エネルギー利用型分散電源と異種電源とを組み合わせたハイブリット発電システムの研究など、最適化計算・統計推測・機械学習などの技法を導入し、出力が天候に左右される太陽光発電をスマートに活用するための技術開発に取り組みます。
天野 嘉春 理工学術院基幹理工学部教授
紙屋 雄史 理工学術院大学院環境・エネルギー研究科教授
田邉 新一 理工学術院創造理工学部教授
林 泰弘 理工学術院先進理工学部教授
村田 昇 理工学術院先進理工学部教授
若尾 真治 理工学術院先進理工学部教授
〒169-8555 東京都新宿区大久保3-4-1
【E-mail】 [email protected]
【WEB】 http://www.wakao.eb.waseda.ac.jp/wakao/