- ニュース
- 「居場所」をキーワードに子どもや若者の多様な学びのありようを考える 【教育学分野】阿比留久美教授
「居場所」をキーワードに子どもや若者の多様な学びのありようを考える 【教育学分野】阿比留久美教授

- Posted
- Tue, 08 Aug 2023

学校だけにとどまらない、人が学び育つ場
私の専門分野である社会教育とは、学校教育・家庭教育以外のあらゆる学びを指します。教育と聞くと学校をイメージする人が多いと思いますが、人が学び、育つ場所は学校だけではありません。実は図書館や博物館、公民館なども社会教育を担う施設だと知れば、社会教育がぐっと身近なものに感じられるのではないでしょうか。学校教育では基本的に「教える人」と「教えられる人」の役割は固定され、覆ることはありません。これに対し社会教育では、その関係性は緩やかで、ひとりの人が学習者と教育者の立場を行き来することもあれば、「教えられる人」という客体から「自ら学ぶ人」という主体に変わることもあります。人と人が交流しながら学び合うなど、学び方に多様性があることも社会教育の特徴です。
学校教育に限定することなく、人が「育つ」「学ぶ」、さらには「生きる」ということを多面的に考えることができる学問分野が、社会教育だといえます。私は社会教育における学びや支援のあり方について、教育学と社会福祉の視点から研究しています。また、子どもや若者が大人になっていく移行プロセスのありようを捉えるために、子ども・若者の「居場所」をテーマにした研究にも力を入れています。
子ども・若者の「居場所」の一例として、主に不登校の子どもが通うフリースクールやフリースペースがあります。こうした学校以外の学びの場所で起きていることを、フィールドワークを通じて明らかにしていくことで、学校に適応・順応できない子どもを含めた誰もが、自分のペースややり方で育ち生きていくことのできる社会へのヒントを探っていきたいと考えています。一方で、フリースクールやフリースペースの対象年齢を過ぎた若者が、学ぶ場所をどこにも持てなくなる問題もあります。そのため現在は若者支援の領域にも関心を向け、支援団体とネットワークを形成しながら、現状の課題や対策などについて研究を進めています。

生きる場所や生き方の選択肢を増やしたい
コロナ禍は若者支援の現場にも大きな影響を及ぼしました。これまでは支援対象者と直接的に会ってサポートすることに重きが置かれていたのが、対面でのやりとりが難しくなったことからオンラインでの支援が急速に進み、支援にあたる人たちも価値観の多様化を迫られている状況です。同様に、「居場所」のありようにも変化が生じ、オンラインでの居場所づくりの取り組みも出てきています。ただし、すべてがオンラインで補完できるわけでは決してなく、その見極めも含め、オンライン時代の支援のあり方についてさらに議論を深めていく必要があると考えています。
遡ると、私が「居場所」について研究をするようになった背景には、自分自身の経験が関係しています。ひとり親の家庭で育ち、そのなかでも気にかけてくれる大人が周りにいたことや、勉強が好きだったことなど、いろいろなものが少しずつ積み重なって自分の資産となり、人生を歩む上での拠り所になりました。一方で、そうした資産を積み重ねることができない場合や、あるいはちょっとした運の違いによって、何かの拍子に生き方を選べない人生に陥る恐れがあることも強く感じました。格差や不平等に直面することなく皆が生きられるような、そんな社会や環境をつくることに関わりたいと、研究者の道を選びました。
「居場所」をテーマに研究をしていますが、究極的には「居場所」という言葉がなくなるような社会が理想だと考えています。子どもや若者が大人になっていくプロセスの中で、誰一人としてこぼれ落ちることなく受け止められる社会であれば、「居場所」を求める必要自体がなくなるでしょう。そうした未来を実現するには、生きる場所や生き方の選択肢がなるべく多くある社会にしていくことが大切で、そのための研究を今後も続けていきたいと思います。

人生の分岐点を支えられる研究にやりがい
人が学び育つという営みは、学校に所属している期間に限られるものではなく、家庭、地域、職場も含めたあらゆる場所に教育は存在します。つまり、教育学研究で一つのテーマを深く掘り下げた経験は、社会に出てからもさまざまな場面で活かし得るということで、この分野の大きな魅力だと思います。加えて、人が育つことや学ぶことは、人が生きることと関係が近いことから、教育学の研究には人間研究にも通じる奥の深さがあります。
その教育学の中でも、社会教育や青年期教育の分野は、子ども・若者の多様な学びのありようを考えたり、教育を通じた新たな社会のあり方を構想したりすることを通じ、皆にとってより生きやすい社会を追究していける醍醐味があります。特に、子どもから大人へと移行していく青年期は、自分の生き方を定めていく人生の分岐点にあたります。人の一生の中でも大切な時期を支え得る研究ができることに、私自身もやりがいを感じています。
学部で培った基礎知識の上に、さらに深く学問を究められるのが大学院であり、自身のテーマに向き合う豊かな時間がそこにはあります。大学院への進学を考える人はぜひ今のうちから、社会にある問題を自分のものにして深め、自分の問いを持つことを意識してほしいと思います。大学院では、論拠に基づきながら、他者を納得させられる新たな展望をひらいていくことが求められます。この営み自体が対話的であり、その繰り返しの中で自分なりのものの見方や解を見つけながら社会像を作り上げていけることが、大学院ならではの研究の面白さだと思います。
早稲田大学文学学術院教授
阿比留 久美(あびる・くみ)
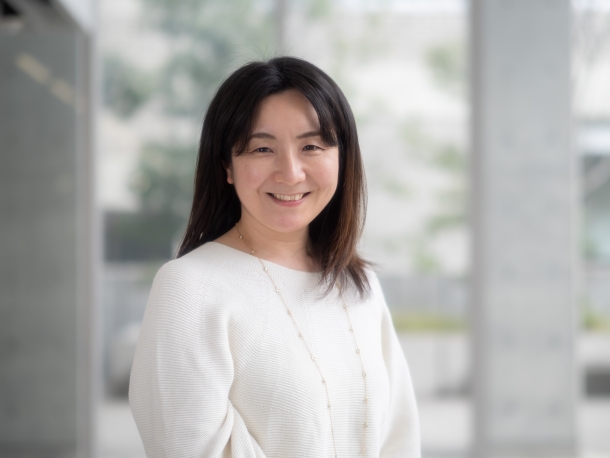
専門は教育学(社会教育、青年期教育論)。
東京生まれ東京育ち。東京大学文学部(社会学)卒業、早稲田大学大学院文学研究科修士課程(教育学)修了、同博士後期課程満期退学。博士(文学)。社会福祉士、精神保健福祉士。これまで十数か所の大学・短期大学・専門学校で非常勤講師を務めたほか、精神障害者の地域活動支援センターでのファシリテーターや、目黒区社会教育委員、かながわNPO映像祭審査員などを経験。早稲田大学文化構想学部准教授を経て2023年4月より現職。著書に『子どものための居場所論』(かもがわ出版)、『孤独と居場所の社会学―なんでもない“わたし”で生きるには』(大和書房)など。
(2023年8月作成)
- Links
- 受験生の方へ
