- ニュース
- 私が今ここにいる理由ーフェミニズムの知をたどって(教育学コース:矢内琴江さん)
私が今ここにいる理由ーフェミニズムの知をたどって(教育学コース:矢内琴江さん)
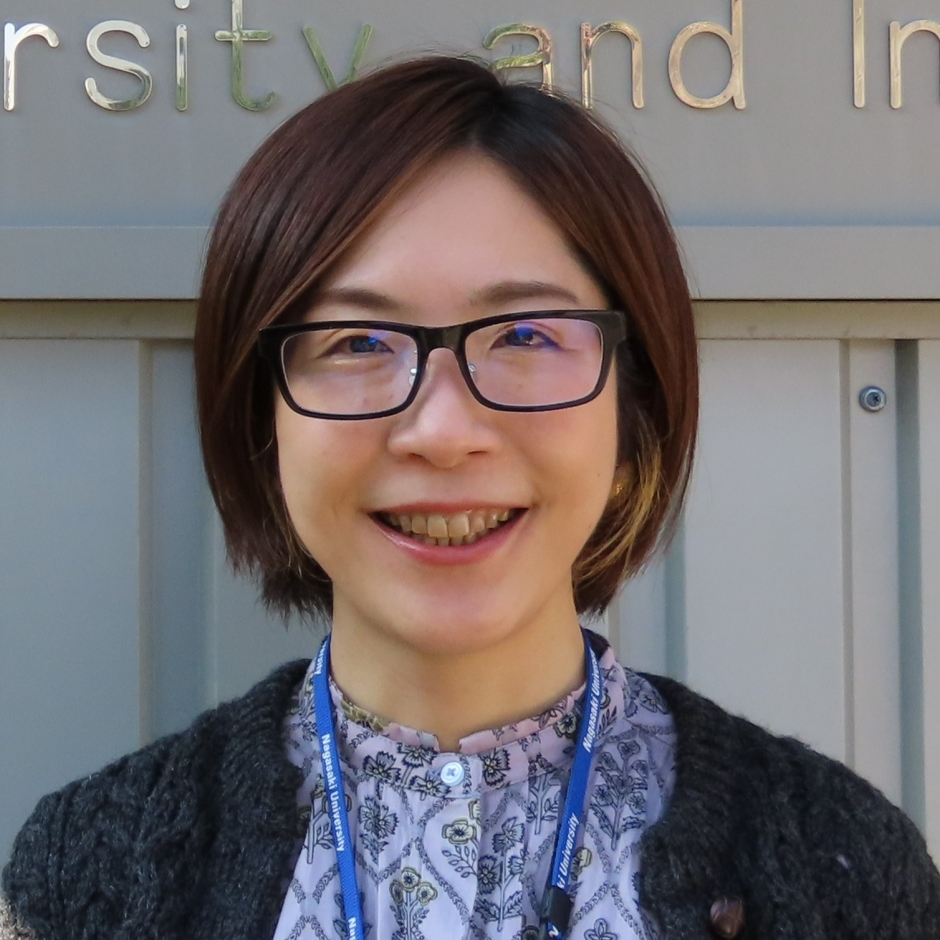
- Posted
- Fri, 04 Mar 2022
矢内琴江(長崎大学ダイバーシティ推進センター・コーディネーター 准教授)
私が教育学コースを志望した理由(研究者を志した理由)
私が教育学コースに入ったのは、博士後期課程からで、2012年4月のことです。それまでフランス語・フランス文学コースの修士課程にいた私が、教育学コースに入ることにしたのは、何よりも、実践を軸にした研究をしたい、実践の中にこそ性差別を克服していく知がある、と考えたからでした。
私は早稲田大学に入学した時から、ジェンダーやセクシュアリティの勉強をしたいと考えていました。そこで、第二文学部に入るとすぐに、このテーマの演習を持っていた村田晶子先生の授業をとりました。そして、色んな個性や経験をもった仲間たちと学んだり、フランスへの1年間の留学を経験しました。修士課程の時、もっと性差別をなくしていくための実践の仕方を学びたいと思い、カナダ・ケベック州の大学に1年間留学し、フェミニズム・スタディーズを学びました。
2010年に帰国後、翌年、東日本大震災を経験します。復興支援活動に携わる中で、支援者自身の中に性差別意識があることに気が付き、そのような意識に無自覚なまま被災者支援を行うことが被災者の皆さんや地域のこれからにとって良いのかと疑問に思ったり、より良い実践を作っていくための活動のあり方について考えたいと思うようになりました。
そこで、性差別を克服していく学習実践のあり方を研究している村田先生の研究室で研究を続けたいと考え、博士後期課程は教育学コースに入ろうと決断しました。
教育学コースの雰囲気、教員・学生との交流
教育学コースに入って、最初に驚いたことは、「自己紹介が長い!」。ゼミの時に、他の院生たちが、自分の研究関心だけではなく、どんな活動をしているのか、どんな経緯があって今ここで学んでいるのかを語っていました。それまで私が経験したゼミでの自己紹介は、自分の研究テーマを一言だけ言うぐらいだったからです。しかし、今ではすっかりこの文化が自分のものになっています。
教育学コースでは、自分ひとりで研究するだけではなくて、院生が協力し合って活動することがたくさんありました。歓迎会や、修了を祝う会、ラウンドテーブル、卒論・修論発表会など、みんなで相談し合って作っていく中で、お互いの研究やその思いについても語り合うことになりました。
研究に関しては、色々な先生方に支えていただきました。論文や発表に関してだけではなく、研究計画の書き方についても指導していただいたり、調査に同行させていただき、研究者としての姿勢を直接見させていただいたり、学会の運営の仕方なども学ばせていただきました。研究を長く続けるための基礎を鍛えていただいたと思っています。
研究にかけた思い
研究を続け、そして様々な人たちと学ぶ中で、強く思うのは、抑圧的な状況を打開していく知は、そのさなかで悩み苦しんでいる人たち自身の中にある、ということです。だからこそ、性差別のない社会をつくっていこう、社会をより良く変えていこうとする実践者たち自身が、自らの実践の道行きを丁寧に記述した実践記録は、私たちの社会の宝だと考えています。「記録に、私たちの社会をより良くしていくための知がつまっている!」。このことを明らかにしたい、そう思って博士論文に取り組みましたし、今も同じ思いで研究を続けています。
修了後、博士後期課程での生活を振り返って
博士後期課程では、研究室の研究活動として取り組んできたこと(東日本大震災の被災者の支援者の支援、対人支援職従事者の研修など)、ひとりの院生として仲間とともに取り組んだこと(学部生・院生の交流会、文研院生研究会、女性研究者のゆるカフェ等)、ジェンダー・セクシュアリティをテーマにした学生たちとのワークショップづくり、色々なことに取り組みました。たくさんの方たちに支えてもらいつつ、仲間たちと何度も相談を重ねながら、「まずはやってみよう!」と、経験できたことが、私の大きな財産になっています。
今、私は大学の中で、多様性の尊重の実現や、女性研究者の支援を行う部署で、コーディネーターであり、研究者として働いています。大学院での経験や、その中で私が深めてきた問題意識などが、すべて今の仕事につながり生きています。
プロフィール
東京都出身。早稲田大学第二文学部社会・人間系専修卒業、同大学大学院文学研究科フランス語・フランス文学コース修士課程修了。修士論文では、カナダ・ケベック州におけるフェミニスト音楽グループの歌がもつエンパワーメントの可能性について研究。博士論文の題目は「ケベックにおけるフェミニズムに関する社会教育学研究-実践コミュニティの意識化と知の生成」。博士(文学)早稲田大学。教育学コース・講師(任期付)、福井大学大学院の特命助教を経て、現在は、長崎大学ダイバーシティ推進センター・コーディネーター/准教授。
- Links
- 先輩紹介ページ

