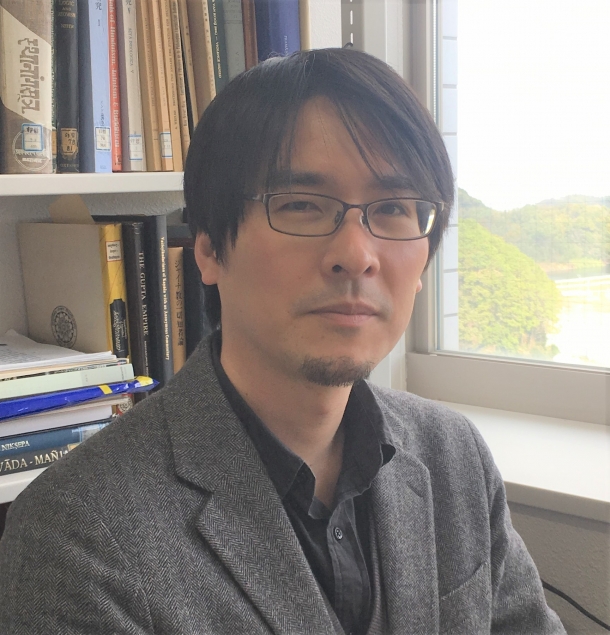- ニュース
- 「知的欲求」に支えられた研究生活(東洋哲学コース:眞鍋智裕さん)
「知的欲求」に支えられた研究生活(東洋哲学コース:眞鍋智裕さん)
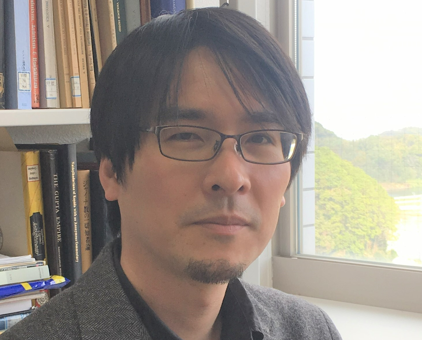
- Posted
- Mon, 14 Feb 2022
眞鍋智裕(北海道大学大学院文学研究院 准教授)
私が早稲田大学の東洋哲学コースを志望した理由
現在専門で研究をしているアドヴァイタ・ヴェーダーンタ学派の研究をしたいと思っていたため、インド思想が学べる東洋哲学コースに進学しました。東洋哲学コースはインド思想のうちでも仏教がメインであったため、インド哲学のゼミのある他大学の大学院に進学するという選択肢もありましたが、指導教員の研究姿勢やゼミのアット・ホームな雰囲気に惹かれ、大学院修士課程・博士後期課程と続けて東洋哲学コースに進学しました。
東洋哲学コースの雰囲気、教員・学生などとの交流
インド思想のゼミでは、指導教員の授業以外にも、仏教文献・バラモン教文献を問わず、様々な古典サンスクリット文献の講読会を、大先輩である非常勤講師の先生を含めゼミ生で行い、自然と先輩が後輩に文献読解の手ほどきを行う体制ができあがっていました。また、学会発表や論文執筆に際しても、指導教員が指導するだけではなく、ゼミ生同士でも積極的に意見交換を行うなど、研究を進めていくのにとてもいい環境でした。さらに、授業や漢文文献の勉強会、また学会をはじめとする東洋哲学コースの様々な行事等を通じて、中国・日本仏教を含め中国・日本思想の諸先生・先輩・同期・後輩とも交流を持ち、中国・日本思想に関する知見をも広げることができました。現在中国・日本思想研究の第一線で活躍されている方々と今でも交流を持ち続けられていることは、私自身が中国・日本に比較的影響の薄いバラモン教・ヒンドゥー教を専門としていることを考えると、大変貴重でありがたいことだと感じています。
研究にかけた思い
私がアドヴァイタ・ヴェーダーンタ学派の研究に従事したいと思ったのは、「もっと知りたいけれども情報が限られている」ので、「それなら自分でやるしかない」と思ったからでした。この学派は、開祖シャンカラに関する研究は膨大な量があるのですが(もちろんだからといってシャンカラ研究が完結しているわけではないですし、また日本語で読める研究は限られています)、特に12世紀の中期以後の研究が薄く、未だ詳細にその展開史を描けない状況にあります。このような状況のなか、謂わば自分の強い知的欲求に従って研究の道を突き進んでいました。加えて、私のようにアドヴァイタ学派に興味を持つ人もいるだろう、そのような人の知的欲求に自分の研究が少しでも応えられるように、ということも思っていました。現在の私の研究推進の動力源も、基本的にはこの頃と変わっていません。なお、具体的な研究テーマとしては、12-13世紀のアドヴァイタ文献を主軸とし、「認識の自己顕照論」の論証方法とその思想史的展開を扱いました。
修了後、博士後期課程での生活を振り返って
在学中ウィークデイの日中は、大学院のゼミのない日は出版社で編集のアルバイトを行っており、ゼミのある日はゼミとその予習で時間を費やしていました。そのため、自分の研究はアルバイトやゼミが終わった後の深夜や休日に行っており、なかなかハードな生活だったと思います。休日でも疲れ切っている時は研究を進めなければと思いつつも寝てしまい、思うように研究に時間がかけられず、自己嫌悪に陥るときもありました。しかし、両親、ゼミのメンバー、アルバイト先の出版社の方々を始めとする周囲の方々の理解や援助もあり、学位を取得することができました。この点、私は環境にとても恵まれていたと思います。しかし頓挫することなく研究を続けられたのは、周囲の方々のおかげもありますが、やはり根底に強い知的欲求があったからであることに間違いありません。いろいろな場面で研究を放棄しそうになり、その都度自分の知りたいことを知らないまま途中で研究を放棄していいのかどうか自問したことが何度もありました。これから博士後期課程に進学することを考えている皆さんも、進学後様々な困難が待ち受けていると思いますが、研究の原点である知的欲求を強固に保ちながら研究生活を送って欲しいと思います。
プロフィール
愛媛県出身。早稲田大学第一文学部東洋哲学専修卒業、早稲田大学大学院文学研究科東洋哲学専攻(修士課程)修了後、同博士後期課程東洋哲学コースに進学。在学中はインドのアドヴァイタ・ヴェーダーンタ学派の教学論証をテーマに研究。博士(文学)(早稲田大学)博士学位論文の題目は「アドヴァイタ・ヴェーダーンタ学派における自己顕照論の展開」。修了後は、早稲田大学文学学術院非常勤講師、日本学術振興会特別研究員PD(九州大学)、早稲田大学高等研究所講師を経て、2021年4月から北海道大学大学院文学研究院准教授。現在は後期アドヴァイタ・ヴェーダーンタ学派の神学理論やバクティ思想の研究を行っている。
(2022年2月作成)
- Links
- 先輩紹介ページ