- 学部について
- 学部長挨拶
From the Dean
学部長挨拶
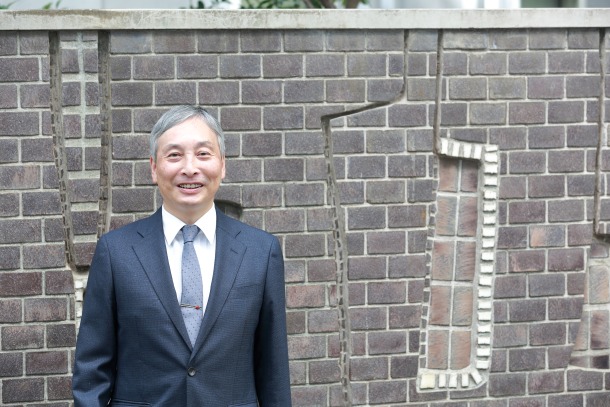
文化構想学部長 柳澤 明
文化構想学部が誕生したのは2007年のことです。その4年後、2011年3月に、東日本大震災直後の緊迫した状況の中で最初の卒業生を送り出してから、すでに10年以上が経ちました。学部立ち上げの直後は、「文化構想」という聞きなれない名前が認知してもらえるかどうか、受験生が集まるかどうか、ずいぶん気をもみました。しかし、年を経るにつれて学部名も次第に定着し、心配はなくなったようです。また、学生の気質も、──簡単に決めつけてしまうのは乱暴ですが──「真面目な」文学部に対して、「明るい」文化構想学部という、そこはかとない違いが生まれてきているように思えて、興味深いです。
文化構想学部発足以前の戸山キャンパスには、第一文学部(昼間)と第二文学部(夜間)の二つの学部がありました。現在の文学部のコース構成はおおむね第一文学部の「専修」(当時はこのように呼んでいました)を引き継いでいるので、文化構想学部は第二文学部の後身のように思われる向きもありますが、そうではありません。たしかに文化構想学部は、多くの社会人学生が集っていた第二文学部の自由闊達な雰囲気を受け継いでいる面もありますが、カリキュラムの組み立てなどは大きく違います。また、第一・第二文学部時代は、教員は基本的に第一文学部のいずれかの専修に所属し、同時に第二文学部の授業を担当する形でしたが、現在は教員が両学部にはっきりと分かれ、それぞれの学部の教育により大きな責任をもって当たる体制になっています。
さて、文化構想学部に関して、一つおもしろいことがあります。学部の英語名称は“School of Culture, Media and Society”で、「文化構想学部」とはまったく違います。特に驚くのは、「構想」に当たる言葉が影も形もないことです!では、どちらがより「正しい」名前なのでしょうか。実は私にもよくわからないのですが、あえて想像すれば、二つの名前は、学部の特徴を異なる角度から表現しているのだろうと思います。“Culture, Media and Society”は、よく見れば、6つの論系が扱う教育・研究分野を、2つの論系を一組にして表していることに気づきます。つまり、現実の文化構想学部の姿を端的に示しているわけです。一方、「文化構想」は、学部の実態というより、この学部での学びを通じて、過去や現在のさまざまな文化に思いを馳せ、あらたな文化を創り出す存在になってほしい、という願望・理想を表しているのでしょう。要するに、どちらも正しいということですね。
