- ニュース
- 「歳をとれば また踊りたく なるかしら」文化構想学部 中島那奈子准教授(新任教員紹介)
「歳をとれば また踊りたく なるかしら」文化構想学部 中島那奈子准教授(新任教員紹介)
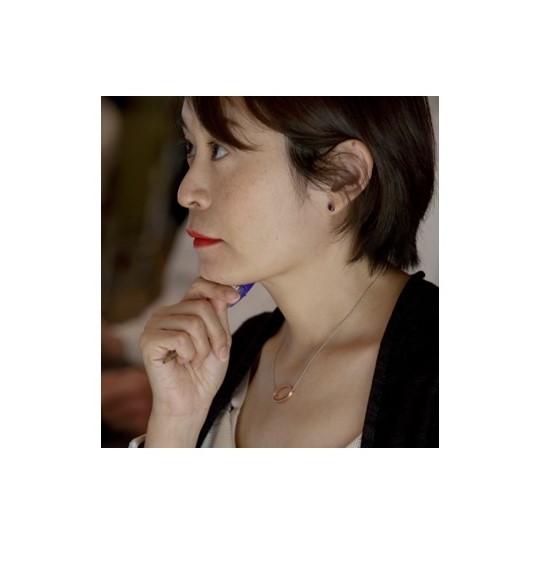
- Posted
- 2024年6月17日(月)

ⒸTAIFUN
<東京からNYへ>
私はダンスの研究をしています。そのなかでも、ダンサーが歳を重ねること(エイジング)がどのようにそのダンスに関係するかを、さまざまなジャンルや文化において考えてきました。また、そのダンスの研究をダンスの作り方に活かすドラマトゥルクという仕事も行ってきました。この二つは、私のこれまでの生い立ちから出てきたものなので、自己紹介と共に説明します。

中島那奈子初舞台
私は3歳から日本舞踊の稽古をしていました。
言葉を習う前から身体の動きを習っていたために、動きには言葉で言い尽くせないたくさんの情報があると感じています。学生時代は日本舞踊だけでなく、ジャズダンスや歌舞伎、能などもこっそり学んでいたのですが、大学では演劇学を勉強していました。ただ、日本舞踊の師範となり私よりも年齢が上の方を教えるような立場になると、自分の若さでは踊りきれない演目があることを実感するようになりました。年齢を重ねるごとに、その人の人生がにじみ出てくるような踊り。それが20代の自分には超えられない大きな壁のように感じていたのと、伝統芸能の世界や日本の大学での学びを超えるものを探して、ニューヨーク大学大学院に進学しました。そして、パフォーマンス・スタディーズという文化人類学と演劇学を組み合わせ、実践と研究を統合させるアメリカ的な考え方にどっぷりハマった3年間を過ごすうちに、ダンスドラマトゥルクの第一人者であるアンドレ・レペッキ教授の授業の一環で、ドラマトゥルクという仕事をするようになりました。ドラマトゥルクとは、演劇やダンス、パフォーマンスを作るときに専門的知識を駆使して、作り手をサポートする仕事です。もともとは18世紀のドイツで誕生した仕事ですが、現在は欧米やアジアの多くの劇場や芸術祭、大学で活躍するドラマトゥルクが生まれていて、日本でも制度化が期待されるものです。
ドラマトゥルクの仕事をNYのコンテンポラリーダンスの分野で始めた途端に、私は数少ないドラマトゥルクとして売れっ子になってしまい、3ヶ月に一つの新作を手がけるハードなスケジュールを送るようになりました。振付家のチャメッキ・レルナー、トラジャル・ハレル、クシルジャ、スズキメソッドなど日本の身体技法を使う演劇作品、そしてその中でもルシアナ・アギュラーとのダンス作品は2006年のNYダンス・アンド・パフォーマンス・アワード/ベッシー賞を受賞しました。ただ、創作現場で働くうちに、さまざまな問題が浮かび上がってきました。日本のダンス界とちがって、NYではダンサーとして年齢を重ねることが喜ばれず、若さや強さや新しさが面白さの基準になっていました。ただ、日本と違って、アメリカには全員が加入できる国民健康保険がありません。そのため、駆け出しの若いダンサーは、自分で高い保険料を払えないため、怪我をしたら高額の医療費がかかって一大事になってしまいます。そのため、みな私と同い年くらいでも、もう歳をとって怪我をして動けなくなるかも、と心配ばかりしていました。そして、私が「老いと踊り」というテーマを発表し始めた時、周りのダンサーや研究者はみな、ものすごい剣幕で怒り出しました。なぜそんな嫌なテーマを話し出すのかと!
そんな中で、ドラマトゥルクとして自分には専門的知識が十分ではないと感じるようにもなりました。修士課程を終えて、ドラマトゥルクの仕事を見よう見まねで行なっていたので、きちんとした訓練を受けたいと思い、NYのアパートを人に貸したまま、数ヶ月ヨーロッパへ放浪の旅に出ることにしました。よりダンスの実験的な作品が作られるヨーロッパで、ドラマトゥルクの訓練と博士論文の執筆を行いたいと、各地のドラマトゥルクを探し出して話を聞き、また舞踊学を教える大学研究者に片っ端から連絡をとり、会いに行きました。そこで、私が次に行くべきところは、国による莫大な助成金がおり、おそらく今後ダンスがますます盛り上がるはずのドイツの首都、ベルリンだと見定めました。
<ベルリン時代>
ドイツ語が全然できない私がドイツに留学できたのは奇跡だったのですが、NY の劇場ジャパン・ソサエティでの公演初日があけた翌日、NYからドイツに引っ越しました。まずはじめの4ヶ月はライプチヒという旧東ドイツの小都市で、ドイツ語の集中語学研修を受けました。それが思わず、ドイツ語以外の言葉を日常生活でも話してはいけないというスパルタ教育でした。大学入学資格試験に合格するまでとはいえ、各国から集まってきた留学生たちに囲まれ、楽しみながらも猛烈な勉強の日々を過ごしました。ベルリンの大学院に入ってからは、それまで以上に大変で、ドイツ語の授業も高度で苦労はつきませんでした。ただ、ベルリン自由大学の指導教授である舞踊学のガブリエレ・ブラントシュテッター教授や演劇学のエリカ・フィッシャー=リヒテ教授の周囲には、おおくの優秀な学生や研究者が集まってきていて、毎週のように関連したシンポジウムが開かれ、街中でも毎日のようにダンスの公演があり、ヨーロッパの歴史と文化の厚みと広がりを体感する時期でした。また、若さをうたうNYのダンス界とは異なるものの、ベルリンでも、ダンサーの老いを見ないようにしてきた制度と記憶があることに気がつきました。50歳を超えるダンサーは、日本から来る暗黒舞踏のダンサーを除いて、ドイツには存在しませんでした。少子高齢化が急激に進んでいたドイツでは、この「老いと踊り」というテーマは、驚きをもって受け入れられました。
私の専門分野であるダンス研究での「老いと踊り」は、このように、東京からNY、そしてベルリンへと私が移動してきた中で生まれてきたテーマです。

ドイツ・ベルリン自由大学で同時期に博士号を取得した友人カトリネル・クラシウムさんと

ベルリンWG(シェアハウス)の様子
<アジアそして京都で>
博士論文を書き終えてからは、ベルリンと東京、京都で研究を続けていました。この時期に私は「老いと踊り」という研究テーマを書籍にするだけでなく、このテーマをベルリンと東京での国際ダンスシンポジウムとして開催し、多くの人がアクセスできるようにしていました。そこでは、このテーマに関連するワークショップやパフォーマンスも上演しました。その中で、日独を橋渡しする障がいとダンスの作品「劇団ティクバ+循環プロジェクト」(振付家:砂連尾 理さん)を立ち上げたり、アジアでドラマトゥルクの仕事をしたりする機会に恵まれました。シンガポールの演出家オン・ケンセンさんとのダンスアーカイブボックスの作品や、北京のメンファン・ワンさんとの引退したバレエダンサーの作品は、この時期に行なったものです。また、京都芸術劇場春秋座を使った、「老いと踊り」研究としてのパフォーマンスも発表していました。京都では、喜多流能楽師の重鎮である高林 白牛口二さんと出会い、継続してじっくり作業をする幸運に恵まれました。高林さんを通して、能で寿がれる老いを、ダンスに応用する回路がひらけてきたのです。

「イヴォンヌ・レイナーを巡るパフォーマティヴ・エクシビジョン」でのTrio A 京都芸術劇場春秋座、2017年 写真:前谷開
どのような空間と時間に、どのように動く身体を位置付けるかが、ダンスの基本です。ダンスの研究は、誰もが持っている自分の身体を起点にして、そこからアイデンティティや歴史、環境や社会との政治的な問題を考える、とても刺激的な分野なのです。私はどこからきて、誰であるのか、そしてどこへ向かうのかという人文学での大きな問題を、自分の動く身体から考える、その醍醐味とスリルをぜひ味わってください。
プロフィール
なかじま ななこ。東京都出身。ベルリン自由大学で博士号(舞踊学)取得。老いと踊りという研究分野を切り拓き、創作を支えるドラマトゥルクの先駆者として国内外で活躍し、2017年アメリカドラマトゥルク協会のエリオットヘイズ賞特別賞受賞。日本学術振興会特別研究員-PD、ベルリン自由大学国際研究センター「インターウィービング・パフォーマンス・カルチャーズ」フェロー、ベルリン自由大学ヴァレスカ・ゲルト記念招聘教授2019/2020を経て、2022年よりカナダバンフセンターでファカルティ・ダンスドラマトゥルク(教員)を務める。近年の活動に2022年Kyoto Experiment 京都国際舞台芸術祭「フォーエバーポストモダンダンス」レクチャーや東京芸術祭Farm-Lab Exhibition のメンターがある。
老いと踊りの研究も並行して進め、その研究をパフォーマンスにする企画に「イヴォンヌ・レイナーを巡るパフォーマティヴ・エクシビジョン」(京都芸術劇場春秋座2017)、老いた革命バレエダンサーの作品(演出・振付メンファン・ワン、烏鎮演劇祭2019)、「型の向こうへ」(コラボレーター、能楽師高林白牛口二ら2022)がある。共編著にThe Aging Body in Dance (co-edit. by Gabriele Brandstetter, Routledge, 2017)、『老いと踊り』(共編外山紀久子、勁草書房、2019年)。2020年にはドイツベルリン芸術アカデミーで「ダンスアーカイブボックスベルリン」を上演。ダンスドラマトゥルギー普及のための日英情報サイトを開設し、2024年3月に日本で初めてとなるドラマトゥルク・ミーティングを開催した。
関連記事「専門知識基に舞台創作をサポート 異なる立場で作品に目を 「ドラマトゥルク・ミーティング」初開催」毎日新聞 2024/4/10 東京夕刊

写真:大曾根麗奈
- 新任教員紹介は、研究紹介・アウトリーチからご覧いただけます。


