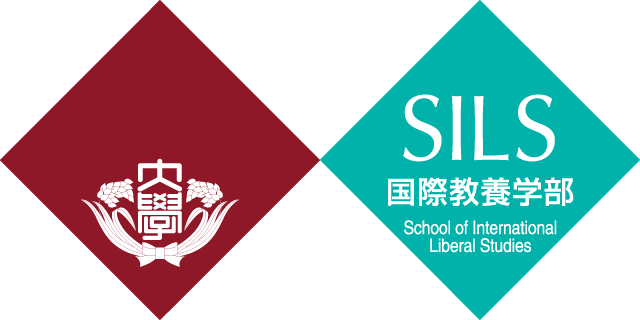- ニュース
- 【卒業生インタビュー】木藤 寛敬(KITO, Hirotaka): SILSから医療の現場へ
【卒業生インタビュー】木藤 寛敬(KITO, Hirotaka): SILSから医療の現場へ

- Posted
- Tue, 03 Oct 2023
 学校法人花園学園 花園高等学校 2010年3月卒業
学校法人花園学園 花園高等学校 2010年3月卒業- 早稲田大学国際教養学部 2015年9月卒業
- 滋賀医科大学医学部医学科 2021年3月卒業
- 京都民医連中央病院 勤務 2021年4月~
- 稲門医師会 理事就任 2021年11月
SILSを卒業後に地元・関西で医学部に編入し、現在は医療現場で活躍されているというユニークな経歴をお持ちの木藤さん。初期研修医としての現在のお仕事、進路選択やSILSでの学びについてお話を伺いました。
― 現在はどのようなお仕事をされているのですか。
私は現在地元である京都市内の病院で初期研修医をしています。地域の中核病院で、内科・外科・整形外科・小児科・産婦人科など様々な診療科を1・2か月ごとに周りながら、指導医の先生と一緒に患者さんを診察し、本人・ご家族への説明、他の医療スタッフ(看護師、薬剤師、リハビリスタッフ、医療ソーシャルワーカーなど)との情報共有・カンファレンスを行いながら、検査・治療方針の決定に携わっています。また、週に1回の救急当直を行い、病院に救急車で運ばれてくる患者さんなどの初期対応を行なっています。

京都民医連中央病院のスタッフのみなさんと
― 現在の進路を選択した経緯を教えてください。
もともと理系分野に対して強い興味はなかったものの、母が管理栄養士として病院で働いていたこと、人と直接関わる仕事がしたいという気持ちがあったことから、医学へ関心を持ちました。高校在学中に高校生を対象とした一日医師体験に参加をしたことをきっかけに本格的に医師という職業を目指したいと考え始めたものの、医学部への進学は叶わず、一度大学に進学し幅広い選択肢を検討してから本当に自分が医師になりたいのかを見つめ直そうと2011年に早稲田大学国際教養学部に進学しました。
入学後は大学で様々な分野の授業を受け、いろいろなことに取り組んでいる学生と接し、座禅サークルで活動したり、病院でのボランティアなども経験しました。その間も医学部受験は継続していましたが残念ながら合格は叶いませんでした。1年間のリトアニア留学から帰ってきて就職活動などが現実的な選択肢となっても「やっぱり医師になりたい」という強い思いが消えず、卒業後、大卒者(見込み含む)を対象とする医学部学士編入試験を受験し、幸運にも滋賀医科大学医学部に合格することができました。
正直に言うと、大学在学中に医学部受験に失敗する度に、何度も挑戦をあきらめそうになったり、就職や大学院への進学を考えたりもしました。国際教養学部の学生の多くは、卒業後医師になる道を選ばないため、医学部受験は辛く孤独でしたし、成功するまで何かを続けるという決断は、他のチャンスを逃す可能性もありました。しかし、それでも自分が諦めなかった理由は、模試やセンター試験では、ある程度医学部に合格できる手ごたえがあったこと、また、自分が本来やりたことではない就職活動や大学院進学のために努力をすることに疑問を感じたためです。やりたいことをやってみないと後悔するのはいつの時代も同じで、失敗しても挑戦することから逃げなかったことで経験が得られ、結局は自分の決断に納得できるものです。成功するまで時間がかかったり、何度も失敗することもありますが、成功するために必要なのは失敗しても諦めない気持ちだと思います。
― SILSでの学生生活と受験勉強の両立は大変でしたか?
早稲田大学在学中には、座禅サークルの先輩や同級生、国際教養学部の職員さん、ゼミの先生など色んな人に医学部進学を応援して頂きました。入試シーズンが近い時は座禅サークルの先輩や同級生が仕事を肩代わりしてくれたり、受験勉強を継続し成績不良者で呼び出されてしまった際も面談担当の先生や職員さんに事情を話すと理解して応援してくれました。ゼミでお世話になった稲葉先生には、当時受験のため留学を延期しゼミにも所属せずに授業だけ履修している私を、ゼミに招いてくださり、おかげで新しい仲間や居場所を得ることができました。稲葉先生には、適宜相談に乗ってもらいながら、編入試験に必要な推薦書なども書いていただきました。
― 今振り返ってみて思うSILSの強みや魅力はありますか。
国際教養学部では、国際関係論、アメリカ政治、イスラム教、シェイクスピア文学、微積分、天文学、脳科学など様々な分野を横断的に学び、留学先のリトアニアでは有機化学や電磁気学などの講義や実習を受けました。これだけ広い学問領域を専門に縛られることなく、自分の興味に任せて好きに学習できる環境はあまりないと思います。さらに海外からの留学生と共に学び、自らも留学することでいろいろな文化や価値観に触れながら、自分自身の物事を考える土台を形成できるのは大変魅力的だと思います。また、国際教養学部では日本で最大規模の海外留学ネットワークを駆使して、世界のさまざまな国に留学することが可能であり、留学中の取得単位を大学卒業単位に互換できるのは大きな強みであると思います。

在学中はリトアニアVilnius Universityへ留学。
― SILSでの学びと、今の仕事にはどのような関係性がありますか。
医師として診療に臨む上で、当然ながら患者さんは医療従事者でないことがほとんどです。普段は医療以外の分野で学ばれたり、仕事をしている患者さんの背景を想像する必要があり、私の中では国際教養学部で学んだリベラルアーツがその強い土台となっていると感じています。医学だけに止まらず、様々な分野の考え方や世の中の仕組みを知ることで、患者さんそれぞれに置かれている職業や家庭の環境、持っている価値観などに配慮しながら診療にあたる手助けとなっています。私は将来小児外科医になりたいと考えていますが、国際教養学部で学んだ英語や海外でのコミュニケーション能力を活かし、ゆくゆくは東南アジアなどでの国際医療活動にも挑戦してみたいと思っています。
近年、COVID-19によって医療の世界にも大きな変化がもたらされました。国内外の学会はオンライン開催やzoomと現地のハイブリット開催がスタンダードとなり、日本国内でもオンライン診療やマイナンバーカードと保険証の一体化や医療機関への保険診療情報の提供など、今まで患者のプライバシー保護の観点などからなかなか進まなかった医療のICT化が急速に進んできています。従来医師の知識や経験に大きく左右されてきた診断領域もAI診断が導入されつつあり、単純な知識量や経験年数だけでは医師の能力は測れなくなってきました。また、手術支援ロボットであるda Vinciの適応疾患の拡大など新しい医療技術の出現と診療環境の変化が次々と起きています。
医学部で学んだ知識は数年もすれば古くなり、常に情報をアップデートしながら環境の変化についていく必要があります。これからは、新しい医療技術や知識を柔軟に吸収し、医療を取り巻く環境が変わり続ける中で、今までのパターンにただ当てはめたり杓子定規にガイドラインに沿うのではなく、個々の患者さんにとって最適な医療を提供できる人材が求められると思います。国際教養学部で学んだ多様な考え方は、環境の変化に適応しながら、自分の頭で考え続けられる能力を涵養するのに大きく役立つと思います。
― 現在の仕事について、どのような点にやりがいを感じていますか。
現在、医師として働く中で、患者さんの命に携わる責任は重く、時に十分に時間がない状況でも適切な判断を求められるため、どっと疲れを感じることはありますし、一生懸命頑張っていても残念ながら亡くなってしまう患者さんもいます。しかし、自分が真摯に患者さんや家族と向き合い、「この人が今一番困っていることは何か?」「退院したら家に帰るのか、それとも施設にいくのか?」「大切にしている価値観は何か?」など医学だけでなく、心理社会的な側面まで考慮しながら「じゃあこの人にとって最適な医療は何か?」を他の医療スタッフや本人・家族と相談し模索し続けることが大切だと考えています。
その結果、いつもとはいきませんが、治療法や退院後の生活に対する患者さんの不安が軽減されたり、希望を叶えることができたりします。例えば高齢で全身状態が悪く回復が見込めない中、「家で最期を過ごしたい」という患者さん・家族の希望に沿って、病院での全身管理や在宅スタッフとのカンファレンスを行いサービス調整を行った結果、退院後に家族から「おうちに帰った後に少し元気になり、誕生日を皆に祝われた後に、安らかに亡くなりました。先生どうもありがとうございました」と言ってもらえた時は、「ああ、頑張って良かったなぁ」としみじみと感じました。このような経験によって医師という職業につくことができて本当によかったと感じていますし、自分が医師になるために下してきた決断は間違っていなかったのだと実感することができています。
― 最後にSILSを目指す受験生のみなさんにメッセージをお願いします!
国際教養学部には多様な選択肢と可能性があります。卒業後一般企業への就職だけでなく、海外の大学院への進学や、私のように医学部に編入し医師になる人もいます。今の時点で自分が何をしたいのか分からなくても構いません。むしろ将来に対して明確なビジョンを持っている人の方が少ないでしょう。国際教養学部で、自分の興味のある分野を授業で取ってみたり、留学生と交流し日本以外の文化や価値観に触れ、海外留学を経験し不測の事態にも対処するレジリエンスを獲得しながら、ゆっくりと自分の進みたい方向性を見出し挑戦してみましょう。国際教養学部の環境はその挑戦を全力でサポートしてくれるはずです。
掲載情報は、取材時点のものになります。