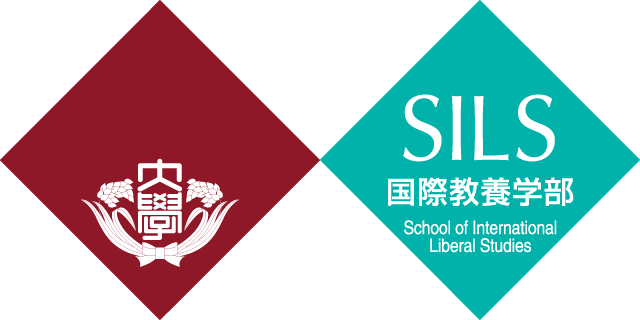- 学部について
- 学部長挨拶
From the Dean
学部長挨拶
学部長からのメッセージ
Message from the Dean
早稲田大学国際教養学部長 稲葉知士

国際教養学部は、早稲田大学の創設者である大隈重信が掲げた「早稲田大学教旨」に基づき、世界に貢献するための基礎を築き、世界に貢献する方法を模索するとともに、世界に貢献する学生を育てることに全力を注いでいます。具体的には、物事を俯瞰的に捉え、様々な可能性を考え、定量的に思考し、多様な価値観を共有しながら、世界のために何かできるか考え、自分の選り好みの判断を超えた地球上に生きる一人の人間として、世界にとって最善な行動ができる学生の育成を目指しています。
国際教養学部は、2004年に早稲田大学で初めて英語のみで学士号を取得できる学部として設立され、2024年に創立20周年を迎えました。日本語を母語とする学生には1年間の留学を義務づけており、毎年数多くの学生が世界各地の大学へ旅立っています。早稲田大学は、1899年より積極的に留学生を受け入れ、1905年に清国留学生課を設置しました。現在の国際教養学部は、入学する学生の約3割が世界各国から来日した留学生で、日本人学生と4年間、切磋琢磨し活発な議論を交わしています。また、世界各地の協定校から毎年約300名の交換留学生が学部に加わり、世界での活躍を目指す多くの機会に触れる貴重な経験となっています。
学部教育は、特定の分野に特化しないリベラルアーツ教育が特徴です。学問分野を7つの異なるクラスタに分類し、まずは様々な学問分野における初級科目をいくつかのクラスタから履修して、それぞれの学問分野の知識を吸収し、学問間の横の繋がりを構築します。その後、中級、上級科目、さらにはコンセントレーションを履修することで、それぞれの学問分野の縦の繋がりを強化して専門性を高めます。このような知識の横編みと縦編みの教育体系を実施することで、すべてについて何事か知り、何かについてすべてを知る学生を育てます。また、少人数制の基礎・中級・上級演習では、白と黒のどちらがいいのかという単純な二項対立で解けない問題に対して、意見を出し合い、それぞれの意見のメリット・デメリットを整理し、その時点でのベストアンサーを探す訓練をしています。議論には定量的な視点が重要なので、その能力を高めるために入門統計学と入門データサイエンスを必修科目としています。大隈重信も統計学の重要性を認識し、統計院を設立し、統計院長に就任しました。また、学部教育や留学に対応するため、英語4技能を強化するプログラムを実施し、アカデミック・ライティングについて学ぶ機会を提供しています。さらに、講義科目の課題を通じてアカデミック・ライティングのトレーニングを行い、学生それぞれの専門分野で卒業論文を完成させます。
国際教養学部は、時代の変化に応じて常に改革を続けてきました。2016年にスタートした、リベラルアーツ教育の中で専門性を高めるための「コンセントレーションプログラム」、2017年にスタートした、フランス語、スペイン語、中国語、韓国語の言語習得と各国の文化、歴史、経済、政治などを多面的に学ぶ「APMプログラム」および、2025年からスタートした「入門データサイエンス」の必修化など、その内容は多岐にわたっています。
今後も、学生のニーズや時代の変化に対応した改革を進めていきます。未来の世界のリーダーとなる学生の教育に、より一層力を注いでいきたいと考えています。