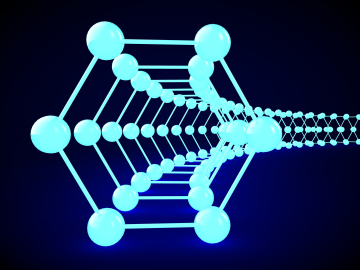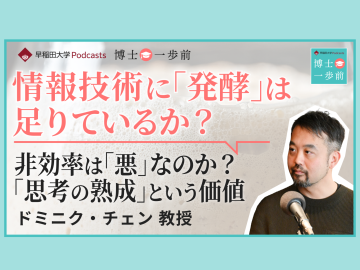早稲田大学重点領域研究機構持続型食・農・バイオ研究所「医食同源の暮らし革命」グループ(主査:理工学術院竹山春子教授)は、株式会社吉野家ホールディングスとの食事と健康科学に関する共同研究の一環として、早稲田大学生活協同組合協力のもと、早稲田大学学生を対象に1日限定200食で牛茶飯を提供します。
「医食同源の暮らし革命」グループは、消費者の意向に基づいた食材を、科学的な検証を伴いながら流通させる実践的なアプローチとして、時間栄養学に着目した機能性食品の開発、安心・安全な食材供給の実現、さらには健康に資する食品の製造・管理システムの開発をおこなうことを課題としています。
本イベントでは、「紅茶の摂取が食後の血糖値上昇を抑制する」という知見(内田 菜穂子、吉本 奈央、仲村 麻恵、髙木 亜由美、本田 佳代子、本 三保子、鬘谷 要、橋詰 直孝:マウスおよび健常女性に対する紅茶の食後血糖上昇抑制作用 臨床栄養協会誌 28(4) p11-19 2013年)より、紅茶の機能性を活かした紅茶含有食品の展開として、日本人の食の基本である米飯に着目し開発した茶飯を提供します。米飯の成分のほとんどが糖質であり、紅茶には糖質の消化を穏やかにする効果があることから、紅茶の茶飯は紅茶の機能性を効率的に利用することができると考えられます。しかし、機能性を重視するあまり食味が好ましくない食事は継続的な摂取が困難であるため、茶飯の食味に関する検討が必要です。また、厚生労働省の平成25年国民健康・栄養調査によると、朝食の欠食率は男女ともに20歳代で最も高く、男性で30.0%、女性で25.4%と報告されています。栄養学、時間栄養学の面から朝食の重要性が示されており、朝食欠食率の低下が一つの課題とされています。
これらの背景から本イベントでは、朝食欠食率が高い年齢層である大学生を対象に茶飯を用いた朝食を提供し、朝食摂取による生活習慣改善効果の検討および茶飯の食味に関する調査を行います。学生の生活習慣を調査することで、学生の健康の維持に必要な課題を見出し、加えて、紅茶を用いた茶飯という新しい食品の食味に関する調査をすることで、機能性を付加し、かつ食味の良い茶飯の開発につながることが期待されます。
早稲田大学重点領域研究機構持続型食・農・バイオ研究所
世界的な人口の急増、気候変動、食生活への量的、質的要求度の増大などの社会的要因に加え、TPPに代表される政治、経済、外交などの制度的要因により、我が国の農業は今、大きな変革期を迎えています。こうした背景を受けて、早稲田大学では社会科学・自然科学分野の研究者が連携し、「食」と「農」、「バイオ」を包括する研究プラットホームとして、「持続型 食・農・バイオ研究所」を2014年4月に設立し、農業の担い手、IT化、里山の環境、機能性食品、時間栄養学、自然エネルギーなど幅広い研究を実施しています。
実施概要
- 実施日時:2016年1月14日(木)15日(金)18日(月)19日(火)20日(水)各日の8:00~8:45
- 場 所:西早稲田キャンパス56号館理工カフェテリア 新宿区大久保3-4-1
- 内 容:早稲田大学生活協同組合協力のもと、早稲田大学学生を対象に1日限定200食を無料で提供。メニューは、茶飯(紅茶で炊いたご飯)、生野菜サラダ、牛皿(牛皿、豚皿、牛すき皿(吉野家提供の冷凍商品を調理したもの)を日替わりで提供)。食事後、牛茶飯の味、時間栄養学(体内時計と栄養の関係学問)の視点を取り入れたアンケートを実施。※好評につき19日(火)20日(水)は、それぞれ120食増の320食を提供いたします。
本件に関するお問い合わせ先
早稲田大学持続型食・農・バイオ研究所事務局(早稲田大学アカデミックソリューション内)
電話:03-3208-0102 メールアドレス:[email protected]