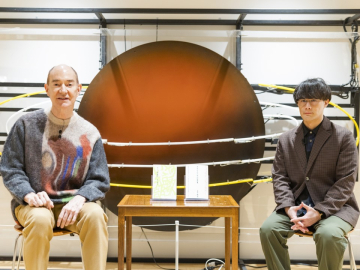7月9日と10日の2日間にわたり、早稲田大学総合人文科学研究センターが、シカゴ大学のマイケル・K・ボーダッシュ教授をお招きして、日本のポピュラー音楽や夏目漱石に関する連続講演を開催しました。学生、教職員をはじめ、多くの方々が日本近代文学研究の第一人者であるボーダッシュ教授の講演を熱心に聞き入りました。

1950年:「東京ブギウギ」が太平洋を渡った年
講演初日は、戦後における日本のポピュラー音楽と冷戦や日系アメリカ人との関係がテーマでした。ボーダッシュ教授は、1950年にカリフォルニア州サクラメント市で行われた美空ひばりのコンサートの録音が数年前に発見されたことを紹介し、実際にその録音を流しながら、その意義について論じました。
3年前に録音機収集家のDieter Hollander氏からメールを受け取ったことが、ボーダッシュ教授の研究の発端でした。Hollander氏は1950年にサクラメントで行われた日本人歌手によるコンサートの録音を入手しており、その中には1920年代と1930年代の流行歌、ブギウギソング、そして戦時中のプロパガンダ歌謡である「大陸歌謡」が収録されていました。ボーダッシュ教授は終戦から5年しか経ていない1950年のアメリカで、「大陸歌謡」が歌われていたことに非常に驚いたと述べました。

いったい誰が録音したのか。それは2013年まで不明でしたが、日本で放映されたスペシャル番組がきっかけとなり、ボーダッシュ教授のもとに当時のコンサートでサウンドボードを担当していた日系アメリカ人のアーサー・コバヤシさんから連絡がありました。コバヤシさんはジミー・アキダ・マツフジさんのもとで演奏を担当しており、アキダ・マツフジさんがコンサートを録音していたことがわかりました。コバヤシさんは今回の講演にも参加し、コンサートの思い出と強制収容所で過ごした日々について語りました。
最後にボーダッシュ教授は、「ミメーシス」(模倣)という概念を用いて、冷戦下におけるポピュラー音楽の意義を解説しました。教授は、植民地主義における「ミメーシス」に関する人類学者Michael Taussigの議論を引用しながら、植民する側と植民される側がお互いに模倣する過程を通して、各々のアイデンティティを形成していく様相について語りました。
「今回発見された1950年のサクラメントでの録音を見れば、どのようにして帝国日本の一部であった『ミメーシス』が、冷戦の一部としての『ミメーシス』に変わっていったかを見ることができます。山口淑子というひとりの歌手が1930年代には李香蘭、1950年代にはShirley Yamaguchiと名乗るようになる過程や、美空ひばりが笠置シヅ子やDinah Shoreの模倣から始まり、やがて偉大な演歌歌手として頭角を現していく過程に、私たちは帝国日本が冷戦期へと推移していく、いくつかの道筋を見て取ることができます。このように、ポピュラー音楽の研究対象としての価値は、それが時代の変化を測る手段、欲望と模倣の歴史的断続の過程を跡づけるきわめて緻密な手段を、私たちにもたらしてくれる点にあるのです。」

崖の下の家、影の中の人――夏目漱石『門』と意識の流れ
2日目の講演では、夏目漱石の『門』における意識の流れが論じられました。講演は日本語で行われ、ボーダッシュ教授は、ウィリアム・ジェームズ等の心理学や、私有財産制度の導入などの明治日本の近代化が、漱石の作品に与えた影響について説明しました。
教授は、作品の本文を実際に読み上げながら、日本における帝国主義、資本主義の発展、そして主人公宗助の過去などを含みこんだ「影」の比喩を例に挙げて、『門』における「影」の意味や心理学との関係について考えるよう、聴衆に促しました。そして、心理学の観点から、「影」は漱石において、過去から現在、未来へと至る意識の流れを阻害し、停滞させるものであると述べました。さらに、「影」の英訳が「shadow」「phantom」「light」「illusion」等、複数にわたることを取り上げ、『門』における様々な「影」には、それらの英訳がすべてあてはまると解説しました。

また、教授は、漱石が文学を科学的に定義することを目的として『文学論』を書き上げ、普遍的な文学理論を構築しようとしたことや、そのためには社会学や心理学の視点が必要と感じていたことを紹介し、その際、ロンドン留学中に触れた「新心理学」の影響を受けただろうと述べました。そのうえで、『文学論』において定義された(F+f)という公式と『門』、「影」、心理学との関係について語りかけ、この公式について詳細に述べながら、焦点的印象または観念を表すFと、これに付着する情緒を表すfについて解説しました。さらに、社会学や心理学の言説を参照しつつ、漱石にとって文学の価値はFとfを同時に表現できる点にあったと指摘しました。教授は『門』のいくつかの場面に言及しながら、(F+f)によって形作られた「意識の流れ」について説明し、講演を締めくくりました。