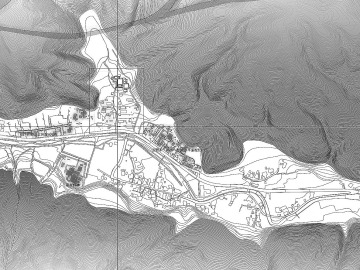ディテール・モデルと建築のアンチ・ユートピア
鈴木了二(2007年度紀要AARRより)
もしも建築がひとつの物質でひと繋がりにできているなら、ディテールは原理上存在しない。そのどこかに開口が穿たれ、サッシュやガラスのような別種の物質が嵌め込まれるとき、あるいは、マッスのどこかに穴が穿たれ、そこに階段のようなものが現れるとき、好むと好まざるとにかかわらずディテールが発生する。きっかけはなんであれ、複数の物質が集まってくることによって起る出来事がディテールであり、また逆に見ればそこは物質が分節化され、切断される場所がディテールである。
したがって分節化された箇所には、必ず相反するふたつの性格を見ることができる。ひとつは繋がること、もうひとつは離れることだ。繋がることが徹底してしまえば分節線は消えてしまうし、離れることが徹底してしまえば文字通り分離し解体してしまうだろう。
したがって分節は、それ自体において必ずジレンマを孕んでいることになる。繋ぎつつ離れ、離れつつ繋がるという、ある種の居心地の悪さが、そこにはある。
しかし、この居心地の悪い分節問題のなかにこそ、近代建築におけるユートピア主義の悪夢から脱却する契機が潜んでいるのではあるまいか。全体から部分へと至る設計方法のなかで、ディテールは相変わらず建築の細部における気の利いた納まりにとどまっているかに見える。もちろんそれが無意味だというつもりはない。それどころか、それこそがすべてなのであって、むしろディテールをその範囲に囲い込んでいることが差別的だと思うのだ。
この分節問題という難問に建築のすべてを賭けたといってもよい近代建築家がカルロ・スカルパである。ケネス・フランプトンによれば、スカルパの場合には「作品全体を通してジョイントは一種の結構的な凝結として扱われている」のである。簡潔に言えば、スカルパの建築はコンセプト自体がジョイントであり、「繋ぐこと」のディテールそのものが建築なのだ。
「彼の場合には人間主義的なあるいは有機的な意味での理想的全体像という意図がまるでなく、おそらく他でもないこのことこそが彼を歴史の主流から切り離しているのだろう(ケネス・フランプトン)」
ユートピア=全体性が、建築=世界を構築するための指針にはもはや成りえない時代において、全体から出発するのでもなく、また全体を経由するのでもなく、にもかかわらず全体に到達し得る建築の可能性がスカルパではないのか。「近代」が問い直されるにつれて、反ユートピア主義者スカルパの政治性がにわかに際立ち始める。
そしてスカルパが「繋ぐこと」から分節問題に切り込んだとすれば、分節の両義性のうちのもう一方である「離れること」にもその可能性があるとはいえないだろうか。分節問題に対する「空洞3部作」のスタンスは、ディテール・モデルを見る限り、分節の「繋がり」と「離れ」の両義性のうち、明らかに「離れ」のほうにウェイトが掛かっているようだ。それぞれのパーツの接触の在り方が、八方塞がりに納まったようはならずに、大概どちらかの方向に開かれていることが見て取れるだろう。
また精度が要求されたこともそれと関係があるかもしれない。「空洞3部作」のディテール・モデルに共通するのは、各部材がそれぞれの指し示す方向へと滑り始めるときを待っている状態、切っ掛けさえあればたちどころにそこから離脱して空中に分散しようとする、そんなスベスベの感じなのである。
ともあれ「ディテール・モデル」の試みは、「空洞3部作」が「全体」でもなく「部分」でもない建築の可能性を示しており、また同時に、その特性が「離れる」力学のもとにあることにおいて、東京という都市の特質である「離散性」に、「空洞3部作」が対応していることをも明らかにしているのではなかろうか。