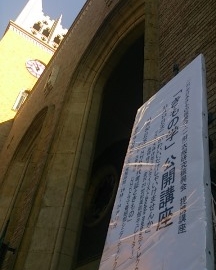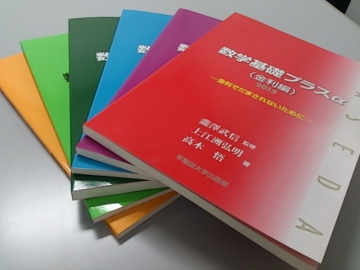Report_きもの学 公開講義「NHK時代考証ときもの」
| 科目名 | 「きもの学」 |
|---|---|
| 担当教員 | 藤井 浩司 政治経済学術院 教授 |
| 履修年度・学期 | 2014年度・秋学期 |
全日本きもの振興会 ・衣服研究振興会の協力による提携講座「きもの学」は、時代と共に海外の技術や文化を取り入れ変化しつつも連綿として伝承されている「きもの文化」について、各界第一線で活躍されている方にご登壇いただき、 その感性に触れ、日本人の心と日本文化の真髄を探る人気講座です。
11月20日、公開講座として、NHKドラマ制作部シニア・ディレクターで『考証要集』(文春文庫)の著者である大森洋平さんが登壇。会場の大隈記念講堂 大講堂には履修者の他、本学学生、一般の方など約600名が集い、「○○○○○○を○○○○こと」(※クイズです)-きものを軸として、時代考証という仕事とその極意、制作秘話を楽しく拝聴しました。
「『源氏物語』をドラマ化したとき、出してはいけない野菜はどれでしょう?1番トウガラシ、2番カボチャ、3番ホウレンソウ」。クイズで始まった冒頭。「正解は全部間違い!」(会場・笑)「トウガラシはメキシコ原産、コロンブスの大陸発見でユーラシア大陸に入ってきた。つまり光源氏の時代には誰も知らない。カボチャはカンボジアという名前からわかるように、日明貿易か南蛮貿易で1575年頃に日本に入った。ホウレンソウも、江戸時代の農業書に“唐菜”という名で載っている」
時代考証は枠を決める仕事。枠の中であれば主人公は何をしてもいいが、外に出ると失敗になる。「枠の大きさは演出意図などにより変化します。例えば、『八重の桜』の山本八重のように主人公の幼少時代がよくわからない場合には大きく、坂本龍馬のように全行動が記録に残る場合は小さくなる。ここがミソで、時代が後になるほど、枠決めはしっかりやらないと怖い」。特に忙しいのが収録前。台本一稿目・白本ができると、演出家やプロデューサー、専門家など関係者が集まって考証会議を開く。その内容を脚本家が反映してできる青本、以後必要に応じて何段階か経て出来上がる完成台本に沿って収録が行われる。収録風景や女優、俳優とのエピソードを交えながら講義は進む。
昔は時代劇の要素が全てわかる考証の専門家がいたが、今は時代考証、風俗考証、建築考証、衣裳考証、所作指導と分野ごとの専門家が集まったチーム制の考証を行う。「専門の先生は、ご専門はさすがに詳しいけれど、範囲外はそういかない。先生と先生との隙間で生じた問題に対処するのが仕事。これを私は“時代考証の隙間産業化”と呼んでいます。先生方をお医者様とすると、私は救急隊員。専門知識だけでなく雑学が必要で、日本史の知識だけでは通用しない。ひたすら本を読んでノートを取るとか、お坊さん、漬物屋の若旦那、自衛官とか、その道の専門家にインタビューをしたり、単なる歴史の枠でないところで勝負する仕事です」
ここからは放送中の大河ドラマ『軍師官兵衛』を例に、衣裳や小道具を解説。「衣裳デザインは、演出、プロデューサーの好みが非常に反映されます。女優さんは綺麗すぎてリアルでない場合もありますが、『平清盛』では、偉い人に会いに行くシーンで、普通なら汚い中にも綺麗な格好をするはずなのに汚いままなのがおかしい。金持ちでも汚い場合もあるし、貧しくても小奇麗に暮らすこともあるわけで、汚い=リアル、でもない」。『軍師官兵衛』では、帯を前に締めて、扇子を指している。「当時の言葉は1600年の『日葡辞書』でわかるのですが、 “ウシロオビ”という言葉が載っている。衣裳の本には、江戸前期に後ろ帯は元服前の女性、文化文政期には一般化した、などと諸説あり、この時代は混在していてよいのですが、要はこのドラマでは帯を前に締めるということを選択したのみで、歴史的にそうだということではない。用語の問題も同じ。風俗考証の先生によれば「打掛」は武家言葉で、公家言葉では「掻取(かいどり)」と言うそうです。これを厳密に対応すると、武家か公家かで台詞を変えなくてはいけない。しかし、大河ドラマはあくまでも演劇ですから、台詞がわからなくなってまでやる必要があるかどうか」。衣冠束帯や履物、左前なども同様で都度考証が必要になる。
現代では、若い俳優の体格が向上し腰骨が高くなって歩くうちに刀が閂刺しから落とし刺しになるとか、日本家屋での生活経験がなくなり日舞やお茶の嗜みがないと歩き方などが洋風になってしまうことから、所作指導も重要。バイバイ、正座などの日常の動作にも、乗馬や血判の流儀にも、変化がある。加えて、御用提灯や脇息、座布団など、時代劇定番小道具の話題など、映画やドラマの豊富な事例や考証の根拠を紹介しながら解説は続く。どこを切り取っても、つい人に話したくなる小ネタの宝庫である。「若いスタッフは、優れた時代小説や映画、芝居を観る必要がある。インターネットの情報は責任編集者がいないので内容が無責任になる。さらに放送の送り手と視聴者の情報源が同じなのも問題で、ネットが社会の弊害になる、製作者として独自の情報源を持たなくてはいけない、と常々言っています」
「『龍馬伝』で手打ちそばという看板を見た視聴者の方から、昔は機械がないから、手打ちそばとは言わないのでは、と電話をいただきました。でも、店の主人が手づから打ったプレミアムそばという意味で当時あった言葉です。言葉の問題は非常に面白くて、衣裳や髪型、大道具小道具の考証をきちんとやって、セットにお金をかけても、言葉の失敗で台無しになることがある。では、再びクイズ。時代劇で使ってはならない言葉はどれでしょう? 1番『青年』、2番『大都会』、3番『ぎょっとする』。正解は青年。明治13年にYMCAができ、Young Menの訳語として出てきた。それ以前は少年でした。このように、言語考証も大事。『軍師官兵衛』では、切支丹言葉や方言の問題。『洗礼』は新しい言葉で、当時は『バウチズモ』と言った。そのまま台詞にしても誰もわからないから時代劇言葉で『切支丹となりましてございます』などとする。『教会』も『太臼堂』ではなく、『南蛮寺』としました」
高じて、現代語を即興で時代劇言葉に翻訳できる特技をお持ちとのこと。「『Twitterでブログが炎上した』は『風の噂が噂を読んで飛んだ火の粉をかぶり申した』とか、「AKB48」は『近頃巷で噂の娘芸人四十八』と言ったらウケましたけど。『発光ダイオード』は『オランダ蛍提灯』とか、語彙を置き換えるだけじゃなくて、江戸時代の人が見たらわかるというのが大切」。会場から募って早速変換。
証は時代劇だけでなく、戦前戦中劇でも必要となる。明治から戦前、特に戦争中の描写や軍服が大切。振る舞いや着こなしについて、『となりのトトロ』に『ひめゆりの塔』、朝ドラ『花子とアン』『マッサン』などを例に、考証事例を説く。時代劇と異なり、その時代を生きていた方が視聴者になっても自然に見えるように苦心するそうだ。戦時中の記憶などは特に思い込みが生じがちなので、公平な観点から様々な対象にあたって考証を行うことも大事で、ドキュメンタリー番組に携わることも多い。
時代劇は、あくまで歴史に仮託したファンタジー、こうだったらいいなぁというロマンです。着物も一要素にすぎず、何を着るかより、それを着てどう動くかが大事。時代考証の極意とは『おかしなものをださないこと』。その時代に存在したかどうか極めるのではなく、出すかことが妥当かどうか。時代考証や言語考証に詳しかった劇作家・真山青果の有名な戯曲『将軍、江戸を去る』のト書きで、西郷と勝の対談回数や場所を変えたことが書かれている。つまり、誤りを指摘するのは野暮なこと。知らないで崩れているはカッコ悪いけれど、知っていて崩すのはいい。ドラマで大切なのは、歴史の再現ではなく、あくまでも質の高いドラマです。その物語の枠内ではこういうこともあり得る、と枠を決めるのが時代考証で、ストーリーテリングのしもべ、ツールなのです。時代劇は無形文化財。なくなってしまうと、もう作れなくなってしまう。NHKは時代劇をメディアの中に残す責任がある。今は大河ドラマが一種のフラッグシップになってしまっているが、黄金時代は去っても、『白銀時代』として良い時代劇を作り続けていく意味がある。一方で需要によっても支えられます。だから、私たちも一生懸命作りますので、どうか皆さんも視てください」
制作現場のエピソードや時代考証の裏話を盛り込んだウンチク満載の90分。着物を通じて歴史や番組制作への熱い想いを感じることができる魅力いっぱいの講義であった。