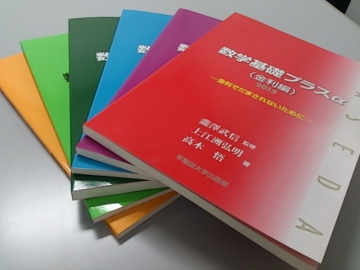Report_きもの学 公開講義「かわいいだけじゃだめですか」
| 科目名 | 「きもの学」 |
|---|---|
| 担当教員 | 藤井 浩司 政治経済学術院 教授 |
| 履修年度・学期 | 2014年度・秋学期 |
全日本きもの振興会 ・衣服研究振興会の協力による提携講座「きもの学」は、時代と共に海外の技術や文化を取り入れ変化しつつも連綿として伝承されている「きもの文化」について、各界第一線で活躍されている方にご登壇いただき、 その感性に触れ、日本人の心と日本文化の真髄を探る人気講座です。
11月13日、公開講座として、スタイリストでdouble maisonディレクターを務める大森伃佑子さんが登壇。金沢21世紀美術館キュレーター・高橋律子さんと、「かわいいだけじゃだめですか」と題し、対談しました。会場の大隈記念講堂 大講堂には履修者の他、本学学生、一般の方など約700名が集い、ファッションの世界で「かわいい」を追求し続ける上で大切にしている気持ちをお話しいただきました。
現在、世界的な話題の「かわいい」(「KAWAII」「カワイイ」)という言葉。大森さんは、1980年代から伝説の雑誌『Olive』などを通じ、「かわいい」を表現し続けてきた。冒頭、これまでのお仕事をスライドショーで提示。「『Olive』という雑誌は、10代の気持ちを体現した雑誌で、友達には負けない、とか、泣かない、といったメッセージを通じ、ライフスタイル全般を提案しました。他に女の子の気持ちをつかむ雑誌がなかったし、インターネットもなく情報も少なかった時代。『オリーブ少女』という言葉もでき、いまだに根強いファンがいます。私たちは最初から、いいものは全部かわいいと表現していましたが、80年代頃は編集長から『なんでもかわいいってどうなの?』と言われましたし、男性には受けませんでしたね」
2000年代に入り、日本のファッション界が変わり始めた。「ミナペルホネンなど、一人のデザイナーがアトリエを持ち、社長も務め、ブランドのすべてを表現する形態が出てきたのを見て、自分がやりたいことと近いと思いました。その後、森ガールが話題になったとき、夢見る気持ちがあまりに強すぎて、それで今から30年間仕事ができるの?と肩を揺さぶりたくなるような子も多く、女子が生きることってなんだろう、とものすごく深く考えることがあって。そして、だったら、私は30年続けた、その先の世界を見てみたい、と強烈に思いました」
そんなとき、株式会社やまとの矢嶋孝敏会長と出会い、着物ブランドを立ち上げることになった。「50代になってブランドを始め、違うフィールドに行く迷い。自分の気持ちを上げる、戦いの気持ちが強くありました」。大森さんは、誌面にどの写真を使い、どういった言葉を、どのレイアウトするか、といったところまですべて手がける。雑誌『装苑』の連載「FOR A GIRL」の誌面に当時の強い気持ちを表現した「憧れの先で戦うこと」と題したメッセージが表現されている――だから負けなくないの。私が女の子であること。私はそこに絶対の自信がある。女の子がどんなに気持ちをいっぱいにして、この街でどんなに懸命に生きようと、活かされたいと思っているか。胸がいっぱいになる。そのドアの前で ただいっぱいで もっと大切なものがほしい だってただドアの前で まだどきどきする。 そのドアですら 女の子にとって、簡単には開けられないもの――。痛感するのは、スタイリストは本当に1人ではできない仕事。服があってモデルさんがいてカメラマンがいて…時には戦いもしながら、一つのビジュアルを作るという作業。独りよがりなものではないのです」
そうして2010年に立ち上げた着物ブランド「double maison」はWeb Shopで展開。「架空の街に住む、架空のアパートにする女の子たちのクローゼット、というストーリーを表現しています。女の子って、明日着る服を今日買うだけではなく、いつか着たいという憧れをクローゼットにしまっていて、扉を開けたとき、その憧れがチラッと見えてほっこりするっていう気持ちありますよね。クローゼットに現れる、それぞれの女の子の性格や生い立ち、環境、今の生活。そこから服や小物を発想しています」
ちなみに、大森さんと着物との関わりは、2002年の雑誌『KIMONO姫』創刊に遡る。「当時は着物も持っていなかったし、着付もわかりませんでしたが、いつもの気持ちでスタイリングして、との依頼に、それならできるかな、とお引き受けしました。この頃、アンティーク着物の可愛さに女の子たちが気づき始めて。柄や色や素材といった、かわいい、のツボがいっぱい詰まっているのが着物。豆千代さんは自身がカリスマになって、着物が決してよそいきじゃなくて、デイリーのものだということを伝え、ブームになりましたね。アンティーク着物は、1000円位から買えて、高くても3万円くらいで手に入る。でも、1点物ばかりで、当時購入した方が30年後にでも手放さない限り、もう市場にかわいいアンティーク着物を新たに発見するのは難しくなってしまいました」
その後、2008年にはテレビドラマ『おせん』の蒼井優さんのアンティーク着物のスタイリングが話題になった。「『KIMONO姫』は雑誌なので、着物を好きな人がやっぱり好き、という反応でしたが、『おせん』はテレビですし反響が大きかったですね。着物は着ないけど、とか、男性からの反応もありました」。今までとは違うフィールドからの声も多くかかるようになったが、「ブレイクして世界を壊すくらいなら、流行る必要なんてない。取材も随分お断りしました」
一方で、懇意にしている女優さんの依頼で着物を作ってコーディネートをしたことがとても面白く、ファッションとしての着物をやってみたいと思うようになった。「いつも洋服を着ている女性が特別な時に着物を着るだけではなく、日常的に、洋服と着物の境目をなくして、もっと着物を着てもらいたい。今はまだ着物に触れる機会の少ない水面下にいる人の胸を打ちたい」
「double maison」では、服地のシルクの上にインクジェットで染色したり、洋服の技法で仕立ては着物、といった製品もあるという。「真っ白の着物は“死に装束だから絶対売れない”と言われましたが、白いワンピースって売れるし、着物もかわいいのになんで?と思って。総レースの着物も、かわいいじゃない?って。単純でまっすぐな気持ちで作っています。また、着物を着る上で自分が思うストレスはなるべくなくし、スタイリストとしてスタイリングの提案を常に心がけています。帯結びが下手で着付に自信がない人や着慣れない人が、隠してかわいく気軽に着られるようなケープ。麻のワンピースや着物とローブ。作り帯もワンタッチというだけではなく見えてもいいようなリボンに。着物もデイリーで着られるようにしたい。しわにならない、とか、襟や足袋をどうやって合わせるか、とか、double maisonの中のものをこう合わせたらどうかと提案し、ファッションという気持ちなら大丈夫という気持ちを後押ししたい。でも、どんなに崩しても上品であることっていうのが着物らしさですよね。これは絶対に外したくない」
着物の世界は携わる人が少ない。「ファッションにも、コンサバやギャル、などジャンルがあるように、着物だっていろいろあっていいですよね。小さな店舗があちこちにできて、そこでいろいろなスタイルが表現されて、お客様が自分に合ったお店を探して入れる、というような形になるといいなと思います」。
ファッションとしての着物道。「かわいい」の中に籠められた強く熱い想いが伝わる講義だった。