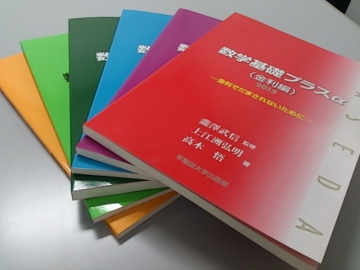Report「早稲田を知る」公開講座
| 科目名 | 早稲田を知る01 |
|---|---|
| 担当教員 | 葛西 順一、鎌田 薫、島 善高、高西 淳夫、中島 国彦、長谷川 惠一、浅古 弘、吉野 孝 |
| 履修年度・学期 | 2014年度・春学期 |
| 氏名・学年 ※掲載時 | 齋藤 健史・教育学部 2年 |
「早稲田大学校歌の由来」を受講して
私は早稲田大学本庄高等学院の出身で、應援部に所属していたこともあり、早稲田大学校歌を歌ってかれこれ今年で5年目になる。しかし、 恥ずかしながら校歌の由来についてはさっぱり分からなかった。また、正直歌詞の意味を全て理解していなかった。
大学進学後も応援部に所属した為、今回の講義の受講は私にとって、良い財産となった。早稲田大学校歌について、最も驚いた点は日本で一番最初に出来た校歌であるという点である。やはり、日本三大校歌と言われる校歌だけあるなと感じた。歴史をもち、日本の校歌の先駆者的存在の早稲田大学校歌を歌えていることに強い誇りも感じた。
国立大学とは異なり、私学として大学色を出し、また大学の方向性を纏める為に校歌を作成することとなった。この校歌作成にあたり、イェール大学など海外の大学校歌を参考に研究された。海外の校歌から学ぼうとする点も早稲田らしいと感じた。
歌詞は相馬御風氏に手掛けられた。現在でも歌い継がれていることからも素晴らしい歌詞であることは違いない。歌詞の冒頭「都の西北」は皇居からみて西北に位置する早稲田大学を指している。実際に地図で確認するとまさにその通りであった。天皇陛下に尽くし、日本の中心となるという強い意志がうかがえた。
校歌の特徴として、歌詞の他にもう一つある。それは音楽である。「早稲田大学校歌はどんなときにでも歌うことができるそれがこの校歌の良さの一つである。」と菊地先生はおっしゃっていた。卒業してから、お酒が入った席、カラオケ、もちろん早慶戦でも。どんな場合にでも歌える、それが早稲田大学校歌なのである。この背景にあるのは校歌の行進曲であり応援歌であるという音楽性の特徴が作用しているようだ。心が震えるような行進曲の顔をみせたり、重厚な音楽に歌詞の意味を噛みしめ涙を誘ったりと様々な面を見せてくれる。また、歌詞が8・7・8・7……とリズムよく繰り返され、これもまた歌いやすい理由であり特徴の一つである。
深い歴史、思い、そして多様性に満ちた早稲田大学校歌。こうして由来や意味を知った今、今までとは異なる思いで校歌を歌っている。秋に野球のリーグ戦が始まる。秋こそは慶應義塾大学を倒し、完全優勝し、涙しながらこの早稲田大学校歌を神宮球場で歌いたいと思う。