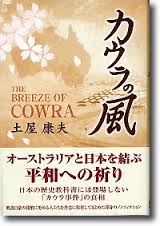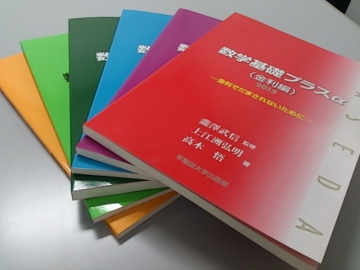Report_全学共通副専攻「オーストラリア研究」全体活動
| 副専攻名 | 「オーストラリア研究」 |
|---|---|
| 科目名 | 「オーストラリアの文化(入門)」 |
| 担当教員 | 澤田 敬司 法学学術院 教授 |
| 履修年度・学期 | 2014年度・春学期 |
| 氏名・学年 ※掲載時 | 嶋田 夏怜 国際教養学部1年 |
「世界中にあふれる憎しみを国同士、人同士、民族同士がどのように乗り越えていくことができるのか」
今年は、太平洋戦争中のオーストラリアで、日本人捕虜が集団脱走し231人が命をおとした「カウラ事件」から70周年を迎えます。それを記念し、ジャーナリストの土屋康夫さんをお迎えして、日本とオーストラリアの関係史を深く学ぶ講演会を開催しました。参加学生によるレポートをお届けします。
2014年はカウラ事件から70年ということで、フリージャーナリストの土屋先生から、教科書に登場しない太平洋戦争時代の日豪関係についてお話を伺った。
日本では太平洋戦争は、あたかも日米間の戦争として教えられることが多い。つまり、日本人の中にはオーストラリアと戦争をしたという歴史的事実さえ知らない人もいるということだ。そんな中で迎える今回のカウラ事件から70年を前に、両国の歴史的関わり、確執、歩み寄りを学ぶ機会が与えられたことは本当に自分の中で大きな意味を持つと思う。
1968年に松尾中佐の母が慰霊と遺骨送還の答礼の旅としてキャンベラをおとずれた際、オーストラリア政府は、戦時中に日本から受けた被害は計り知れないのにも関わらず、沈没船から遺骨を引き揚げ、また、船が引き上げられない場所では、ダイバーを使って海底の砂を採取することまでをも日本人遺族のために行ったという。この話を土屋さんから伺い、日豪が計り知れない憎しみをも乗り越えて、現在環太平洋諸国の中で最も緊密な関係を築き上げることが出来ていることに感動した。
日本とオーストラリアの戦中戦後の歴史をもう一度ひも解くことで、現在世界中にあふれる憎しみを国同士、人同士、民族同士がどのように乗り越えていくことができるのかというヒントを得ることができ、それは戦争を抑止する大きな力になるのではないかと考えさせられた。