- プロジェクト研究
- 実験・理論・計算が融合したケム・インフォマティクス研究
実験・理論・計算が融合したケム・インフォマティクス研究

- Posted
- Thu, 06 May 2021
- 研究番号:
- 研究分野:
- 研究種別:研究重点教員研究
- 研究期間:2021年04月〜2026年03月
代表研究者
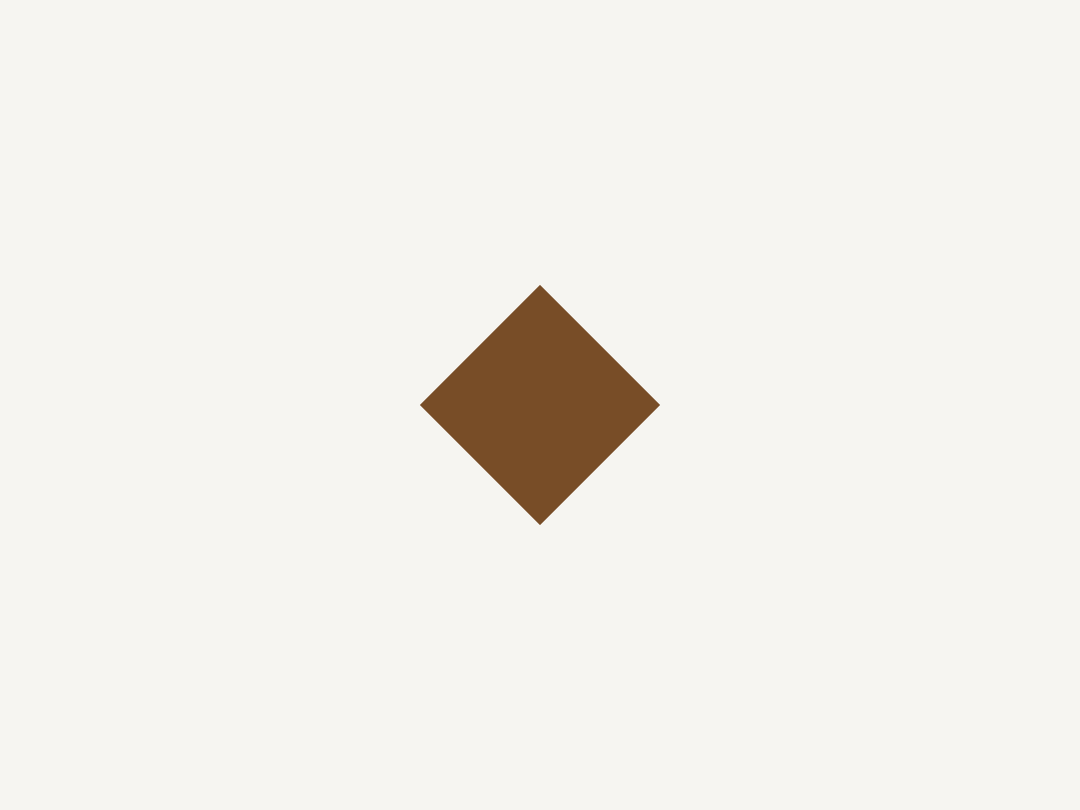
清野 淳司 准教授(任期付)
SEINO Junji Associate Professor(without tenure)
先進理工学研究科 化学・生命化学専攻
Department of Chemistry and Biochemistry
研究概要
化学では100種類程度の元素の組み合わせから、無限に近い化合物が創出される。実際に合成が確認され、化合物データベースCAS REGISTRYに登録されている化合物数は1億7千万以上(2021年2月現在)にも及び、さらに年間約1千万個の新たな化合物が登録され続けている。しかし、このような膨大な数の化合物の創出において、従来の化学研究では実験化学者の経験と勘に頼ってきた。そのため、その化合物が所望の物性を示すか否かは、必ずしも自明ではない。化学研究において、セレンディピティ(偶然の発見)がしばしば取り沙汰されるのはこのためである。近年のコンピュータの発展により、計算化学を用いることで、化合物の物性を高い精度で予測できるようになり、いわゆる順方向のスクリーニングが可能となってきた。しかし、革新的な材料の開発などで求められる、物性から化合物を予想するという逆問題を解くには至っていない。インフォマティクスと実験・計算化学の融合は、双方の問題を解決に導くことができると考えられている。
そこで本研究では、次の3つの難題の解決に寄与するための諸手法を開発する。①データベース内の1億7千万を超える化合物の中からどのように所望の物性を持つ化合物を選択するのか、②1060通り以上の可能性を持つ未知・既存化合物の中からどのように有用な化合物を設計するのか、③有望な化合物をどのように合成するのか。これらの問題を解消することにより、セレンディピティを回避した革新的な材料の開発が可能となる。これを実現するためには、データ数は限定されているが正しい結果を与える「実験化学」、結果は必ずしも正しいとは限らないが大量のデータを生成できる「理論/計算化学」、実験/計算データを繋いてまとめ、さらに未知の化合物群も探索できる「インフォマティクス」、の融合が不可欠である。この融合により、所望の物性を持つ材料探索や、化合物の合成経路設計を完全自動化するスキームを確立し、実際に実用化することができる。
本研究では、上記において特に重要となる3つの研究を重点的に遂行する。インフォマティクスと実験・計算化学の融合による(A)分光などのスペクトルに対する同定・評価・解析の自動化、理論化学との融合による(B)データ駆動型次世代密度汎関数理論(DFT)の開発、実験・理論・計算化学との融合による(C)合成経路設計システムの開発、である。また並行して(D)学内外における『ケム・インフォマティクス』の普及、を行う。
