- ニュース
- 【開催報告】早稲田地球再生塾第5回勉強会「食と社会受容」(2022年8月26日)
【開催報告】早稲田地球再生塾第5回勉強会「食と社会受容」(2022年8月26日)

- Posted
- Wed, 31 Aug 2022
世界の食糧システムの課題に対し、その打開策として期待されているのがPBF(植物由来食品)、昆虫食、培養肉といったフードテックである。しかし、こうした技術が社会実装されるにはいくつかの規制や法的課題があり、こうした食の課題について文と理の垣根を超えた議論が求められている。
早稲田地球再生塾(WERS)では、こうした食の社会受容における課題や今後の展望を議論する場として、2022年8月26日に「食と社会受容」と題し、第5回勉強会をWeb開催した。ウクライナ問題などで食糧需給の問題がクローズアップされる中、140名を超える参加申し込みがあり、盛況に開催された。
最初に、早稲田大学理工学術院総合研究所所長の木野邦器氏から開会の挨拶を頂いた。サスティナブルな社会構築、高付加価値なタンパク源を供給する研究としてフードテックは非常に重要な研究課題であると述べられた。
続いて、早稲田大学大学院先進理工学研究科生命理工学専攻・准教授の坂口勝久氏より本プログラムの開催趣旨を説明頂いた。今回の勉強会は、前半は培養肉に関するテーマを2名の講師にお話し頂き、後半は昆虫食に関するテーマと社会受容に向けた研究開発の在り方に関して2名の講師にお話し頂くプログラムとなっていると説明された。
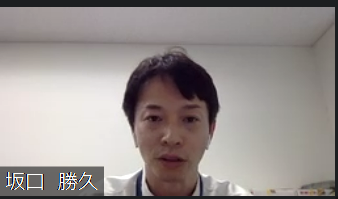
先進理工学研究科生命理工学専攻 坂口 勝久 准教授
最初の培養肉に関する講演は、坂口勝久氏より「藻類・動物細胞を用いたバイオエコノミカルな培養肉生産システムの開発」と題し、培養肉開発における世界の現状を俯瞰頂き、その中でどの様な技術が開発され、課題は何なのかを判り易く説明頂いた。特に、坂口氏の大きなブレークスルーは藻類培養で培養肉に必要な栄養源を抽出する点、そして牛筋芽細胞の攪拌浮遊培養技術を開発する点にポイントが有ると述べられた。
続いて、ティシューバイネット株式会社社長の大野次郎氏から『ネットモールド法による本物の食肉に近い培養肉の製造』と題して、網状井形を用いた細胞の組織化技術に関しての研究開発が紹介された。この方法は無駄が無く、安心・安全・安定供給ができ、多様な基礎研究にも応用可能な技術である点を強調された。

ティシューバイネット株式会社 大野 次郎 社長
後半最初の講演は、早稲田大学総合研究機構・次席研究員(研究院講師)の片岡孝介氏より、『昆虫を起点とした循環型食料生産の実現に向けた学際研究の最前線』と題して、昆虫食の中でも特にコオロギ食に関しての現状や技術的課題に関して述べられた。コオロギをミツバチ、カイコに次ぐ三つ目の家畜化昆虫として確立する、魚粉の代替として虫粉を普及させるなどといった将来展望を述べられた。
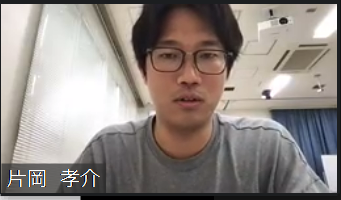
総合研究機構 片岡 孝介 次席研究員
最後の講演は、早稲田大学政治経済学部・准教授の下川哲氏より『持続可能な「食」を取り巻く世界的動向』と題し、未来の食の在り方に関して説明された。土壌・食料・人間・環境の四つの健康(健全な状態)を同時に高める事が重要であるという点、食生活は急激な変化が求められており将来の理想の食生活は果物の消費を増やし肉食は減らす方向に移行する(EATラインセット基準)点など、社会科学と自然科学の両面から説明された。

政治経済学部 下川 哲 准教授
最後に、早稲田大学理工学術院総合研究所・副所長の高橋大輔氏より閉会の挨拶があった。食の未来に関してアカデミアと企業が一緒に考える良い機会であった。次回は、リアルの勉強会で、開発された培養肉や昆虫食を食べる機会ができたら面白いと締めくくられた。
(早稲田大学理工学術院総合研究所 荒勝俊)
