- プロジェクト研究
- 地域密着企業による歴史的資産とナラティブのホリスティック保存を通した まちづくりCSVモデルの開発
地域密着企業による歴史的資産とナラティブのホリスティック保存を通した まちづくりCSVモデルの開発

- Posted
- Fri, 11 Apr 2025
- 研究番号:25C13
- 研究分野:environment
- 研究種別:奨励研究
- 研究期間:2025年04月〜2026年03月
代表研究者
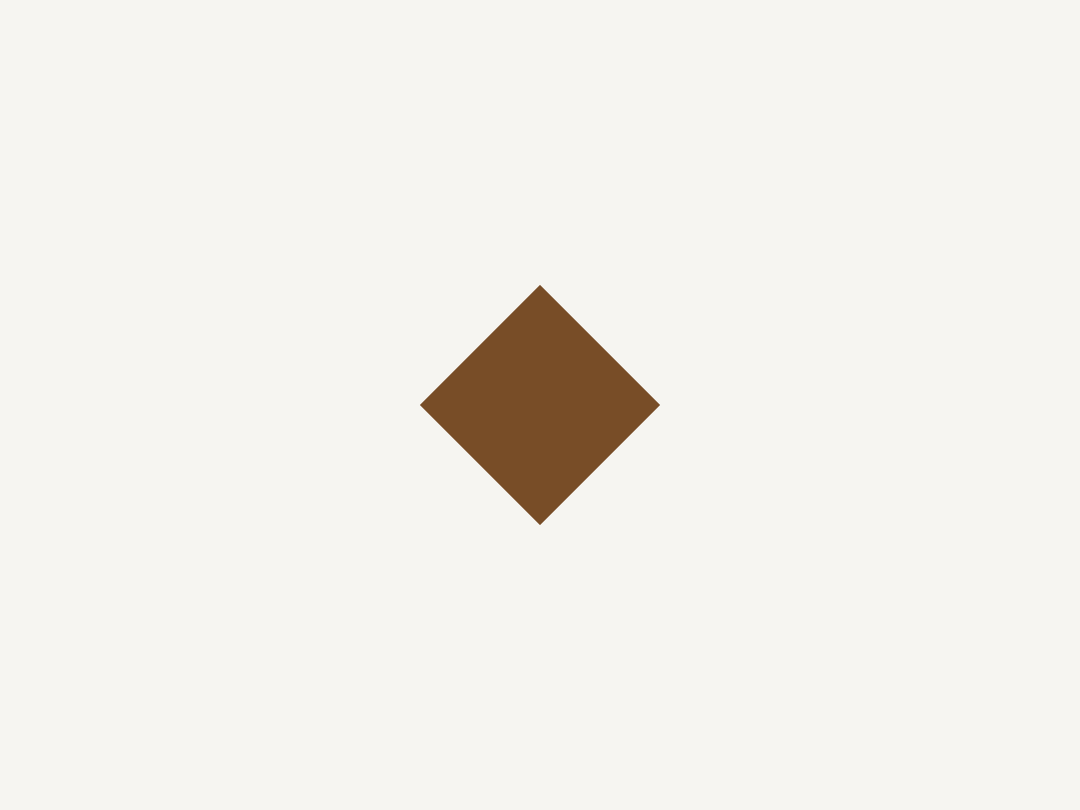
林 廷玟 理工総研が募集する次席研究員
RHEEM Chungmin Junior Researcher
理工学術院総合研究所 後藤 春彦 研究室
Research Institute for Science and Engineering
研究概要
近年、基礎自治体の範域を越えた広域圏における計画に対し、その連携の新たな担い手として自治体と協働する民間企業に注目が集まっている。このような「地域密着企業」の動きとして公共サービスの市場化、公共施設の指定管理や各種PFI事業へ参画する例が見受けられるようになり、地域密着企業が複数の自治体と協働した「まちづくりマネジメント」業へと転換する可能性に大きな期待が寄せられている。本研究は地域密着企業に着目し、同企業が地域資産である歴史的資産を有効に活用し、共有価値の創造を行うための「まちづくりcsv」モデルの開発を試みるものである。
本研究は歴史的資産である「蔵」や「町屋」を数多く有する「埼玉県越谷市」を対象として、地域密着型の協力を得て、民間企業が地域資産を有効に活用し、まちと企業の価値を同時に高める「まちづくりCSV(Creating Shared Value)」を実現するための具体的な手法を開発することを目的とする。
具体的には、従来の歴史的資産の点的保存から面的保存への移行に向け、研究者が提案する「ホリスティック保存」の考えを援用することで、これまで十分になされてこなかった歴史的資産間に生じる関係性を評価し、まちづくり手法に応用するものである。地域が歴史的資産を活かしたまちづくりCSVを実践する手法開発を行い、その知見をもとに他事例へも適用可能な「モデル」として一般化することを目指す。
本研究は、以下3つの研究計画より目的達成を目指す。
(研究1)地域内で活用可能な歴史的資産の抽出とインベントリ開発によるデータ整備
(研究2)歴史的資産に関するナラティブの収集と市民への還元手法の検討
(研究3)歴史的資産とナラティブの相互連関から成立する「ホリスティック保存」手法を活用した「意味的な統合を持つ資産の保存」のモデル化
本研究では、地域に存在するナラティブ(物語)の収集を通し、ナラティブに対して共起ネットワーク分析を適用し、ナラティブ間ネットワークおよび地域内の歴史的資産のネットワーク構造の結びつきを評価することを通して、「意味的な統合を持つ資産の保存」のモデル化を描出する。また、オーラルによるナラティブの収集のみならず、定量的・データとして収集可能なナラティブの可能性提示も行う点に新規性を有する。調査にあたっては、国内の類似事例(企業によるまちづくり・歴史的資産活用の先進事例)を取り巻く現状もまとめ、より一般化可能な手法開発を目指す。
本研究の成果は、地域の歴史的資産となりうる有形無形の諸要素が持つ価値を「総体」として恒久的に保存・継承することを支援する社会技術の獲得につながることが期待される。地域資産保存と開発が協調共存した郊外都市のありかたを示すことで、地域密着型企業が「量産・売り切り」の短期志向を脱して、まちの価値と企業価値を同時に高める「価値提案型」の高付加価値ビジネスモデルへの転換を可能とするものであり、「まちづくりCSV」のモデルケースとなり、地域資源の保存・保全からまちづくりに展開する場面において、本研究の成果が活かされることになる。本成果は地域文脈の継承手法のあり方を示すものであり、ひいては今後の「近代」時代の足跡ならびに叡智の記述に寄与する意義ある成果となる。
年次報告
- Tags
- 研究活動 理工総研が募集する次席研究員
